偏見の中でも強力な「政治的偏見」を利用する
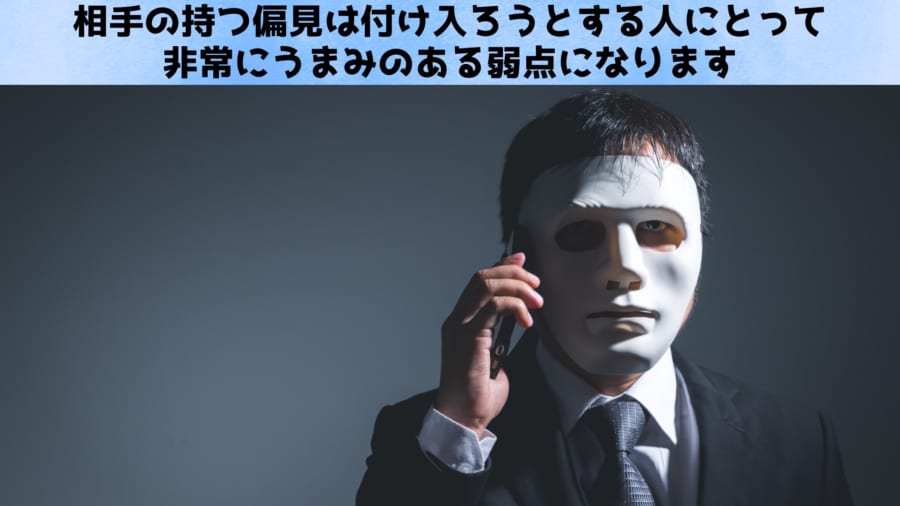
近年、米国をはじめ世界の多くの国で、政治的立場の対立が顕在化・先鋭化しつつあります。
いわゆる「政治的二極化」が進むと、政治家やコメンテーターのみならず、SNSや一般メディアにおいても、自分たちの支持者をより強く惹きつけるために“党派的言語”が積極的に用いられるようになります。
たとえば、同じ出来事を「抗議」と呼ぶか「暴動」と呼ぶかで、聞き手が感じる意味合いや重みがまったく変わってしまうのは、その好例といえます。
この背景には、「分断を煽るような内容のほうが目を引きやすく、拡散されやすい」という情報拡散メカニズムが存在しているという指摘もあります。
不特定多数の大勢を味方にするよりも、争っている一方から好かれるようにするほうが、低コストかつ短期間で多くの指示を得られるからです。
ソーシャルメディアのアルゴリズムやオンラインでの情報消費パターンに関する過去の研究(Brady, Crockett, & Van Bavel, 2020 など)によれば、感情的な内容ほど“バズ”を起こしやすく、結果として対立や偏見を増幅する投稿や報道が注目を集めやすい傾向があります。
党派的言語は、こうしたメディア環境の中で特に有効であり、同じ立場の人々の結束を高める一方、異なる立場の人々との距離をさらに広げるリスクを孕んでいます。
政治的二極化が深まるほど、党派的な表現によって得られる「同調のメリット」はますます大きくなる一方で、異なる意見を持つ人々や中立的立場の人々に対しては、過度なバイアスや“不公正なレッテル貼り”として受け止められる恐れがあります。
つまり、あるグループからの支持を得るために使われた言語表現が、同時に別のグループからの反感や不信を生み、意見の対立をより強めるという悪循環が生じやすいのです。
今回紹介する研究では、こうした「党派的言語」がどのように話し手への信頼や reputational benefit(評判的恩恵)につながり、また同時に相手を遠ざける要因にもなっているのかを、実験的に検証しています。
このように、政治的二極化が進む社会状況下では、党派的言語が生むインパクトは単なる“言葉選び”の問題にとどまりません。
どのような言語フレームを選ぶかによって、私たちが出来事そのものをどう捉え、誰を信じ、どんな立場をとるかが変わりうることが、より明確に示されつつあります。
また、こうした「偏見に寄り添う発言」の問題は政治領域に限ったものではありません。
職場やコミュニティ、あるいはSNS上の議論でも、同じグループに属する人々のバイアスを肯定するような表現を使えば、瞬時に“味方認定”されやすくなり、逆に相手の偏見から外れる表現をすれば“敵認定”されやすくなることが想定されます。
そこで今回、ブラウン大学の研究者たちは、偏見の中でも最も根深い「政治的偏見」が相手の好感度や信頼にどれほど甚大な影響を与えるかを調べることにしました。
調査にあたっては、同じ政治的出来事をリベラル寄り、保守寄り、中立的な3種類の言葉で表現し、参加者に話し手の信頼度や道徳性などを評価させました。
その結果、自分の政治的立場に合う表現(集団内言語)を使う話し手はより高く評価され、反対の立場(集団外言語)の場合は信頼度や道徳性が低いと見なされました。
この戦略を使うと、高い評価や信頼を得られるだけでなく、道徳的にも優れた人間とみなされるわけです。
一方、中立的な言葉を使う場合は、どちらの立場からも一応の理解を得られるものの、バイアスの強い参加者にとっては「頼りない」と映ることもありました。
また、もう1つの実験では、同じ出来事をリベラル寄り、保守寄り、中立的な言葉で表現した場合に、参加者自身がどのように出来事を捉えるか(同意・反対の度合い)を調査しました。
その結果、バイアスのある言葉で説明された出来事は、参加者が既に持っている政治的傾向をより強化する(分極化を深める)働きを持つことが示唆されました。
このことは、「自分の立場に一致する」表現(政党が好む表現:『アメリカを偉大に』や『アメリカンファースト』など)を目にすると、たとえ発言内容の質にそれほどかかわらず、評価や態度がプラスなりやすいことを示しています。
研究者たちは、この結果について、「人々が自分のイデオロギー的傾向に沿った形で政治的出来事を語る演説者を非常に信頼できるとみなす、という証拠を発見しました。政治的分極化が進むほど、人々は中立的な報道よりも、むしろ自分のバイアスを肯定してくれる報道に信頼を寄せるかもしれません。」と述べています。
また、本研究の大きな意義は、誤情報が必ずしも必要なくても“偏った言葉選び”が分断を助長し得る、という点にあります。
研究者たちは、「誤情報の悪影響ばかりが注目されがちですが、今回の結果は、真実であっても党派的な表現を用いれば、相手への不信感を煽り、意見対立をさらに先鋭化させる可能性があることを示しています。」と述べています。
相手からの信頼を楽して得ようとするときにはしばしば「嘘」が用いられますが、嘘が露見するリスクと常に向き合わなければなりません。
しかし政治的偏見を利用する場合は嘘に頭を使わず本当のことを言うだけで、相手の信頼を勝ち得ることができるのです。
ただ研究者たちは「相手の政治的偏見に合った言葉選び」が、自分と同じ立場の人々からの信頼や好感を高める大きな効果がある一方で、反対の立場を持つ人々からの支持や信用を著しく損なうリスクもあることを示しています。
さらに、言葉の使い方ひとつで現実の出来事そのものへの認識や評価が左右され、場合によっては分断が一段と拡大する可能性があることが明らかになりました。
研究チームは、こうした「イングループからの賞賛や信頼を手にする方法」としての党派的言語が、長期的には分断を深めるリスクを孕んでいることにも触れています。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)



























