それでも私たちは共存を選べるのか
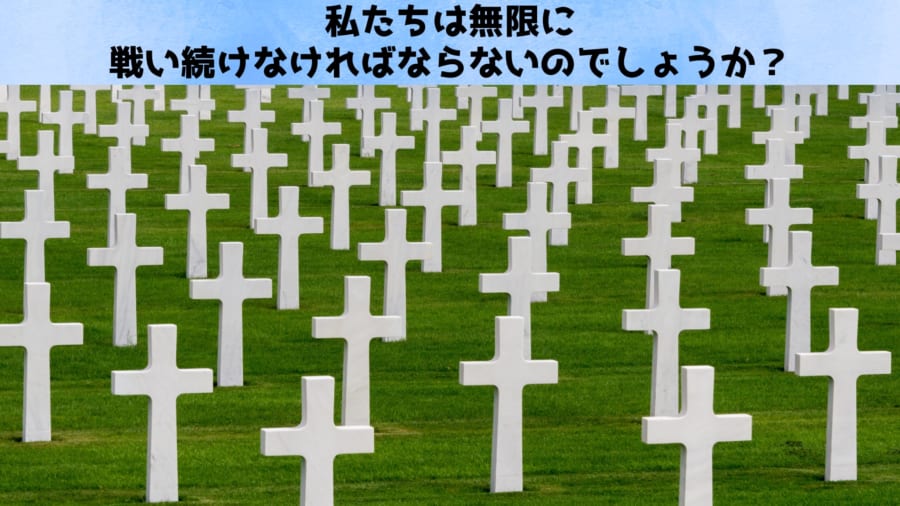
違いの認知が闘争を引き起こすならば、人類は無限に戦い続けなければならないのでしょうか?
半分は、その通りと言えるでしょう。
人類の自分と他者を区別する能力をのものが、既に闘争の下地を作り上げているからです。
しかし、闘争と同じように、人類は他者との協力を続ける本能も備わっています。
自己と他者を意識する認知は、闘争だけでなく他者と協力し合うための「必要条件」にもなっているからです。
実際、もし違いの認識が闘争しか生まないのならば、人類はとっくの昔に、1種類の人種、1種類の民族、1種類の国家しか生き残らないようになっていたでしょう。
他者との協力を必要とする同盟、連合、連邦、国連、二重帝国といった概念も存在しなかったはずです。
しかし、そうはなりませんでした。
現在の地球上には180カ国以上の国が存在し、無数の言語を話す人々で溢れています。
違う部分を認知して殺し合うよりも、同じ部分をみつけて協力するほうが最終出力が高かったからです(Tomasello (2009) 、Bowles & Gintis (2003))。
そして、違う相手からは違う利益が得られることを知れたのも大きなポイントとなったに違いありません。
(※利己的に考えるならば、他者を根絶やしにするよりも、他者を利用したほうがいいことに気付いた……とも言えます)
違いを認識し闘争を引き起こす本能と、違いから利益を得る知恵。
それらは、まるでコインの裏表のように、私たちの中に同居しています。
必然として備わっているこの本能を変えることはできなくとも、その反応や活かし方を変えることは可能です。
この先も、私たちの社会はさまざまな価値観や国籍、文化が入り交じり、かつてないほどの多様性を迎えるでしょう。
闘争か共存か、最終的にどちらを選ぶのかは、その時々の経済・政治・社会情勢の影響も受けつつ、やはり私たちの意志にかかっているのです。




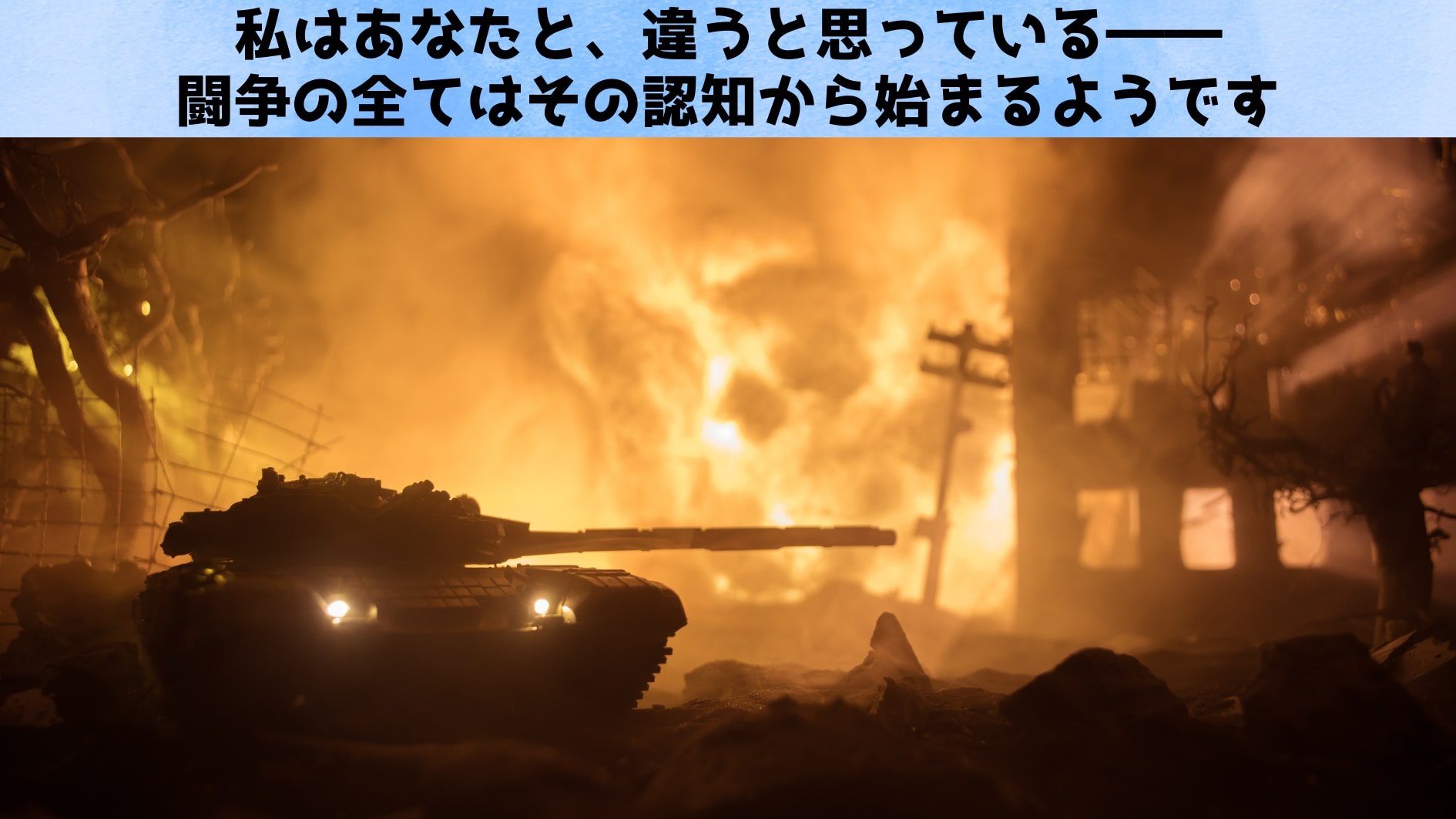

























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)




























研究結果のデータより
やや飛躍しているに感じました
A県の医者の件は、偏狭な村のサンプルとしてよく上がるけど、実際は5〜6人のちょっと変な住人達が粘着して起こしたってのが真相っぽいんだよな
仮に同じ村民だったとしたら、この暴力的な人たちをどうすれば良かったのか
1「彼らは自分たちとは異質である」← わかる
2「彼らは我々の生存と利益を脅かす存在だ」← ??
1から2へは飛躍があると思います
ちょっと偏見含みですが、いわゆる左派の人たちは2になりがちな気がします
>この何気ないように思える認知プロセスこそが、数え切れないほどの歴史的闘争や血塗られた対立、さらには現代におけるあらゆる争いの出発点であり、生存戦略として冷徹に進化の中で刻まれた必然の仕組みなのです
分裂したクローン個体の間でも資源に限りがあれば競争は起こる。真社会性の昆虫や動物が持つ巣仲間認識は防御に使われる。直接互恵や間接互恵で協力関係を築くためにも違いを認識する能力は必要だろう。ヒトの闘争にフォーカスして自他の違いを認知するプロセスのみを原因だとする論法は科学的なのだろうか?
チンパンジーは道具を使うことで有名では
争いを無くすためには争ったら損で仲間になったら得だと相手に思わせること
つまり戦う意思と能力を持つことと相手に利益を与える余裕が必要
このバランスが崩れた時に争いが起こる