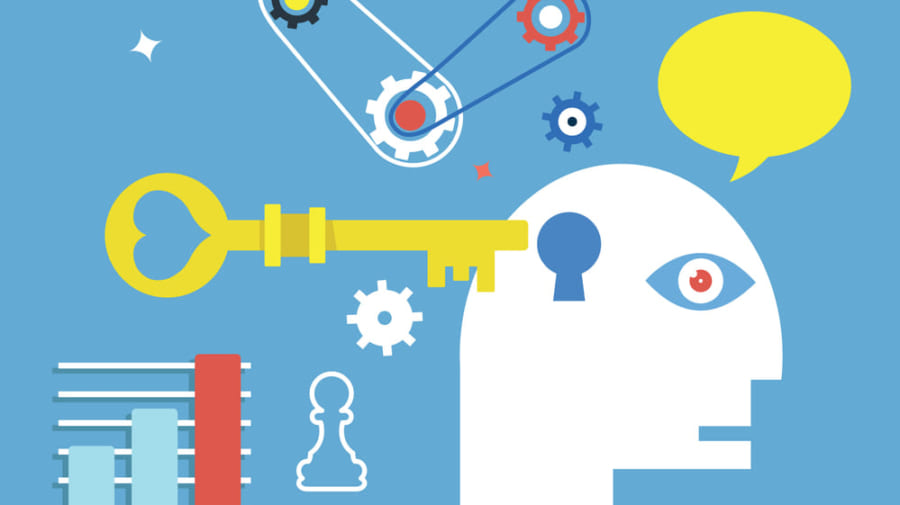何重にもわたる根回しが必要であった主君押込

そもそも、大名たるもの、己の立場を弁えて然るべきです。
しかしながら、時代が時代、身分が身分、主君たちはしばしば「やりすぎてしまう」ことがありました。
新たな法を定め、専制を志向し、果ては領内の財政を危機に追いやるほどの浪費を行う大名は少なくなく、こうした主君に仕える家臣団が「これでは藩が傾く!」と青ざめるのも無理はないでしょう。
しかし主君押込の動機が主君本人の抱える問題にある場合ばかりというわけではありません。
中には主君の政治路線を巡り、反対派の家臣たちが失脚させるために行おうとすることもありました。
この主君の押込を決定するのは、もっぱら家老たちの役目です。
もちろん、「殿が少々調子に乗っているから押し込もう!」などと軽率に決めるわけではありません。
問題は慎重に討議され、綿密な計画が練られます。
また主君の押込は、ただ家老たちの独断で決行できるものではありません。
藩の存続を左右する大事である以上、主君の親戚たちの了承が不可欠でした。
さらに主君の親戚たちの了承を取り付けたとしても、計画はこれで終わりではありません。
主君押込を成功させるためには、最後にして最大の難関である幕府の同意を取り付ける必要があるのです。
江戸幕府は基本的に、大名家の内部問題には深入りしません。
しかし、主君の押込ともなれば話は別です。
主君押込に対し、幕府は慎重に対応していました。
事を荒立てれば、藩内が混乱し、場合によっては幕府の権威に傷がつくからです。
そこで、幕府の重役たちは密かに「内意」を発し、「黙認」という形を取ることが多かったのです。
こうして、各方面への根回しを終え、家老たちはようやく主君押込を決行することができるのです。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)