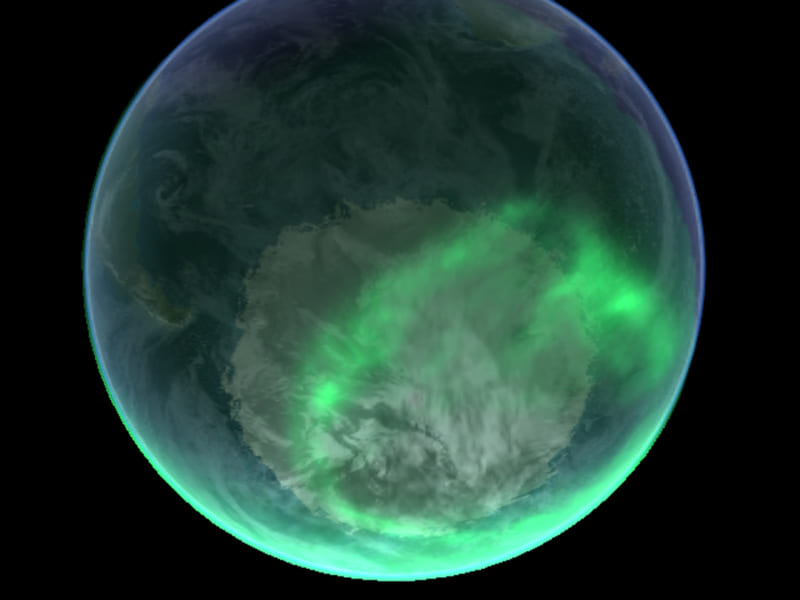無性愛はどうやって生まれるのか?
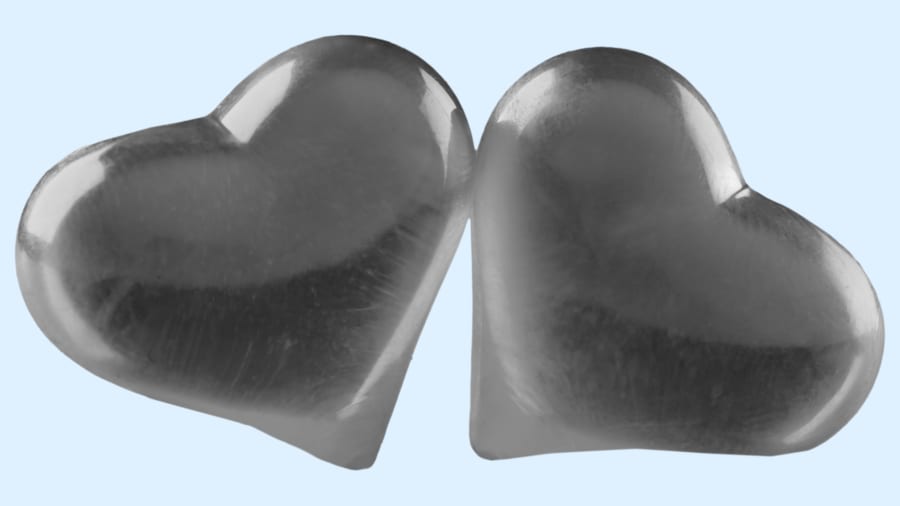
本研究では、まず世界各国から1,634名という比較的大規模なサンプルを集め、参加者一人ひとりにオンラインで詳細なアンケートを実施しました。
このうち、無性愛者が366名、ゲイ・レズビアンが276名、バイセクシュアルが267名、異性愛者が725名という内訳です。
アンケートの内容は、「自身がどのような性的指向を自覚しているか」「兄弟姉妹は何人いて、年上・年下どちらが多いのか」「どのような家庭環境で育ってきたのか」など多岐にわたります。
ここでユニークなのは、ただ単に「兄弟姉妹が多いか少ないか」を調べるだけでなく、たとえば「姉が何人、兄が何人いるのか」「自分が何番目に生まれたのか」まで細かく区別したうえで統計的に分析を行った点です。
しかも、その分析には最新の手法が2種類(Ablaza らの方法と Khovanova の方法)使われました。
一般的な分析では、兄が多いのか、姉が多いのか、あるいは家族の総人数が多いのかなどがごちゃ混ぜになってしまい、どの要因が本当に性的指向に影響を与えているのか判別が難しくなります。
ところが今回の研究では、こうした背景要因を細かく分けて見られるような工夫がなされたため、「兄弟姉妹の数の影響」と「性別や出生順(兄か姉か、何番目か)の影響」をある程度切り分けて判断できるようになったのです。
なお、フラテナル・バース・オーダー効果に関しては、Ablaza らの手法では有意な結果が得られなかったものの、Khovanova の手法ではゲイ男性においてのみ有意に確認されるなど、分析方法の違いによるばらつきも見られました。
結果として最も注目を集めたのは、“男性の無性愛者”に関するデータでした。
調べてみると、兄弟姉妹の総数が多い男性ほど「無性愛である可能性が高まる」という傾向がはっきりと浮かび上がったのです。
たとえば、兄が多いか姉が多いかにかかわらず、とにかく家族の人数が多い男性は、無性愛を自認する割合が高いというわけです。
一方、女性の場合は、「姉が少ない」「一人っ子である」といった条件が、無性愛である傾向と関連していたという興味深い結果が得られました。
また、バイセクシュアルの男性では兄弟姉妹の総数が多いほどその傾向が高まったり、バイセクシュアルの女性では姉が少ないほどその可能性が上がるなど、指向ごとに異なるパターンも見られました。
既存の研究でしばしば話題になる“フラテナル・バース・オーダー効果”や“ソロラル・バース・オーダー効果”に新たな視点を加える形になったという意味で、非常に興味深い結果といえるでしょう。
なぜこの研究が革新的といえるのか?
最大の理由は、まだまだ手探りだった「無性愛と家族構成の関係」を、ここまで大規模かつ精密なアプローチで取り上げた点にあります。
これまでは、たとえば男性同性愛と兄の数の関連が盛んに議論されてきた一方で、無性愛にまで踏み込んだ研究は非常に限られていました。
しかも、今回の研究では同じ人々を「無性愛」「同性愛」「両性愛」「異性愛」に分け、さらにその兄弟姉妹構成を徹底して分析しているため、さまざまな性的指向を横並びで比較できるデザインになっているのです。
こうした包括的な視点は、性的指向に関する研究ではまだ珍しく、得られたデータが今後の議論や追加調査に役立つことが期待されています。
端的に言えば、本研究は「無性愛にも出生順や兄弟姉妹の多さが関係する可能性がある」という仮説を、より確かなエビデンスで示した初めての試みといえるでしょう。
その意味で非常に画期的であり、性的指向の形成要因をさらに深く探る次のステップとして、大きなインパクトを与える結果となっています。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)