無性愛が生まれる仕組みを解き明かす

今回の研究は、無性愛も含めたさまざまな性的指向と「兄弟姉妹の構成」が、思った以上に深く結びついている可能性を示唆しています。
なかでも、男性の無性愛者には「家族の人数が多い」という背景が見られる傾向があったり、女性では「姉が少ない(一人っ子の場合も含む)」ほど無性愛になりやすいかもしれないという点は、とくに目を引く発見です。
しかし、だからといって、「兄弟姉妹が多いと必ず無性愛になる」「姉がいない女性はみな無性愛になる」といった単純な結論が導けるわけではありません。
実際、同じ大家族のなかでも、ある兄弟は異性愛者、別の兄弟は無性愛者というケースはいくらでも考えられます。
それでも、こうした統計上のパターンが浮かび上がったことには大きな意義があります。
これまでは、男性同性愛と「兄が多い」ことのつながり(フラテナル・バース・オーダー効果)が注目されてきましたが、それだけでは説明しきれない部分がたくさん残されていたからです。
たとえば、「女性の高い生殖力(female fecundity)仮説」のように、母親やその家系が多産である場合に、非異性愛の男性が生まれやすくなる可能性があるという考え方も、無性愛者の存在を踏まえると、さらに複雑で面白いテーマへと展開していくかもしれません。
無性愛にも関係する可能性:胎児期のホルモンや生理学的要因
では、同性愛以外の非異性愛、たとえば無性愛に関しても同じような胎児期ホルモンの影響があるのでしょうか。実はまだ結論を出せるほどのデータは少ないものの、近年の研究では「あらゆる性的指向は、生物学的な要因と社会・心理的な要因が掛け合わさって成立する」という考え方が一般的になりつつあります。無性愛に関しても、胎児期のホルモン分泌や母体免疫の影響を受けて、脳の“性欲や性的興奮”をつかさどる仕組みが変化する可能性があるという仮説は否定できません。
一部の研究では、無性愛者のホルモンレベル(テストステロンやエストロゲンなど)を測定して、異性愛者・同性愛者と比べて統計的に明確な差があるかどうかを調べようと試みています。しかし、現在までのところ「ホルモン値が常に一般的な基準と異なる」といった決定的な結果は報告されていません。むしろ、無性愛者でもホルモン値は一般的な範囲に収まるというケースがほとんどで、「脳が性的刺激をどのように処理するか」や「性欲を生じさせる神経経路の感受性」といった、より微細なレベルでの違いが関与している可能性が考えられています。たとえば、性的刺激に対する脳活動を計測する研究などでは、無性愛者の脳が性刺激に対して他の人よりも低い反応を示すケースが見られる一方、まったく変わらない人もいて、まだまだ研究者を悩ませている状況です。
もちろん、ホルモンや遺伝といった生物学的な要因も無視できず、今後は多角的な視点で研究を進める必要があるでしょう。
研究者たちは、こうしたパターンがどのような仕組みで生まれるのかを解き明かすには、まだまだ多くのデータが必要だと考えています。
たとえば「なぜ姉や兄が増えると、ある性的指向が生まれやすくなるのか」という疑問に対しては、胎児期のホルモンや母体免疫だけでは説明できないかもしれません。
家族の中での役割分担や、兄弟姉妹間の力関係、コミュニケーションの取り方など、社会的な影響も大きい可能性があります。
今回の研究に参加したのは主にシスジェンダー男女であり、ノンバイナリーやトランスジェンダーなど、多様なジェンダーの人々は分析対象外になっている点も今後の課題でしょう。
さらに、人種的に白人が中心のサンプルであるという点も含め、文化的背景の違いによる影響を検証する必要があります。
研究者たちが今後さらに多様なサンプルを集め、文化的背景やジェンダーの違いも含めた検証を進めていけば、無性愛やその他のセクシュアル・マイノリティが生まれるプロセスがより鮮明になっていくはずです。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)




















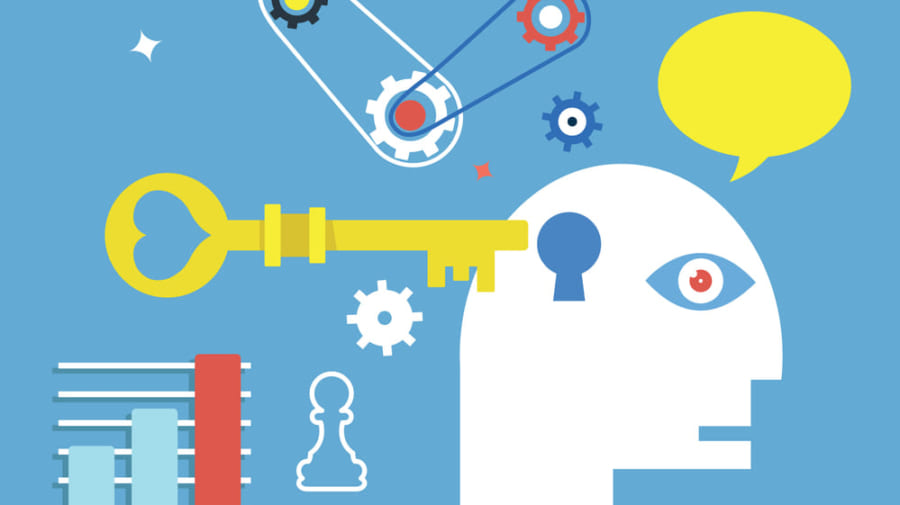







男性と女性で起きてることが違うというのが面白いですね。
男に関しては男性同士の過剰な競争で共倒れになる確率を下げるための安全装置がある
で説明がつくような気がします
男だらけの環境だったら男同士カップリングし
個体数そのものが多すぎたら無性愛になって繁殖しなくなることは
群単位で見れば適応度が上がる気がする
幼馴染に性的感情持たないウェスターマーク効果しか知らなかったのでそこから数段上の知識を得られました。他に昔聞いた話で「倫理的に潔癖だとゲイになる」という説があるけどその理由は何十年経った今も分かりません。
あまり馬鹿な論文発表しないで欲しい。ややもすると、情報操作ではないかと——-。
僕は兄弟多いけれど、チャンと大人の女性を好きになったぞ。生物学的に男を好きになったことはないし少女を好きになったこともない。タイプの女性でも、人前ではその素振りは見せないようにしていますが。
兄弟が多ければ、小さい時から金銭的とか大変な環境が多い可能性が高い。あるいは僕の背景を知ってか理不尽な言動で対応してくるのが何名かいた。そういうクソ野郎には言葉で年上だろうとある一線を超えて攻撃してきた時はどやしつけた。現在のネットニュースでの選挙をめぐる事件などをみても、最低その位の対応をしなければ相手はやめなかっただろう。本当にクソ野郎は多い。こちらから殴り合いになっても警察沙汰になるだけで損するだけだから。損することは元来嫌いなのです。陰湿なのが多い。
ところで生物学を専攻なさっているようだからよくご存知でしょうけれど、家系で頻発する病気ってあるでしょう。逆の見方で、例えば一つ取ってみるとうちはガン家系ではないようです。兄弟が多く還暦とうに過ぎているのだからそう言い切れるでしょう。皆元気です。
プライベートライアンなどが好きでしたか。ナチスは戦争に負けたけれど理にかなった点も少しはあったかもしれません。