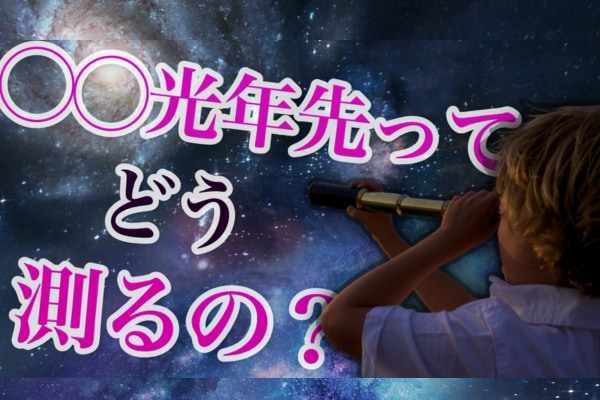火との共存によって人類の遺伝子は書き換えられていた

人類はどのように軽い火傷へ「適応」したのか?
謎を解明すべくロンドンのインペリアル・カレッジなどの研究チームは遺伝子レベルでの分析を行いました。
彼らは人間と他の生物の火傷時の遺伝子の働きを比較し、人類特有の進化の痕跡を探したのです。
具体的には、火傷を負った人間とラットの皮膚で活性化する遺伝子群に注目し、その中でヒトとチンパンジーの間で進化の速度に差がある遺伝子を絞り込みました。
その結果、約94種類の遺伝子が火傷に対する反応として人とラットで共通して変動しました。
ですがそのうち10%ほどの遺伝子にヒト特有の正の選択(有利な変異が蓄積した形跡)が見られました。
通常、無作為な遺伝子変化で正の選択が起こる割合は数パーセント程度とされるため、これは統計的に有意な偏りと言えます。
進化の兆候が確認された遺伝子には、傷口への免疫細胞の呼び寄せや炎症反応の制御に関わるものが多く含まれていました。
例えば次のような遺伝子が挙げられます:
CXCR1:白血球(好中球やマクロファージ)を傷ついた組織に呼び寄せるシグナルを出します。
TREM1:免疫細胞の炎症シグナルを増幅する受容体タンパク質をコードします。
OASL:抗ウイルス物質であるインターフェロンの作用を強化します。
これらはいずれも火傷後の感染予防や治癒促進に重要なプロセスであり、人類の系統でこうした遺伝子に変化が蓄積していた事実は、火傷への適応進化を裏付けるものと言えるでしょう。
さらに興味深いことに、この研究では人類の集団間(アフリカ、ヨーロッパ、東アジア)の遺伝情報を比較し、火傷関連の遺伝子に地域ごとの選択の偏りが見られるか調べました。
その結果、地域によって異なる遺伝子に進化の痕跡が示唆されました。
例えば、アフリカ集団では創傷治癒や瘢痕形成に関連する遺伝子に特徴的な選択のシグナルが見られました。
この結果から、たとえばアフリカの集団は露天のかまどや金属・陶器づくりなど、高温に直接触れやすい「点的・高温接触火傷」が多かったため、早く硬い瘢痕を作って傷口を閉ざすことが有利だった……というような推測が成り立ちます。
一方、ヨーロッパ集団では免疫細胞の動員や細胞膜修復に関与する遺伝子に特徴的な選択のシグナルが見られました。
こちらからは、寒冷なヨーロッパ地域では長い冬に屋内で火を絶やさず維持する文化が発達し、飛び火や小さな煤火で「慢性的・低温の擦過火傷」が繰り返し起こったため、素早い炎症誘導と細胞膜の微小修復が選好された……という推測が可能です。
研究チームも、これが過去に地域ごとで火の利用方法や頻度が異なっていた歴史を反映している可能性があると述べています。




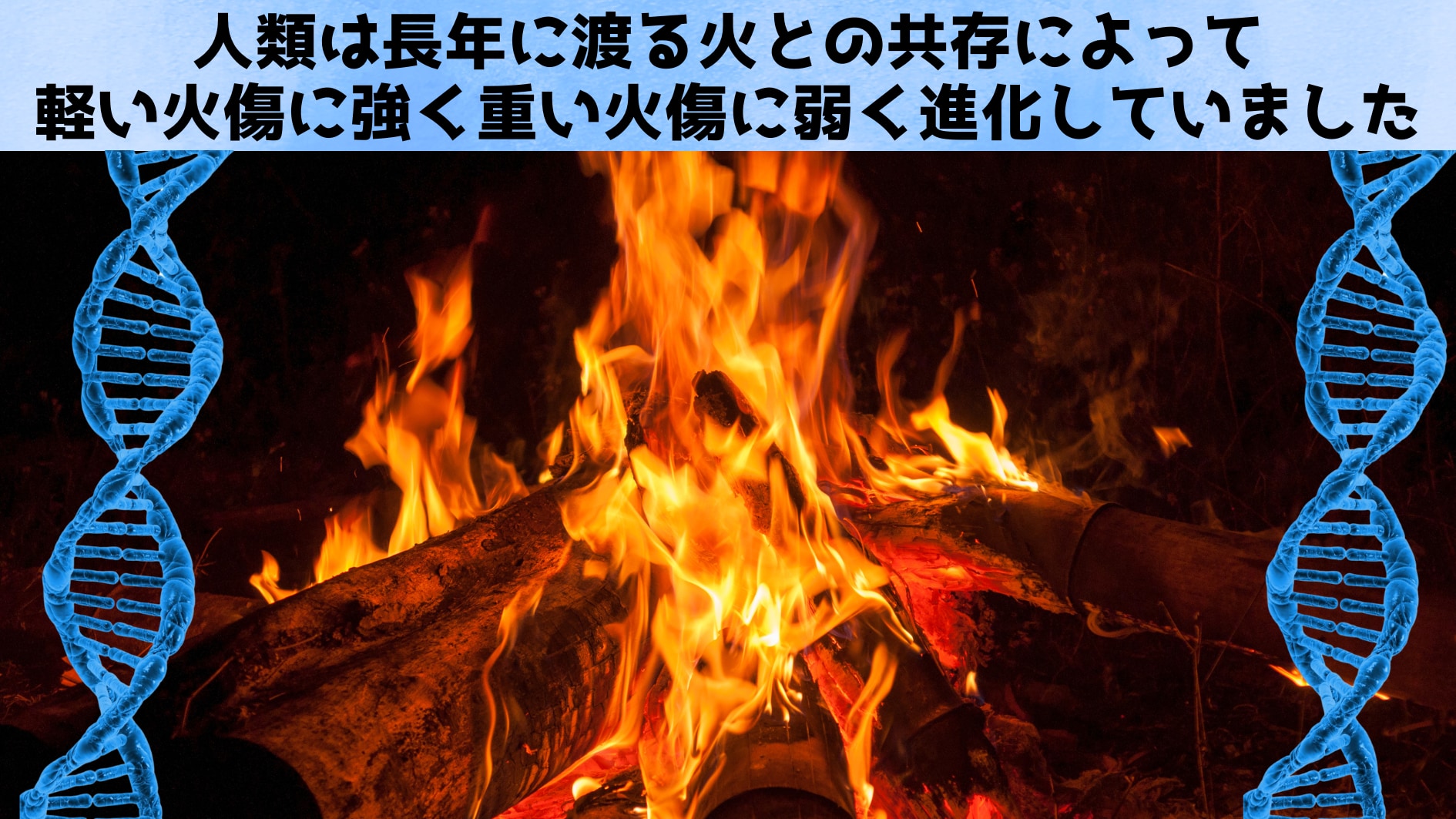

























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)