素早い進化は突然変異が原因ではない
私たちが「進化」と聞いて思い浮かべるのは、たいてい「突然変異によって新しい性質を持つ個体が現れ、それが自然選択によって広がる」というイメージです。
たとえば、キリンの首が長くなったのは、あるとき偶然に首の長いキリンが生まれ、木の高い場所の葉を食べられたから…というような話を、学校で習ったことがあるかもしれません。
このような考え方では、「進化=新しい遺伝子(突然変異)が生まれること」が出発点になります。新しい性質が“生まれる”ことこそが、進化の第一歩だというわけです。
ところが今回のキリフィッシュの研究は、まったく違う進化のあり方を示しました。
彼らが毒に強くなったのは、突然変異によって新しい性質を獲得したからではありません。もともとその魚の集団の中に「毒に強くなりやすい体質」を持つ個体が少しだけ存在していて、それが川が毒で汚染されるという強いプレッシャーによって選ばれた結果だったのです。
このような「もともと持っていた遺伝的なバリエーション(=多様性)」を使って進化する仕組みは、専門的にはstanding genetic variation(既存の遺伝的多様性)に基づく適応と呼ばれます。
つまりこの研究が突きつけた問いは、「進化とは新しいものを作ることではなく、すでにある選択肢の中から何を選ぶか」ということなのです。
そして、それがいかに早く起こりうるかということも示されました。遺伝子の引き出しが多い集団であればあるほど、環境の変化に対してすばやく反応し、生き残る道を見つけやすいということです。
多様性という形で遺伝子を保持しておく意味
しかしここで、素朴な疑問が浮かぶかもしれません。
「毒に強い体質がそんなに役に立つなら、最初からそういう魚だけで集団をつくればいいのでは?」
確かに日本の川でもよく見かけるコイ(鯉)は、汚染に強い魚として知られていて、汚れた用水路なども平然と泳いでいる姿を見かけます。彼らはキリフィッシュとは異なり、もともと汚染に強い生物です。
なので、毒や汚染に強い遺伝子があるなら、最初から集団内で共有されているはずじゃないかと考えるのは、もっともな疑問です。けれど、進化の視点から見ると、この考え方には落とし穴があります。
進化では、「いつでもどこでも強い性質」が選ばれるわけではありません。ある性質が“有利”か“不利”かは、まわりの環境によって絶えず変わるからです。
たとえば、こんな人間の例を想像してみてください。
ある人が、どんなに小さな音にも気づくほど鋭い聴力を持っていたとします。騒がしい工事現場では、その人は周囲の変化にすぐ気づけるのでとても頼りになるでしょう。でも、静かな図書館では、わずかな物音にも反応してしまい、集中できずに困るかもしれません。
このように、「敏感であること」が良いか悪いかは、その人がどんな場所にいるかでまったく変わってしまうのです。
魚の場合も同じです。キリフィッシュが住んでいた川がまだきれいだった頃、毒に過剰に反応しない“鈍感な体質”はむしろ不利だったかもしれません。体に入ってきた小さな毒物に気づかず、処理が遅れて体調を崩してしまうからです。
でも、川が汚染されてしまったとたん、逆に“鈍感な体質”の方が生き残りやすくなりました。というのも、センサーが働きすぎると、かえって体に負担をかけてしまうからです。キリフィッシュたちは、もともと集団の中にいたさまざまな体質の中から、「いまの環境に合った体質」が自然と選ばれていったのです。
進化とは、つねに環境に合わせて「ちょうどよく」調整される現象です。「最強の体質」ではなく、「その時、その場所で生き残れる体質」が選ばれるのです。
つまり、持っていた方が有利だが、環境によってはデメリットになってしまう特性が、遺伝的多様性という形で保持されることで、環境が変化したときに素早く適応できる進化に繋がっているのです。
これをのんびり突然変異を待っていたのでは、環境に適応する前に種が全滅してしまうかもしれません。
当然環境に合わない遺伝子を多様性の名のもとに保持させられた個体は、それが不要な時期には何らかの不自由を味わっていたかもしれません。しかし進化というプロセスは、「一部の個体が犠牲になること」を前提としています。
進化は、いつも長い時間をかけてゆっくり進むとは限りません。場合によっては“新しいもの”ではなく、“すでにある多様性”を利用した急速な進化が起きるのです。
そして、その多様性は魚だけでなく、私たち人間の体の中にも、きっと眠っているのです。



























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)























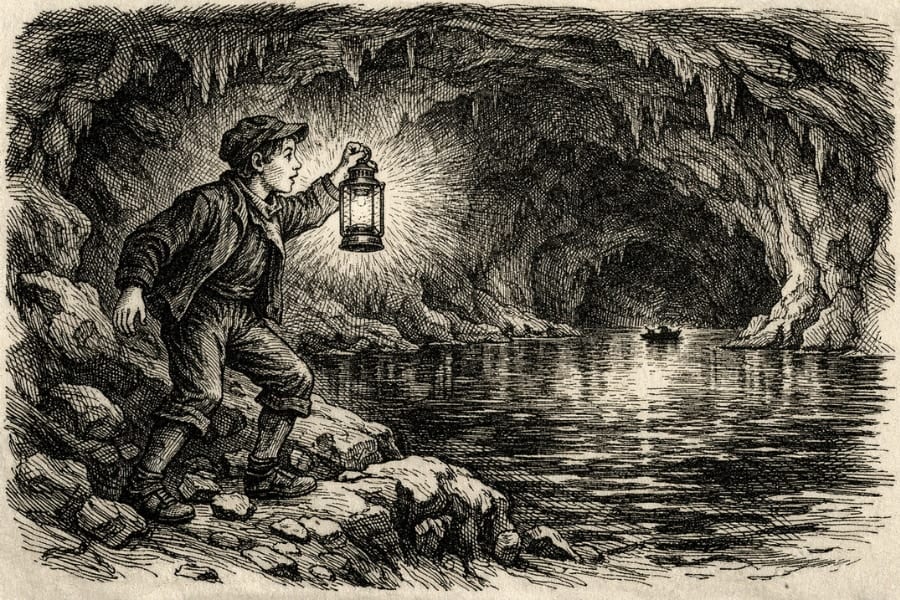




強い個体が生き残ると言うより生き残った個体が強いということで。
進化のスピードは、基本大陸が動くスピードじゃないかなぁ。その位のスピードの環境の変化なら生物はなんとか適応できる。
しらんけど
何だか人間社会にも当てはまりそうな話で(文中でも例えで人を例に出していましたが)考えさせられてしまいました。
来るべき危機の時代に備えて、平常時には不利な特性を保持させられる個体とか。
生命(人生)とは何のためなのか。
個(あるいは一定集団)の幸福はどうなる?とか。
こんな事を悩むのも人間だけなのか。
そりゃ急激な環境変化への適応なら既存の形質からの選択じゃなきゃ間に合わないのは当然
突然変異は適応よりも種の中に限った環境変化を「引き起こす」側で意味が違うし
だから環境が安定してると突然変異は淘汰されるケースが多いでしょ、細菌なんて日常茶飯事だからね
突然変異は形質に現れなかったり、あまり意味を持たない場合が多いそうです
もちろん生存や繁殖に関わる場合は淘汰されるからですが
そうでない部分へ変異が蓄積されていくことで、安定した環境下においては種の遺伝的多様性がむしろ増すようですね
なんかクリアになった
生物種は広がりをもって存在していて
安定した環境下では、その分散は拡大していき
いざ生命に関わるような環境の変化が起きると、その分散の縮小とともに残った部分に平均が動く
勝手に動いていくのが性選択とかバイアスとか
遺伝的アルゴリズムも確かに同じ仕組みで動いている
もっと露骨なやり方だけど
怠惰で太りやすい体質も、飢饉の時には役にたってた遺伝子なんだろうなぁ
マツコデラックスの唾液はデンプンの分解性能がやばいそうで
今更すぎる当たり前の話だな
だから多様性というのは本来淘汰のプールとして肯定されるものなんだよ
ただ無条件にそこにあることを肯定するのは多様性の意義を履き違えている
人類っていう一つの種なのになんで肌の色とか身長とか顔の形とかが違うんだろうって思ってたけどこういうことが
全く説得力がありません。
何の科学的エビデンスが紹介されているわけでもないので。
中立進化による遺伝的浮動性の証例がまた一つ増えたことは素直に喜ぶべきことであろう。ただ同時に、同種はおろか、他種にさえ、あまりに多くの人為的な選択圧を与えているホモ・サピエンスという生物の業の深さを自覚すべきではないのかとも考える。また、生存に有利不利にかかわらず、遺伝子のストックが多いことに越したことはないと知りながら、遺伝子の擾乱を招くような乱獲、棲息域外への動植物の異動といった過度の生態系への干渉が、多くの生物を絶滅又はそれに近い状況に追いやっていることについて、警鐘を鳴らすことはしないのかと記事の締めにも疑問を呈したい。