重力再定義:アルゴリズムか、基本力か

重力を宇宙における情報最適化の手段と捉えることには、驚くべき意味合いがいくつかあります。
まず、情報は物質やエネルギーと同様に、物理的現実の基本的な構成要素であるという主張を強め宇宙現象に対する新たな視点を提供することになります。
例えば、ブラックホールの深い重力井戸は情報圧縮の極端な例である可能性があり、暗黒物質/エネルギーの謎は情報理論的に説明できるかもしれません。
ヴォプソン博士の枠組みが、重力と量子情報理論の間に新たな橋渡しとなり、計算と現実が交差する物理学の統一的理解に一歩近づく可能性もあります。
一方で、この考え方はまだ推測の域を出ず、限界もあります。
私たちの宇宙が「計算的」であるかどうかをどのように検証できるでしょうか?
新たな研究が作成したモデルはニュートンの万有引力の法則を見事に再現し、一般相対性理論と原理的に整合しているように見えますが、最終的な結論を出すにはさらに具体化する必要があでしょう。
というのも現在の研究は、相対論的効果や量子重力をまだ取り入れていないからです。
今後の研究では、この考えを確固たるものにする(あるいは反証する)ために、いくつかのステップに取り組む必要があります。
必要とされる具体的なステップ
モデルを新たな領域に拡張する:情報アプローチが依然として有効かどうかを検証するために、相対論的条件(高速で移動する物体、非常に強い重力)と量子スケールの下で理論を構築する必要があります。
検証可能な予測を行う:重力が本当に情報圧縮によって生じるのであれば、観測可能な微妙な違いや現象はあるでしょうか?実験的または天文学的な検証の可能性を提案する必要があります。
既存の物理学との整合性:この概念は、従来の物理学における謎と合致するか、あるいはそれらの謎を説明できるものでなければなりません。宇宙がなぜこれほど高い対称性を持つのか(これは情報効率の高い状態である可能性があります)、あるいは情報の観点から重力が他の基本的な力とどのように相互作用するのかについて、新たな知見が得られるかもしれません。
文字通りのシミュレーションの中にいるかどうかに関わらず、宇宙を計算論的な観点から考えることは、非常に優れた洞察を提供してくれます。
少なくとも、ヴォプソンの研究は、情報を実体、つまり現実を形作るものとして扱うという物理学の新たな潮流に加わるものです。
もしかしたら重力の真の正体は時空構造に埋め込まれ、宇宙のデータを休むことなく圧縮し続けるアルゴリズムなのかもしれません。




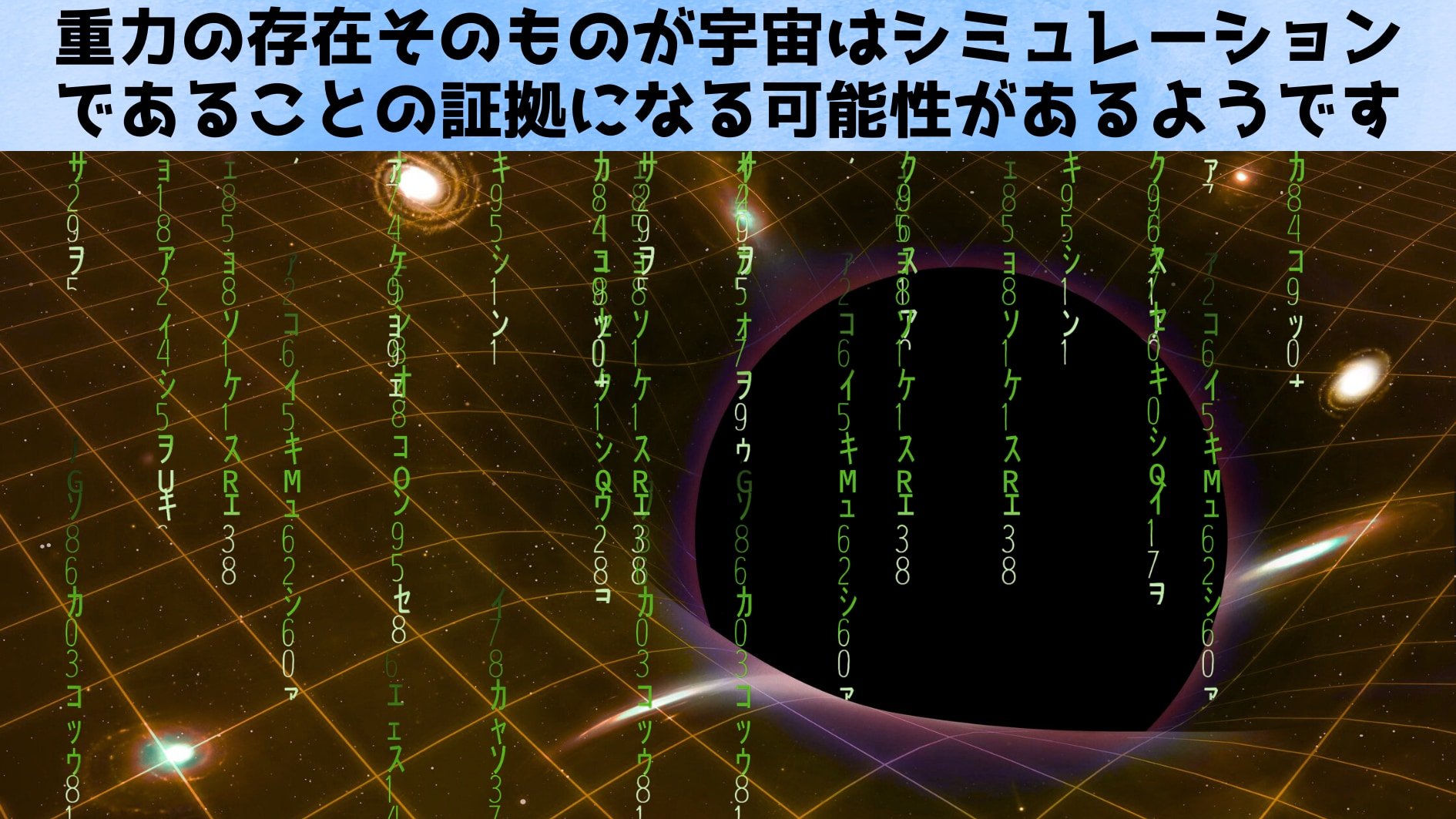
























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



















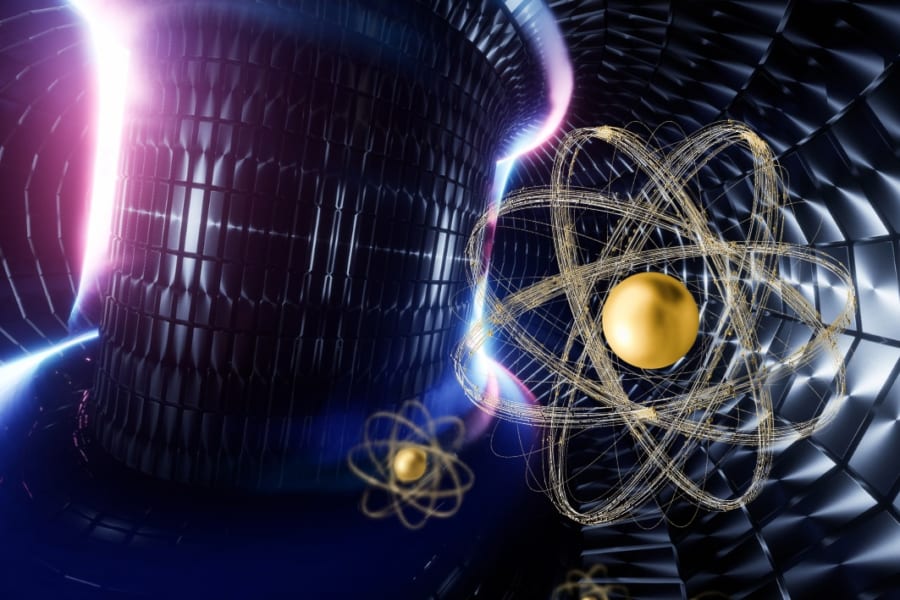








Received:
February 12 2025
Accepted:
March 28 2025
こんな短期間でマトモな査読がされたとは思えないんだけど
質が高い査読者は当然こんな論文もどきの査読を拒否するから
質の低い査読者を引き当てるガチャ
このような「完全に新規な物理学理論」がちゃんの査読されるには半年〜1年半はかかる
内容を見ればこのヴォプソンという人間が書いた「情報力学」を自己引用して正当化したいくつかの論文しか根拠がない
つまり第三者が「情報力学」の有用性を認めて発展させた痕跡が存在しない
こんな論文もどきを読むならSFの方がマシ
まだ面白いからな
デタラメで面白くないならSF以下で、そんなのに税金が使われる英国市民が可哀想だが
そういう知的詐欺を見抜けない市民に責任があるというのが民主主義
そもそも熱力学第二法則で熱力学的エントロピーが増大するケースは
「分子的混沌の仮定」により人間が粗視化という近似を入れたときのみに成立する事はボルツマンのH定理論文に書かれている
なのでエントロピー増大法則は「この宇宙の持つ性質」ではなくて
粗視化の近似モデルが持つ性質に過ぎない
通俗本やメディアにはこのようなことは書かれておらず、ボルツマンの原論文をちゃんと理解して初めてわかる
このヴォプソンという著者はエントロピーに対して通俗本レベルの理解しかしてないので
熱力学エントロピー増大がなぜ起こるのか理解してない
それは粗視化の近似が情報を捨てるから怒るだけなので何も謎などないし解明するべきこともないし
情報力学とやらはその根本からして全く意味がなく必要がない
それを出発点にしたこの「論文」も全く意味がない
「情報力学」を誰も利用せずに自己引用しかないのはそれに有用性がなく利用価値が無いから(実用上の話ではなくて学問的に有用性がない)
論文よろ
いやこの記事何も説明してないし、論文もないのはわかる
エントロピーに対しての理解がないとする根拠は、めんどくさいので無視
理解してると期待した場合、この記事で「紹介」されようとしてる内容の飛躍部分を埋める論理は
一応ありえる。これも、説明するには論文レベルのめんどくささがある。
ただそれだけ
もし宇宙が情報をひたすら圧縮しているのであれば、その圧縮アルゴリズムを解析してコピーすればおそらく高効率かつ高速演算可能なチート圧縮アルゴリズムを人類が手に入れることも…。
今の圧縮アルゴリズムは全てをそれでという万能のものはないわけですが、おそらく宇宙が採用しているものは音声であろうが動画であろうがテキストデータであろうが同じアルゴリズムで超圧縮しているのでしょうから。
宇宙がシミュレーションだという仮説は70年代からあるよね。そもそも時空には最小単位、プランク定数があり、相互作用とは演算そのもの。ブラックホールのように演算の密度が上がると処理落ちせず時間が伸びて解決される。
コンピューターの方が宇宙の劣化模造品なのだから、当たり前といえはあたりまえ。
処理落ちの結果が時間の伸びとして観測されるのかも。
宇宙がシミュレーションかどうかはさておき、重力の背後にあるメカニズムの説明としては
・物質(素粒子)の存在確率が「何らかの影響」を受けている
・そのため物質は存在確率が高くなる状態を確率的に選択してゆく
・それを大域的に見ると物質間に力が働いているように見える
ということなのだと思います。
その「何らかの影響」というのが情報圧縮だとヴォプソンは主張しているのでしょう。そしてシミュレーションしてみたら再現できた、と。
可能性の一つとしてはアリな気がします。
でも情報圧縮が起きる原因を「宇宙がシミュレーションだから」としてしまうと科学ではなくオカルトになってしまいますね。
最近宇宙論で新しいものがバンバン出てくる
何が正しくて何が間違ってるのか
まだそれは分からんか
既存の宇宙論、物理学が通用しなくなってたり
量子力学でどんどん進歩してる感じで
新しい物理学が生まれてくるのが必然なのか
この種の話って後出しジャンケンみたいな形で新説が出続けるので、永遠のイタチごっこになるんだよなぁ
前提となる量子スケールだが、今の人類には量子の観測で手一杯だけど更に天文学的に分解能を上げると、この程度の計算機では計算できないような緻密な世界が広がってるかもしれない
その頃には人類の根幹技術として、シミュレーションの上位バージョンのハイパーシミュみたいな概念ができてるかもしれないが、そしたらそしたで宇宙はハイパーシミュでできているとか言うやつが絶対出てくる
結局の所、宇宙…というより『宇宙像』はその時代の人が思いつく程度の概念でできている
これはアナロジー的モデルを作ったにすぎないのでは?
高速で回転するものに引き寄せられているのであって圧縮とは別では無いかと思っています
物体が散乱して乱雑になっていくのがエントロピーが増大するって事なんだからエントロピーが減少してゆくなんてパラメータを設定したらそりゃ勝手に纏まっていくよなぁ…と思うんだけど
このジャーナルAIP Publishingは査読が怪しいハゲタカです。
この記事を書いた川勝康弘という人は他にもArXivという査読なし論文投稿サイトから論文を引っ張ってきて記事を書いてます。
全般的に信用できませんね。
宇宙は何でも有りなんです想いつくもの・😃😂😂
例えば電磁気学では電子の振る舞いや力の説明が具体的に数式を使って計算でき、現実の物理現象を操作することができる。
が、この理論だと宇宙が大きなコンピュータであるとして、そのコンピュータが情報を圧縮しようとしている。うん、わかった。なるほどなるほど、じゃあ重力を強くしたり弱くしたりするには?はい!使えませーん。
実際、熱の場合は熱の第二法則のおかげで熱の特性から様々な装置が作られた。だが、この情報を圧縮しようとしているその源は?結局人間が都合良くプログラムした結果をみているに過ぎない。圧縮しようとしている作用そのものが利用出来ないではないか?
粒子をまとめようとする仕組みであるなら、重力崩壊や超新星爆発はどうしておこる?