食事に頼らなくても腸内細菌は脳活動で変わる

今回の研究は、「腸内細菌叢は食事など受け身の要因で変わるもの」というイメージを覆し、脳が能動的にその構成を素早く作り替えられる可能性を示しました。
言い換えれば、腸と脳の対話は単なる一方向ではなく、脳から腸への指令という新たな連絡経路が存在することが明らかになったのです。
専門家らは、これは腸内細菌叢研究におけるパラダイムシフト(発想の転換)であり、脳と腸のネットワークが想像以上にダイナミックに連携していることを示すものだと指摘します。
イメージとしては、脳がオーケストラの指揮者となり、状況に応じて「腸内細菌オーケストラ」のメンバー構成を即興で入れ替えているかのようです。
例えば空腹時には、脳がある種の細菌に「出番です」と合図し、食後には別の細菌に「次は君たちの番だ」と指示しているのかもしれません。
こうした即時の編成替えによって、毎日の食事サイクルに合わせた最適な消化・エネルギー収支が実現している可能性があります。
研究者たちもこの発見の意義について強調しています。
共同研究者のルーベン・ノゲイラス氏(スペイン・サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学)は「これらの発見は、腸内細菌叢が他の臓器と情報をやり取りする仕組みに関する現在の定説に疑問を投げかけるものです。」と指摘しています。
本研究を主導したマルク・クラレット氏(IDIBAPS研究所)は「今回の結果は、脳と腸内細菌叢と代謝の関係を理解する上で役立つもので、将来的には代謝疾患や肥満に対する新たなアプローチへの道を開くでしょう」とコメントしています。
もちろん、今回の知見がヒトにもそのまま当てはまるかは今後の研究で検証が必要です。
しかし、空腹を司る神経回路やホルモンの仕組み自体はヒトにも共通するため、同様の脳-腸内細菌の連携システムが私たちの体内にも備わっている可能性は十分にあります。
もし将来このメカニズムを人為的に調節できるようになれば、脳を介した新しい腸内細菌叢コントロールという斬新なアプローチが、肥満や糖尿病といった代謝疾患の治療に役立つかもしれません。
実際、研究者らは脳神経への介入によって腸内細菌叢を操作し、健康に好影響をもたらす治療戦略の可能性に期待を寄せています。
腸内細菌叢は近年「もう一つの臓器」とも呼ばれるほど健康に重要だと注目されていますが、本研究はその腸内細菌叢が決して独立独歩の存在ではなく、脳という司令塔からの指令によりダイナミックに影響を受ける相棒でもあるわけです。
食べ物を介さずとも脳が腸内細菌叢を短時間で調節できるという発見は、私たちの体が持つ精巧な自己調節システムの一端を物語っているのかもしれません。




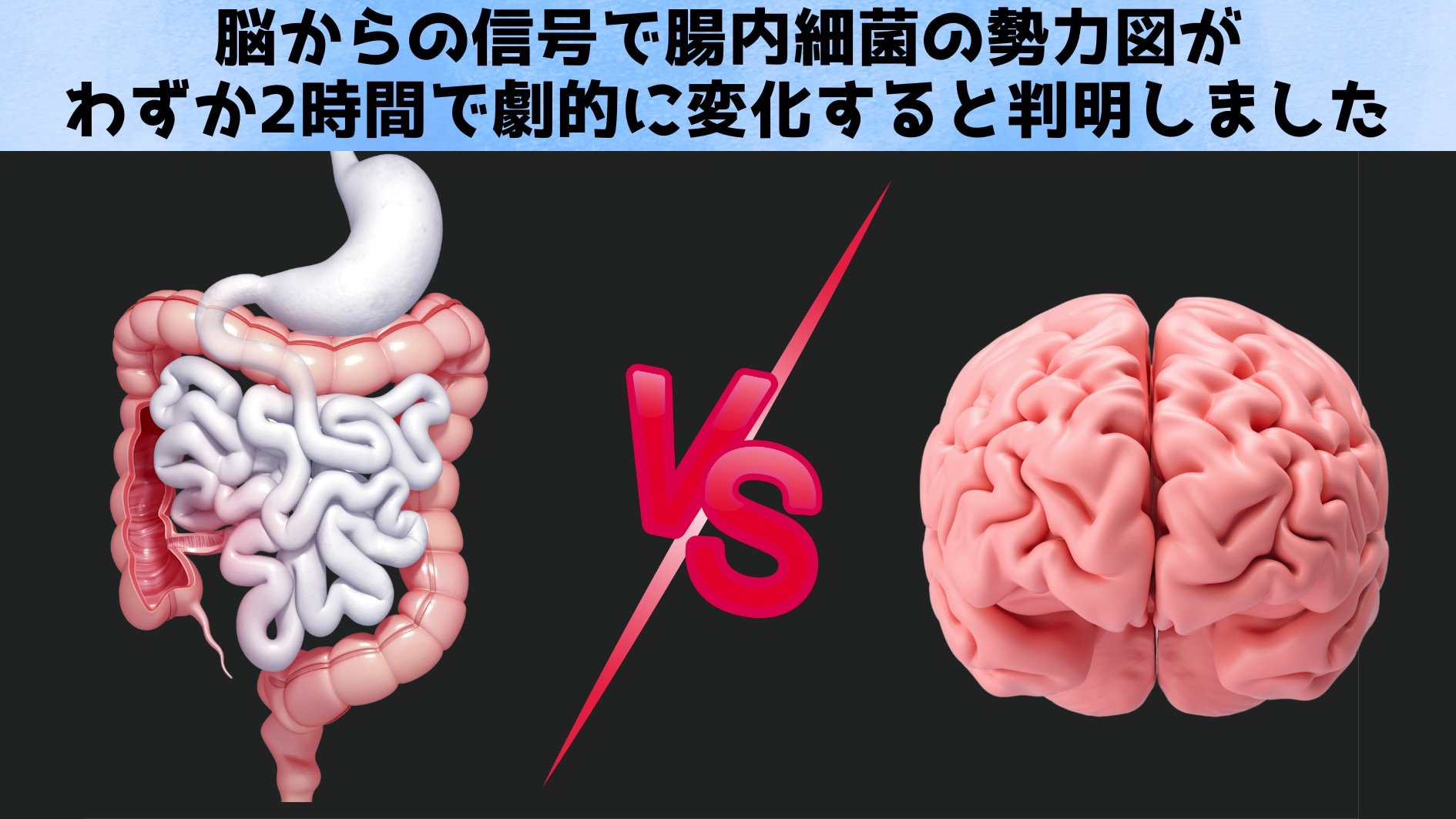
























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)




























腸内と同じ組成の細菌が脳内にいるという研究もありますから、そちらの細菌同士がやっているという可能性も…。
なんかすごい?色々複雑だよなぁ
近年の研究から、脳、ひいては動物(ヒトを含む)自体が腸内共生細菌の牧畜なのかもと思うところもあったが、やはりそこまで単純ではなかったよね
双方向のコミュニケーションの上で協力や対立をしながら共進化してるんだろう
ただ、内胚葉(腸管)が外胚葉(脳、神経、皮膚)より先に誕生したことを考えると、脳は腸と共生細菌の相互作用の結果として機能を備えているように思える