絵文字は言葉の省エネ──保守派のコミュ術?
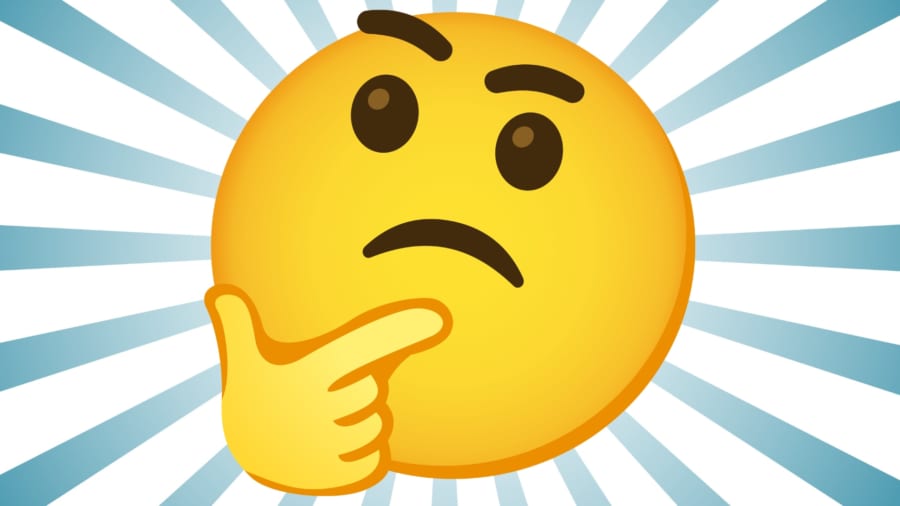
この研究から、「絵文字の多用」と「開放性の低さ(新しいものより慣れ親しんだものを好む傾向)」との関連が示されました。
ではなぜこうした傾向が生まれるのでしょうか?
筆者らは明確な因果関係までは断定していませんが、いくつか考えられる理由や示唆を述べています。
まず考えられるのは、絵文字という表現手段自体の性質です。
絵文字は直感的で分かりやすく、世界共通で通じやすい「具体的」なシンボルです。
高い想像力や抽象的な表現力を駆使しなくても、ニコニコマーク一つで「嬉しい気持ち」を手軽に伝えることができます。
新しい言葉をひねり出さなくても既存のアイコンから選ぶだけなので、ある意味「手堅い」コミュニケーションとも言えます。
こうした特徴から、普段から新奇な表現よりもお馴染みのやり方を好む人(開放性の低い人)は、文章を書く際にも絵文字という安定したツールに頼りがちなのではないか――そんな仮説が考えられます。
逆に開放性が高い人は、文章だけでユーモアを表現したり独自の言い回しを工夫したりする傾向があり、絵文字にあまり頼らないのかもしれません。
実際、本研究とは別に「開放性が高い人ほど長めの単語や専門的な語彙を使う」といった報告もあります。
絵文字多用派は語彙の豊かさがやや低い傾向があったという今回の結果とも照らし合わせると、開放性の高低で言語スタイルが異なる可能性が考えられます。
もう一つ、絵文字の役割についての示唆も興味深い点です。
絵文字というと一見、喜怒哀楽を直接表す感情そのもののように思われます。
しかし研究チームによれば、絵文字多用派の投稿から見られた感情表現の傾向はごく控えめで、必ずしも絵文字はストレートに感情を伝えているわけではないとのことです。
では人々は絵文字を何のために使っているのか?
その答えの一端として、著者らは「ネガティブな内容を和らげるために絵文字を使っている可能性がある」と述べています。
例えば「あなたとはもう二度と一緒に行かないからね(ニッコリ)」といった具合に、本来きつく聞こえる否定的なセリフでも、後ろに冗談めかした絵文字を付け足すことでトゲを抜く効果が期待できます。
確かに、絵文字には文章のトーンを調整する「緩衝材」のような役割があると日々実感するところではないでしょうか。
研究では絵文字をよく使う人は否定表現も多い傾向があり、さらに絵文字多用派は開放性が低いことがわかりました。
そのため否定的な言い回しに絵文字を添えて柔らかく伝える――このようなコミュニケーション術が背景にあるのかもしれません。
本研究は主に英語圏の若者(大学生)のデータに基づいており、文化や年代が異なれば絵文字の使われ方も変わってくる可能性があります。
著者らも「我々のサンプルは女性が多数を占めた。将来的には性別や文化による絵文字使用の違いについても研究が必要だ」と述べ、結果の一般化には慎重さを示しています。
実際、日本語圏では顔文字やスタンプ文化も根付いており、英語の絵文字とはまた違ったコミュニケーション習慣があります。
こうした違いが性格特性との関連に影響するのか、今後さらに研究が進められるでしょう。
では、この研究結果にはどのような意味や活用が考えられるでしょうか。
例えば、人材採用やマーケティングの分野では、SNS上の言動からその人のパーソナリティを推測する試みが行われ始めています。
もし絵文字の使用頻度が一つの性格シグナルとなり得るなら、将来的にAIが応募者の投稿から開放性の高低を推定するといったことも理論上は可能かもしれません。
(もっとも、性格を読み取られることにはプライバシーや倫理の問題も伴いますが…)。
いずれにせよ、本研究はデジタルコミュニケーション上の何気ない振る舞いに、私たちの内面が表れている可能性を示した興味深い一例と言えます。




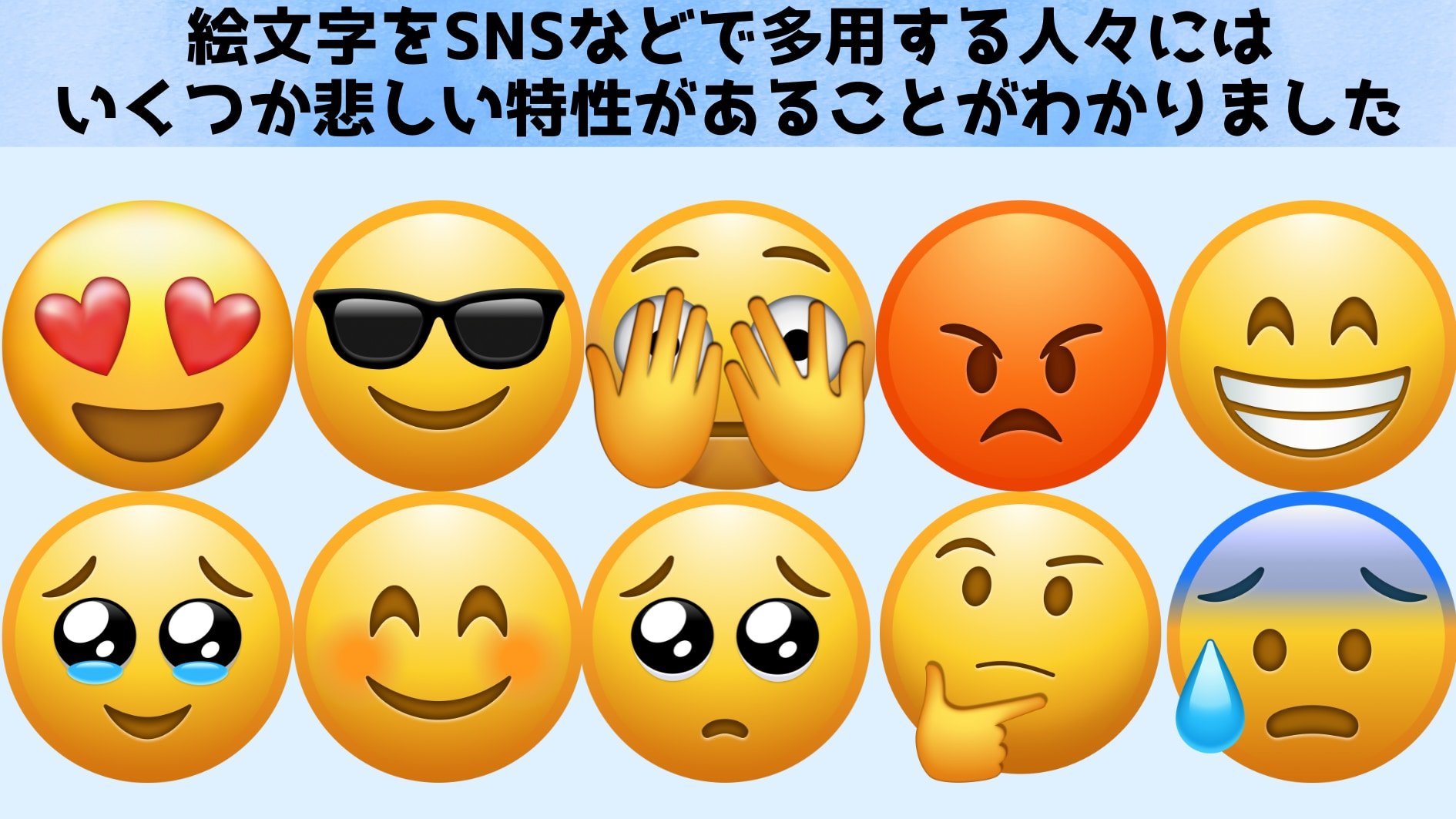



























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)




















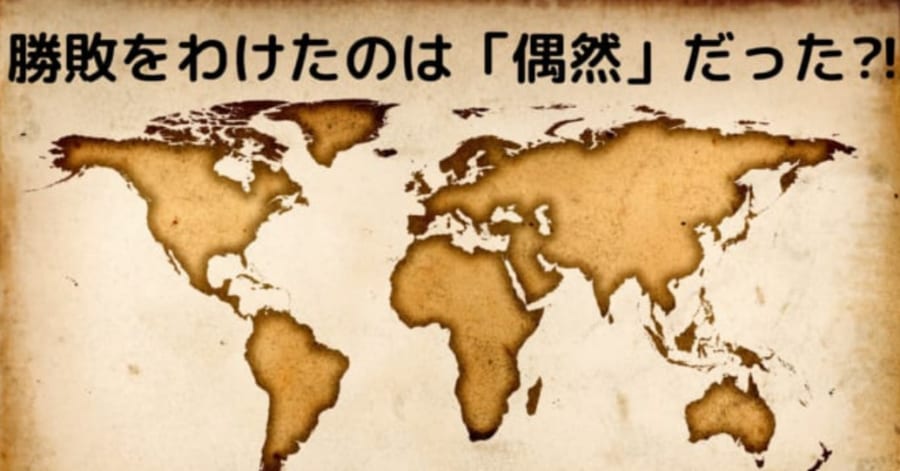







要は補足より強迫やアリバイ作りに多様されやすいと
文脈からの読解や類推を阻止して思考を限定させる効果を期待させちゃうのか
詐欺師の手口そのままって感じ
絵文字は全く使わないけど語彙力もコミュ力も低い私のような人間は一体…。
日本、海外問わず、陰○論界隈の人のポストにはなんで絵文字が多いんだろう…?と思っていたのですが、そういうことなのかもしれませんね。すっきりしました。
>絵文字は直感的で分かりやすく、世界共通で通じやすい「具体的」なシンボルです。
日本と海外では同じ絵文字でも違う意味にとられてるってニュースありましたよ
そりゃそういう文字もあるでしょう
通じるじゃなくて通じやすいだからね
絵文字多いのは相手の気持ちを配慮しまくる人でリアクション大きい人ですよ
最後に閉める為に、絵文字を使ったり!?ちょっと、笑いを演出する為に、スタンプを打ったり!用は、ご機嫌取りです。文字だけで、伝える自信がないから…堅苦しく、しないように!
題名用の釣りとは思うけど、絵文字を多用したがる性格傾向や性質を「悲しい」と言い切ってしまう筆者も悲しい。
絵文字に頼る人は生きるなとでも言っているの?
ソースなしただの落書きですね
たしかに絵文字を多用した文章って頭悪そう🤪だなあーって、直感的に思いますよね⁉️⁉️😂
あらかじめ用意されたものを使って済ませる人は創造性に欠けるって事かな⁉️
しかし世代によっても違うかなぁ❓❓❓🤔
今の30〜40歳は若い頃にガラケーで絵文字を使うのが流行っていたから、多用する人は多いのでは❓❓❓🤔
開放性とIQの相関0.20~0.30程度は弱い数字だと学校で習った覚えがあります。記事中の誰が作ったか分からない画像の「相関の強さ」という項目に(ざっくり目安)と書かれていますが、やはり中程度というのは言いすぎなのではないでしょうか。
それから、IQは1人調べるのに2時間くらいかかるのにいちいち300人も調べたのかと気になり、リンクを開いてみたら知能検査に関する記載は見当たりませんでした。私は絵文字が好きなだけのド素人なので何とも言えませんが。
加えて記事でも言及されているとおり日本語圏にも同じことが言えるとは限りません。日本人向けの記事でこのタイトルは一瞬ドキッとします🥺
この記事を読んだ上で、自分の開放性がどうであれその部分が気になる人はそう多くはないと思いますが、IQはデリケートな問題なので絵文字を好んで使う人の中には気になってしまう人もわりといると思います。多くの人の関心は統計ではなく自分や周りの人のことですからね。私も特に😀😃←このまったく目が笑っていない絵文字が大好きなので少しばかり遺憾です😤😇
感情的なコミュニケーションは分かりやすさ重視で絵文字使います
より厳密な情報伝達は勿論言語を用います
個人的には絵文字は内輪で家族や親戚に使うことが多い。保守的運用=開放的ではない、か。
アメリカ人で絵文字使ってるとナイーブって思われちゃいそうですね。日本人同士だと(私は)感情のやりとりを斜め上からする時に絵文字使ったりする。
無味乾燥で行き詰まりなトークを打開するために使ったりするので一概には言えないかな、、
iOSやAndroidの絵文字って定型だけど、2cのAAなんかはどうなんですかね?
(´・ω・`)ショボーン m9(^Д^)プギャー (#,゚Д゚)ゴルァ! キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!! などなど
こういうのはちょっと改変するだけでも表情、伝わり方が全然変わってくるから楽しくて今でもよく使います。
定型絵文字よりはるかにクリエイティブで大好き!
ま、使うには頭使うけどね
絵文字ばっかり使う人の文章には知性が感じられない。それに他者を嘲笑するような使い方もしばしば見受けられる。文字と比べて目立つから、余計に腹が立つ。識字率や言語能力がなにか関係してくるのだろうか?個人的にだが、絵文字より顔文字やAAの方が好きだ。
え~、絵文字を多く使う人は保守的でネガティブでユーモアも語彙力も無い人ってことか…
ここのコメント欄を見る限り当たってそう笑 保健所で駆除してもらっていれば方が良いかも
定型化すると安心できるのは分かる気はするね
次はダジャレを頻繁に使う人の悲しい特徴を
どうでもいい