幼少期の虐待が「体への信頼」を蝕む
最新のメタ分析が示した事実
ドレスデン工科大学の研究チームは今回「子ども時代の虐待と内受容感覚の関連」についてのメタ分析を行いました。
この研究では、過去の17件の研究(計3,705人のデータ)を統合し、虐待と内受容感覚の4つの側面
1. 正確性(身体信号の正確な認知)
2.感受性(身体信号を敏感に感じ取る主観的な能力)
3.気づき(意識的な身体感覚の認知)
4.身体への信頼感(身体信号への信頼度)
との関連を分析しました。
その結果、「正確性」「感受性」「気づき」には有意な関連が見られなかったものの、「身体への信頼感」だけは明確に低下していることが示されたのです。
しかも、この関連は身体的・性的虐待よりも、情緒的虐待やネグレクト(育児放棄)において特に強く現れることも判明しました。
自分の体を信じられないということ
研究者は次のように述べています。
「情緒的虐待を受けた人は、“自分の体が何を感じているのか”に対して信頼を持てなくなる傾向があります。
これは感情調整やストレスへの対処、そして自己認識を大きく妨げる原因となり得ます」
実際、「自分の感情がよくわからない」「お腹が空いているのか分からない」「疲れているのに頑張りすぎてしまう」といった訴えは、こうした内受容感覚の信頼低下によるものかもしれません。
また、身体信号を正しく信じられないことで、「感情の反応がおかしい」「相手の気持ちが読み取れない」といった人間関係のトラブルや孤立を引き起こす可能性もあります。

身体の内側からの声に耳を澄ますこと――それは、私たちが自分自身とつながるための基本です。
「お腹がすいた」「胸が苦しい」「不安で心臓がバクバクする」
そんな体の声は、感情の羅針盤であり、健康のナビゲーターでもあります。
しかし幼少期に十分な感情的ケアを受けられなかった人は、この「体との対話」を信じることができなくなるのです。
そしてそれは、ただの“感覚の問題”ではなく、生涯にわたって続く心と体の課題を生む可能性があるのです。
チームは今後、12〜17歳の青少年を対象に、内受容感覚と虐待歴の関係をさらに詳しく調べる研究を進めています。
「体を信じる力」を育むこと。
それは子どもを守るということ以上に、人間としての根っこを守ることなのかもしれません。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
















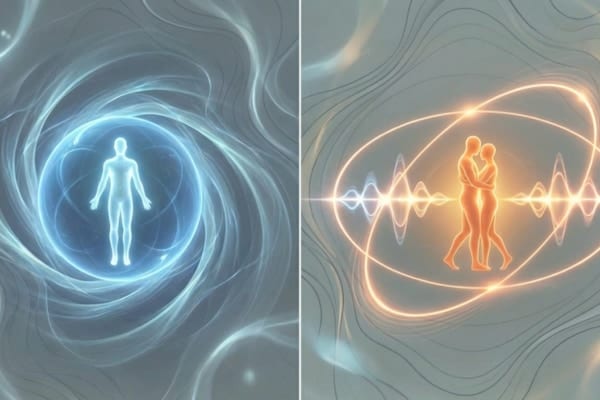











長いこと体の調子が悪い状態が続いているので、正常な体の反応も本当にそれが正常なのか分からなくなるというのは経験してますね。
健康な人も空腹になれば多少は吐き気がしたりするものですが、それが空腹によるものなのか、胃腸の調子が悪くて本当に吐き気がしているのか判断がつかなかったりとかですね。
機能不全家庭で育ちましたが、兄弟とわたし含めて「全然お腹が空かないので食事を取らない時がある」や「嫌なことを言われてもそれを感じることができず相手を嫌えない」や「緊張が高まってもそれを感じられず体調に突然現れる」という傾向にあります。安定した情緒が保てないなら三人も子を産まないでほしかったです。
親に言語化してもらえなかった感情はないことになるって本当なんでしょうか…
毒親のいる機能不全家庭育ち 現在双極性障害治療9年目の精神障害者手帳持ちです
空腹や体調不良や感情の消失(一時的)等すべてに気付かず虚空を見つめる虚無と化して一日を終える事も度々あります
体の異変に何も疑問を抱かず虚無の時間を過ごしてしまうので良くないですね