なぜ結び目は『計算通り』にほどけないのか?数学が示す新たな視点

今回の研究によって、「複雑な結び目同士をつなげると、逆に簡単にほどけてしまう場合がある」ことが示されました。
この発見は数学の研究だけに留まらず、私たちの日常生活や社会に対しても興味深い示唆を与えます。
例えば、イヤホンコードや荷物の紐の絡まりを考える際にも、『複雑な絡まりは必ずしも見た目通りの難しさとは限らない』という直感を与えてくれます。
さらに、DNAの分子やタンパク質が体内でどのように絡まり合っているかという生物学的な問題や、通信やデータ管理における暗号理論、さらにはコンピューターが難問を解決するための機械学習の手法に至るまで、幅広い分野への応用も考えられます。
つまり、この研究は、私たちが結び目という現象を新たな視点から捉え直すことで、意外な発見や革新的な方法が生まれる可能性を示唆しているのです。
また、この発見が数学者に対して特に大きな影響を与えたのは、結び目理論の根本にある「複雑さ」の概念を見直す必要性が出てきた点です。
【コラム】なぜ複雑+複雑は2倍の複雑にならないのか?
「なぜ複雑+複雑は2倍の複雑にならないのか?」残念ながら、研究を行った数学者たちも、その背後にある明確なメカニズムをまだ完全には解明できていません。しかし、彼らはこの驚くべき現象について、一つの重要なヒントを与えています。それは、「私たちが『結び目をほどく』という操作を理解しているつもりでも、実は見えていない部分がまだあるかもしれない」ということです。結び目をほどくための最短の手順を探すことは、実は非常に難しい問題です。数学者たちは、「絡まりをほどく最も良い方法はこれだ」と決めつけてしまいがちですが、実際には思いもよらないルートが隠されているかもしれないのです。今回の研究で見つかった反例は、まさにそのことを示しています。二つの結び目が連結された時、絡まり方が変化し、「それぞれを単独でほどく時とはまったく異なる、新たなほどき方」が生まれる可能性があるのです。これは例えば、2つの複雑なパズルを組み合わせた時に、予想もしていなかった解き方が浮かび上がるようなものです。それぞれ単独では難しい問題だったのに、組み合わさった瞬間、意外なほど簡単に解けるようになる、そんな逆説的な現象が起こっているのかもしれません。
これまで数学者は、結び目の複雑さを理解するために、「複雑な結び目を細かく基本的な結び目(素結び目)に分解して、それぞれの結び目の性質を足し合わせれば良い」と考えてきました。
しかし、今回の結果は、「複雑な絡まり同士の間に相互作用が生まれることで、足し合わせた以上の効果や予想外の簡単さが現れることがある」ということを意味しています。
これは結び目をほどくための実際の手法やアルゴリズムを作る上でも、新しいアイデアを提供する可能性があります。
また、この研究を通じて、SnappyやSageといったコンピューターを使った計算手法が結び目理論の難問を解く際に非常に強力であることも示されました。
つまり、この成果は結び目を研究する数学者に、実験的かつ計算的な手法の有効性を改めて示したという点でも重要です。
数学の世界では、一見当たり前と思われてきた法則が覆ることで新たな地平が開けることがしばしばあります。今回の成果もまさにその一例であり、結び目という身近で不思議な対象の奥深さを改めて示す出来事となりました。












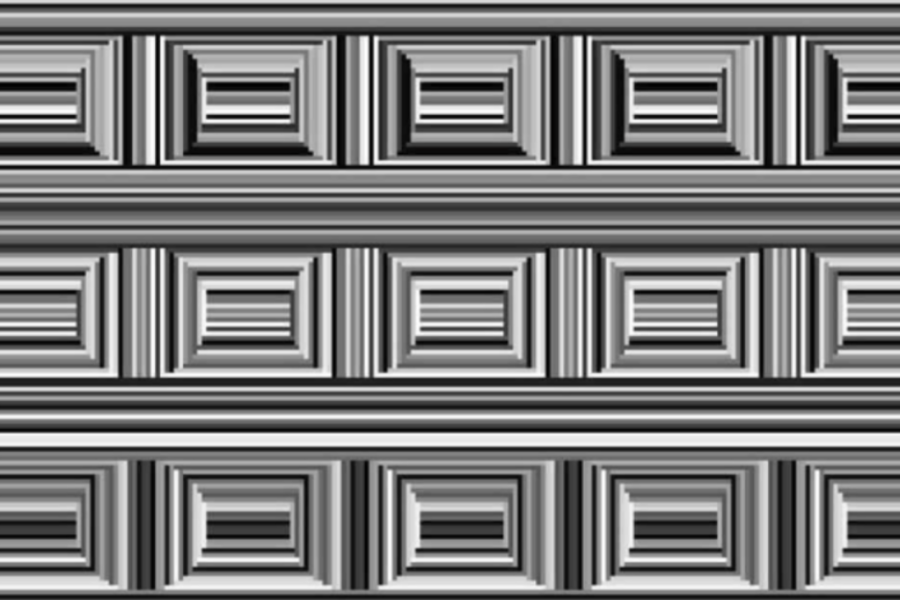















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
















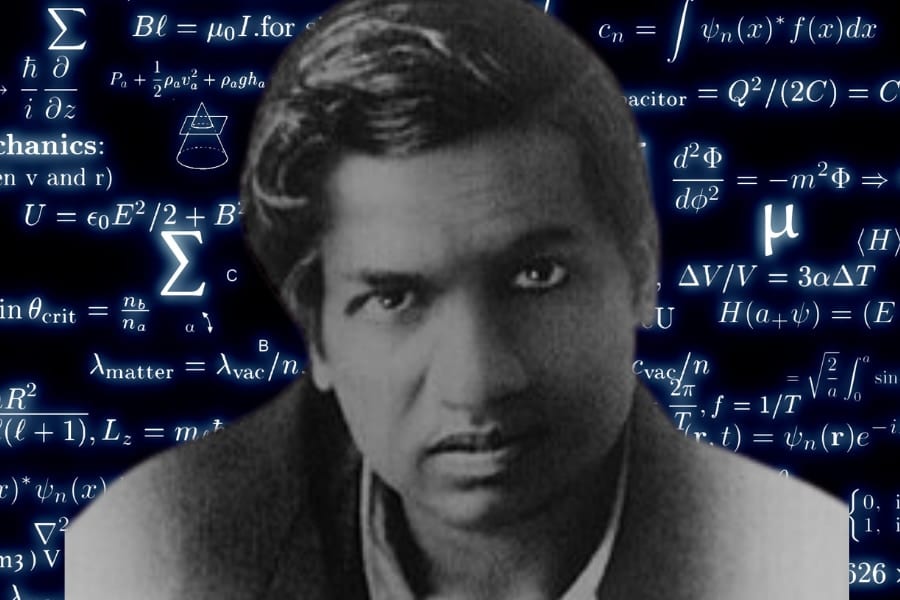
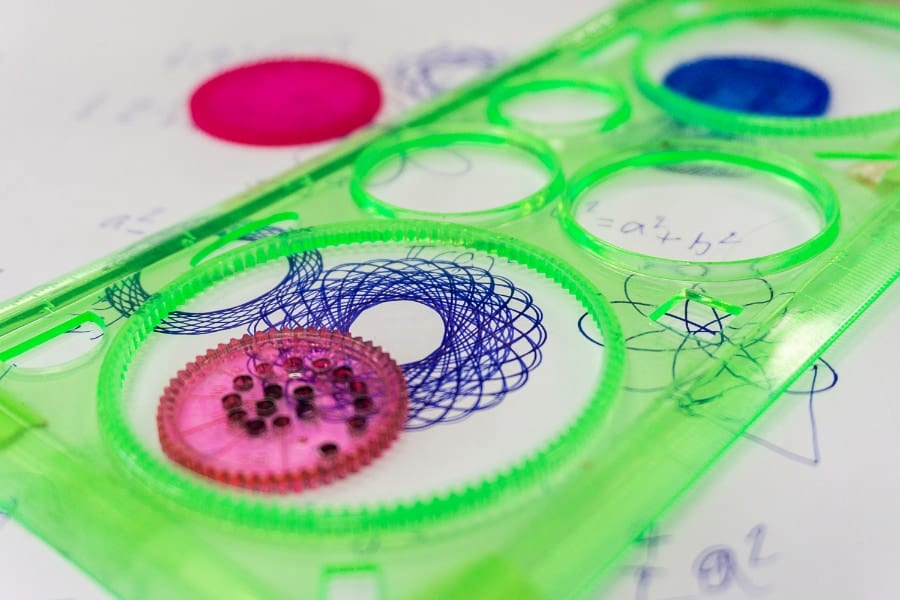
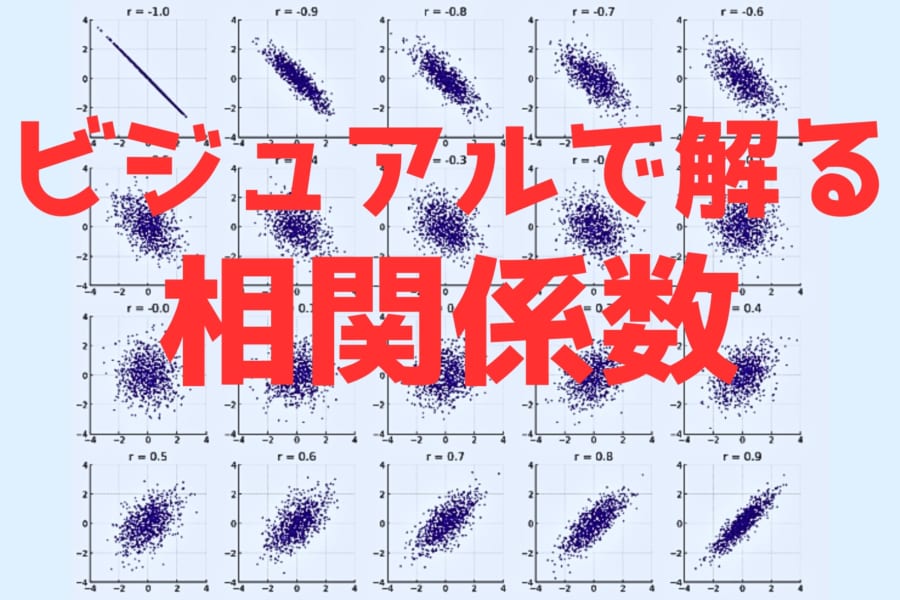
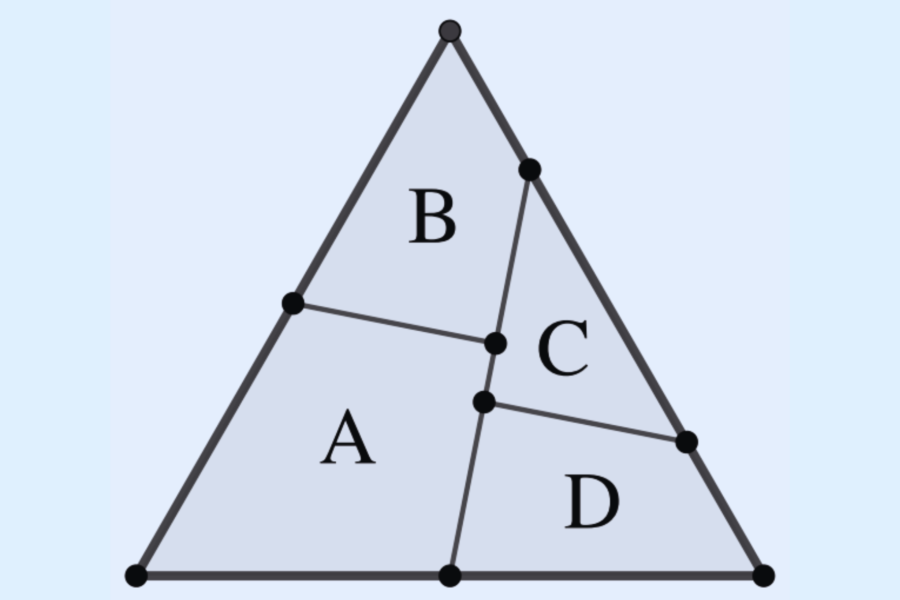








人工知能がすごく得意そうなジャンルに思えますけど、あんまり活躍はしてないのでしょうか。
いつか写真に結び目を撮れば人工知能が手取り足取り解き方を教えてくれたりとか…。
決定論的で足し算引き算のたぐいに近いから、
確率論的で基本的には分類器である人工知能が得意ではない分野かもです
部分的結び目構造の単体の解消操作の最低数をnとする。全体の結び目構造によらず、部分的結び目構造解消に必ずn回の操作が必要となるなんていう有り得ない仮説を数学者が立てたとは思えないんだけど。全体最適な解消操作でついでに個々の部分結び目が解消されるっていうのはむしろ自然なんだが。
ホントですよね。何か解説か解釈が間違ってるんだと思われます。
『結び目』を作るのではなくて、『結び目』を『拡げる』事と『移動する』事を考えて、『困難を分割する』事が実践的な手法だと想います。
水中ドローン事業経営者にして、リレーショナルデータベース技術者の私の登場です。どちらも結び目が、幸運だろうが、不運だろうが関わってきます。リレーショナルデータベースの始祖コッド博士はハーディ(整数論)の教え子と聞きます。この分野の勉強していたのでしょう。私、アホなので、あと、靴紐のおしゃれな結び方は大好きです。統計学が微分積分より好きです。学生のころ、意味不明の線形代数。ブツブツいいながらやってました。それが役に立つと分かったのが水中ドローンでした。ご存知のように海中では、テーザーケーブルが100メートルもあるのです。人手不足で、しょうがなく地元の水産高校生を雇います。もう、考えません。ケーブルをどんな状態でも巻きます。それを解くのが私です。最初は、もう、殺意と複雑のジレンマでした。しかし、この時ほど、線形代数、統計学、リレーショナルデータベース論理が役に立ったときはありません。言葉に出来ません。解きながら、線形代数の勉強の時に感じた正規直交基底の解を感じた時以外は、結び目を解こうとはしません。何故なら、最初の2手で解けるのです(普通の人には分かりません。僕は柔道2段で県で3位の奴に優勢勝ちする、地区で1番の怪力と引き分ける中国立大卒業なのです。組手争いをします。相手に組まれた瞬間の相手の力の引きの瞬時に、いいとこ掴まれたと分かるんです。いいとこ掴まれたら非力の僕は負けるんです。しかし、これは、基本を地獄のように、飾り気なしにさせる、良き先生に出会うかもあります。弱い僕を強くした)。そして、ケーブルに正規直交基底を感じたとき、手を止めます。ここは、本当に紐を解きにかかります。なるほど、為になりました。正解だったんですね、多分、数学、物理を地獄にやったものは、漁師も早いです。みんなに見せてあげたい。私がデザーケーブルの結び目を解きながら、巻いていく姿を。芸術です。マトリックスという映画で。スミスというエージェントのパンチを正規直交基底で交わす。あれに似たシーンです。柔道と数学を地獄のようにやったものしか真似出来ません。
俺、頭悪いからよくわからないんだけどさ、手順aと手順bを足してるつもりなのが、実は手順abcと手順cdeが合体してるだけなんじゃないのか?(共通のcは合わさり一回で処理される)
きゃーちょーあたまよさそーないけん
素敵―
さすが!知らなかった!すごーい
わかりやすくしてみた
僕は水中ドローンの仕事をしている。
説明しようとすると少しややこしいけれど、要するに、海の中を自由に泳がせるロボットみたいなものだ。人の代わりに深い場所へ行き、暗い世界を見て、戻ってくる。それが僕たちの代わりに何を見ているのかは、僕にもよくわからない。でも、そういう不確かさが、この仕事にはつきものだ。
ドローンには長いテザーケーブルがついている。言ってみれば、深海に降ろす糸電話みたいなものだ。でもこの糸電話、100メートルもあると、まるで人生のように絡まる。
人手が足りないので、水産高校の生徒たちに手伝ってもらってるけれど、彼らはケーブルの気持ちなんて考えちゃいない。ただ黙々と、いや、むしろ気まぐれに巻いていく。まるで人生を雑に巻き取るように。
結果、ケーブルはぐちゃぐちゃに絡まり、僕の手元に戻ってくる。
そして、それを解くのが僕の役目だ。
はじめのころは、怒りと無力感とが、心の中で綱引きをしていた。でもある日、ふと気づいたんだ。
これは、たぶん僕にとっての「数式」なんだって。
学生時代、僕は線形代数というものに苦しめられた。教科書はまるで遠い星の言語で書かれているようで、何を言っているのかさっぱりわからなかった。「正規直交基底」なんて言葉を聞いたときには、魔法か呪文かと思った。でも、今ならわかる。あれは「世界をほどく鍵」の一つだったんだ。
ケーブルが複雑に絡まっているとき、僕はその中に見えない軸を探す。
一本の線を引き抜けば、他の線も自ずとほどける。無理に引っ張らない。力でどうにかしようとすると、かえって硬くなる。そういうときは、静かに待つ。音楽を聴くみたいに。バッハでも、ビル・エヴァンスでもいい。
そこに流れる「構造」を聴く。すると、不思議と手が動いて、ケーブルはほどけていく。
僕は昔、柔道をやっていた。相手と組んだ瞬間に、その力の方向がわかることがある。
それとよく似ている。ケーブルにも、目には見えない「組み手」がある。どこに重心があるか、どこを引けば世界が動くか。僕の手はそれを探っている。
ときどき、自分でも驚くほど見事にほどけることがある。そういう瞬間、僕は思うんだ。
このケーブルは、たぶん僕自身なんだって。
これ、マジックとかで、「一見複雑に見えるけど、実は絡まってない」っていう形を、スルッと解くアレじゃね?
だとすると、少ない回数で解ける事があるのはむしろ自明な気がするけど…。
そういうことじゃないのかな?
数学よくわからんけど結び目を組み合わせたら解き方向が重なる=同時処理可能になって解き手数が減る事があるのは当たり前じゃないの?
確かに不思議です
人間と人間の絡み合うのも
結び目があるかもしれません
楽しくなるような
結び目は
大歓迎します
アレキサンダー大王、今頃天国で悔しがってるだろうなぁ
あれは連結していない単一の結び目だから
有識者の見解とか驚きの声、賞賛の声が聞きたいぜ〜!
組み合わせることで、逆に手順が増えることはないのかな?
GDPも関税も似て
キ―プ
チエノワ
受験数学で徹底されたのは、例外なく全てのパターンを網羅することでした。例えば証明問題の場合分けなんかです。
基本方針は問題を細かく条件で分けること。
でも実生活で、あっちとこっちの問題を個別に解決していくと、網羅しようとすればかけ算でパターン数が増えます。
意外と、コンピュータで全パターンを試したり統計取ったりするより、人間の脳みそによる直感的なファジーでアナログな方が問題解決に近かったりするのかもしれませんね。
ただファジーな分見落としや錯覚もあるので、論理による最終チェックはそれはそれで必要でしょう。
量子コンピュータの実用化が楽しみですね。
右巻きと左巻きを合わせたら打ち消しあって一つになるみたいなもんじゃないの
サインコサインは複雑な関数で、サインを2乗するとさらに激しい波になるが
サインの2乗とコサインの2乗を足すととっても簡単になっちゃうみたいな感じをイメージしました