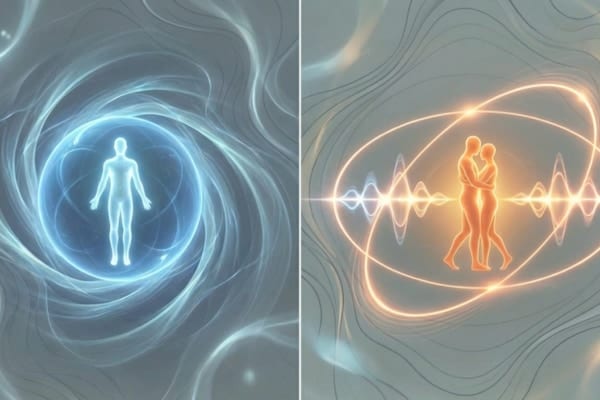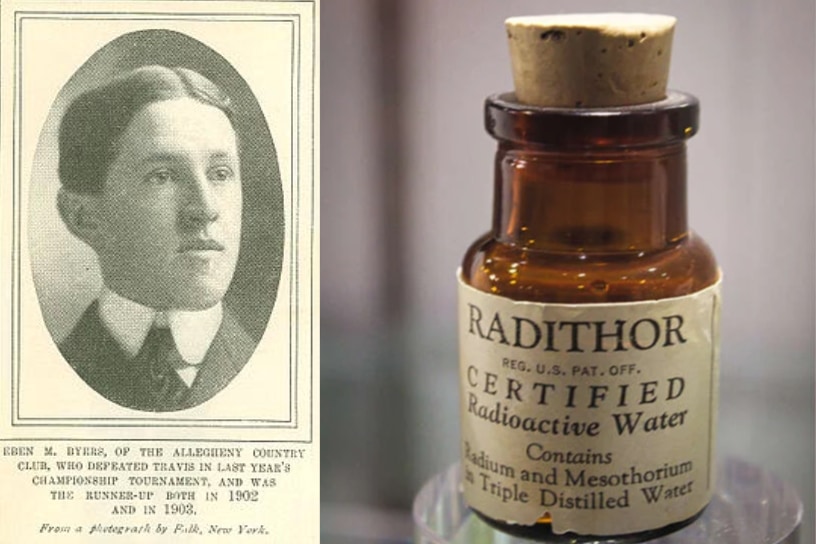感情のスイッチで記憶を使い分ける未来
今回の研究によって「音楽と記憶力」の関係は、音楽がアリなら記憶力が上がり、ナシなら下がるという単純なものではなく、記憶の中身によって効果が異なることが示されました。
どういうことかというと、音楽が記憶に与える影響は、「どんな記憶を残したいか?」という目的によって違ってくるということなのです。
たとえば、あなたがテストのために勉強をした後を想像してみてください。
その直後に「ちょうど良いテンション」を感じられるような曲を聴くと、勉強した内容の細かい部分がしっかり記憶に残りやすくなります。
でも、もし「すごく興奮してしまう」曲を聴いたらどうなるでしょうか。
実は、細かな内容よりも「ざっくりとした大筋の内容」だけが記憶に残って、細かな部分は忘れやすくなってしまうのです。
ある意味で、音楽は単純に記憶力を上げる道具というよりは、「記憶をどのくらい細かく残すかを調整するツマミ」のような役割を持っていると言えるでしょう。
これは音楽を聴けば何でも覚えられるという魔法のような話ではありませんが、うまく使えば、自分が必要とするタイプの記憶を強化することができる可能性があるということを示しています。
実際に研究者たちは、記憶には「細かい記憶(細部記憶)」と「大まかな記憶(全体記憶)」の二つの種類があり、音楽を聴いて感じる「ドキドキの度合い」によって、この二つが逆方向に影響されることを見つけました。
つまり、「ほどほどにドキドキした人」は細かな記憶が良くなり、「ドキドキが強すぎたり弱すぎたりした人」は大まかな記憶の方が良くなったのです。
これは今まであまり知られていなかった重要な発見です。
さらに、この新たな知見は、将来的に医療や心理療法にも役立つ可能性があります。
例えば、不安症やPTSD(心的外傷後ストレス障害)などにつながる辛い出来事を経験した直後に「あえて感情を強く揺さぶるような曲」を聴いてもらうことで、辛い出来事の細かい部分をぼかし、大まかな記憶だけを残して、ショックや辛さを和らげることができるかもしれません。
ただし、音楽によって感じる「ちょうど良いドキドキ感」は、人それぞれ全く違います。
同じ曲を聴いても、ある人はリラックスし、ある人は興奮しすぎてしまうように、曲の感じ方は人それぞれなのです。
実際、今回の研究でも、参加者たちはみんな違う反応をしました。
ある人にとってちょうど良い曲が、別の人には強すぎたり、逆に物足りなかったりすることがありました。
つまり、この方法を実際に記憶力の向上に使おうとするときには、「その人にとってちょうど良い曲と興奮の度合い」を見つけることが重要なのです。
研究者たちも今後この技術を普及させるには、さらに詳しい調査が必要だと考えています。
例えば、今回の研究は大学生だけを対象にしましたが、他の年齢層でも同じような効果があるかはまだわかっていません。
また、心拍数や瞳孔の開き具合など、「身体の反応」を測ることで、その人がどれだけ興奮しているかをより客観的に測定することも検討されています。
さらに、記憶が音楽によってどのくらい長期間保持されるのかや、クラシック以外のさまざまなジャンルの音楽でも同じ効果があるのかを調べる必要もあるでしょう。
このようにデータをたくさん集めることで、将来的には「あなたにはこの曲がベスト!」という、一人ひとりにぴったりの「音楽処方箋」のようなものを作れるかもしれません。
実際、今回の研究を率いたリール教授は「音楽には、治療の目的に応じて記憶を強めたり弱めたりすることが可能かもしれません」と述べています。
音楽は身近で気軽に楽しめるものでありながら、記憶という私たちの大切な機能をコントロールするツールとして、大きな可能性を秘めていることがわかります。
今回の研究は、音楽の持つこの新しい可能性を示した重要な一歩となっています。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)