だから何が変わる?反証が効きにくい訳

この研究から言える最も重要な点は、陰謀論を信じる人が「ただ単にだまされやすい人」というわけではないということです。
むしろ、陰謀論を信じる人たちは特定の情報に対して独特な脳の反応パターンを持っており、それが彼らの信念を支えているのです。
現実の情報に対しては普通の判断ができているのに、陰謀論に触れた途端、脳内で別のスイッチが入ったように情報の受け取り方が変わってしまうのです。
こうした「陰謀論モード」の存在は、なぜ彼らが反証を突きつけられても考えを改めないのかを、神経科学的に説明する手がかりになるものと言えるでしょう。
実際、高い陰謀論信奉者では、不確かな情報に対しても前頭前野が活発になり信念を維持する方向に働く一方、低い人では豊富な記憶ネットワークを動員して真偽を吟味するという“すれ違い”が起きていました。
ただし、本研究には注意すべき点もあります。
被験者は中国の若い成人に限られ、異なる文化や状況でも同じ結果が得られるかは今後の研究で確認が必要です。
しかし、こうした制約がある中でも、陰謀論にハマる心理の一端が脳の働きとして示された意義は大きいと言えます。
従来は「情報リテラシー教育を強化すればデマに騙されないだろう」と考えられがちでしたが、本研究は問題がそれほど単純ではない可能性を示唆します。
つまり、人によっては脳の情報処理の偏りとして陰謀論へのハマりやすさが現れているため、単に事実を提示するだけでは効果が薄いかもしれないのです。
では、陰謀論に立ち向かうにはどうすれば良いのでしょうか?
今回の研究はこの点についても重要な示唆を与えてくれます。
陰謀論を単に事実で論破しようとするだけでは不十分で、感情面や価値観に訴えるアプローチが必要だと考えられます。
今後の研究では、情報の伝え方や情報源の示し方によって、人がどのように陰謀論的な情報を評価するかが調べられる予定です。
例えば、単に「それは間違いだ」とデータを示すだけでなく、「なぜその陰謀論が魅力的に感じられるのか」を共有しつつ、その上で事実を伝えるといったコミュニケーションが有効かもしれません。
研究チームは今後、AIが生成する偽情報など新たな問題に対して人々の脳がどう反応するのかも調べたいと述べています。
脳のメカニズムまで理解できれば、「なぜデマに引っかかるのか」をより深く解明でき、より効果的な対策が見えてくるかもしれません。
陰謀論という謎に脳科学のアプローチで光を当てた今回の研究は、社会がこの問題とどう向き合うかを考える上で大きな一歩となりました。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
















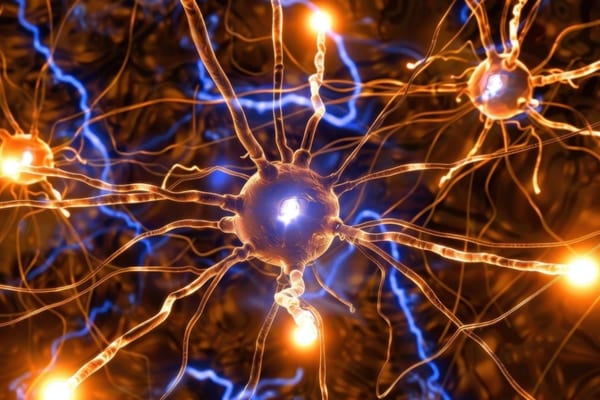

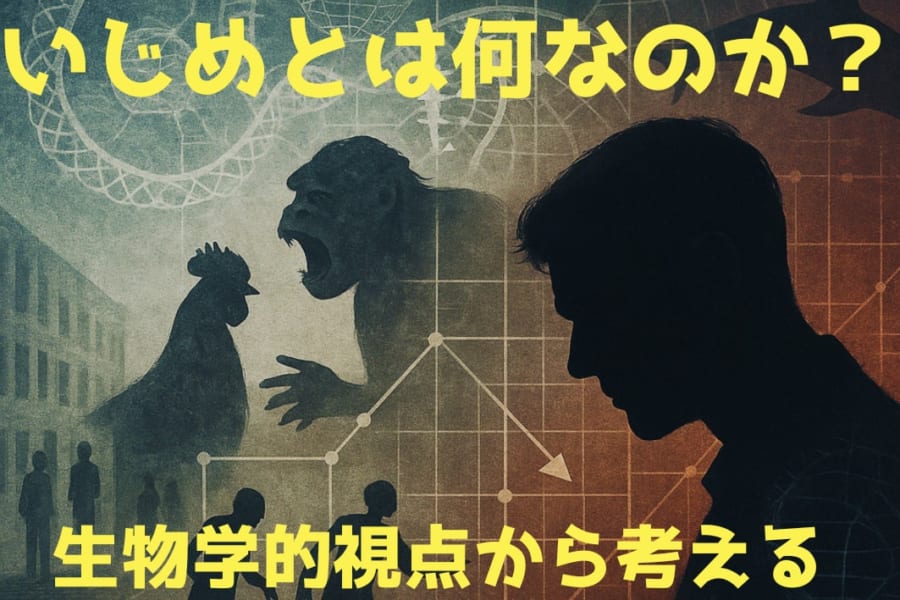









陰謀論者叩いてる構図って異端審問だよなぁって歴史や宗教に興味ある人間としては思うんですよね。
現代では科学者がインクジィターとして異端者を次々裁いているんだなと。
結局科学もそうなっちゃうんだ…って思いますね。
ウォーハンマーの帝國かよ、スターゲートのオーライかよって言う。
人って宗教から逃げられないんですよね、結局は。
陰謀論者がてきとーな対象を叩いてる構図って異端審問だよなあって思います。
客観的根拠なく思い込みで批判して責任取らないところとか。
フフフ…争え…もっと争え…
陰謀論者ってカルト宗教的な思考方法だなって思っていたので面白い視点だと思いました。
カルト宗教の信者はその宗教の教義を肯定するような情報は無条件に信じて
その宗教の教義を否定するような情報は信じないじゃないですか?
陰謀論を否定するような証拠や証言が1つでもあれば普通ならアレっ?と思って陰謀論を否定するまではいかなくても
真偽の判断を保留したりとブレーキが効くのに陰謀論を信じ込んでる人はその証拠や証言を否定するか捏造だと主張しだす。
正にカルト宗教的だなぁと思ってました。
>つまり陰謀論を信じやすい人は、陰謀論を読んだ瞬間に「自分の考えにぴったり合うか」「本当かもしれない」と迷ったり、魅力を感じたりする回路が働きやすいと考えられます。
>海馬は記憶の中枢として知られ、今まで自分が学んだことや経験したことを思い出して、新しい情報と照らし合わせる役割を持っています。
>楔前部も、自分自身がこれまで経験したことを振り返りながら情報を吟味するときに活躍します。
つまり陰謀論者はもともと陰謀論が好きで現実は見てなくて夢見がち、と
>被験者は中国の若い成人に限られ
ここはいつから共産党のプロパガンダサイトになったんだ?
陰謀論者の実例の提供ありがとうございます。
なるほど、ハードディスクは書き込まれたデータ以外は存在しないのと同じか
この研究の弱点は、因果は言えないことです。
設計上は相関的な観察にとどまります。つまり、「特定の脳領域の活動が強いから陰謀論を信じるようになった」のか、「もともとの信念傾向が強いからその脳領域が動く」のかは、この研究だけでは決められません。今後、縦断データや介入研究(たとえば記憶想起を促す教示)で検証が必要だと考えられます。
記事の解釈は妥当か、
記事は「陰謀論者=だまされやすい」ではなく、「陰謀論に触れたときだけ脳の使い方が変わる」という点を丁寧に説明しています。つまり、バイアスは内容特異的だという原著の含意をうまく噛み砕いています。一方で、「感情や価値観に訴えるアプローチが必要」といった対処の提案は、論文の記述(“批判的な情報評価の手立てを考える材料になる”程度)より半歩進んだ示唆です。ここは「仮説として読む」くらいの距離感が安全です。
研究自体は慎重に読めば有益で、内容特異的な処理(価値・不確かさ vs 記憶系)という枠組みは、今後の再現研究や文化差の検討につながります。ただし、サンプルの偏りと刺激の出典の偏りがあるので、他文化・他言語への一般化を語る前に追試が必要です。つまり、「面白い初期報告」として位置づけるのが妥当です。
お前らネタなのかマジなのか分からんから怖いんよ
反ワクチンのお母さん(本人)が反ワクから目を覚ました
経緯をまとめたツィッターでも同様の記載があったな
ネットの情報から子供や家族のワクチン接種に断固反対してた。
周囲から浮いてしまい、気が付いたら反ワク情報しか信じなくなった
ある時、小児科を受診した際に先生と看護婦さん複数人から1時間ほど実際の症例を交えて説得された
『顔も見たことのないネットの声より、目の前で熱心に説明してくれる方を信じよう』
それが目を覚ましたきっかけだそうです。
この例よりも重度に何かの陰謀論やカルトに嵌っている人達には、熱心に説明してもかえって反発を抱き難しいので、例えその教えが間違っていることでも論理的に否定せずにちゃんと彼らの話を最後まで聞き、聞きいた後にあなたと自分とは考えが違うようだけど、あなたが誰かを助けたいという気持ちや世の中を良くしたいという気持ちはだけは同じだよと言って、寄り添った方がいいらしい。
何れ陰謀論やカルトの矛盾に少し疑問を抱く機会が何度か訪れるので、その機会を逃さず、その時に彼らが何気なく安心して皆の元へ戻る場所を常に用意した方が、陰謀論やカルトから抜け出させる為の良い方法らしい。
ワクチンから陰謀論と言う都合のいい言葉が流行ったけどワクチンは結局効かなかったし人が亡くなってるじゃん
後遺症で苦しんだり亡くなった人から目を背けて陰謀論と言う誰かが定義した都合の良い甘言に浸らないで新聞にすら書いてある現実を見て欲しいな
陰謀論に嵌る人達は物事を深く考えて調べないか、自分が属する集団の意見に流されやすいようなタイプが多い印象。また何かに対して常に不満があったり、精神的に疲れている印象もある。カルトに嵌まる人も似たような印象だ。
政府は何か悪いことをしているはずだ、という反政府的な陰謀論の洗脳を受けた人は、他の陰謀論に次々のハマりやすいのだな。どんなに根拠を示しても、政府は悪いことを企んでいるとう信念を捨てようとしないんだな。
人類が生き残るには必要な機能だったのかな
中国のネットで『政府は重大なことを隠していると思うか?』
って質問されて、『ハイ』と答えられる人いるか?
器具不要な脳の電子マップモニターが一般流通してほしいな。やベー党の人は本気で言ってるのかプロパガンダで表集めの煽り構文言ってるのか判断しやすくなるかも
宗教(特に原理主義的な)についてもやってみてほしい、似たような結果が出ると思う
陰謀論に限らず意固地な状態の話題だと脳が同様の反応することはないかね?