専門化向けざっくり解説
1) 問題設定:量子重力を「有限・計算可能」な形式系として捉える
著者は、量子重力の計算核(computational core)を以下の形式系として明示化する。
F_QG = { L_QG, Σ_QG, R_alg }
— L_QG:一次言語(量子状態・曲率・因果関係などの語彙)
— Σ_QG:有限または再帰的列挙可能な閉文の集合(公理)
— R_alg:効果的推論規則(計算可能な導出規則)
(i) effective axiomatizability(Σ_QG は有限/再帰的列挙可能)、(ii) arithmetic expressiveness(自然数演算を内部表現可能)、(iii) internal consistency(矛盾なし)、(iv) empirical completeness(物理現象を予言・説明)。この前提の下で、時空は F_QG の定理レベルで出現する(emergent)とする(例:弦理論・LQG・ホログラフィ等)。
2) 論理三定理の適用:計算核 F_QG の限界
-
ゲーデル第1定理:Th(F_QG) は True(F_QG) の真部分集合(proper subset)。
記法(Word安全な表現):
Th(F_QG) := { phi in L_QG : Prov(Σ_QG, R_alg, phi) }
True(F_QG) := { phi in L_QG : true_in_standard_model(phi) }
結論:Th(F_QG) ⊂ True(F_QG)。すなわち、F_QG では真だが証明不能な命題が必ず存在。 -
ゲーデル第2定理:自己無矛盾性 Con(F_QG) := not Prov(Σ_QG, R_alg, contradiction) は F_QG 内では証明不能。
-
タルスキーの定義不可能定理:L_QG 内に「全域真理述語」Truth(x) を定義し、Prov(Σ_QG, R_alg, Truth(code(phi)) ↔ phi) を全 φ で満たすことは不可能。
-
チャイティンの情報理論的不完全性:定数 K_FQG が存在し、Kolmogorov 複雑度 K(S) > K_FQG なる文 S は F_QG で決定不能(不可判定)。
帰結:純粋にアルゴリズム的(計算可能)な TOE は原理的に不可能。F_QG は真理全体を捉えきれず、自己健全性も内部証明できない。
3) メタ万物理論 MToE:外部真理述語と非効果的推論の導入
不足を補うため、著者は外部真理述語 T(x) と非効果的推論規則 R_nonalg を付加した拡張を提案:
MToE = { L_QG ∪ {T}, Σ_QG ∪ Σ_T, R_alg ∪ R_nonalg }。
Σ_T(T に関する外部公理)は次を満たす:
(S1) soundness for F_QG(T( code(phi) ) が公理なら phi は F_QG の全モデルで成り立つ)、
(S2) reflective completeness(もし Σ_QG ⊢_alg phi なら、(phi → T(code(phi))) を Σ_T に含める)、
(S3) modus-ponens closure(T は論理的帰結に閉じる)、
(S4) trans-algorithmicity(Th_T := { phi | T(code(phi)) in Σ_T } は再帰的列挙不能;任意に大きい Kolmogorov 複雑度の命題を T-真として扱える)。
F_QG では決定不能な命題(例:特定のブラックホール・マイクロステートの実在性等)にも、T を介して意味論的(semantic)な真理付与を行い、ゲーデル型障害を越える。
4) 物理への含意:不可判定性が顕在化する領域
-
熱化(thermalization)の不可判定性:多体系の熱化判定は一般に不可判定。Planck 領域から古典時空への“熱的再出現”を厳密に追跡するには MToE の枠が必要【8:p.5†】。
-
スペクトルギャップ問題(局所量子 Hamiltonian のギャップ有無):不可判定。
-
RG フローの非計算性:一般のリナーマリゼーション群流が非計算的になり得る。
-
テンソルネットワーク/スピンネットの計算困難性、2次元 QFT の不可判定的性質など、現代理論物理の要所に不可判定セクターが散在。
計算核 F_QG の上に、T を用いる MToE を重ねることで、非計算的だが物理的に意味のある性質を“証明不能=無意味”にしない。これは「計算説明の破綻 ≠ 科学の破綻」を保証する構造だと位置付ける。
5) シミュレーション仮説への示唆
「宇宙は計算機上で完全に再現可能」という前提は、F_QG 全体=物理理論の全体という同一視に依存する。しかし MToE は、物理的真理が F_QG を越えて非計算層(T)を含むことを主張。ゆえに有限アルゴリズムによる宇宙の完全再現は原理的に不可能、との結論に至る。
6) 位置づけと限界
-
位置づけ:F_QG を厳密な形式系とみなし、論理三定理(Gödel–Tarski–Chaitin)を系統的に適用したうえで、T(x) と非効果的推論を導入するメタ理論構成を提示。Lucas–Penrose 型の「非アルゴリズム的理解」の物理的表現としても読むことができるがT の自然化(自然界における実在化)と検証戦略は今後の課題。OR(orchestrated objective reduction)等との関連付けは興味深いが、ここでは構想段階に留まる。




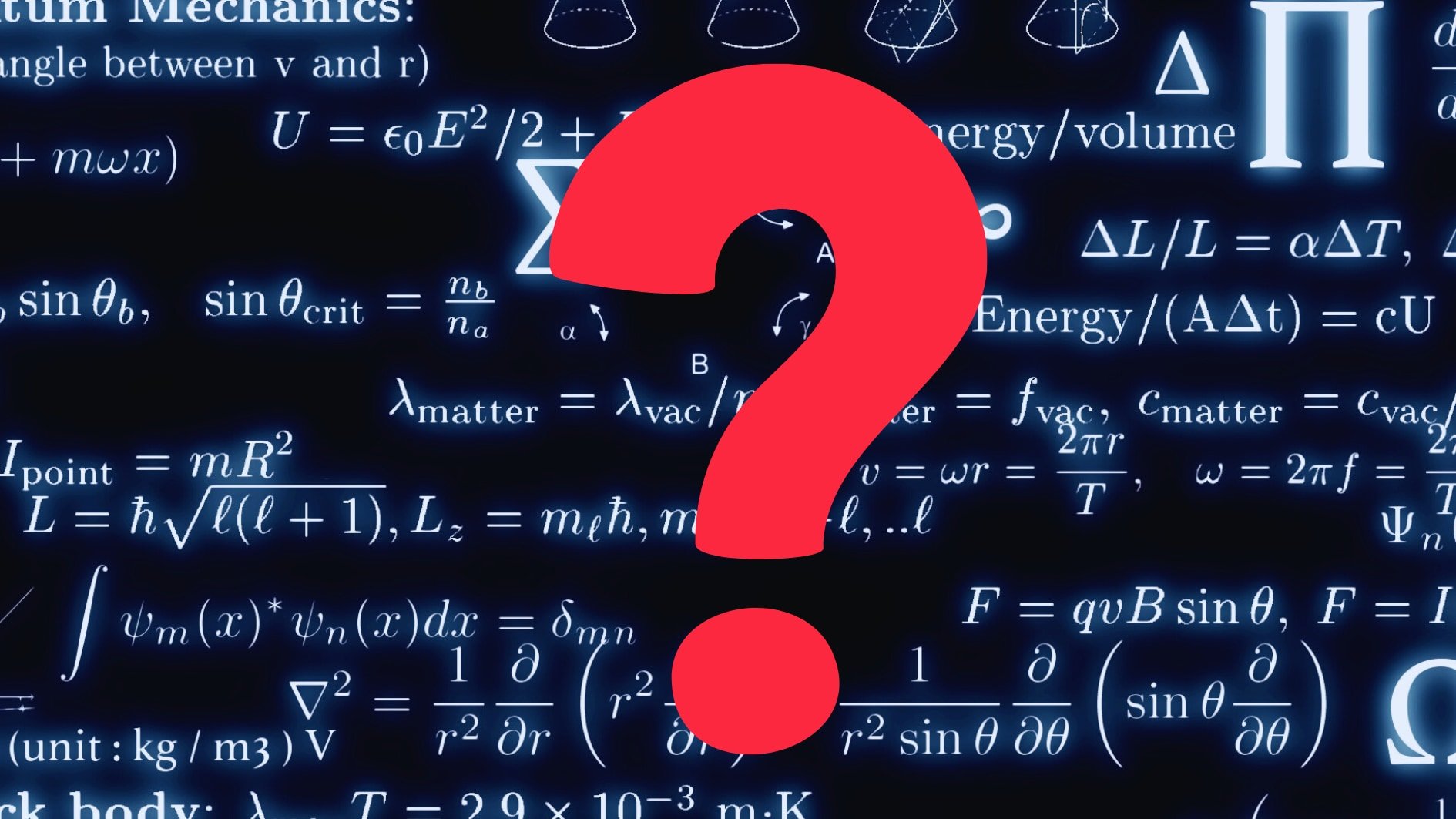























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
















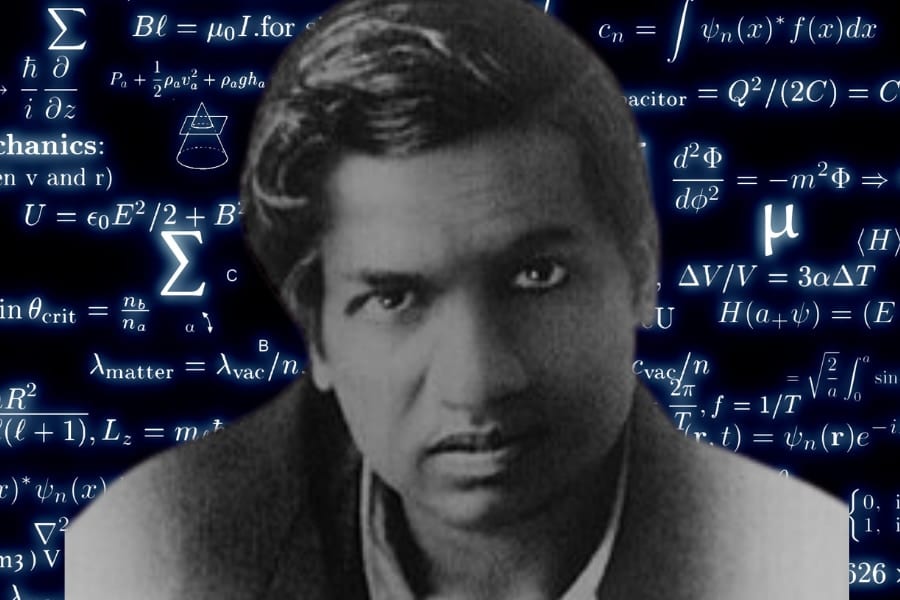
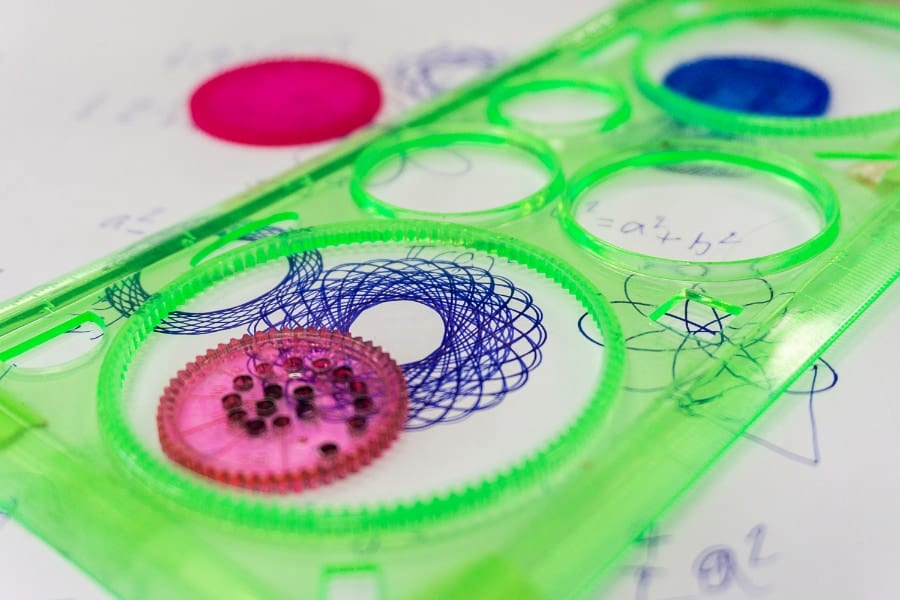
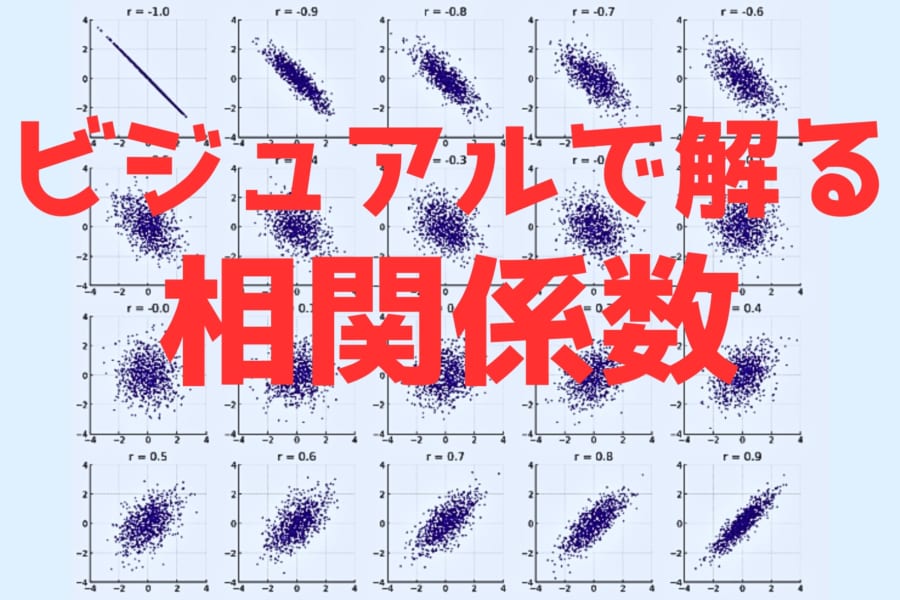
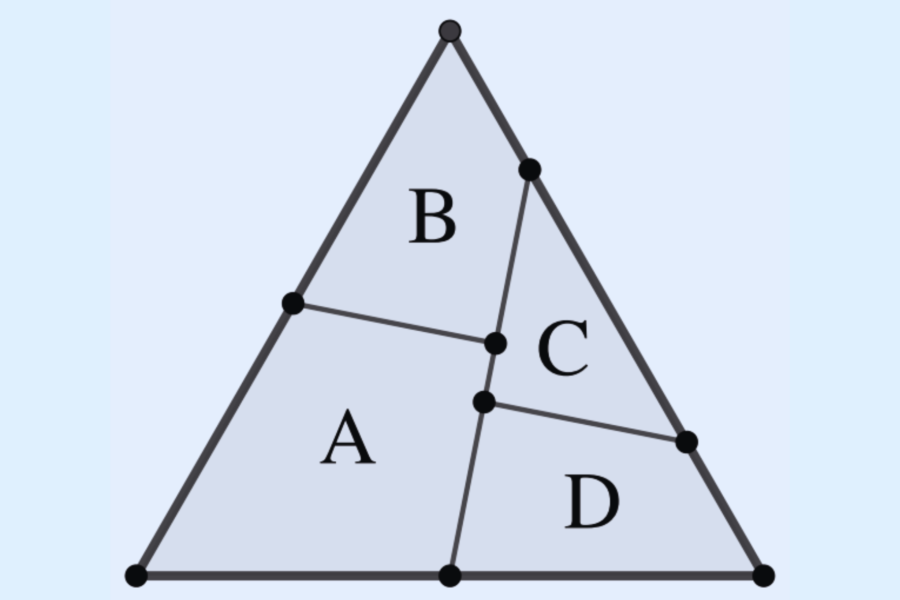
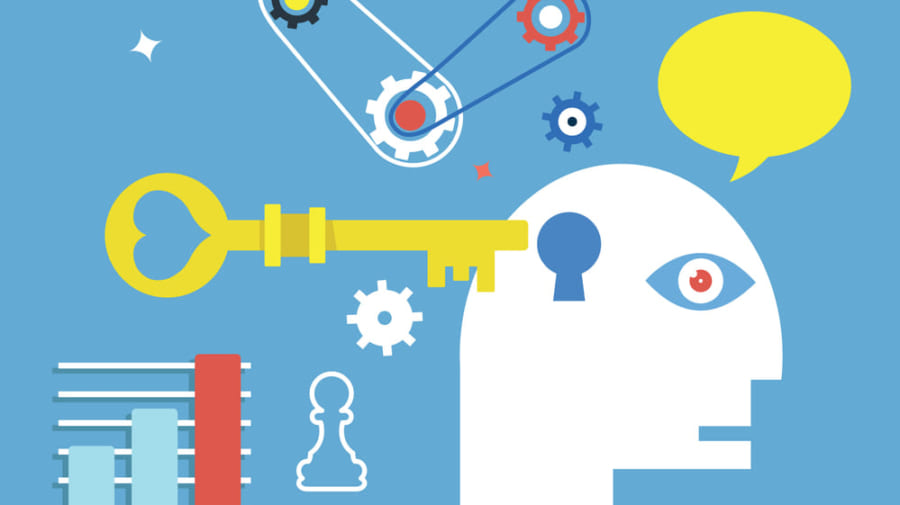







無限に求め続ける必要があるのなら無限に求めればいいだけでは?
やることがなくならないってことが分かったのですから物理学者たちはむしろ喜んでいるのでは?
永久機関肯定派なのはわかりました
1.我々はアルゴリズムを用いてシミュレーションを作成できる。
2.シミュレーション世界内の住人は本文と同じ論法でその世界はシミュレーションではないと結論する。
3.しかしその世界はシミュレーションなので矛盾。
1と2のどちらかが誤ってるわけだけど、1にシミュレーションの完成度を求めないなら、すでに実現できてるので、2が誤りかと。
シミュレーション世界内の住人がその世界のアルゴリズムに辿り着ければ、世界はシミュレーションかもしれないと結論づけるでしょう。「本文と同じ論法」が使えるとしてる点が間違いだと思います。
If you can email me on my email [email protected] the email I can use to send me toe candidate l et me know and delete this message.
ディラックのデルタ関数は、数学者が考えたものでは、ないじゃん。物理学には、まだ、新しい数学関数を発見する余地があるのでは?
川勝さん、いつも興味深い記事を解説ありがとうございます。
しかし、
最後のページ、専門化向けざっくり解説の文章は、日本語として非常に不自然で、説明文としては論理の繋がりが弱くなっています。おそらく、ChatGPTの推論モードが出力した文章をそのままにしているからだと思われます。
例えば、
「不可判定。」「~セクターが散在。」など、体言止めが頻発し、論理的な説明よりもメモ風の断片になっています。本来なら「〜である」「〜といえる」と動詞を使っているはずです。
また、
4)物理への含意:不可判定性が表れる領域
の、文中【8:p.5†】のような表記は、「出典」を示すための引用マーカーです。これは GPT が情報検索やファイル参照を行ったときに内部で使う形式であり、これは「推論モードの文をそのまま残した痕跡」だと思われます。
他にも、数式や記号の羅列(例:Th(F_QG) := { phi in L_QG : Prov(…) })がそのまま入り込み、これは説明文ではなくメモの断片のような印象です。
なぜ推論モードで日本語が不自然になるのかを考えると、
推論モードでは、内部で推論のステップを検討してから最終文をまとめるのですが、このとき「論点の結論を短くまとめる」方向に偏り、途中の“なぜ・だから”といった論理を明確にするための接続詞などが省かれやすくなります。
結果として、結論や要点は言うのに、前提や根拠のつなぎが抜け、読者には飛躍に見えるのです。
このままでは読みにくすぎるので、上記のような文章を自然な表現に直す工夫が必要だと思います。
メタ理論は孫の手みたいなものかな。自分じゃないものを使えば背中も搔いてる腕自体も掻ける
また不完全性定理が濫用されてる……
中身をちゃんと見ずにこんな事言うのはホントに良くないんだけど、雑誌が微妙すぎないか?
IF0.624でQ2て…
こういう理論を聞いているとニセモノの宝石を押しつけられているような気がする(+_+)
非アルゴリズム的な要素を理論に組み込めば記述証明できるなら、それは理論と呼べるのか?
また、神の存在証明は、多分出来ないかと。
でも、どうせメタ理論が不完全だから、それを補完するメタメタ理論がでてくるんでしょ?
論理の外とかスピリチュアルが捗りそう
最後のページ、絶対ChatGPTに書いてもらった文章コピペしただろ
この世に「無限」とか「0」とかが存在していると認識している事自体が間違っているんだよ。
単純に、人類が先に進むための道具が論理で、論理だとまだ足りない部品があるから他の手段は今はない。時代が進むのに期待するしかない。そんな話でないの
だから今科学の人員も資金も足りない現状に一致するし
AIを自由に使いこなせたら、格段にいろんなことがわかるのかな?ただ指示役はあくまですべてを理解した人しか想像すらできないでしょうが。
zenodo投稿論文の『ガンマ理論』v1~v4にその解決策の論文概説を投稿しております。
本記事はその私の論文の追い風となりました。
ありがとうございます。
よろしければ、ガンマ理論をお読み下さいませ。
上位の存在がこの宇宙のシミュレーターを走らせた上で、気まぐれに介入してるだけなのでは?これはどうやって否定するの
そもそもが、私どもの認識出来ている世界なんて、既存の物理法則の枠内でしかありませんし。
ブラックホールの存在自体が冷静に考えると異常ですし、量子力学なんてものになってくるともう、
理屈でどうこうなるものではありませんし。
結局、MToEは「完結できない有限体系」→「外部にTを置く」という伝統的逃げ道。
これは “無限と外部依存を温存したままの再定式化” にすぎない。
外部不存在、内部無矛盾、限界予測、自己予測と自己体現を全て同時に達成した理論=内部での自己監査出来る定理しか、基底理論にはなり得ない。
https://note.com/melanie_daisky/n/nc64daaca0076
Proofが一切ないけどこれまともな論文なんですかね
一般化の厳密性:「熱化が決定不能であることが ToE 全体の不可能性を意味する」点は依然として論理的に強い仮定を含みます。arXiv 版は MToE を導入すれば問題を扱えると示すが、“どのクラスの理論的拡張でも undecidability を避けられない”という逆方向の普遍的証明は提示していません。つまり「量子枠組みを超える別の ToE のあり得る形」を排除する論理的証明は無いままです
ロングバージョンでも万物の理論が不可能というまともな証明はないそうです。
ひどくない?
やっぱ「オッカムの剃刀」は害悪やったんやな。