くわしい解説(専門家向け)
本論文は、二次元の超流動ヘリウム薄膜における量子真空トンネル生成としての渦の核生成を、外因的(境界に依存する過程)と内因的(バルクでの過程)に分けて定式化し、従来ほぼ一定とみなされてきた渦の有効質量がトンネル過程の進行に伴って連続的に変化することを明示的に取り込んでいます。
特に、均一な超流によって駆動される渦・反渦ペアの自発生成を、量子電磁力学におけるシュウィンガー効果と厳密に対応させ、零温における量子相転移として記述しています。
解析はWKB近似を用い、数値評価可能な生成率を与える点が特徴です。
理論は長波長ボース超流体作用から出発し、渦の有効作用にベクトルポテンシャル様の項を含める形で構築されます。
渦中心まわりの位相・密度ゆらぎを消去すると、有効作用は最小形に帰着し、そこには位置依存の動的有効質量と流れエネルギーが現れます。
孤立渦では質量とエネルギーが単純な関係を満たしますが、境界像渦や渦対生成を含む場合には成り立たず、質量はトンネルの進行とともに増加します。
これが作用積分に決定的な影響を与え、生成率の大小を左右します。
外因的核生成の検討では、半円状の突起を伴う境界を超流が横切る幾何を考え、突起近傍での流れの増速によりエネルギー障壁が形成されることを示します。
背景流速を上げると障壁は低下し、臨界速度に至ると消失しますが、実際にはその前に量子トンネル効果で渦が核生成されます。渦の質量は突起から離れるにつれて増大するため、トンネル過程の初期では比較的容易に進行し、その後は減速するという特徴的なふるまいを示します。
内因的核生成では、境界から離れた領域に一様超流を加えると、渦・反渦ペアの自発生成が起こります。
ここで有効ポテンシャルは、対間の引力である対数ポテンシャルと外部流れによる一様な引張り力の拮抗で形成される障壁を持ちます。
渦の有効質量は対の分離とともに増大し、流速が増加するにつれて障壁が低下し、最終的には臨界速度で消失します。零温では障壁を量子トンネルで越える確率が支配的となり、生成率は閾値的に急増します。
典型的には、実験で得られるクロスオーバー速度は臨界値の一桁低い領域に現れると見積もられます。
この研究の含意は二点にまとめられます。
第一に、位置依存する渦質量を正しく組み込むことで、これまでの三次元系での理解に比べ、二次元系では渦の生成がはるかに有利になることが示されました。
これは障壁下での質量の増加が対数的に緩やかであるため、作用が相対的に小さく抑えられる幾何効果によります。
第二に、内因的核生成は零温における量子相転移として捉え直せるため、有限温でのコスタリッツ–サウレス転移との連続的な接続が期待されます。
超流速を制御しながら渦の発生数を計測する「渦カウント実験」によって、生成率の指数的性質と前因子を同定することが可能になると提案されています。
さらに、フォノンやロトンといった準粒子との散逸結合は定式化上取り込めますが、その補正は小さいため主結果に大きな影響を与えないとされています。
観測上の制約としては、外因的過程では境界の粗さやケルビン波励起が問題となり、内因的過程では膜厚による最低励起エネルギーが鍵を握ります。薄膜かつ低温条件が観測に有利であると結論づけられています。
最後に、流れが排水口に向かう幾何を考えると、半径依存の流速と密度を背景にホーキング放射のアナログ現象を模倣できる可能性が示され、さらに連続生成が引き起こす量子アバランシェや二次元量子乱流への遷移といった拡張も議論されています。
総じて、本論文は、座標依存の渦質量を取り込んだ厳密なWKB定式化と、シュウィンガー型の内因的核生成を量子相転移として再解釈する二本柱によって、二次元薄膜系での渦核生成の理解を刷新しました。
理論的に数値評価可能な予言を与え、具体的な実験手順まで示したことにより、凝縮系の量子真空トンネル研究を一段と現実的な段階へ押し上げた点に大きな意義があります。




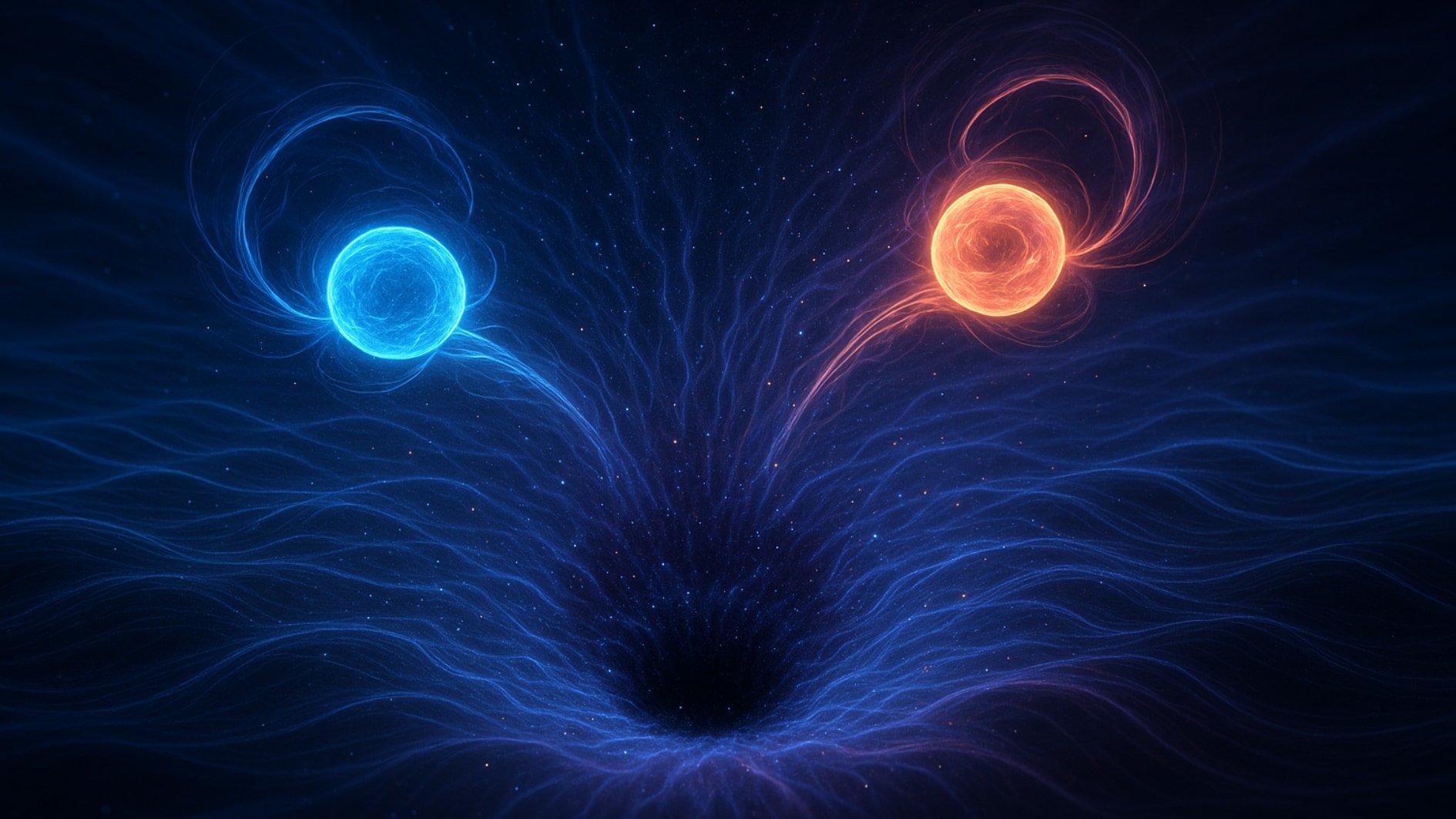





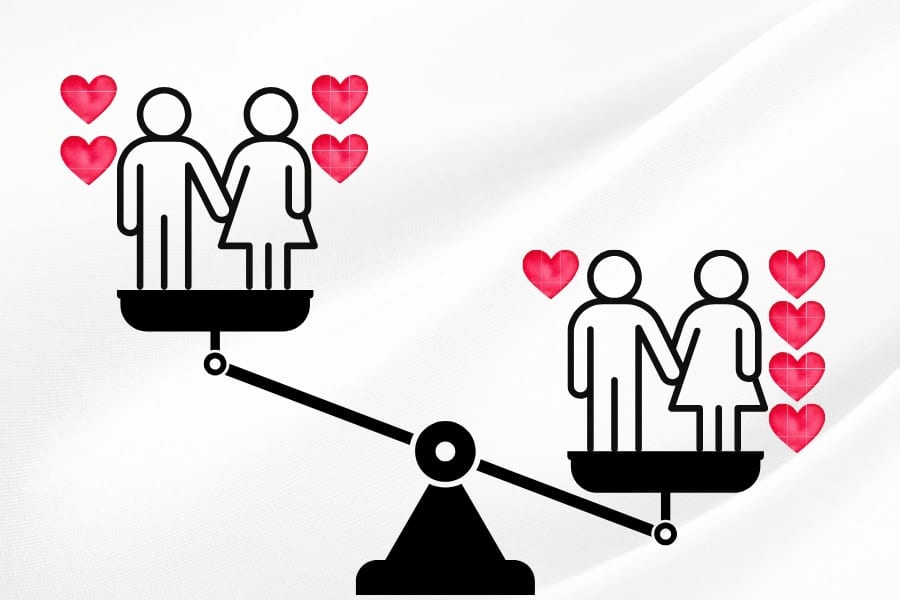


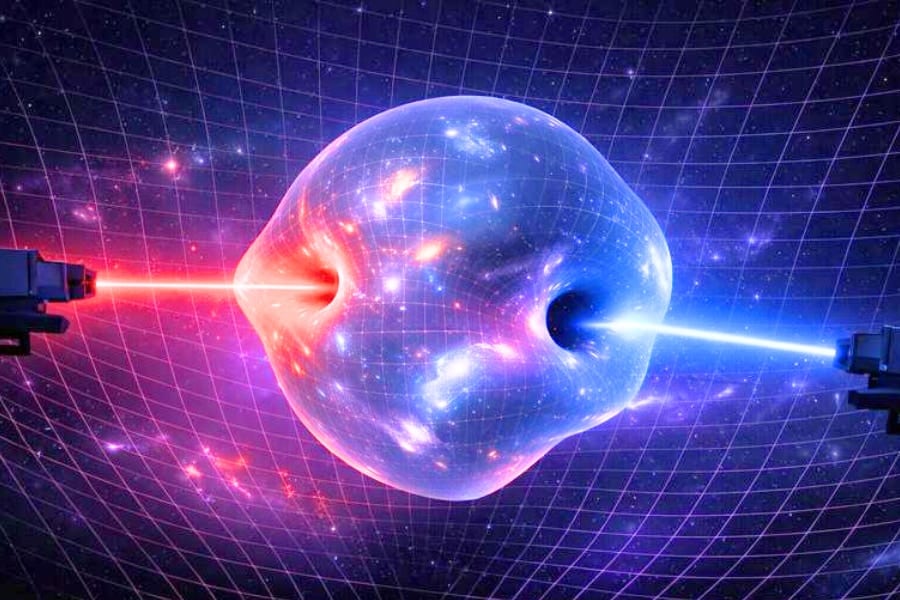
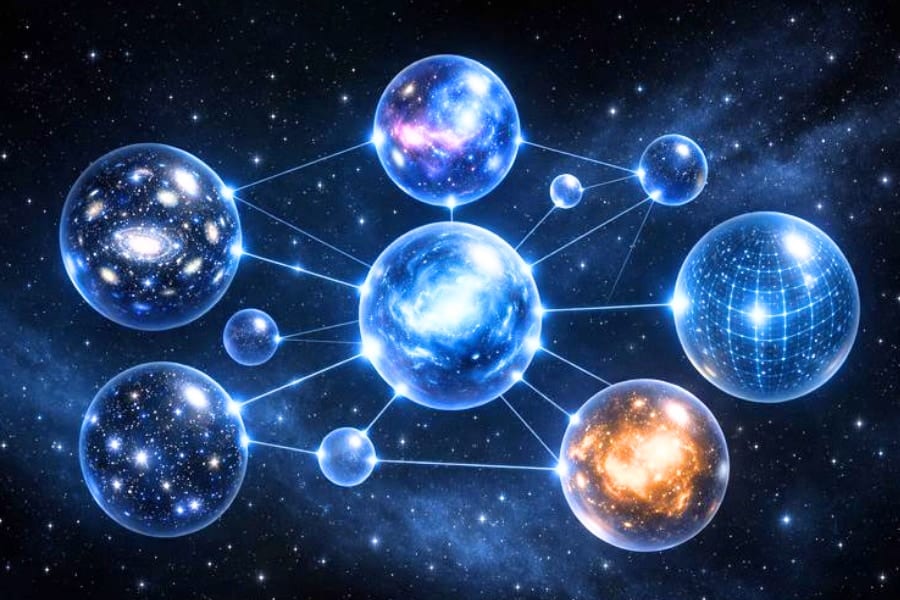















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)















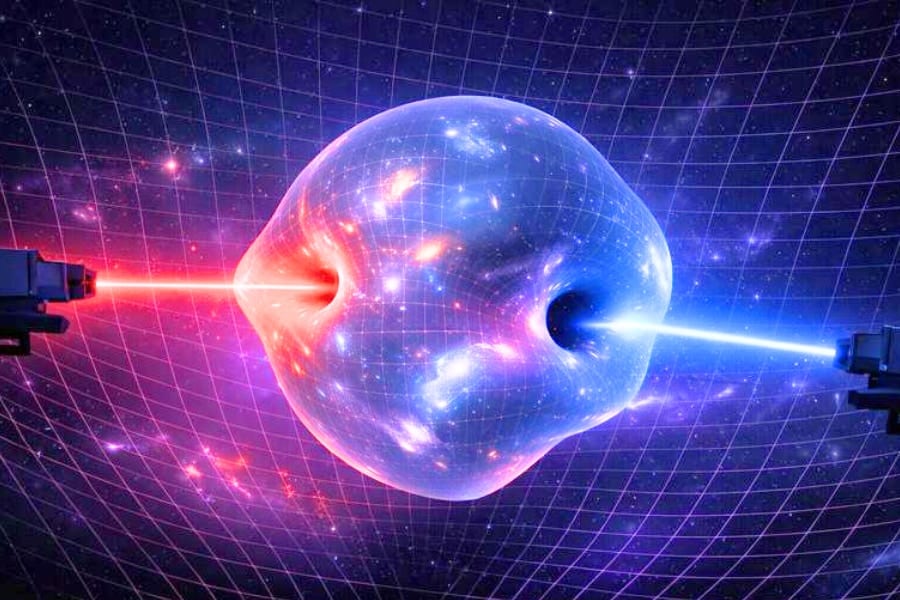


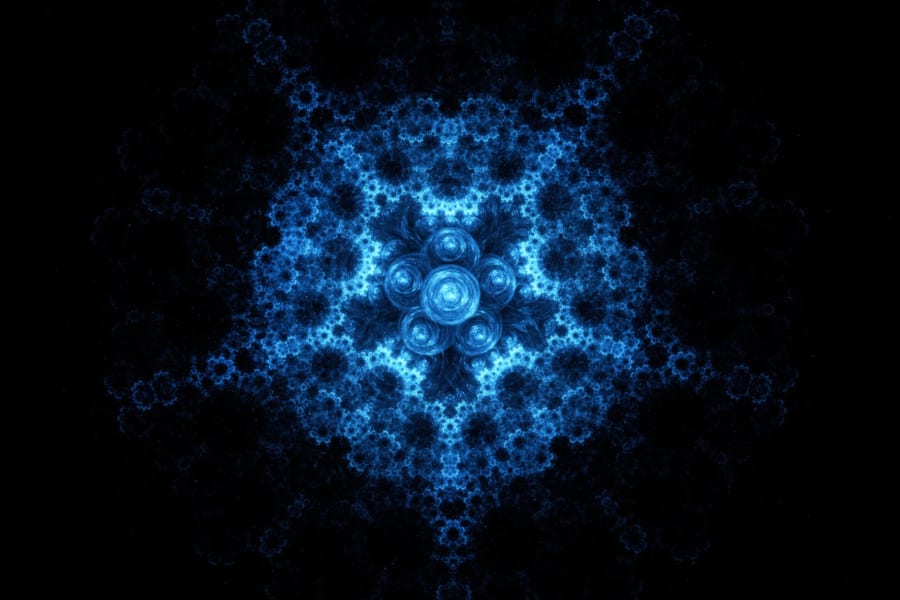

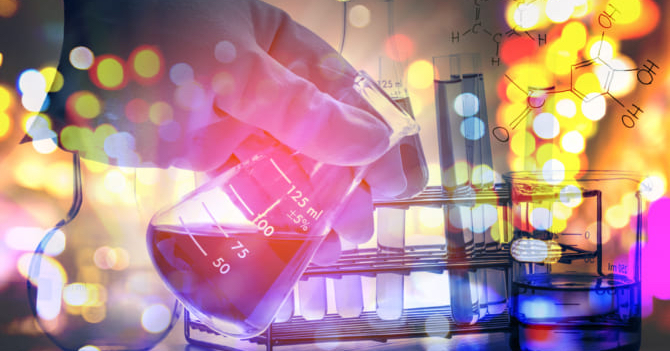







模倣じゃなくて模倣する理論の提唱じゃねーか
シュウインー効果の何も無い真空から生まれるという見た目現象は私たちの周りにも存在します 日常の空間から白い発光体が飛び回り空間や物質に消えていきます 余りにも日常的な虫や埃などと類似しており私達は対比や過去の知識と比較することで思考を確認する為目の前の現象を宇宙現象と結びつけることが出来ません 科学研究に大事な条件の再現性を重視すると大きな研究課題に思われます
うろ覚えだけど、十年以上前の某科学雑誌(の日本語版)に掲載されていた論文で、アクチノイドのような特に重い元素のターゲットに、加速器を用いて重金属イオンのビームを照射し、「特に重い元素の原子核」と「重金属の原子核」を衝突させる事で、一瞬だけではあるものの陽子数が非常に多い原子核(=陽電荷の空間密度が極めて高い領域)を作り出して、その高い正電場によって電子-陽電子対が発生する事を期待する、という構想が論じられていたのですが、その話はあれからどうなったのかなぁ…
うちでは、コバエが無から発生してるよ
カオスが量子効果のマクロ的な模範ということか?
ナビエストークスを逆に量子的に説明できる可能性とか
模範そのものの妥当性がいえるなら、無から有が生まれるかどうかと同等かそれ以上に
すごい発見ではなかろうか
ということではない
とおもう
現代物理学では完全な「無」は存在しないと言われているため、『”見た目上”無から有が生まれる』という記事名のほうがより正確だと思われます。