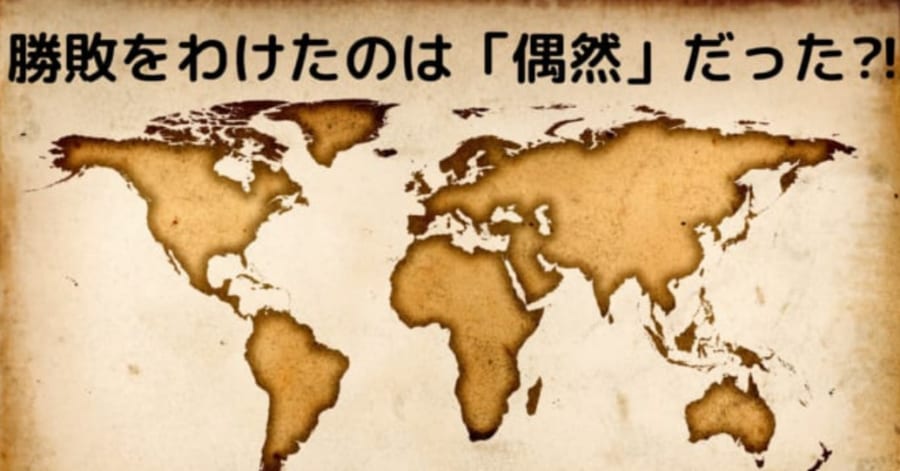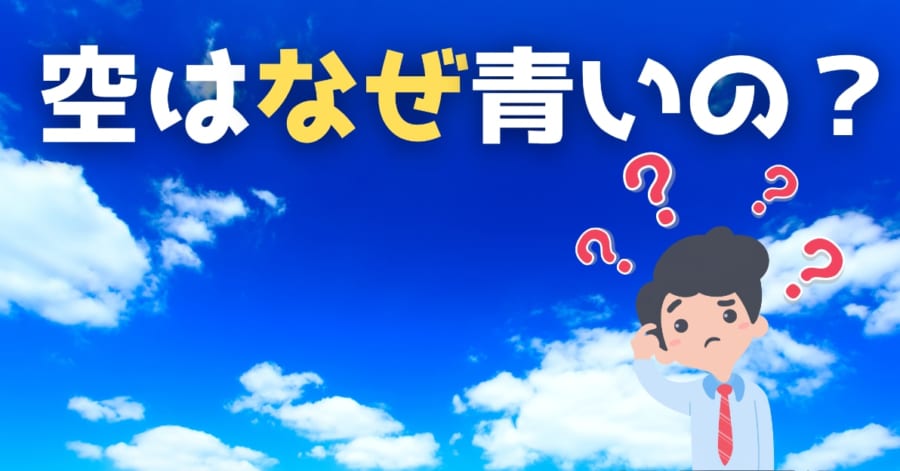恐怖が楽しい理由

世の中には、わざわざお金を払ってまで怖い思いをしたがる人がいます。普通、人は痛みや恐怖からは逃れたいものです。
それなのに、遊園地のお化け屋敷やホラー映画には行列ができ、激辛グルメやジェットコースターにも熱狂的なファンがいます。
事実、この10年でホラー映画の市場シェアは約2倍(2013年4.87%→2023年10.08%)に伸びており、怖がらせる娯楽ほど人気が高まっているのです(アメリカの映画市場データによる報告)。
この不思議な現象について、心理学者たちはこれまでにも様々な説明を試みてきました。
例えば、一つはスリルを追い求める性向、いわゆる「センセーション・シーキング(刺激追求型の気質)」です。
また、これまでの研究によって「怖さ」と「楽しさ」は逆U字、つまり“ほどよい恐怖が一番楽しい”という関係があると考えられています。
このことは人類は適度な恐怖を遊びとしてとらえる性質を持っていることを示しています。
実際、夢の「脅威シミュレーション理論」では、私たちの心は古くから、襲撃・追跡・迷子といった危険を仮想的に何度もリハーサルし、察知や回避のスキルを鍛えるように進化してきたとされています。
お化け屋敷やホラー映画は、その“稽古場”を現代に残したものだとみなせます。
安全圏から恐怖をのぞくとき、私たちは「どこで逃げるか」「音や影をどう手掛かりにするか」といった判断の回路を、痛手なく試運転できます。
こうした反復練習が、生き延びるための力を育ててきた可能性もあります。
そして、生存に有利になる行動に対して進化はそれを「快」と感じるように変えてきたのです。
また、感情には“後味の快”があるという考え方もあります。
対過程理論では、強い恐怖の直後には安堵や高揚といった逆向きの感情が立ち上がり、繰り返すほど恐怖は弱まり、後味の快が強くなるとされます。
絶叫マシンやホラー映画の「見終わったあとの爽快感」や「笑い合う高揚感」がやみつきになるのは、この反動的な快が学習によって強まるためだと説明できます。
そして、「恐怖の共有」という社会的な側面も重要です。
人は恐怖を共にすることで仲間意識を高めたり、絆を深めたりする傾向があります。
文化人類学的には、祭りや儀式の中にあえて恐怖や不安を煽る要素を盛り込み、その感情をグループで共有することで集団の団結力を高める仕組みが昔から知られています。
この文脈で言うと、「なまはげ」もまたその一例と言えるでしょう。
しかし、恐怖を好む理由はそれだけではありません。
もう一つの有力な考え方として、「人生経験をコレクションしたい」という欲求があります。多少苦しくても珍しい体験を思い出として積み上げ、自分の心を豊かにしたいという考え方です。
言い換えれば、「多少不快でも心が揺さぶられる体験こそが自分を成長させる」という価値観です。
ただし、この考え方は、スリルや恐怖の心理を説明する従来の理論に比べ、研究があまり進んでいませんでした。そこで今回の研究チームは、心理的豊かさを追い求める内面的な動機が、恐怖や不快な体験を求める心の働きと関係しているのかを調べることにしました。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)