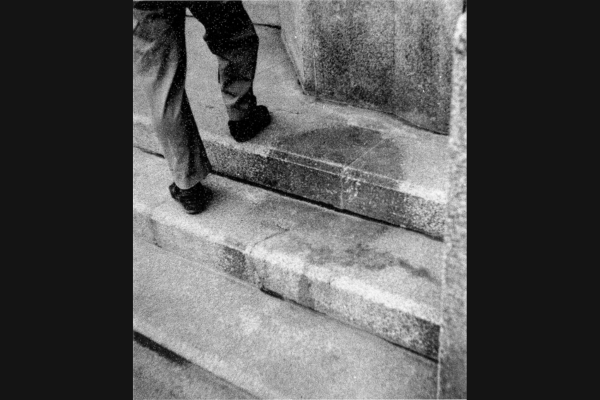動物模様の再現に挑む!従来のモデル「反応拡散系」とは
自然界には、整然とした美しさと、絶妙な“不完全さ”を併せ持つ模様があふれています。
シマウマの縞やヒョウの斑点、ハコフグの皮膚の六角模様など、一見すると規則正しく見えますが、よく見ると一本ごとの太さや間隔、斑点や六角形の大きさや形が微妙に違っていることに気づきます。
こうした“美しく不完全な模様”が、どのような仕組みで生まれるのか。
その基本的な理論は、1952年に数学者アラン・チューリングが提唱した「反応拡散系」にさかのぼります。
彼は、「組織が発達するにつれて化学物質が生成され、コーヒーにミルクを一滴落とすとそこから模様が広がるようなプロセスで、体内に拡散されていく」という仮説を立てました。
体内で広がる化学物質の濃度が細胞のふるまいを変化させ、それぞれの場所で色素が生まれたり抑えられたりして、模様が自然に現れるというのです。
この理論は、シマウマの縞や魚の模様など、実際の生き物のパターン形成を説明するのに役立ってきました。
しかし、計算機で反応拡散系をシミュレーションしてみると、ミルクとコーヒーの境目がなくなっていくように、どうしても「模様の輪郭がぼんやりしてしまう」という問題が生じました。
また、「斑点や縞の大きさや間隔が均一になりすぎてしまう」ことも課題でした。
自然界で見られるような、“粒々の質感”や“細かいズレ”“途中で模様が途切れる”といった要素までは、従来のモデルでは再現できなかったのです。
このような限界を乗り越えるため、コロラド大学ボルダー校の研究チームは「自然の模様がなぜ“美しく不完全”なのか」を数理モデルで解き明かすことに挑みました。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)