反応拡散系を改良し、「美しく不完全」な動物模様の再現に成功
まず研究チームは、2023年に反応拡散系に新しい要素「diffusiophoresis」を加えました。
これは、拡散する粒子が他の粒子を引き寄せる現象を指します。
身近な例でいうと、洗濯で洗剤が洗濯物から水に広がるとき、汚れが布から引き出される原理と同じです。
この効果を加えることで、たとえばオーストラリアのハコフグに見られる六角模様のような「輪郭のシャープな模様」を計算機上で再現できるようになりました。
しかし、ここで新たな課題も見えてきました。
それは、「模様が完璧すぎてしまう」という点です。
六角形がすべて同じサイズや形で、間隔もピッタリ等間隔になってしまい、実際の動物の模様にあるような“自然なばらつき”や“線の途切れ”、“粒々の質感”までは出てこなかったのです。
そこで今回、チームはさらにモデルを進化させました。
新たな改良点は、「細胞(粒子)にそれぞれ違う大きさを与え、個々が重ならない“硬い球”として扱う」ことです。
イメージとしては、大きさがバラバラなピンポン球が細いチューブを流れていくようなものです。
大きい球は小さい球より太い輪郭線を描き、時に球同士が詰まって流れが途切れますが、似たような現象を細胞に生じさせるのです。
実際、細胞同士がぶつかって詰まったり、大きい細胞が集まって太い線や模様を作ったり、小さい細胞が集まって細い線ができたりと、現実の生物の模様にある多様な“ズレ”や“粒状感”が自然に生まれるようになりました。
さらに、細胞の大きさ分布や移動速度、粒子の密度などのパラメータを調節することで、模様の太さやばらつき、粒々感の強さをモデル上で自由に再現できることも示されました。
研究者は「細胞にサイズを与えるだけで、模様の破綻や粒状テクスチャが現れる」と強調しています。
この仕組みの発見は、生物の模様の不思議を解き明かすだけでなく、今後は「周囲の環境に応じて色や模様を変える布や材料」、「指定した場所だけに薬を届ける新しい医療技術」、「自己組織化するソフトロボット」など、幅広い応用のヒントにもなります。
研究者は「私たちは自然の“不完全な美しさ”から着想を得ており、この不完全さを新しい機能に活かしたい」と語っています。
動物の模様が“美しく不完全”である理由は、細胞や粒子の大きさや動きのばらつき、そのちょっとした偶然が重なり合って生まれる自然の奇跡です。
科学は今、その“ゆらぎ”の秘密を、数理モデルで明らかにしつつあります。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



















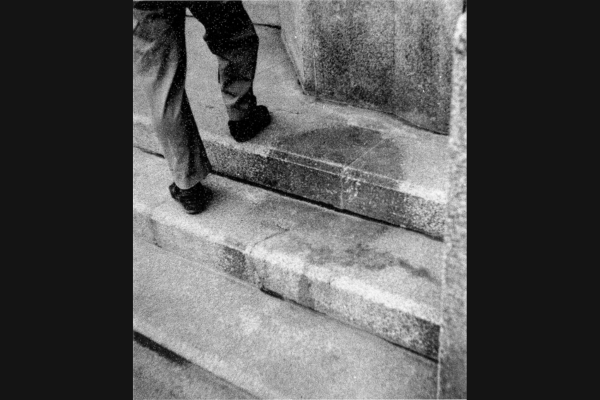

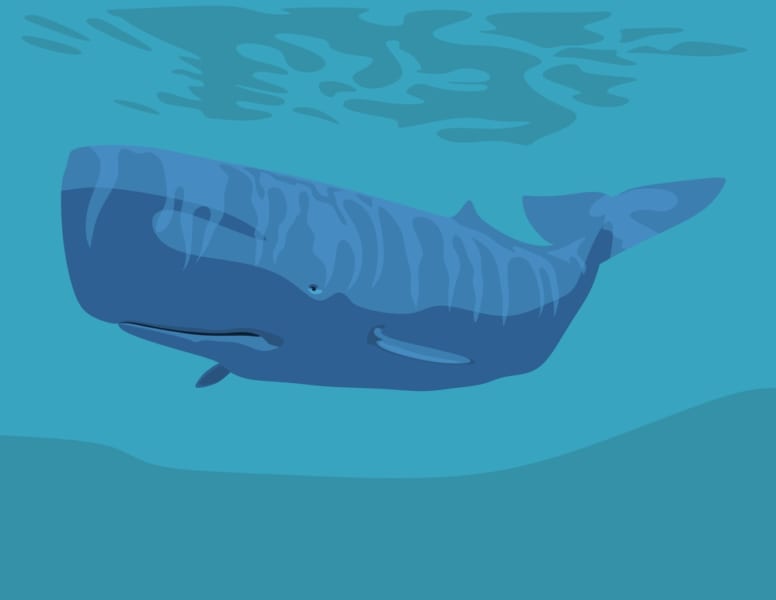






レポートのテーマが素晴らしいと思いました、そして自然界の神秘を追求しようとする科学者方の姿勢と自然界の生物を理論化する試み、精神と能力に感心いたしました。
美しく不完全と言うキャッチコピーにリーマン予想が思い浮かびましたが、特に関係無かった見たいです!
生き物の模様にかぎらず、よごしの手法としてモデリング一般で思考の材料になる
綺麗すぎるシミュレーションっていろいろ思い当たるものありませんか