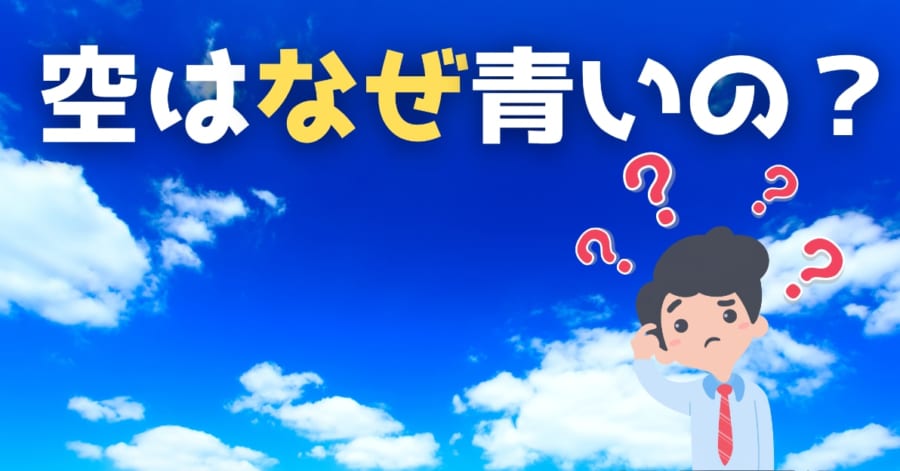わかりやすさは武器にも罠にもなる

単純な説明を好む人間の性質は変えられないのか?
答えを得るため研究チームはアメリカの成人約1000人を対象に実験を行いました。
実験の内容は一見シンプルです。
参加者には、いくつかの物語や出来事を提示します。
たとえば「アンティーク時計が壊れた」「ある患者が症状を訴えている」といった場面です。
そしてそれぞれの場面で、参加者に2つの説明を示しました。
ひとつは「原因がひとつだけ」の単純な説明、もうひとつは「複数の原因を組み合わせた」複雑な説明です。
例えば時計の例では「ばねの栓の不具合だけが原因」vs「歯車の摩耗とぜんまいの故障という二つの原因」、患者の例では「単一の病気」vs「二つの病気の併発」といった具合です。被験者は一般の成人であり、専門知識を前提としないシナリオでした。
もし偏りがないなら、単純な説明と複雑な説明は同じくらい選ばれるように思えるでしょう。
しかし結果は違いました。
被験者たちは提示されたシナリオの原因が日常的に良くあるケースでもレアな事態の場合でも単純な説明を選びやすいことがわかりました。
本来なら、日常的に見聞きする原因では複雑な説明の方が“より確からしい”はずですが、それでも単純な説明が好まれたのです。
これは、私たちの脳がいかに強く「わかりやすさ」を求めているかを示す興味深い結果です。
しかし、このような単純への偏りは、実験で「隠れた原因を意識せざるを得ない状況」でヒントとして与えると大きく変化しました。
追加の原因にスポットライトを当てて、参加者に追加材料のアピールを行ったわけです。
するとそれまで単純な説明を選んでいた人たちが、「あれ、ちょっと待てよ」と立ち止まり、複数の原因がある複雑な説明も無視せずに検討するようになったのです。
ただこの段階では、平均としては単純な説明への傾きがまだ残っていました。
単純さの持つ魅力は大きく、追加で考慮すべき情報を得ても、多くの人はまだ単純な原因を好んだのです。
そこで研究者たちは、さらにもう一歩進めて、工夫をしました。
今度は「隠れた原因」を単に指摘するだけでなく、「その原因が別の重要な結果も生み出す」——つまり“別の働きを持つ原因(代替原因)”として示しました。
つまり、「目立たない歯車」にスポットライトを当てるだけでなく、「実は時計の動きに直接関わる重要な役割の歯車」だと伝えたわけです。
すると、ようやく逆転が起こりました。
最初は「原因が1つだけ」の単純な説明を好んでいた人たちが、この手がかりによって「複数の原因がある」複雑な説明のほうをより多く選ぶようになり、それまで単純に傾いていた判断が反転したのです。































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)