
Point
■米コーネル大学が固形電池ではなく、流体バッテリーで動くフィッシュロボットを開発
■2本の電極の間を流れる電解質溶液の圧力が変化することで、シリコン製のヒレが動くという仕組み
■固形電池よりも保持できるエネルギー量が格段にアップし、再充電なしで37時間泳ぎ続けることが可能
涙はなくとも血はあるんです。
固形電池ではなく、人工の血流バッテリーで泳ぐロボットフィッシュが開発された。
開発を行なった米コーネル大学の研究チームによると、液体バッテリーは、重くて場所を取る固形電池よりもわずかなスペースでより多くの電量を保持することができるという。
研究主任のロバート・シェファード氏は「有機体を模倣した血液循環型のバッテリーというアイデアが、ロボット工学の新たな道を切り開くかもしれない」と話した。
研究の詳細は、6月19日付けで「Nature」に掲載されている。
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1313-1
溶液の圧力変化でヒレが動く!
今回製作されたロボットは全長40cmほどのシリコン製で、固形電池は一切搭載されていない。その代わり使用されているのが電解質のバッテリー溶液だ。
ロボット内には2本の電極が挿入されており、ボディ同様にロボットの柔軟な動きが可能なようにニッケル製のワイヤが用いられている。
バッテリー溶液はその間を流れており、電極から受け取った電気により圧力を変えるという。
具体的には、一方の電極側で溶液の圧力が増すと、その部分のヒレが外側に膨らみ始めるという仕組みだ。それと同時にもう片方の電極面にある溶液は内側に圧縮する。
これが交互に行われることでヒレの動きが再現されるというわけだ。
バッテリー溶液にすることで、ロボット内の貯蓄エネルギー量は固形電池と比べて325%も増量したとのこと。これはフィッシュロボットが再充電なしで37時間遊泳し続けるのに十分なエネルギー量だという。
ロボット工学において重要な点は、いかに自動で作動する時間を長くできるかということだ。今後ロボットは救命ミッションや深海探索といったタスクを任されることになるだろう。
そこで問題になるのは、エネルギーをいかに効率的に貯蓄しておけるかということである。ロボットは任務完了まで再充電しなくて済むようなエネルギー量を持っていなければならない。
しかし単に固形バッテリーの大きさや数を増やすだけでは、ロボットの重さが増すばかりである。
そのため効率的にエネルギーを保持することのできるバッテリー溶液は、ロボットの電力として極めて有効なのだ。




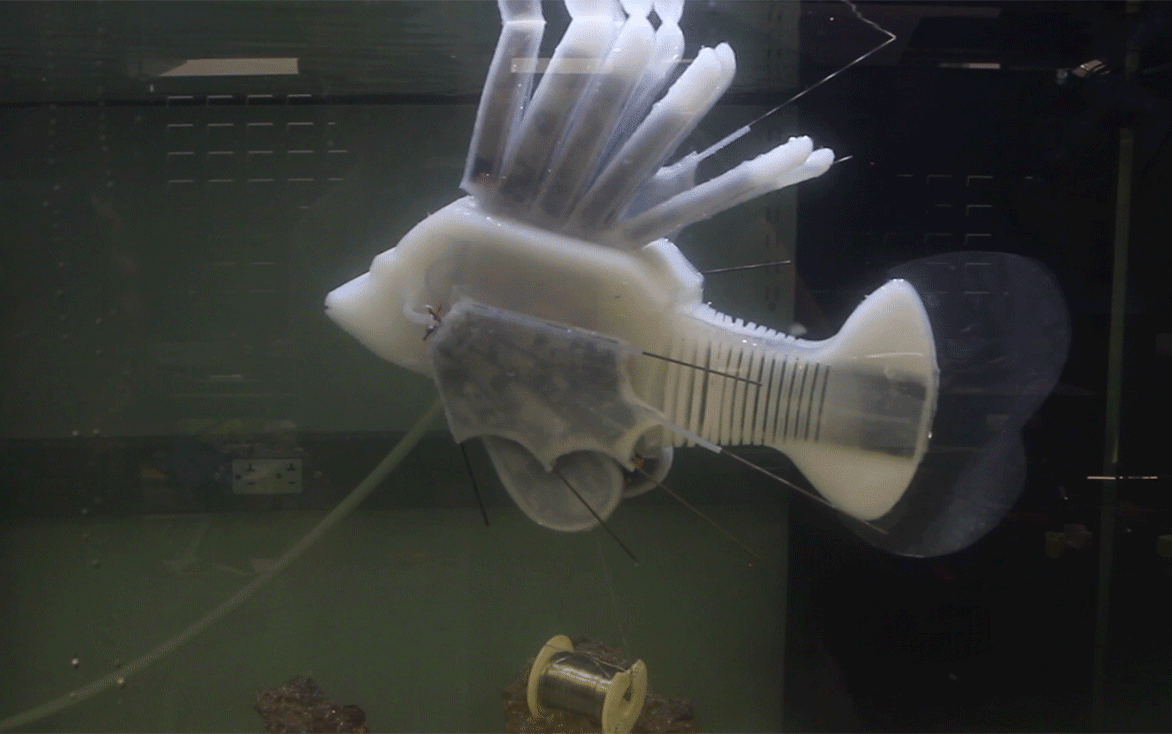

















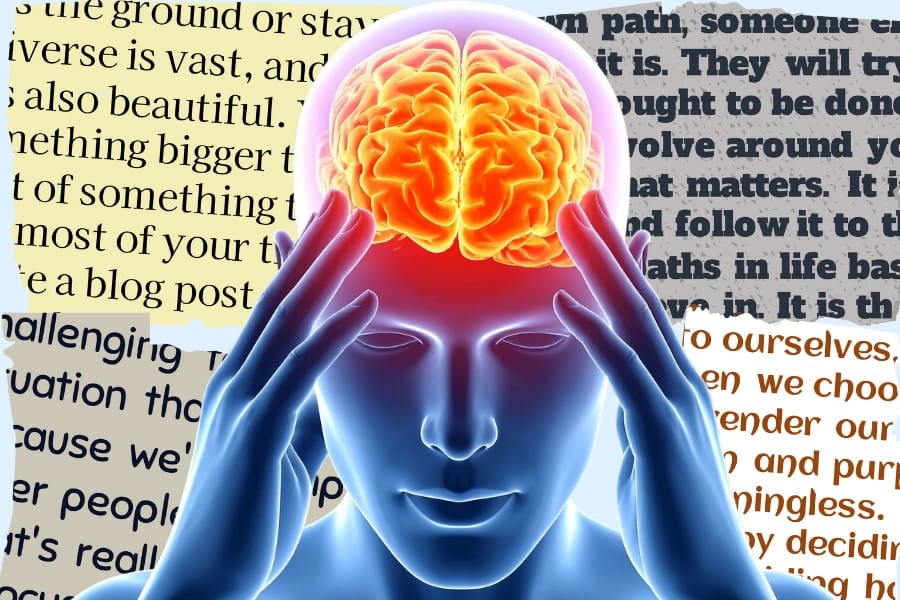





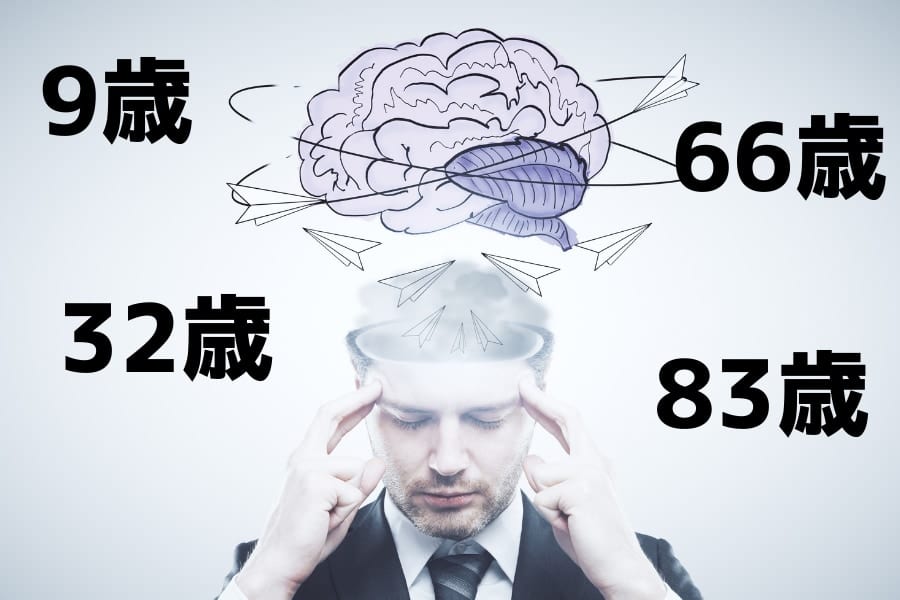



![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)







![流星のロックマン パーフェクトコレクション -Switch【Amazon.co.jp限定】特典 アイテム未定 & 【早期購入特典】『アレンジBGM4曲』+『「星河スバル」と「ウォーロック」の待ち受けキャラクター』DLC印字チラシ[有効期限:2027年3月27日(土)まで] 同梱](https://m.media-amazon.com/images/I/51NUH0kspfL._SL500_.jpg)




















