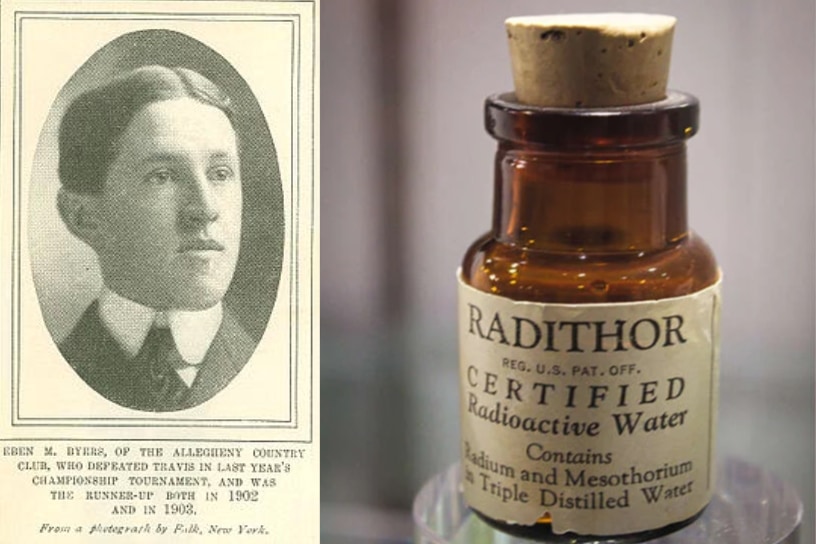獣医師は「犬の痛み」を総合的にみて評価する
研究者らは、獣医師の評価は、犬種に紐づく性格や行動などを勘案して行われるため、実際の痛み感受性と差異が生じるのではないかと推察しています。
獣医師が痛みに敏感だと報告した犬種は、感情反応テストにおいて、見知らぬものや人、大きな音を避ける傾向を示したそうです。

つまり獣医師らは、「ビビり」だったり、表現力豊かだったり、あるいは反応しやすい犬種特性を勘案したりして、「痛み感受性が高い」と判断した可能性があるのです。
一方、一般の人々は、犬種による痛みの感受性の違いを、主に犬の体格によると考える傾向があります。一般的に、大型犬はあまり敏感でなく、小型犬はより敏感だと考える傾向にあり、これらが実際の痛み感受性と合っていたというわけです。
チワワやマルチーズなどの「おチビさんたち」は痛みに敏感で、強そうなピットブルや、おおらかなレトリバー種は痛み耐性が高いという結果は、飼い主だけでなく皆が納得するものでしょう。
本研究により、犬種の特性や反応が、痛み感受性のイメージ形成に影響する可能性あることが示されました。研究者らは、「犬が痛みを感じているかどうかについての誤った認識は、治療に影響を与える可能性があるため、注意が必要です」と述べています。
研究者は今後、獣医師がどのように「犬種ごとの痛みの感じ方の印象」を形成したのかを評価することに焦点を当てたいとしています。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)