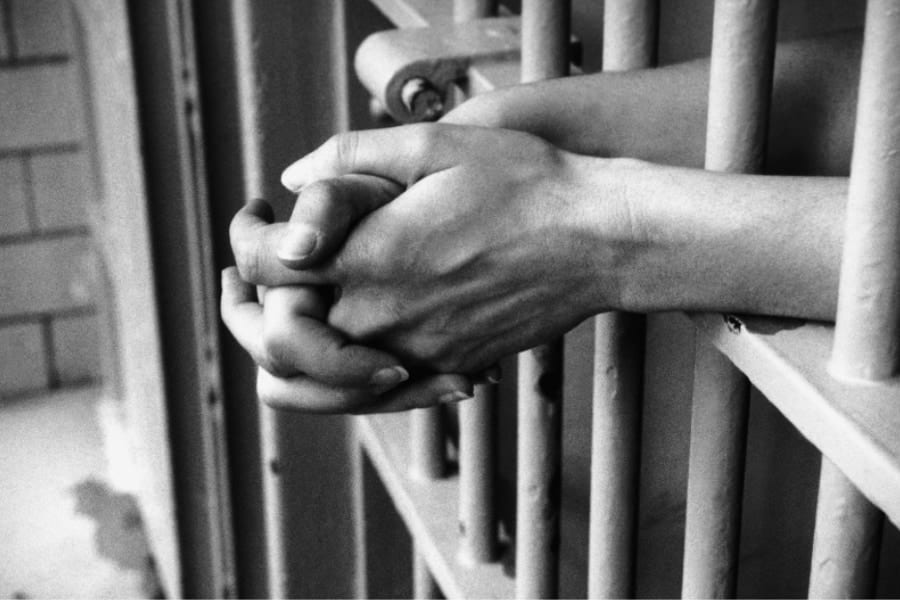人々はどのように自分を正当化するのか
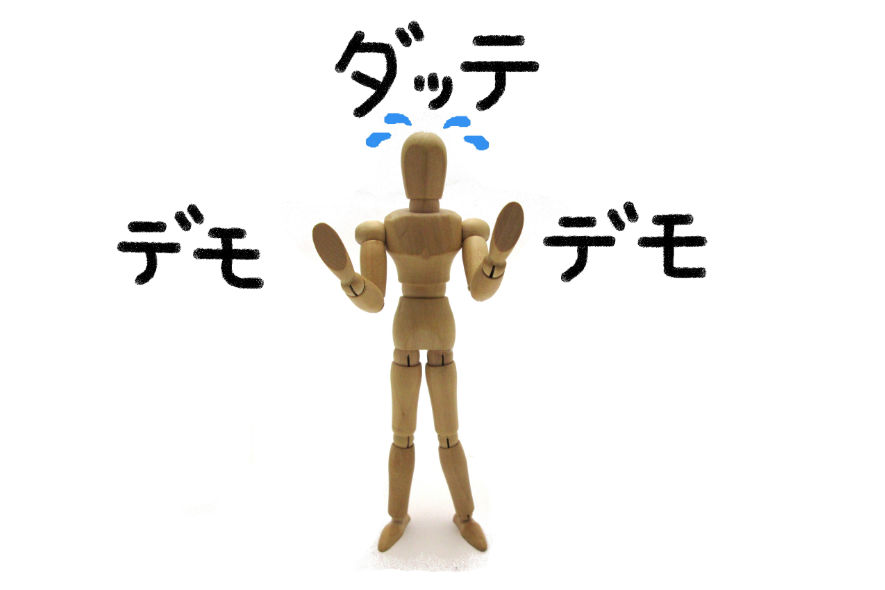
私たちの身の回りでも、フェスティンガーの実験で示されたような認知的不協和の基本原理が見られます。
最初に示していた例から考えると、喫煙者の場合、「タバコを吸いたい」という欲求に対して、「肺がんになりやすい」という情報は認知的不協和を起こします。
そこで喫煙者は「タバコは肺がんになりやすい」という認知を歪め、「そんな事実はない」「我慢する方が身体に悪い」と考えることで気持ちよくタバコを吸えるようにします。
また、「タバコが肺がんを誘引する」のではなく、「肺がんになりやすい人がタバコに引き寄せられているだけ」と、タバコと肺がんの因果関係を否定するかもしれません。
「なるべく節約したい」のに「ガチャ課金したい」人の場合も同様で、「課金は無意味な支出」と考えると、せっかく楽しみでゲームを遊んでいるのにストレスが強くなってしまいます。
そこで、「節約ばかりしていたら心の方が貧しくなる。課金は食費と同じ必要な出費だ」「いいゲームだったから楽しませてもらった分のお礼をしているんだ」と認知の仕方を変えることで、行動のストレスを減らすのです。
加えて、イソップ物語の「酸っぱい葡萄」もこれに当たります。
この物語の中で、お腹を空かせたキツネは、木の高いところに「美味しそうな葡萄」を見つけます。
しかし、何度跳び上がっても届くことはなく、入手できません。
この矛盾を解消するため、キツネは狙っていた葡萄に対して、「酸っぱくて美味しくないに決まっている」と認知を変えるのです。
いくつかの例をあげましたが、こうした正当化の傾向は、多くの人に見られるものです。
主観的には、自分の中の矛盾を解決することでストレスを減らして暮らしていくための心の機能と言えますが、客観的には「誤った判断・主張」である場合が少なくありません。
当然ながら、これらの正当化は、健康リスクを無視したり、人間関係を悪化させたりするものにもなり得ます。
では、自分の中で生じる正当化の傾向を抑えるには、どうすればよいでしょうか。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)