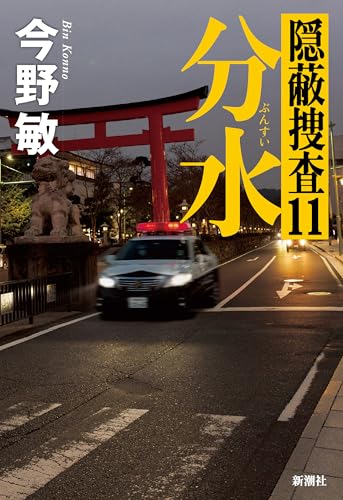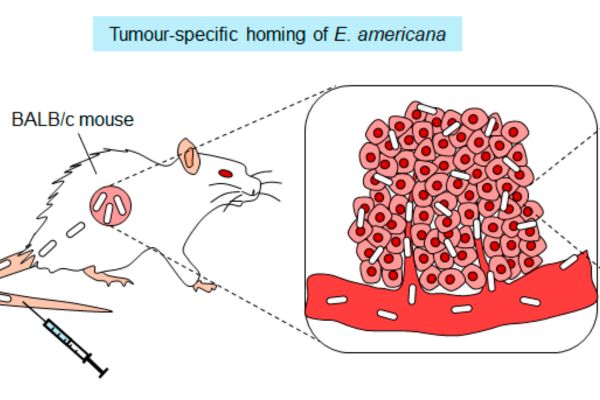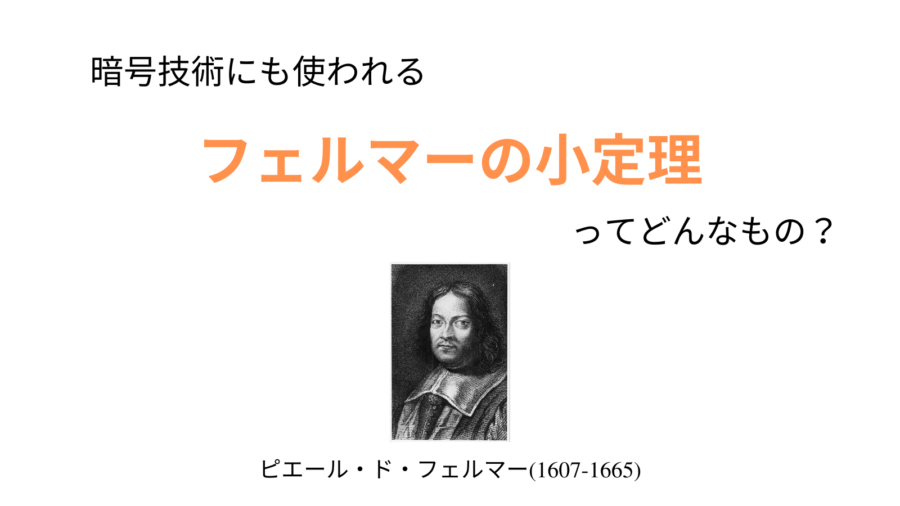薬が感情にまで効く? アセトアミノフェンの謎

アセトアミノフェンという薬は、多くの人にとって「頭痛や発熱が起きたときにまず手を伸ばす安心の相棒」です。
夜中に不意に電気が消えたとき、どこにあるのかもはっきり覚えていないのに、探せば意外とすぐ見つかる懐中電灯のように、いつも生活のそばにある存在といえるでしょう。
そのおかげで、実際にどんな作用をもっているのかを深く考える機会はあまりありません。
薬局で買った総合感冒薬や市販の頭痛薬の成分表をよく見ると、アセトアミノフェンが配合されていることがほとんど——つまり、わたしたちは意識していないだけで、頻繁にこの薬に助けられているのです。
ところが近年の研究では、アセトアミノフェンが「身体の痛み」をやわらげるだけでなく、「心の痛み」や「感情の強さ」にまで影響を及ぼす可能性がある、と注目されるようになりました。
たとえば、人間関係のトラブルで落ち込んだときの“心の痛み”や、他人の苦しみを見たときに共感する気持ちが、アセトアミノフェンを服用すると弱まるかもしれないというデータが出てきたのです。
さらに驚くことに、ネガティブな映像を見たときの嫌悪感だけでなく、ポジティブな画像を見たときのワクワク感までも“少し鈍くなる”のではないかという報告があり、つまりこの薬はわたしたちの「感情全般」を少しだけ麻痺させる効果をもつ可能性があるのです。
この「感情を緩和・鈍化させる」作用が話題になる理由は、私たちの行動が感情に強く左右されているからです。
よく「理屈ではわかっていても、感情が追いつかない」などといいますが、実際、リスクのある状況でどこまで踏み込むかは、論理よりも“怖い・怖くない”といった感情が決め手になることが多いのです。
もしアセトアミノフェンによって「不安」や「恐怖」といったネガティブな感情が弱まってしまうと、私たちが危険を危険と感じにくくなる恐れが出てきます。
実際、リスクを好むか嫌うかは「アフェクト・ヒューリスティック」という考え方でも説明されています。
これは、難しい計算をしなくても“直感的な感情”で判断してしまう人間の特性です。
たとえば、少しでも不安を感じれば「これは危ない」と足を引っ込めるし、逆に「面白そう!」と胸が高鳴れば多少の危険を冒してでも行動してしまう。
つまり、アセトアミノフェンのように感情を鈍くする薬は、この“怖い or 楽しい”という直感スイッチを誤作動させる可能性があり、結果として「まぁ大丈夫だろう」と高を括って、破裂寸前の風船にさらに空気を送り込むような行為に踏み切ってしまうかもしれません。
さらに、アセトアミノフェンは19世紀末から研究が始まり、20世紀に入って鎮痛・解熱薬としての地位を確立し、今や「約600種類以上の市販薬」に含まれると言われるほど幅広く流通しています。
アメリカでは週に一度は何らかの形で服用している成人が23%もいるという統計もあり、まさに世界的に最も一般的な鎮痛薬のひとつといえます。
友人との飲み会の前にちょっとした頭痛を抑えるために飲むこともあれば、仕事中に熱を我慢できずに一錠……という具合に、ほとんど無意識のうちに使われている薬と言えるでしょう。
こんなにも多くの人が使っているならば、その影響が「感情」にとどまらず「重大な意思決定や行動の選択」にまで波及している可能性は見過ごせません。
たとえば、運転中の判断や、投資などで大きなお金を動かす際の度胸の加減、さらには手術などの医療行為を選択する場面でも、リスク感や不安感が薄まったまま判断すると、思いもよらないミスや後悔が生まれるかもしれないのです。
アセトアミノフェンが持つこの意外な心理的影響に、多くの研究者や医療関係者が注視するようになってきました。
そこで今回、研究者たちは「アセトアミノフェンを飲むと、本当にリスクの高い行動をとりやすくなるのか」を実験的に検証することにしたのです。
さらに、「そんな行動の変化はどういう心理的メカニズムによって起こるのか?」「危険度をどのように認知しているのか?」を詳細に調べるため、複数の実験やアンケートを組み合わせ、参加者たちの意思決定を隅々まで観察していきました。
































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)