遺伝子に刻まれた音を楽しむ力

この研究は、単に「音楽が好きか嫌いか」という二分法ではとらえきれない、“音楽の楽しさ”の真髄に迫ったと言えそうです。
何よりも大きな発見は、音程やリズムを感じ取る力や、報酬系全般への敏感さだけでは説明できない“音楽特有の報酬感受性”が、私たちのDNAと密接につながっているらしい、という点です。
これは「音感がないから音楽を楽しめない」「もともと喜びを感じやすい人だけが音楽に酔いしれる」という固定観念とは異なる見方を提案しています。
実際、音楽的能力はそこまで高くなくても、ある曲に心底ハマってしまう人もいれば、演奏が上手でも“鳥肌が立つような感動”はあまり味わったことがないという人がいるのは、この別の“遺伝的ルート”が作用しているからかもしれません。
さらに面白いのは、音楽を“楽しむ”といっても、感情が揺さぶられるタイプもいれば、リズムに合わせて体を動かしたり、人と一緒に聴くことで一体感を得たりするタイプもいます。
これら複数の要素が、それぞれ微妙に異なる遺伝的影響を受けているという示唆は、音楽の多面性を改めて浮き彫りにしました。
ある人にとっては「仲間とのカラオケが最高の幸せ」でも、別の人にとっては「お気に入りの曲を静かな場所で聴くひととき」こそ至福――この違いが、単なる趣味嗜好だけでなく、遺伝子レベルで異なっている可能性があるのです。
もちろん、“音楽の楽しさ”がすべて生まれつきで決まるわけではありません。
双子研究では約半分以上が遺伝の影響を受けていると推定されましたが、残りの部分は個人が育ってきた環境やその後の経験によって生み出されます。
たとえば、幼い頃に音楽に触れる機会が多ければ、大人になってから音楽に対する関心や楽しみがより強まるかもしれません。
あるいは、友人とライブに通う習慣が始まったことで、一気に音楽の魅力に開眼するケースもあるでしょう。
要するに、私たちが音楽をどれだけ楽しめるかは、遺伝と環境が絶妙に混ざり合って形成されるのです。
今回の成果が画期的なのは、人間の感情や行動における遺伝と環境の関係を、“音楽”という身近で多彩な刺激を通して具体的に示した点にあります。
これまで「楽しむ力」は測りにくいとされてきましたが、BMRQのようなツールを活用して「音楽を楽しむ度合い」を数値化し、それを双子研究で裏付けることで、単なる好みや素質を超えた仕組みが見えてきたのです。
これは音楽教育や音楽療法への応用などにも大きな可能性を開きます。
たとえば、どのような環境要因が音楽をより楽しめるようになるかを探ったり、逆に音楽を使って脳の報酬系をうまく刺激し、精神的ストレスを緩和したりするアプローチにもつながるかもしれません。
まだ解明されていない部分も多く残ります。
たとえば、文化的背景や言語が異なる地域で同様の研究をしたらどうなるのか。
子どもの頃の音楽経験がどのくらい長期的な影響を及ぼすのか。
あるいは、遺伝子レベルで見たときに“音楽を楽しむ力”に関わる具体的な遺伝子配列が存在するのか――興味は尽きません。
とはいえ、すでに明らかになったのは「同じ曲を聴いても、人によって心の揺れ方が違うのはあたりまえ。
そしてその一部は、生まれもったDNAによるところが大きい」という事実です。
考えてみれば、私たちが音楽に求めるのは、ただ耳に心地よいだけでなく、“他人と共感する瞬間”や“自分の心を動かしてくれる刺激”といった多様な要素です。
今回の研究は、それらをひとまとめにせず、丁寧に切り分けて一斉に検証し、さらに遺伝と環境の区別を可能にする双子研究で挑んだところに価値があります。
いわば、人間の“心のオーケストラ”の中で音楽がどんな役割を果たしているかを、遺伝学というスポットライトで照らし出したのです。
この発見をきっかけに、音楽が持つ奥深いパワーがいっそう明るみに出てくるだろうと期待が高まっています。




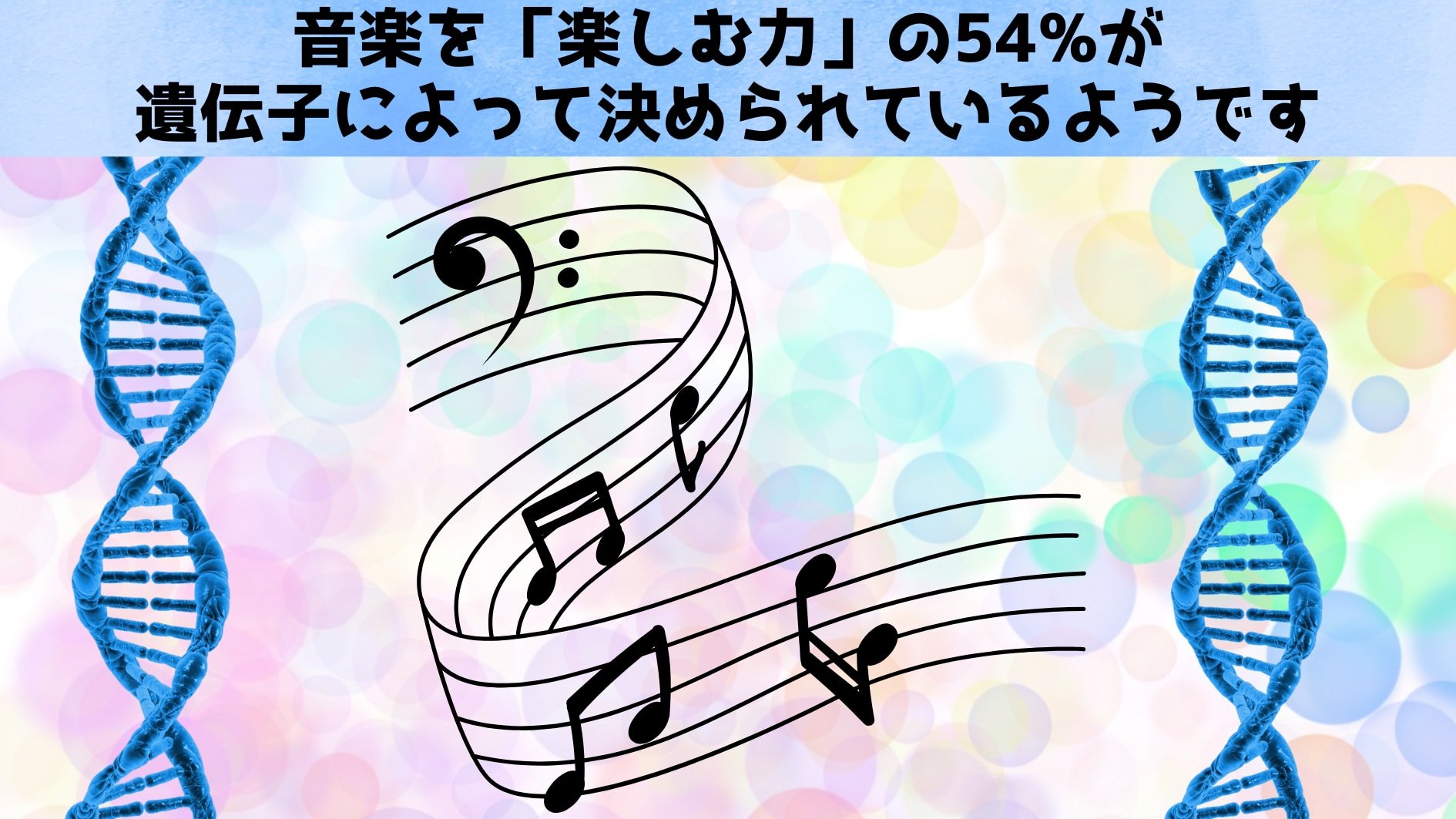
























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)




























遺伝子に刻まれてるならばこれが種か個体の生存に役立ったということかな
ある一定のリズムやメロディーを聴いて好ましく感じることが進化の上でどんな利点があったのか知りたい
心の栄養と思う
現生人類の母音と子音の発音によるコミュニケーションの前(旧人類)は、メロディーラインやリズムがメインのコミュニケーションだったんじゃない?
発音による「情報」の交換よりも、メロディーによる「感情」の共有がコミュニケーションの目的だったのかも。感情が揺さぶられるのはその名残では?
〉〉メロディーラインやリズムがメインのコミュニケーションだったんじゃない?
語尾を上げると問いかけになるのは世界共通だそう
人類全体の音楽を楽しむ能力がワンランクUPしたら、もっと良い地球になるように思いますね。
なるほど、言葉より先に音楽があったのか、「No Music No Life」(音楽なくして生命なし)