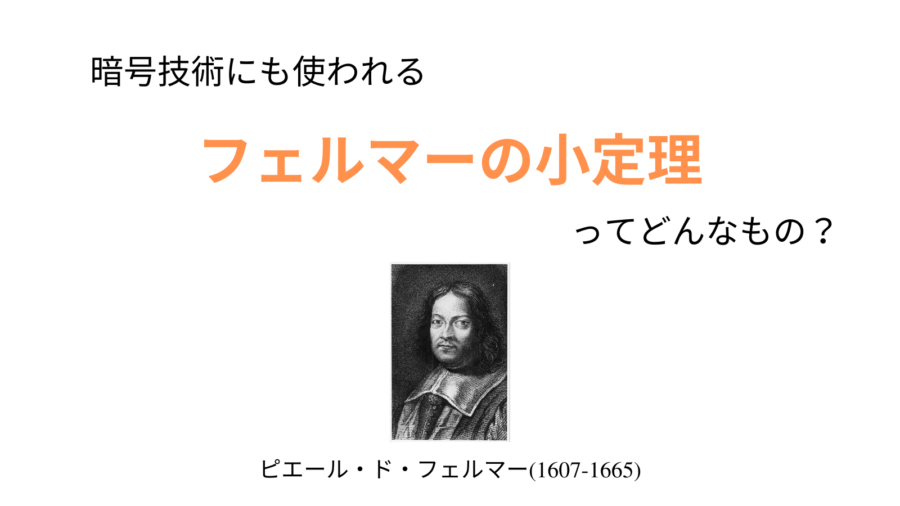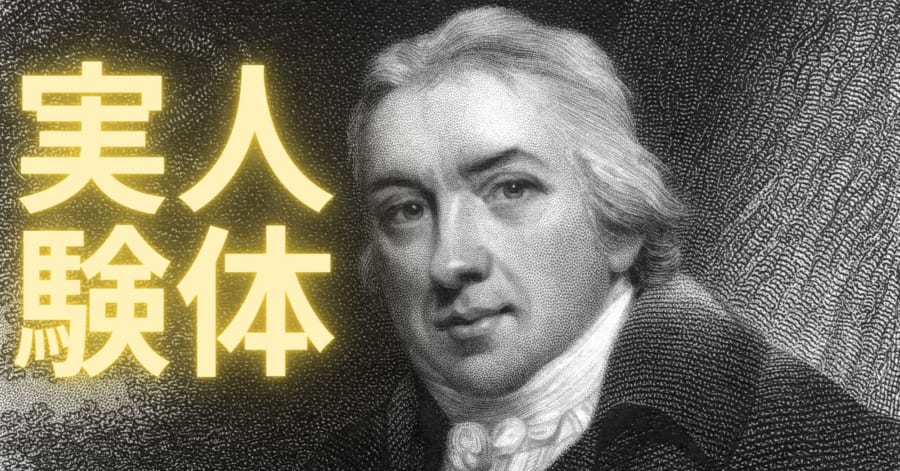1,200人調査で判明:過信する人ほど対立が深まるワケ

研究者たちはまず、韓国の一般市民約1,200名を対象にオンライン調査を行いました(最終的に第1波で1,175名が回答し、第2波でも948名が継続回答)。
この調査では、政治知識に関する10問程度のクイズを用意し、その正答率を“実際の知識レベル”とみなしました。
ところが、その平均正答率は約48%にとどまったのにもかかわらず、参加者のうちおよそ6割が「自分は平均以上に政治に詳しい」と回答していたのです。
クイズの成績が最下位25%に入る人でさえ、約4割が「自分は上位のほうだ」と思い込んでいたことが判明しました。
これは、服のサイズを測ってみたら実際にはMサイズなのに、「自分はLサイズを着るべきだ」と信じているようなものです。
次に研究者たちは、「SNS上で反対意見を持つ人(クロスカッティング・ディスカッションの相手)と、どれくらい頻繁にやり取りをしているか」を質問しました。
回答者のうち、約35%が「週に1回以上は別の政治的立場の人と意見を交わしている」と答えています。
本来なら、こうした交流は互いの視野を広げる機会になると期待したいところです。
しかし1か月後に行った追跡調査(第2波)のデータを分析してみると、“過度に自分の知識を高く見積もっている人”ほど、意見が食い違う相手に対して批判的な投稿や“嫌い”ボタンを押す行動が増える傾向が強く、結果として感情的な対立(アフェクティブ・ポラライゼーション)が深まってしまうことがわかりました。
具体的には、自分を過大評価している層では、クロスカッティング・ディスカッションに積極的に参加しているほど否定的な反応を示す割合が約1.5倍に高まるという統計的な関連が見られたのです。
いっぽう、実際のクイズで高得点を取りながら「もっと勉強が必要だ」と謙虚に考えている人たちの場合は、クロスカッティング・ディスカッションへの参加がむしろ対立感情を弱める方向に働く可能性が示唆されました。
こうした“謙虚な知識人”に分類されたグループでは、反対意見に直面しても否定的な反応を示す割合が他のグループよりも**およそ20%**低かったのです。
自分の理解不足を認める姿勢が、結果的には安全運転へとつながるイメージです。
最終的にこの調査から浮かび上がったのは、「実際の能力」よりも「自分の能力をどう認識しているか」がオンライン討論の雰囲気を左右する重要な要因になっているという点です。
過度な自信に基づく批判や攻撃が積み重なると、SNS上での議論は建設的な議論どころか、深刻な罵り合いや敵意の増幅につながりやすい。
そして、いったん感情的な溝が生まれてしまうと、時間が経つにつれ対立はますます根強くなってしまう――研究者たちは、そうした悪循環を断ち切る方法を模索することが、社会の分断を食い止めるカギではないかと指摘しています。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)