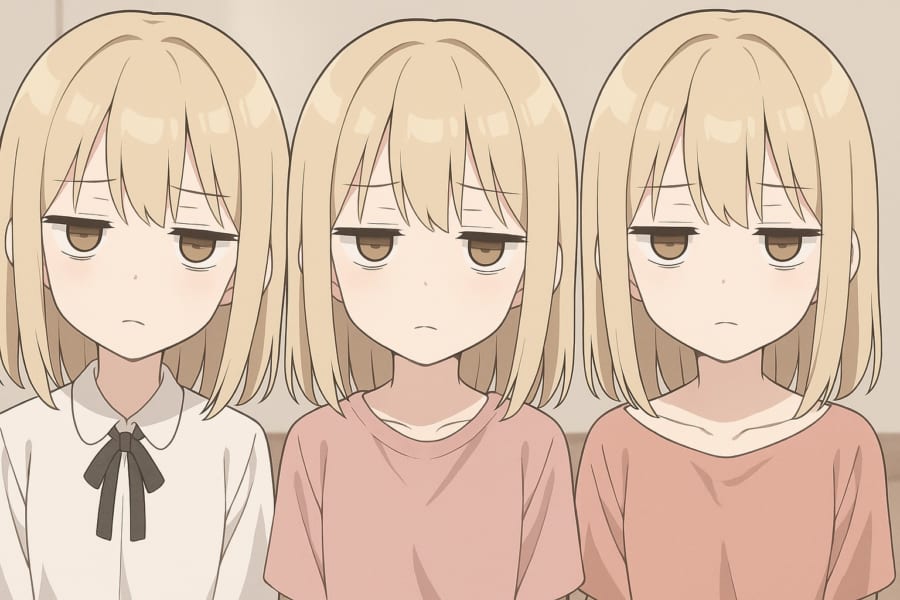ビッグデータで判明:読書率年2%ずつ蒸発

研究チームは米国労働省が実施する「全米時間利用調査 (American Time Use Survey, ATUS)」のデータを分析しました。
ATUSは全米から抽出した15歳以上の人々に対し、「昨日24時間のうち何にどれだけ時間を使ったか」を細かく記録してもらう大規模調査で、日々の行動実態を把握できる点が特徴です。
今回の分析では、2003年から2023年までの延べ23万人以上(236,270人分)のデータを用い、その中から「娯楽目的での読書」に該当する行動(仕事や勉強以外の読書)があったかどうかと、その時間を抽出しました。
ただしCOVID-19流行の影響で2020年は調査が一時中断したため、この年のデータは除外されています。
まず最新の2023年の状況を見ると、ある日のうちに少しでも読書をした人の割合は18%にとどまりました。
裏を返せば「5人中4人以上(82%)は1日の中で全く読書しなかった」ことになります。
一方、読書をした人について見ると、その読書時間は平均1時間31分(中央値1時間)に達していました。
つまり「読む人は比較的しっかり読んでいるが、読まない人が大半」という二極化した実態が浮かび上がっています。
全体で平均すると2023年時点の1日あたり読書時間は16分程度でした。
次にこの20年間の推移を分析した結果、日々の読書実施率(その日に読書した人の割合)は2003〜2004年頃をピークに一貫して低下していることが明らかになりました。
2004年には約29%だった読書率は、年平均2%ずつ相対的に減少しながら2023年には18%前後まで落ち込んでいます。
統計解析でもこの減少傾向は有意で、偶然の変動ではなく長期的な真の減少トレンドであることが示されました。
また1人あたりの読書時間も2004年の平均約23分から毎年0.37分ずつ減少し続け、全体として娯楽読書に割かれる時間が着実に減っていることがわかりました。
こうした減少は主に「個人が自分の楽しみのために読む読書」の頻度低下によるものであり、親子での読み聞かせ(子どもに本を読んであげる行為)はこの期間で大きな変化が見られなかったとのことです。
興味深いことに、実際に読書を行った人たちの読書時間平均はむしろ僅かながら増加傾向を示し、2003年には約1時間20分だったものが2023年には1時間31分に延びていました。
これは「読む人は減ったが、残った読書層は以前より長く読むようになった」可能性を示唆しており、研究チームは今後この理由を詳しく探る必要があるとしています。
読書によって得られる恩恵が「読む層」と「読まない層」で大きな格差となっているのです。
さらに、読書習慣の人口層ごとの違いも明らかになりました。
もともと女性の方が男性より読書率が高く、高齢者ほど若年層よりよく読書をする傾向がありましたが、こうした差は20年間で大きく変わらず維持されました。
一方で人種や学歴、所得、地域、健康状態による差は拡大しています。
例えば2023年時点では、黒人の読書率は白人の約半分程度(その日の読書実施率が白人より45%低い)というデータが得られています。
学歴についても差が顕著で、大学院卒など高学歴の人は、高卒程度の人より約3倍も読書習慣があることが示されました。
所得が高い層も低所得層より読む割合が高く、都市部在住者は地方在住者より読書率が高い傾向が強まっていることがわかりました。
また障がいを持つ人は健常者より読書する割合が低く、このギャップも拡大していました。
このように、娯楽読書離れの傾向は社会の中で一様ではなく、特に社会的・経済的に不利な立場にある人々やマイノリティー層で顕著であることが示唆されています。




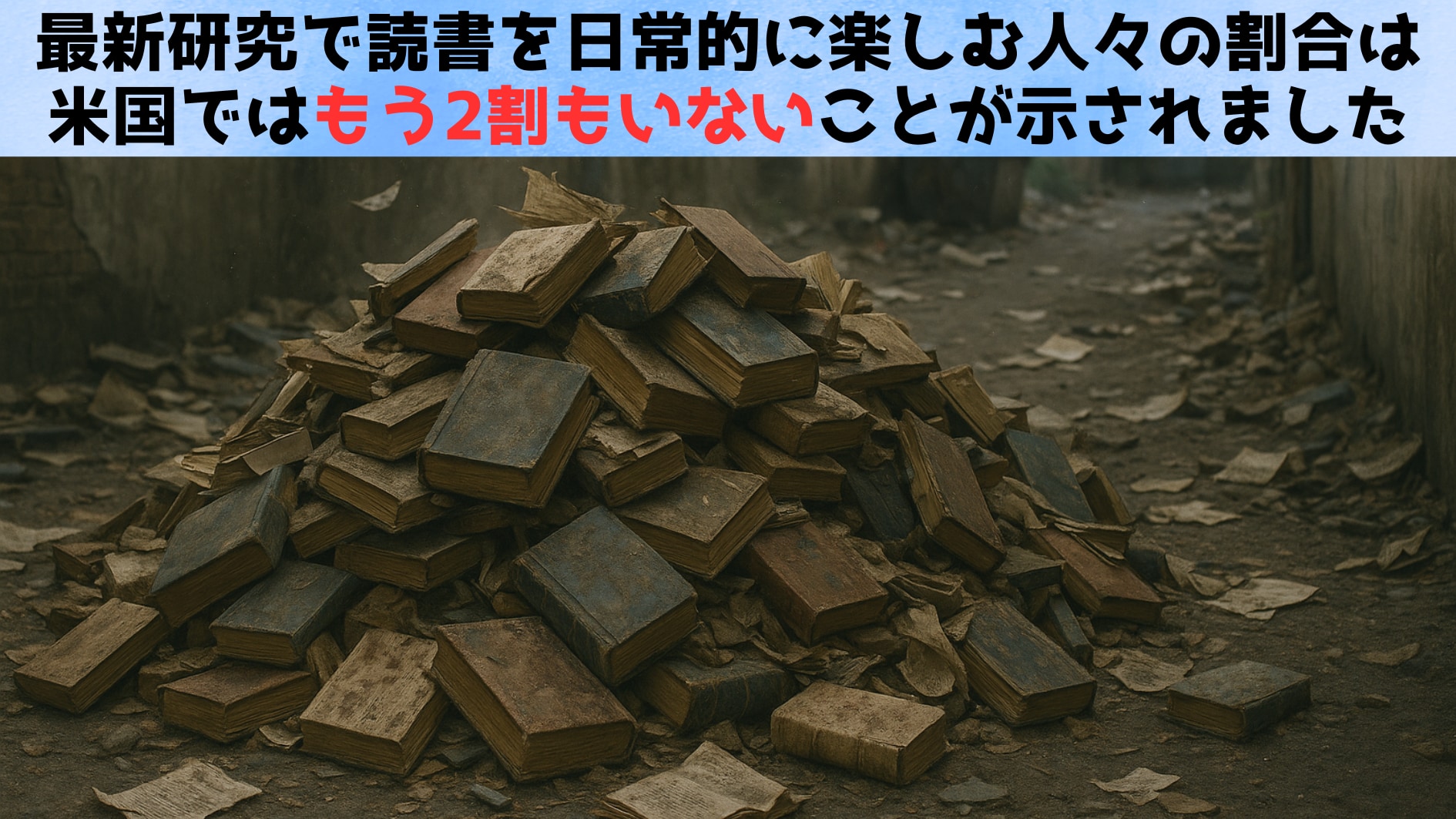




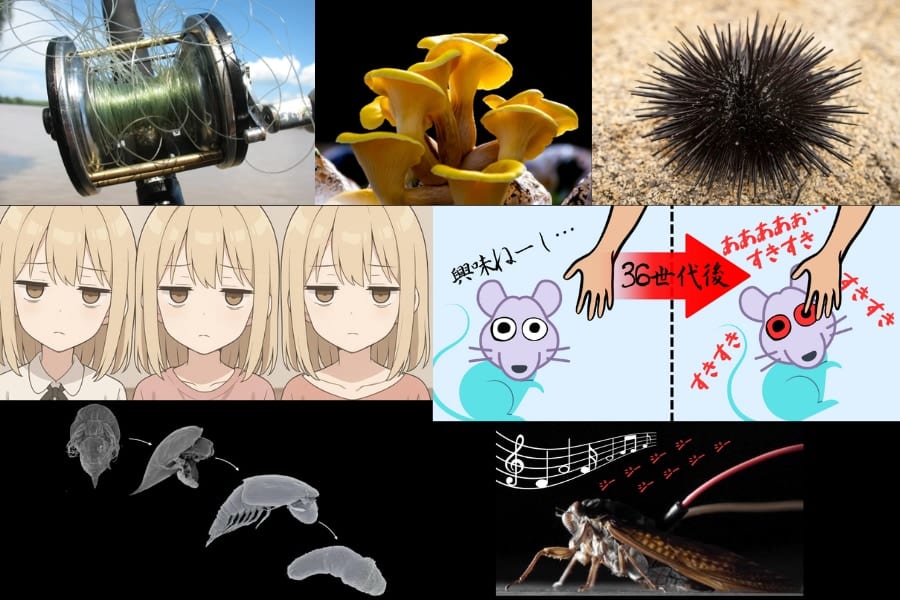


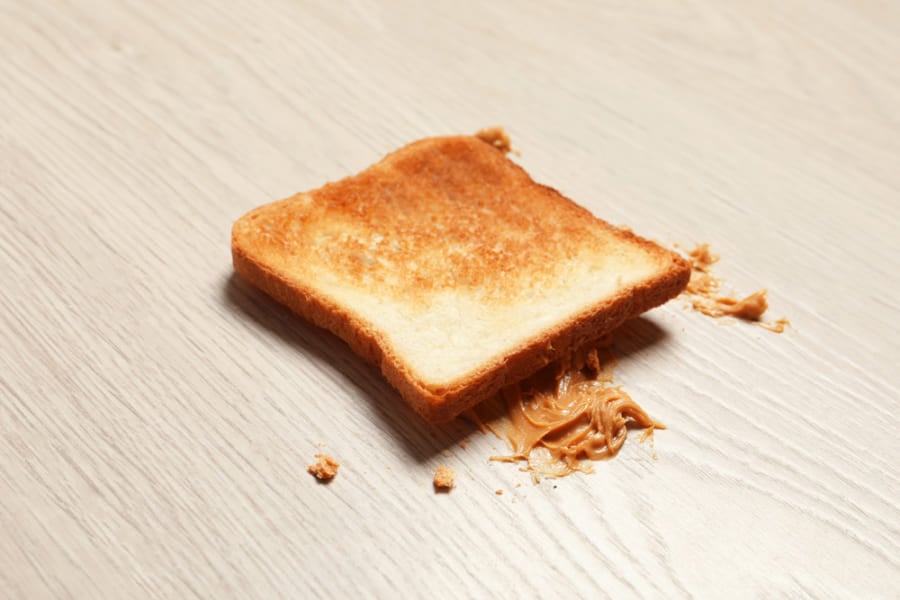



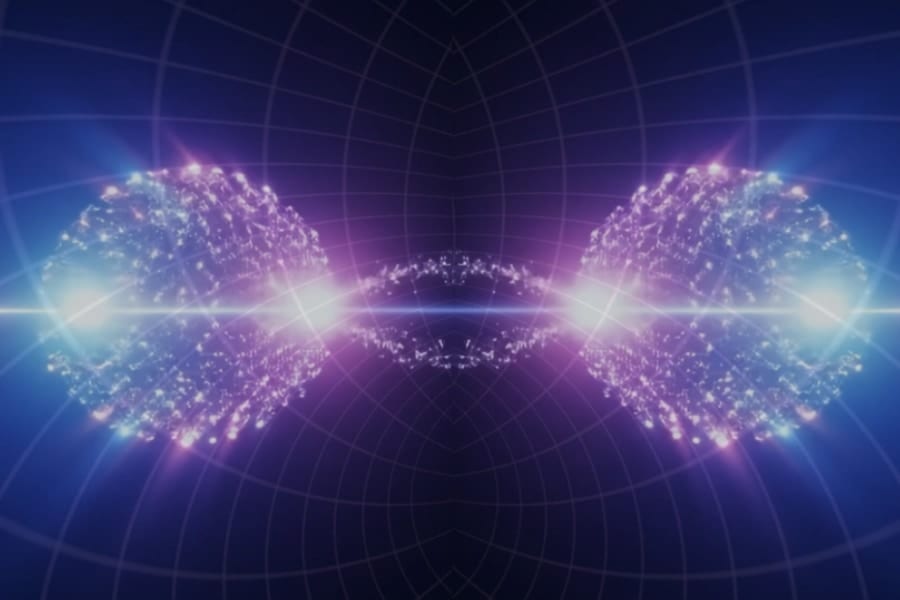
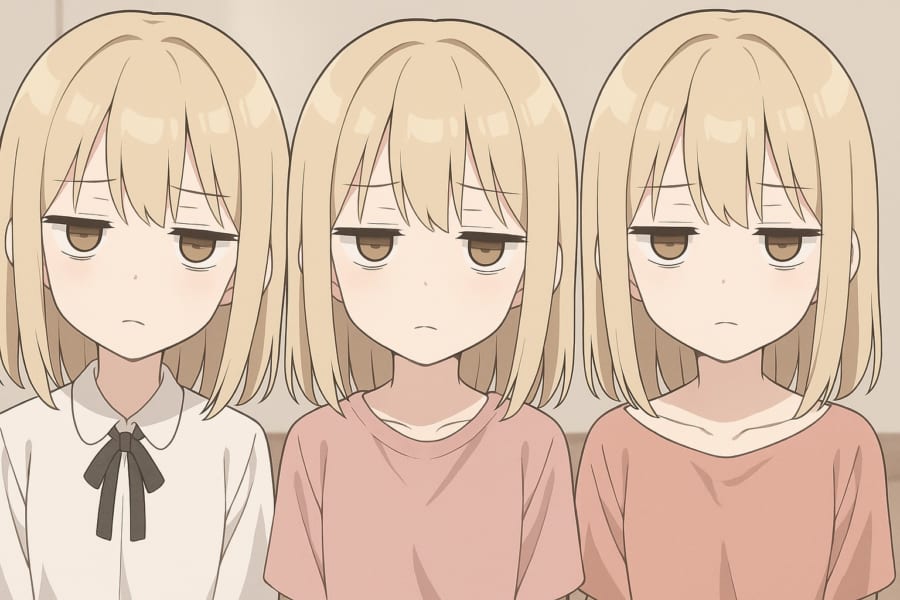











![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)