心理学の入門書に潜む間違った事実12選
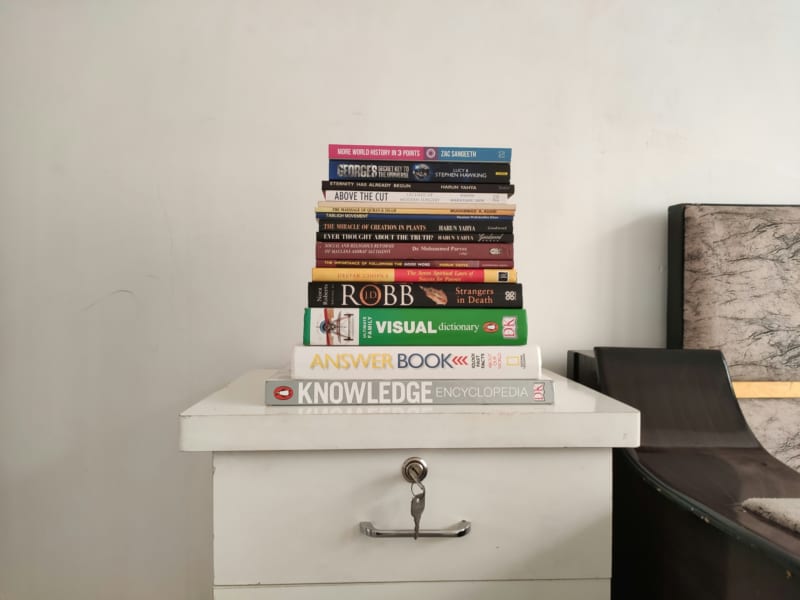
米ステットソン大学のスコット・リリアンフェルド氏(Christopher Ferguson)らの研究チームは、実際に多くの大学で使われている心理学の入門書を調査し、その内容の正当性を検証しています。
以下に、調査で焦点を当てられたトピックを箇条書きで示します。
<論争のある研究分野>
- メディアと暴力: メディアでの暴力描写が視聴者の攻撃性や社会的な暴力に寄与する説。一般および学術界で最も議論されており、まだ結論が出ていない。
- ステレオタイプ脅威:「女性は数学が苦手」や「男性は共感性が低い」などの情報にさらされると、実際にその能力が下がる現象。結果が一貫していないとの主張がある。
- ナルシシズムの流行:近年、若者の間で「ナルシシズムの流行」がある説。支持する学者もいれば、欠陥のある統計に基づく誤った主張だとする学者もいる。
- 体罰の影響:懲罰的な体罰は将来的に攻撃性の高い大人に育つとする説。否定的な結果につながるのか、あるいは大きな影響はないという点が激しく議論されている。
- 多重知能理論:人間の「賢さ」はIQだけでは測れないとし、個人の持つさまざまな才能(芸術、運動など)を知性として扱う理論。近年では、科学的な根拠に関して強い疑問が呈されている。
- 進化と配偶者の選択:進化のプロセスが人間の恋人選びに大きな影響を与えているとする説。ほとんどの心理学者は進化が人間の行動を形成する原動力の一つであることを認めているものの、進化心理学はしばしば論争の的となっている。
- 抗うつ薬の有効性:気分障害や不安障害の治療における抗うつ薬の使用は近年増加していますが、その有効性については時に論争がある。
<根強い都市伝説>
- キティ・ジェノヴィーズ事件:1964年に米国ニューヨークで起きた殺人事件で、「38人の目撃者がいたにもかかわらず誰も助けなかった」と広く報じられた。しかし後の調査により、事件の全体を正確に目撃していた人はごくわずかで、多くの住民は悲鳴や物音を聞いただけで状況を把握できていなかった。また警察へ通報していた住民もいた。
- 洗脳された朝鮮戦争の捕虜:朝鮮戦争中に捕虜になった兵士が共産主義者によって洗脳され、戦争犯罪を自白させられたり、共産主義側に寝返ったりしたという話。洗脳の主張は一般的に誇張されており、自白のほとんどは拷問下で行われた。
- ブローカ野:言語機能が脳の特定の領域に局在しているという理論は、エルネスト・オービュルタン(Ernest Auburtin)により提唱されたものであり、外科医のポール・ブローカ(Paul Broca)はその理論を裏づける初めての解剖を行った人物。「ブローカ野の発見はブローカの功績」という説明は、厳密には正しくない。
- 脳は10%しか使っていない: 人間は脳の潜在能力の10%しか使用しておらず、残りの90%を解放すれば驚くべき認知能力が発揮できるという説。初期の神経精神医学研究の誤解や誤った解釈から生じたようで、デマであると結論が出ている。
- モーツァルト効果:クラシック音楽を聴くことで子どもの頭が良くなる現象。のちの追試で再現できないと否定された。
心理学に興味・関心がある人なら一度は見聞きしたことがあると思います。
研究チームは、心理学の入門書として人気のある教科書24冊を対象に、心理学において論争の的になっている現象や神話がどのように本書の中で扱われているのかを確認しました。





























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























