“無”が語る意識:静寂もまた脳の声
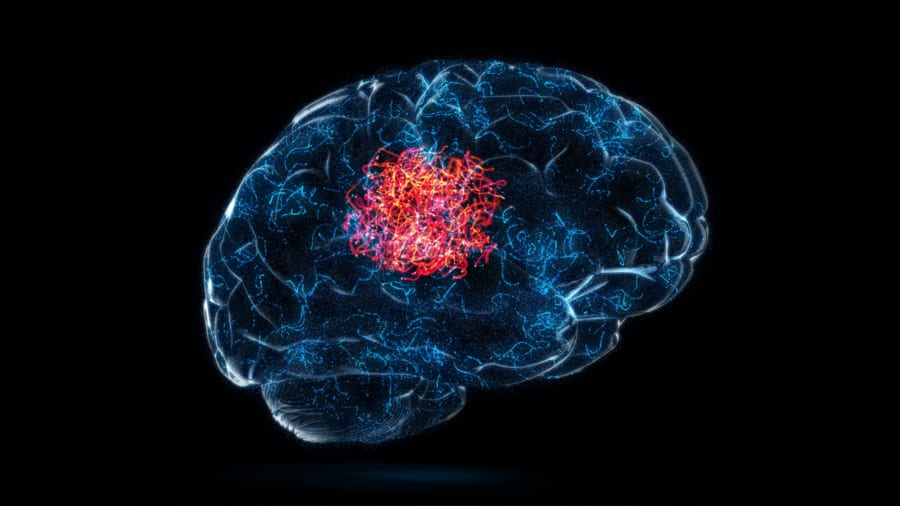
この新たな「マインド・ブランキング」を独立した精神状態と認める見方は、大きな示唆をもたらします。
まず、起きている限り何かを考えているものだという直感的な考えを覆します。
「マインド・ブランキングは、目が覚めている間は常に思考が流れているという一般的な概念に挑戦します」と、本報告の主執筆者であるトマ・アンドリオン氏は指摘しています。
実際に、私たちの覚醒時の経験には定期的に“空白の時間”が含まれるのです。
こうしたブランクの瞬間を研究することで、科学者たちは意識そのものの理解をより洗練させたいと考えています。
意識はすべてあるかないかの二択ではなく、思考の豊かさにさまざまな段階があるように見えるからです。
ときには頭の中が鮮やかな考えや感覚で満ちあふれ、ときにはぼんやりと空虚になる。
こうしたブランク状態を認めることは、意識がときに変動し、ときにはゼロに近い水準に落ち込むことさえあるという、より繊細な心のモデルにつながるでしょう。
実用的な側面も考えられます。
マインド・ブランクは、個人差を探るうえで有益な手がかりとなる可能性があります。
ある人の内的経験は、注意スタイルや神経学的特性といった要素によって、より空白になりやすいかもしれないからです。
また、不安症や脳損傷などの臨床的状態にも関連が示唆されており、将来的には診断や治療のアプローチを検討するうえでも役立つ可能性があります。
著者たちが特に興味を持っているのは、瞑想などの「最小限の意識」状態との類似点です。
「“頭が真っ白になる”という体験は、何かを考えている体験と同じくらい身近で直接的なものです」と、共著者のジェニファー・ウィント氏は述べています。
これは、内容のない心の状態であっても、なお有効で具体的な経験であることを強調しています。
マインド・ブランクを、瞑想による精神の静寂(頭を空にしようとする)や浅い眠りのぼんやりした意識状態と比較することで、「最小限の意識」がどのような姿をしているのか、またどんな役割を果たしているのかを探ることができそうです。
最終的に、マインド・ブランキングはただの一時的な不注意ではなく、私たちの心的生活において規則的かつ意味のある一部を成しています。
それは、脳が自らの内容を遮断する能力を表しており、“音量を最小まで下げた”ときの意識の状態をかいま見せてくれます。
神経科学者のアントワーヌ・リュッツ氏によれば、今後は、マインド・ブランキングが他の体験とどのようにつながり、なぜ脳がこうしたオフスイッチを備えているのかを「議論し始める」ことが重要だといいます。
次に、ぼんやりと宙を見つめているときに頭の中が空っぽになっていることに気づいたら、その瞬間に起きている逆説的な状況を考えてみるといいでしょう。
脳は起きているのに、一時的に何もない空間へ滑り込んでいるのです。
それは決して「何でもない」わけではありません。
この空白は、にぎやかな思考の街並みだけでなく、その合間にある静かな未知の領域も心の風景の一部だということを示してくれます。
そこに光を当てることで、意識のスペクトラムをより深く理解する手がかりが得られるでしょう。
それは、もっとも鮮やかに彩られた瞬間から、もっとも色のない状態に至るまでを含む、意識の全体像に近づく道筋なのです。




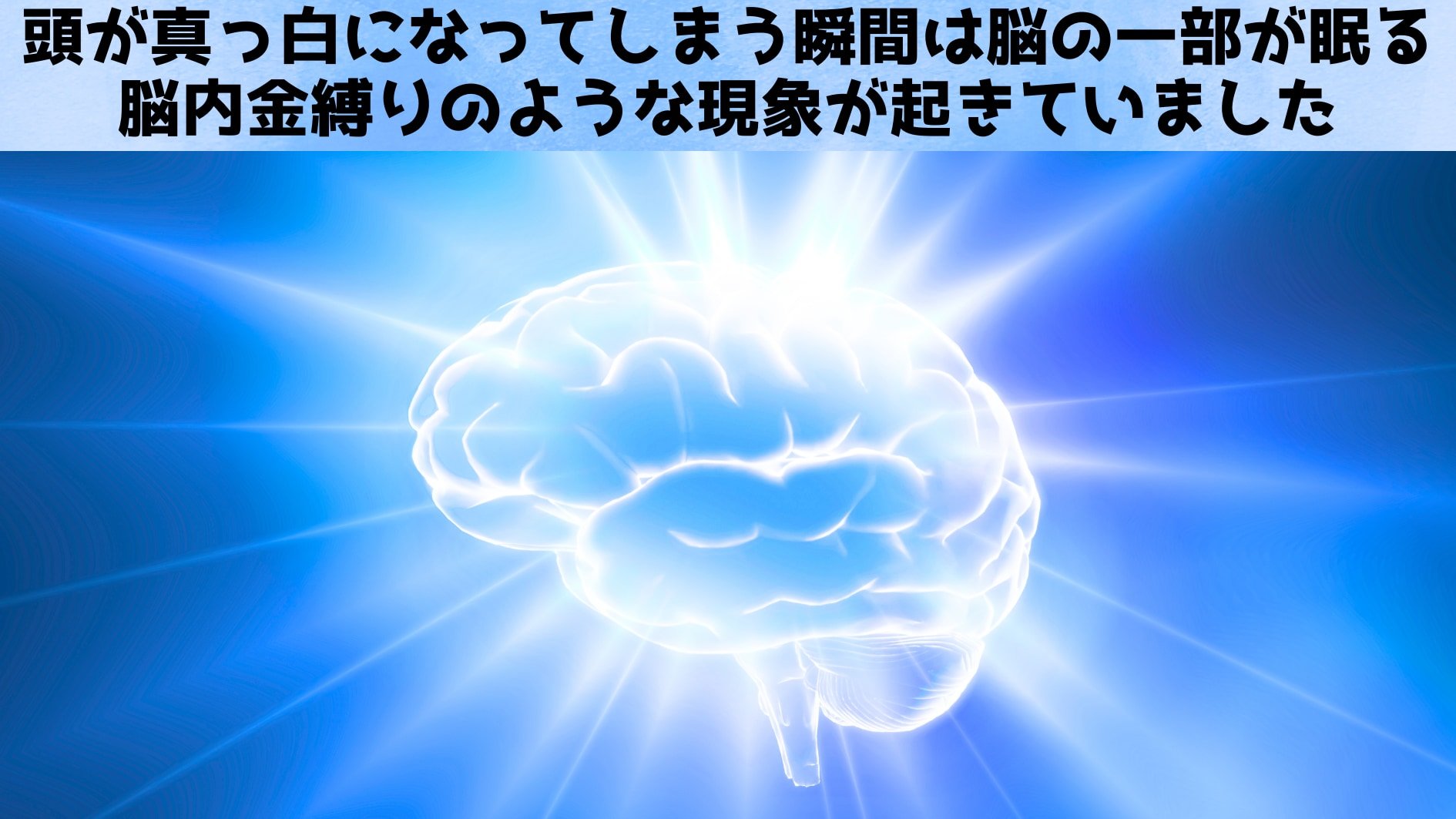











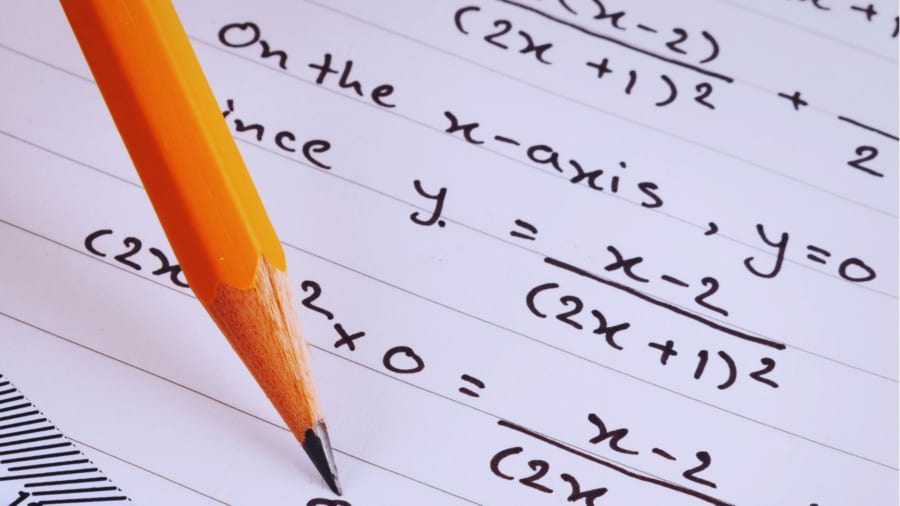












![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
















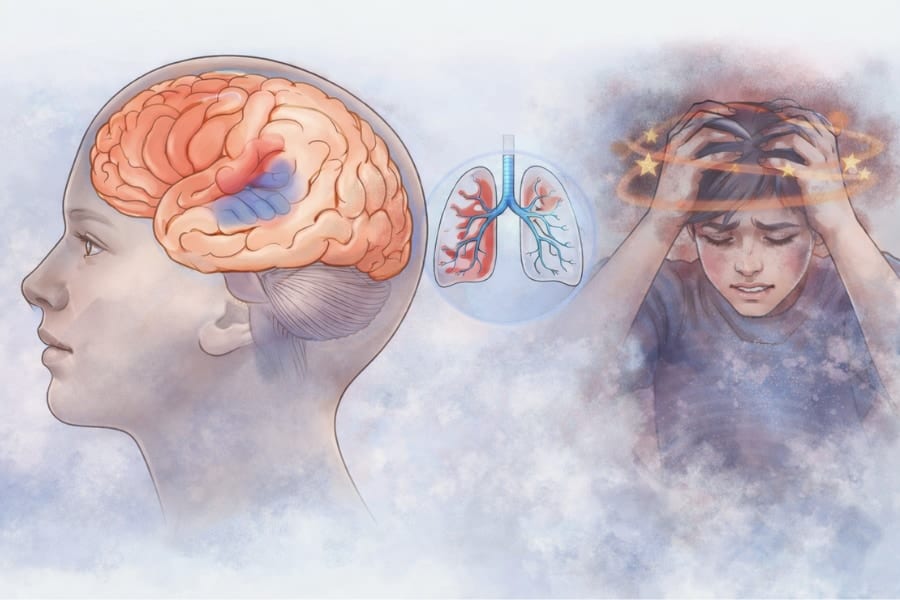



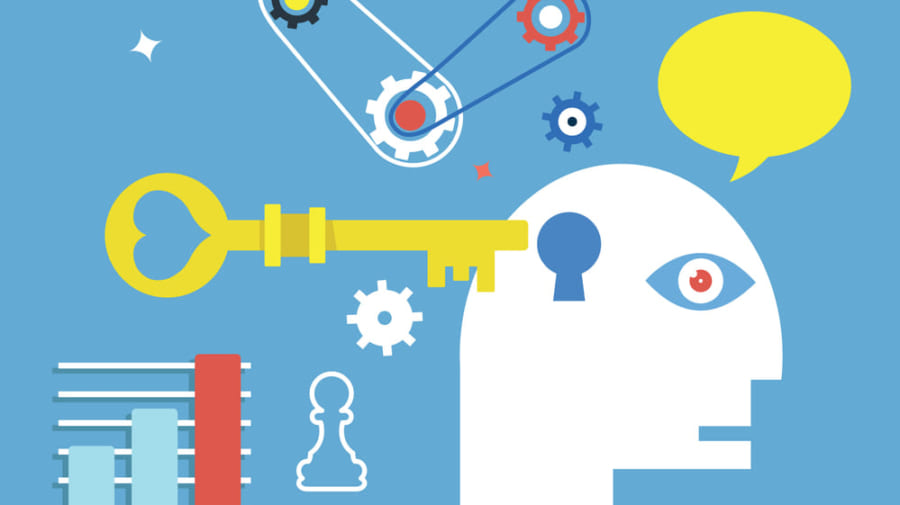
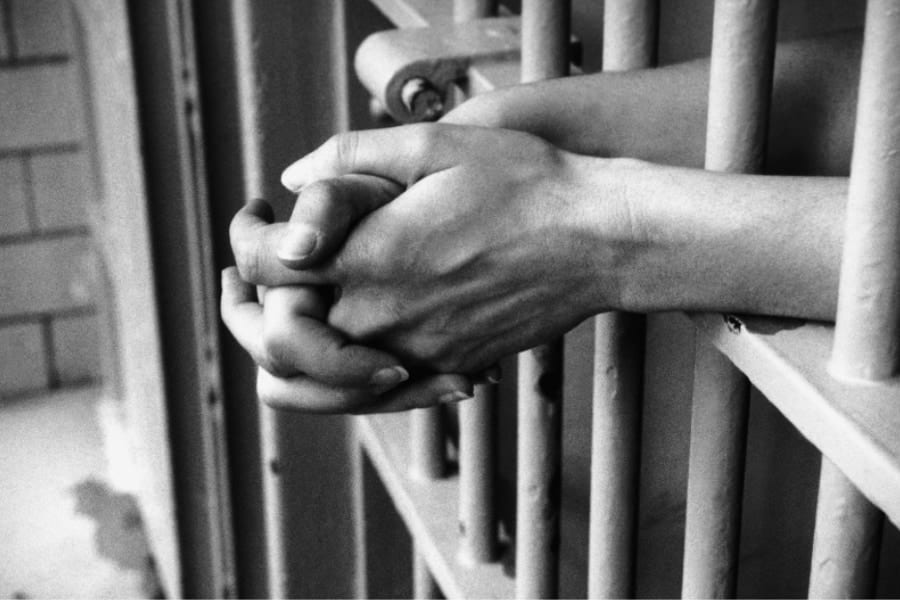






そんなときは寝てしまうに限ります。