「生殖に有利なはずの個体が出産しない」人間社会が抱える矛盾
研究チームが注目したのは、知能の高い人がなぜ出産を後回しにし、最終的に子どもの数が少なくなるのかという点です。
ここで浮かび上がってくるのが、「キャリアと出産の時間的衝突」という現代特有の問題です。
知能の高い人は、しばしば医師や研究者、弁護士、公務員、大企業の管理職など、高度な専門性や長期的な訓練を必要とする職業に就いています。
そうした仕事では、20代〜30代前半までを教育や経験の蓄積に充てる必要があり、社会的に安定した立場を得る頃にはすでに30代半ば、あるいは40代に差し掛かっているケースも少なくありません。
このタイミングで出産・育児に踏み切るには、それまで築いてきたキャリアを一時的に中断するリスクを受け入れなければならなくなります。
とくに女性の場合、「出産適齢期」と「キャリア形成のピーク」が重なることが多く、判断はよりシビアです。産休・育休制度が存在していても、実際には長時間労働文化や「出産=離脱」という無言の圧力が残っている職場も少なくなく、「せっかく積み上げてきた努力が無駄になるのではないか」「評価が下がるのでは」といった不安がのしかかります。

男性にとっても事情は同じです。共働き世帯が当たり前となった現代では、家事や育児を担う時間が求められる一方で、昇進や評価の競争から降りるわけにはいかないというプレッシャーがあります。結果的に、「今はまだタイミングではない」という判断が繰り返され、機会を失っていくのです。
これは単なる個人の問題ではなく、社会が“キャリアと家族形成の両立”を許容していない構造そのものの問題です。
さらに、研究チームは心理的要因にも注目しています。知能が高い人ほど計画的で、将来のリスクに敏感である傾向があり、「完璧なタイミングで子どもを持ちたい」「育児に失敗したくない」といった思考が働きやすいと考えられます。
このように、身体的には早く親になれる能力があるにもかかわらず、社会的・心理的な圧力によってそのタイミングを遅らせざるを得ない──それが現代の人間社会が抱く大きな矛盾点なのです。
少子化は経済格差だけの問題ではない
今回の研究は、少子化問題が「お金がないから子どもを産めない」といった単純な構図だけでは説明できない、根深い問題であることを指摘しています。
むしろ知的で計画的に人生を歩んできた高学歴・高収入の人ほど出産をためらい、最終的に子どもを持たない選択をする可能性が高いという事実を明らかにしています。
これは、「誰かが悪い」わけではありません。進化的には生殖に有利な個体が、社会制度や労働文化、家族観の変化と衝突することで、逆に子孫を残しにくくしているという、現代ならではの構造的ジレンマです。
経済格差が出産における大きな障害になっていることは事実です。そのため経済的支援や育児制度の拡充はもちろん必要ですが、それだけでは少子化問題は解決できない可能性が高いのです。
キャリアと家庭を両立させることは困難だ、ということはすでに多くの人が実感している問題でしょう。
現代の社会システムでは、出産・育児が「人生のリスク」となってしまい、「人生を豊かにする選択肢」として受け入れられていません。ここには社会の意識変化を含む文化的な土壌づくりが必要になってくるでしょう。
「賢い人ほど子どもを持たない」という問題は、実は、現代社会がどれだけ個人の選択を許容できているのかを映し出す鏡なのかもしれません。


































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)




















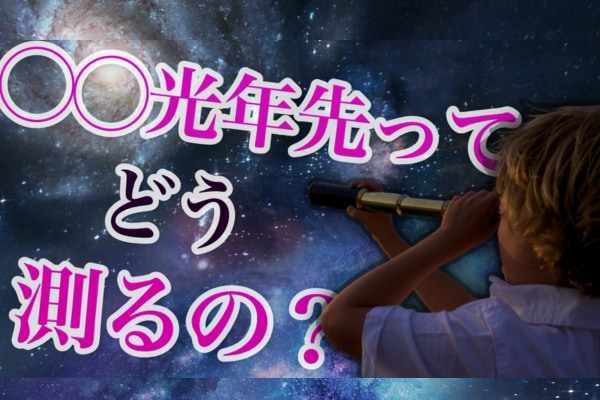







実際に出産と子育てはリスクでしかないのですから仕方ないですよね。
そのリスクに見合うリターンを誰も提供できないのですから。
この場合リターンは提供されるものではなく見出すものではないでしょうか。
生まれてくる子どもが自分たちよりも幸せになれそうな世の中なら出生率は多少増えるかと
この一言に尽きる。ルッキズム、デジタル社会、紛争、物価高騰…なんか産むのが申し訳なくなる。
出産と子育てに投資をする事は、老後の生活に返ってくるんですけどね。お金だけでは解決できない様々な事が、次の世代、また更に次の次の世代から幾何級数的に供給可能性が高まります。
要は、お金の過信(その程度の節約で万能なレベルに到達すると勘違いしている)と長期投資のイメージ、想像力を欠く人々が増えたということでもあります。
子育てをしない分だけ増えたお金程度の「はした金」で、その後の安寧を買うことは、実は難しいのです。
開拓資源が無限にあるならそうだったのだと思いますが、今は有限のパイを取り合う状況のため必ずしも供給可能性が高まるとは言えないのでは…
その安寧とやらのために産まれさせられた子どもは不幸だろうよ。
安寧のために子供を産むという思考こそ知能の低さの現れ
子供って安寧のために産むものなのですか?
このコメントの返信欄にも多数湧いている
「安寧のために子どもを生むなんてだめでしょ」
みたいなクソ低能なコメントまじで辟易する。
特にXなどのネット空間でよく見かける。
生き物が子孫を残すのに崇高な理由なんかないし
好きにしていいし、好きにできるべきだろ。
なんでこいつらごとき個人が、「子どもをつくる資格」みたいなやつを判断してんだ?
お前は神かなんかですかw
クソほどの価値しか無い感情論をさも正義のように語るな、ホンマに気持ち悪い。
おまえらどうせ
「駅にゴミ箱無いのはサリンやテロ対策だから仕方ないだろ」
「遅刻するやつは人の時間を奪っている自覚がない」
こういうことも言ってるだろ。
頭の悪いやつが言うことってだいたい同じなんだよなまじで。
日本が子だくさんだった頃は確かに専業主婦率が高かった。実際私も仕事と育児を両立するのは難しいと実感し、結果キャリアを諦めることに…
一時的に仕事を辞めたり休んだりしても、また子どもがある程度大きくなった時に、パートなどではなく第一線でキャリアを積める社会にしないと、子どもを産みたいと思う人は増えないと思う。
人生や社会の上で第一線という程の価値が今後も職場にあるのかという疑問
AIが事務作業を全てこなすようになり一部の意志決定者で効率良く利益を生み出す仕組みが成り立てば
そこは単に従業員が所得を得て株主が配当を増やす為の場でしかない
ベーシックインカムを配るから無駄に就労を求めないでくれと言われるようになるかも
自己実現、社会貢献の舞台は家庭や地域コミュニティ、福祉団体などへ移り
所得を得るための就労と自己実現の活動を分ける、文字通りのワークライフバランスを重視する社会が到来しそうではある
別に矛盾でも何でもないのでは。もし成熟が早いことで子孫を残しやすくなるものなら、生物は早期に成熟する方向に進化するだろうけど、人類の性的な成熟が早まっているとは思えないですよね。昔は14歳とかで結婚、出産してたのだし。
成熟が早い(知能が高い)というのは、もともと子孫を残すのに有利に働く要素ではないと思いますけどね。
俺は以下の事を5年は言い続けてるんだけど誰もろくに話を聞いてくれない事にうんざりしています。人の話を聞かないのは成長する気が無いという事。みんな成長したいんじゃなくて今の自分が承認されたい思いばかりからコメなどの自己表出で頭が一杯になり他人を受け入れられない。だから成長もしないし承認も増々得にくくなる。自分の思い付きばかりを書きたがって真面目に勉強しようとしない。
まず合計特殊出生率は一人当たりGDPと人口密度に反比例します。それら三要素を色分け世界地図で画像検索して見比べたら一目瞭然。
人口密度は他の生物でも例えばカモは繁殖地で個体数が飽和状態になると男児が巣立ち適齢期になっても巣立ちません。自分の縄張りを作る物理的空間が得られないからです。人間で言えば人口の都市部集中が進むと家賃が高騰して家賃払えなくて最低限のプライベートスペースを確保出来ません。4畳一間とか、相部屋宿で個人空間が二段ベッドの上だけみたいな状態では自身の生存空間の維持だけで精一杯で、その狭い中で更に子供を立てられません。だったら田舎に行けば良いかというと少なくとも男は最低限の収入が無いと上昇婚指向の女が寄って来てくれないのでこれも論外。今の日本なら年収300万円無い男の婚姻率は25%。もし夫婦は貧乏でも良いとしても収入が少ない田舎暮らしでは子育て課金ゲーに参加できないので事実上児童虐待になってしまいます。
一人当りGDP≒豊かさとはつまり知力体力に関わる生命力です。記事内容は質か量かのr-k戦略仮説のうち質の部分だけを細かく見たものだけど、その外観を体系的に説明していないので読者も視野の狭い感想になってしまいます。
魚は卵を何万個も生むけどそのうちの一握りが成長して孫を作ってくれればいい、熊やライオンなど生命力が強い動物は個体数は少ないけど産んだら大事に育てる、夭折率が魚よりずっと低い。強い動物の方が個体数が多いなら食物連鎖は崩壊してしまうのは人間社会でも同じです。院卒みたいな勝ち組が子供を4人も作って、途上国人は一人が精一杯だったら、先進国は途上国から搾取できず社会崩壊します。今も経済的には搾取してるのは同じで日本も立派に搾取側です。搾取側でも国民の過半数はさほどラクな生活ではないのはローマでもムガールでも大英帝国でもそれら全盛期が全てそうだったのと同じ。自分たちがラク出来てないからって搾取してない国の民だと誤解しやすい。ラクしてのは先進国の中間層以上だけ。そしてその層がこの記事に該当。
途上国は子供を無理に大学に入れても元が取れる仕事が無い。今でも小学校なんかに通ってたら野生動植物を暗記する時間が無くなって困るという国地域が1億人規模で存在する。先進国に比べて質より量の社会です。先進国は子に投資すればしただけ元が取れる確率が高いから青天井的な投資合戦、課金ゲー化する。そのための収入を確保する手段としてこの記事のように収入が地位的事業的に安定するまで子供を作れなくなる。今の日本で世帯年収が300万無かったら事実上貧困虐待になりかねないのは、日本は権威主義直系家族社会で冷たく差別的で不平等が好きな国民性で、だからOECD加盟国の中でジニ係数も貧困率も高い方で、絶対的には必要なものを親が子に買い与えていても、相対的には子が例えばみんなswitch持ってるのに自分だけ持ってなかったりの些細な事から徐々にスケープゴート化して行ってしまうからです。二歩んは同化度の高い単一民族国民国家で、水稲圏ゆえの集団主義且つ高モニタリング社会だから、些細な違いがすぐいじめ原因に昇華されてしまう。異質な存在に対する免疫と包容力が絶望的に弱い。鎖国してたのもその国民性のせいです。17世紀に開国しててもスペインポルトガルを追い払うだけの軍事力なんて余裕であったのにとにかく余所者が嫌いだから島内に引きこもりたがる。それは他国に対してだけでなく国民同士でもそうなんです。電車で席譲らないのもその表れの一つ、精神的に自分の中に引きこもっている。
子供に自分が子供だった時よりも良い環境を与えたい気持ちは分かるし、俺も毒親家庭だったから心底そう思うけど、それが少子化に繋がっている事に気付いて欲しいです。良い環境≒金が沢山必要≒子供は少なくしか作れない。良い環境を与えられるなら一杯育てるのに、というのは妥当なようでも唯物的には矛盾してるんです。質か量どっちかしか取れない。良い環境へのこだわりが強まるほど子は減って行きます。
マイケルサンデルやトマピケティやエマニュエルトッドなどの本を読めばわかるけど、1950年代のアメリカ富豪は相続税率が95%という今では信じられないくらいの高さの平等主義時代だったのが、1980年代の新自由主義によって今では20%程度まで低下していて、国民間の経済格差が開いて、教育課金ゲーも熾烈になっています。戦後ほぼ全ての先進国が学歴社会化して以後、子の生涯収入はほとんど親の富裕度に比例するようになりました。どの子供も努力出するしないの幅は大差無いから、幼少期にどんな経験や環境を与えられたか、情操教育やアイデンティティ形成機会をどれだけ与えられたかで人生半分決まります。ジャネの法則的に85歳寿命の人の精神面の折り返しは7歳時点なので、小学校入学までに人生半分決まってるんです。私立中学受験とか躍起になったってもうほとんど手遅れです。ここ数年になって高額教育費を注ぎ込むのは大学以後ではなくむしろ幼児期と理解されるようになり、それを可能にするためにも結婚した時点で大金を持っていなければいけない事は、教育の課金ゲー化に拍車をかけ少子化を加速させています。子供を幸せにしたかったらやはりまず親が可能な限り豊かになっていなければなりません。良い幼稚園に入れて、長時間一緒に遊んで、海山や遊園地にも一通り連れて行けなければいけません。貧しくて仕事が忙しくて家族全員が揃う機会がほとんど無いような状態だとその時点で負け確です。子は精神的に落ち着かないから就学後も勉強の成績が良くならない、親は焦ってとりあえず高い塾にぶち込もうとする、子はプレッシャーばかり掛けられて鬱になり、親は増々焦って教育虐待家化、一方で幼少期から精神的に十分余裕が持てるくらい裕福だった家の子は親にも精神的に余裕があるから承認も十分与えられていて、自分のペースで自我やアイデンティティ形成をして行けて、中高生くらいになる頃には以後の学歴がどうだろうがほぼ幸福な人生を送れる事が確定します。
この記事もそうだけど少子化の話になるとみんな親や酷の都合ばかりを考える事に俺は汚らわしさしか感じません。子供本人の事を第一に考えろよと。このコメ欄には幸い一人いたので救われましたが。子は介護マシーンでもねえし国家の奴隷でもねえよ。子の気持ちより親の気持ちを優先してしまうあたりにも日本が権威主義社会である事の無自覚さが表れています。
国のGDPが上昇しなくても経済格差が縮まれば親は教育課金ゲー難易度が緩和されて子を作り易くなります。相対的貧困を無くせるからです。でも権威主義直系家族社会は右翼的国民性だから平等が大嫌い。自己責任論が大好きなのもそれ。これを能力平等信仰と言います。みんな生まれた時点では能力も環境も同じなんだから成功しないのは本人が努力しなかったのが悪いという妄想。実際には能力は遺伝か環境かは100年前に相互作用説で結論が出ていて、今はIQや身体的健康や倫理観は遺伝子が関わっている事が統計的に表されています。数学や音楽の才能は遺伝が大きくて語学はそうでもないとか、支配欲や野心は遺伝が半分くらい影響してるとか。でも日本の権威直系社会はそれを無視したがる、堂々と自己責任論を自他に浴びせる。自身に浴びせると他人を頼らない事になり、人との繋がりが希薄な社会になり、共感乏しくエンドルフィン分泌が捗らず幸福感が低下し鬱になり身体的にも不健康になります。なのにネトウヨ的な奴らはいつまでも「幸福度ランキングなんて白人都合のインチキだろ」と言いたがってばかり。それを否定するなら自分たちで万人が納得する別の指標を作って見せればいいのに奴らは文句言ってばかりで何もしない。「幸福感なんて人それぞれなんだから比べても仕方ない」も思考停止。そんな事言ってたら不幸でいつも泣いてる人に対してどうすれば幸せしてあげられるのか何も考えない事になる。豊かなのと貧乏なのでどっちが幸福か、友達がいるのといないのとでどっちが幸福か、結婚相手や仕事を選べるのと選べないのとでどっちが幸福か、そういうのを考える事を一切法規すると宣言してるようなもの。そんな奴が子育てしたらどれだけ不幸な子になってしまうのか? 他人の価値観に合わせすぎる主体性が無い人も不幸だけど、全く気にしない人よりはましです。余所は余所、うちはうちを言いたがり過ぎる親も、全く言わない親も、どちらも子を虐待しやすい。そのバランスを0でも100でもなく1から99の間で緻密に手探りし続ける事に意味があるのに、地道な事が面倒だからってテキートに二行程度の思い付きコメを書いて、二分後には名に書いたかも綺麗に忘れてて、次の日もその次の日も延々二行の思い付きばかりあちこちに書き散らしてばかり。そういう人生を20代から70代くらいまで続けたとしてくだらない人生だったと思わないんですかと。なんで専門書も読まないで自身の曖昧で根拠に乏しい価値観ばかり表出し続けるんですかと。せめて思いつく疑問を5つでも検索したらそれだけで論理的嗜好がそれなりに可能になるのに。少子化は政治が悪いせいだとか他国が悪いせいだとかとか言う奴を見ると、俺はそういう汚らわしい奴と同じ日本人である事に自分が汚らわしくなります。国の人口増やしたければまず左派思想を中露北の軍事話と結びつけるのをいい加減辞めろよと。経済の左右、権利の左右、軍事は本来別々の話です。中間層以上の相続税の累進課税率を2%強めるだけでも女子大生全員が学費のために売春しなくて良くなるし子供も10万人は増えるだろうに、ネトウヨはそれすらストローマン的に共産主義とかケチつけたがる。俺は政治家よりもガーシーを当選させるような腐った国民を信用しません。この記事はキャリアどうこう言ってしまっているせいでもっとメタ視点のr-k戦略仮説を読者に与えられておらず、主観の世界に誘導してしまっています。
よくアフリカが子が多いのを指して「一夫多妻こそ多子化だ」とか言いたがる奴も長年現れ続けている事にも辟易しています。最初に書いたようにアフリカは人口密度が日本の80倍、一人当たりGDPは1/20なので、子が多くて当然です。どうしても人口増やしたかったら日本はまず江戸時代みたいに貧しくなれば良い。人を都市から地方に追い出して強制的に一次産業に従事させたらいい。文革みたいに中学校までしか行かせなければ良い。大人たちは教育課金ゲーから解放されて子供を5人くらい作れるようになるでしょう。寿命は60代まで低下するでしょう。アフリカの真似しろってのはそういう事です。
婚姻形態で子供が増え易いのは一夫一妻>乱婚>一夫多妻>一妻多夫です。乱婚社会は権利格差が小さい原始的小規模集団でしか成立しないので考慮対象外。一夫多妻は大部分の男が子育てに参加しないから本当はむしろ子を増やすのに向きません。間接的には独身税を取られるけど、血のつながりがある子に対して積極的に課金するのと、血のつながりが無い子に政府を介して嫌々課金させられるのとでは金の集まり方が違う。アフリカが一夫多妻社会なのは古い社会ほど権利格差の大きい権威主義社会だからです。老若男女の権利が平等傾向で新しい社会である欧米は世界一発展していて、権利格差が極端で児童婚が蔓延ったりしている古い社会のインドイスラムアフリカは世界一貧しい側である。少子化とさえ聞けば条件反射的に一夫多妻言いたがる奴は、二言目にはシナチョンブリカス言ってないとしんでしまうキチ〇イと同じです。
文章は長いけども、言ってることは正しい。でも。もっと短くまとめられる能力がないからみんな聞く耳を持たないんでしょう。人に教える時は短くシンプルにしないと伝わらない。お前が成長したいんなら俺の長話を聞け!というのは傲慢だと思います。正論なのは間違いないです。
話が途中で飛び過ぎなんですよ
哲学書じゃないんですから
要点を簡潔に、そして解決策を第一に
仰る事は正しいとしても関係性の薄い人間を引き寄せるには単刀直入に伝えましょう
シンプルイズベストですから
ネズミだと、もうこれ以上スペースない状況でも産ましてしまい、子供が踏み潰される状況になりますが…
そこは知能の差、ということでしょうか?
長い!文字のオンパレード
もっと分かりやすくまとめて
よくこれ掲載が許可されたね
2chや爆砕にも乗せてる?
まあ、そこは個人の考えだけれども、今の20〜30代は自分のことも周りの社会も達観しすぎているんだろうなあ。かと言って現実を全く見れていない人もいるわけで。就職と受験までは狂った状態で動けるのに結婚と出産子育てといった生物的な部分に来ると急に冷静になってしまうから少子化が進むんでしょう。結婚出産なんてタイミングと縁なんだから、そこで一気にアクセル踏めないから結果変な言い訳して諦めたフリしてるだけだと思う。
増税してもその使い道を管理できない民主主義
自由主義なので増税すればするほど優秀な人材も企業も逃げ出す
だから子供が減ったら移民で賄えばいいんだよ
ありがとう安倍ちゃん😊
社会的要因が改善しても知能が高い人ほど計画性が高くリスク回避が上手いのは変わらないから出生率は低いままだと思うよ
26世紀青年の世界にそっくりだよね。
Universe25という実験をご存じでしょうか。.7m×2.7m×1.4mの空間内に、256個の巣箱を設置し、マウスを放ちました。絶え間なく食料と水が与えられ、マウスは順調に増えましたが、最大2200匹になった後、個体数は減少に転じ、最後は絶滅したのです。人間の社会でも、これと恐らくは同じ要因があるのだと思います。経済やら学歴やら色んなことが言われますが、それらは本質ではなく、増えすぎた個体数を調整する生物の機能が本質なのでしょう。
1968年に実施されたこの閉鎖系実験を初めて知りました。都市伝説という話もありますが,まだ巣箱のスペースに余裕があるにも関わらず,300日頃から正常な社会行動が崩壊し,約600日で出産が停止して,約900日後に絶滅したそうです。少子化対策を議論する前に,この実験の追試をぜひ行って貰いたいものです。
このサイトにも乗ってるよね
シンプルに自分の時間が足りていない。だから他者である家族や子供に割く時間が取れない。昔よりも情報や遊びが圧倒的にあふれている時代というのも理由としてはあるけど、結局のところ、それだけ利便性の高い社会になっているのに労働時間は100年前から1日8時間、30年以上前から週休二日制と現代においても一向に短縮されていない。つまり労働に割く時間が長すぎるということ。現に育児中は時短勤務が当たり前になっているように、それは8時間も働いていたら育児がままならないということを社会が暗に認めているということ。ならば育児云々は関係なくそもそも働き過ぎだという結論にならなければ状況は打破されないのではないか。
働く必要がなくなっても
無駄な仕事、無駄な産業を新しく作ってそれをやる構図は変わりません。AI時代になると
もっとシビアになるでしょうね。人はスポーツ選手と関係者に金を与えるために安く働きます。
まずはほとんどの仕事が無駄であると言う認識を人民が持つところからです。
プロスポーツ=無駄と言うことが理解できないのですからw アマだって無駄ですよ。用品製造や販売もね。経済の伸び代がエンタメていうのは
国際的な認識のようです。
みんな働くのが好きなんですよ?w
労働は嫌だ嫌だと言いながらももっと働きたいんです。実際に行動はそれですからw
院生やポスドク、非常勤講師、助教が無給・薄給、ポストが少なく、数年で首を切られるのも高知能な人の少子化・無子化の原因です。少子化と国力の問題に本気で対処するなら、この層を経済的に手厚く支援し、安心して生活できる環境にするのが効果的なのに、逆の政策をした結果が日本の現状です。
単純な話だ。高学歴で頭が回る人は、恋愛以外の娯楽に楽しみを見出すというだけ。恋愛しないから結婚しない、結婚しないから子供が産まれない。それだけ。
なんで恋愛に興味がなくなったかというと、男女平等だから。平等が進んで男女の差異がなくなれば、その分、異性としての魅力がなくなるのは当たり前。先進国で少子化になるのは男女平等のせい。逆に、男女平等なんて言わないイスラム圏は、いまだに子沢山。
というわけで、少子化を解決する方法は至って単純。男女平等をなくせばいい。
頭のいい男はモテない
服に興味がないし、低俗な趣味をやらないし
頭の悪い女は頭のいい男を嫌うし、男も
馬鹿女を嫌うからだ。
頭がいい=高学歴とも限らない。高卒で読書家やIQ高めで頭のいい人も居る
ボリューム層が子供残した方がいいという「意識」が人間にはあるのかもねぇ
夫婦ともに高IQだと子供いる率極端に下がるしいても少ないしねぇ…
20年ちょっとまえなんて十代はセックスするなって言う洗脳がありましたけどね
男の立場が弱くなる事ばかりやってるんだからわがまま女が増えて少子化になるのも当然だと思います。あと地方には物理的に女がいないからね。都会や地方都市に出ていってしまって。
十万人の田舎に居ますが、昔から若い女なんてほとんど見ないよ
あとルッキズム(ファショズム)のせいで
35歳以上の男は生きづらくなってます
昔は服に興味がない人やヘアセットなんて概念はなかったし、覚えづらかったはずです
今はyoutubeで美容師が指導してます
信じられない時代ですよ。全てのノウハウがつべに無料である時代。
Z世代のせいで外に出づらいです
科学に興味のない人間は頭のいい人たちが作る社会に乗っかって生きられて幸せだよね。
IQ100ぐらいが一番得じゃないかな
金は欲を助長し失うことを嫌う
金持ちはなんとしても今日より明日は金持ちになってないといけないからその策を作るよう迫る
せまられた方は選挙制度で決まる人だから選挙のためにその策を作るしかなくなる
ますます金が同じところになだれこむ
金の整合性取るために負を部分を庶民に押し付ける
貧富の差がますます開いて研究開発労働どころではなくなり不満が噴出する
金という数字にすべての技術サービスを作らないといけないから
金にならないことはすべてぽしゃる
国力が落ちる
没落する
手っとり早い金の儲け方だけが残る
産業が消え国力が落ちる
進化が消え文明が停滞する
貧富の開きはその中でも進み文明が終わる
女性がキャリアを断念し、生涯収入が低下したところで死ぬわけではないのだから「キャリアと出産の二者択一」を悪いものだとして煽る風潮はおかしい。
むしろ悩む選択肢がある分、女性のほうが恵まれていると考えることもできる。