2:ストーカー通報に対する警察対応の実態

しかし悲しいことに勇気を出して警察に通報しても、被害者が直面する対応には地域や機関によってばらつきがあり、中には「怠慢」とも言える不十分な対応が指摘されています。
米国の全国調査では、警察に通報したストーキング被害者の約半数(49%)が捜査当局の対応に満足していないと回答しました。
同調査では、約5人に1人が警察は何も行動してくれなかったと感じていることも明らかになっています。
被害者にとって、せっかく勇気を出して通報しても十分に動いてもらえない現実があります。
英国でも状況は深刻で、2017年の質的研究では被害者が証拠不足を理由に門前払いされたり、形式的な危険度評価しか行われなかったという証言が多く寄せられました。
さらに、2023年に発表された警察監察機関の報告書によれば、ストーキングの通報事案の約21%が適切に記録すらされておらず、リスク評価ツールも現場で十分に活用されていませんでした。
証拠収集の遅れも指摘され、これらの問題に対処するために同報告書では29項目もの改善勧告が提示されています。
デンマークの最新調査(2024年)でも、被害者の67%が警察から十分な説明を受けられなかったと感じており、接近禁止命令を発付できたケースは全体の2割未満にとどまりました。
法律整備が進んだ国でさえ、被害者はなぜもっと保護してくれないのかという思いを抱えています。
日本においても警察対応の消極さが指摘されており、内閣府の調査では被害者支援窓口の約3割が警察との情報共有が不十分と回答しました。
また、警察の現場対応を分析した研究では、相談を受けたケースの約半数が被害者への防犯指導に留まり、警告や逮捕といった踏み込んだ措置はわずか16%に過ぎませんでした。
被害者たちはこうした対応を実効性に欠けると評価しており、形だけの対応では問題が解決しないことを痛感しています。
さらに、警察庁の委託研究では、加害者に警告を出した後のフォローアップが行われないために再度つきまとい行為が繰り返されるケースがあると指摘されています。
1999年の桶川事件でも、警察の捜査怠慢が被害拡大を招いたとして遺族が国家賠償訴訟を起こし、警察の過失が認定される事態となりました。
これらの事例から浮かび上がるのは、被害者の訴えを軽視し、法制度の限界を言い訳に対応を怠るというパターンです。
ストーカー被害を軽視した対応は、単に被害者の不安を募らせるだけでなく、最悪の場合は命に関わる結果に繋がります。
ストーカー行為は「しつこい嫌がらせ」程度に思われがちですが、その背後には深刻な暴力リスクが潜んでいます。
米国の調査では、ストーカー被害者の約3分の2(67%)が「自分は殺されるかもしれない、または身体的に害を加えられるかもしれない」という強い恐怖を感じていたことが報告されています。
これは、ストーキング行為が単なる迷惑ではなく被害者の生命を脅かしうると多くの人が直感的に感じ取っていることを示しています。
実際、ストーカー被害はしばしば重大犯罪の前兆となります。
とりわけ元交際相手や配偶者など親密な関係にある加害者によるストーキングは、後に深刻な暴力(ドメスティックバイオレンスや殺人)に発展する危険性が高いことが研究で示されています。
米国で行われた大規模調査では、親密なパートナーによる殺人未遂・殺人事件の被害女性のうち、殺人未遂の85%、殺人の76%がその事件前12か月間にストーキング被害を経験していたことが明らかになりました。
さらに、それらの被害者の多く(半数近く)は事件前にストーカー被害を警察に報告していたにもかかわらず悲劇を防げなかったという指摘もあります。
この調査から、ストーカー被害を甘く見て適切に対処しないことが致命的な結果につながりうる現実が浮かび上がります。
ストーカー被害と殺人リスクの関連性は国際的にも認識が深まっています。
あるメタ分析研究では、ストーキング被害があると親密パートナー間の殺人リスクが3倍に高まると報告されています。
英国でも「ストーカー被害を軽視した結果、防げたはずの殺人が起きた」とされる事件が注目を集め、警察の責任が問われました。
被害者に「被害届の乱発だ」として罰金を科した後に殺害されてしまったケースや、繰り返し警告を発しながら実効性のある措置を取らず被害者が殺害されたケースなどが報道されています。
これらは極端な事例に思えるかもしれませんが、日常的にもストーカー被害者は常に殺傷の不安と隣り合わせに暮らしているのです。
日本でも毎年のようにストーカー事件が凶悪犯罪に発展しています。
警察庁の統計によれば、2020年に全国の警察が扱ったストーカー事案の中で殺人に至ったものが1件、殺人未遂が7件発生しています。
被害者の約9割が女性で、そのうち加害者が交際相手・元交際相手または配偶者・元配偶者だったケースが全体の5割近くを占めています。
こうした数字は、ストーカー被害が決して他人事ではなく、誰にとっても命に関わる深刻な問題であることを物語っています。
1999年の桶川事件でも、警察の捜査怠慢が被害拡大を招いたとして遺族が国家賠償訴訟を起こし、警察の過失が認定される事態となりました。
これらの事例から浮かび上がるのは、被害者の訴えを軽視し、法制度の限界を言い訳に対応を怠るというパターンです。
初動の遅れや判断ミスが、ストーカー被害をより深刻な局面へと発展させてしまう現実があるのです。
せっかく警告を与えても継続的な監視がなければ、被害者は再び危険にさらされかねません。
被害者から見れば、警察の対応は受け身で不十分に映り、必要な保護策が講じられないまま放置されている――まさに助けてもらえないという深い失望感に繋がっているのが現状なのです。
しかしなぜストーカー被害に対して、世界中の警察機構は十分に対応しないのでしょうか?
世界中の警察官がストーカーに対して特に怠慢なのか、それとも現行の警察システムそのものにも原因が潜んでいるのでしょうか?




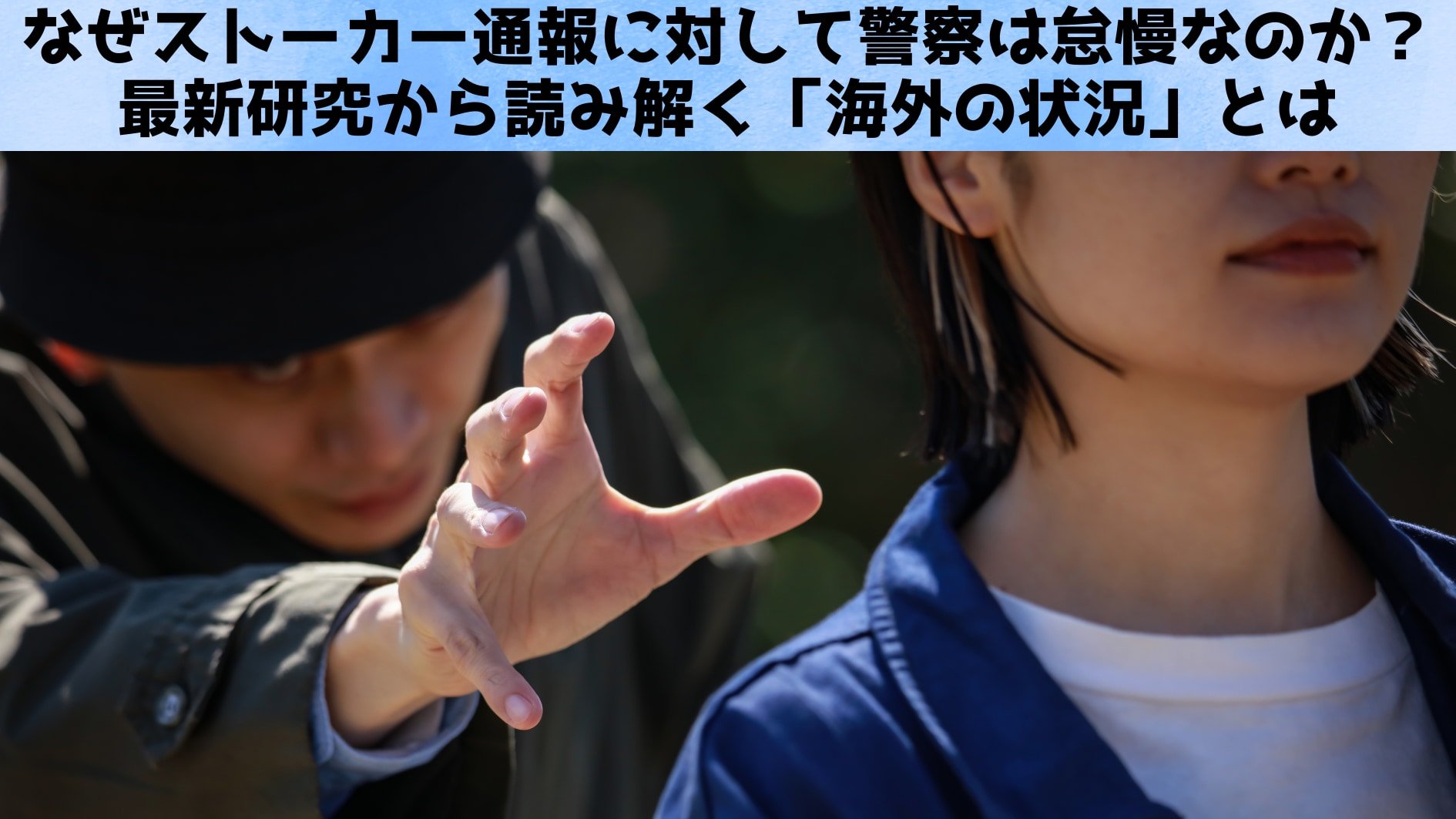























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























