やせている人の死亡リスクが高いのはなぜ?
「やせている人ほど自殺による死亡リスクが高くなり、反対に太っている人ほどそのリスクが低くなる」
この逆相関について、研究者たちはいくつかの生理学的・心理学的メカニズムを仮説として挙げています。
まず注目されているのが「セロトニン仮説」です。
セロトニンは脳内で感情の安定や衝動の抑制に関与する神経伝達物質であり、その分泌量の低下は衝動的な行動や自殺と関係があるとされています。
肥満の人ではインスリン抵抗性が生じやすく、これによりトリプトファン(セロトニンの前駆物質)が血中で増加しやすくなる可能性があります。
結果として、脳内のセロトニン合成が促され、衝動性が抑えられることで自殺リスクが低下するのではないかと考えられています。
次に指摘されているのが「レプチン抵抗性による衝動性の抑制」です。
レプチンは脂肪組織から分泌され、満腹感や報酬系の制御に関わるホルモンです。
肥満者ではこのレプチンに対する感受性が低下し(=レプチン抵抗性)、脳の報酬系への刺激が変化することで、行動の衝動性が低下する可能性があるとされています。
これは結果的に自殺の実行性を下げる要因となりうるという仮説です。

さらに、身体的要因として「自殺の手段における制限」も考慮されています。
調査データによると、肥満の人は体格的に首を括る、高所からの飛び降り、入水などの自殺手段を選びにくく、服薬による自殺を選ぶ傾向がありました。
ところが、肥満者は体格の大きさから薬物への耐性が比較的高いため、服薬による自殺の致死性が低くなる可能性があり、それが死亡率の低下に寄与しているのではないかという見方もあります。
一方で、やせすぎの人が自殺のリスクを高める要因としては、うつ病や摂食障害、睡眠障害、社会的孤立感、いじめや被害体験など、多くの精神的・社会的ストレスが重なりやすいことが挙げられます。
加えて、やせている人は筋肉量が少なく、身体的な脆弱さや慢性的な疲労感を抱えやすいため、生理的にもストレスに対する耐性が低下している可能性があります。
こうした要素が複雑に絡み合い、BMIと自殺死亡リスクの逆相関を形成していると研究者たちは推測しています。
今後は、これらの仮説を裏付ける神経生理学的データの蓄積や、筋肉量やホルモン指標を含めた多角的研究が求められるでしょう。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



















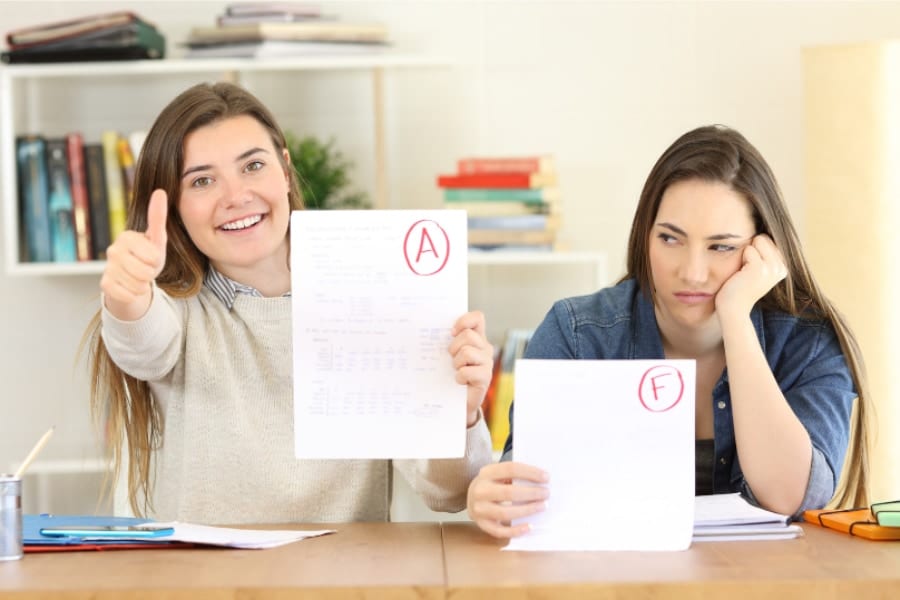








太っててよかった
脂肪組織は骨に次いでミネラルなどを蓄える、同時に毒も蓄えるけど
過剰だと長期に悪影響が増える可能性があり、
欠乏だと短期に悪影響が増える可能性があるはず、
必須なものが余っているほうが短期耐性は強いのは
デブは非常時や飢えに強い理由
レプチンで衝動性が抑えられてるんなら、なんでデブは衝動的に食いまくるんだよ。
と、深刻な矛盾を突いてみるw
順番が逆なのよ、食べまくるからこそレプチン抵抗性がつくのよ
要は才能
女性の場合、常に「痩せて綺麗でなければいけない」という社会からの無言の圧力があり、痩せている人はそれを維持するために、無意識に食べ物を制限し、他人と比較して、周囲からの目を意識して恒常的ににストレスを貯めている。イライラしたり神経症になったり衝動的になったり、精神が不安定になる下地がある。
韓国に限らず世界中で男性の自殺率は女性の2倍以上もあります。ですから,女性が社会からの無言の圧力を受けたり,精神が不安定になる下地があるという可能性は低いと思います。むしろ,女性より皮下脂肪が少ない男性は,太るとレプチン抵抗性になりやすいので,衝動的に自殺することが減るということではないでしょうか。
好きなだけ食べて幸せなら自殺はしないだろう
神経症傾向が高くて、いろんな情報を処理するのにエネルギー使うから痩せるんじゃない?そして、そういう人ほど、美醜とかセルフイメージにすごく関心があるから、理想と現実とのギャップにやられて病みやすいんじゃない?なんか太ってると、大概は鈍感で気にしてなさそうじゃん。
私の記憶が正しければ、この同じ研究内容の記事を20年以上前に当時紙の雑誌で読んだことがありますね。
研究の主題はデブと痩せは自殺を含めるとトータルでは死亡率は変わらないという分析の記事でしたね。
その際の分析では、コレステロールが攻撃中枢を抑える作用があるという所に着眼して分析していました。
つまり、デブはコレステロール値が高いので脳の攻撃中枢を抑えられている。デブに朗らかな人が多いのはそのため。一方、痩せている人間はコレステロールが低いので攻撃中枢が活発になる。その攻撃性は他責はもちろん、自分にも向けられる事があるので、自殺に繋がる人が多いから痩せはデブに比べて自殺率が高いという分析でした。
科学なので,同じような研究が多数あって当然です。元論文を読む限り,同じ研究内容ではないことが明白です。なお,最近の研究によると,LDL(悪玉コレステロール)が高い男性の自殺率は低く,女性は相関しないことが報告されています。因みに総コレステロールは影響しません。「セロトニン仮説」「レプチン仮説」「LDLコレステロール仮説」のどれかが自殺の作用機序に関係するのかも知れません。