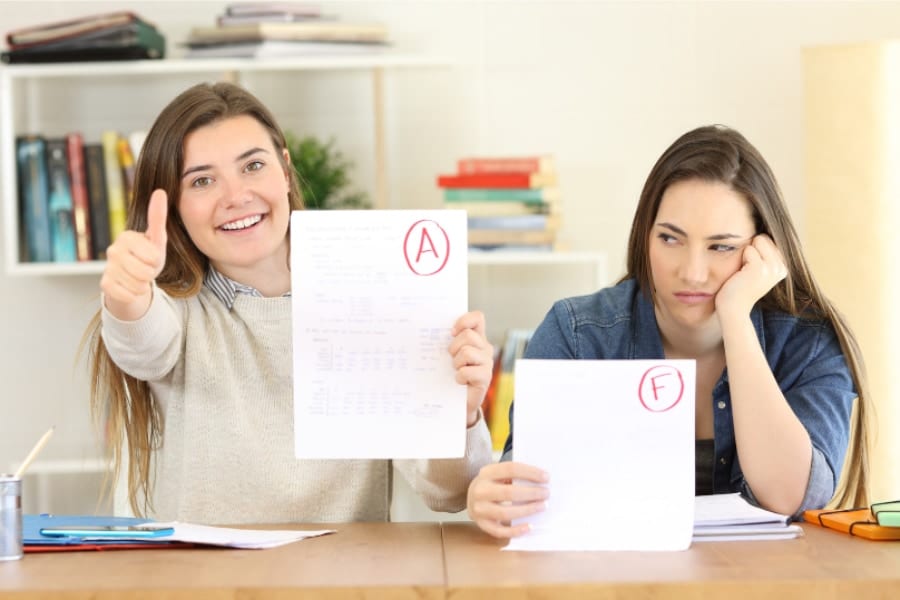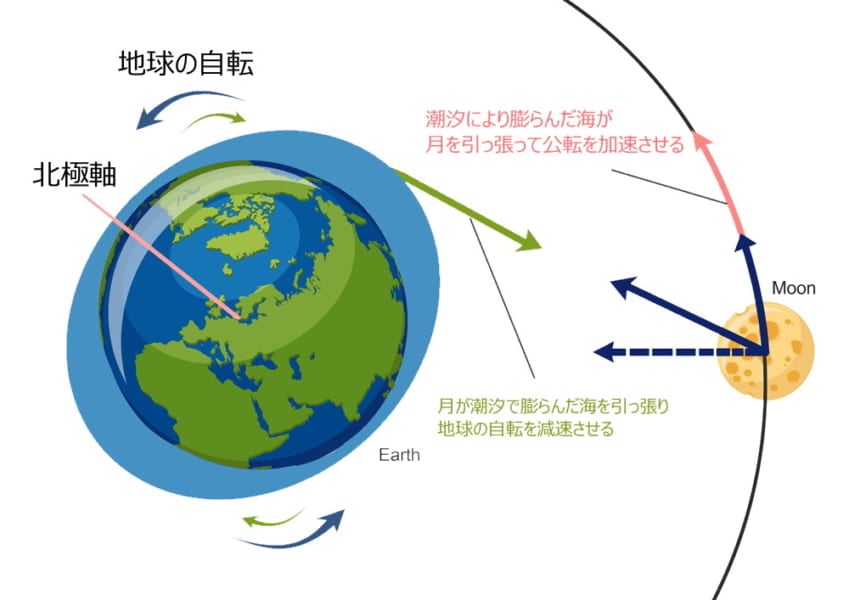孤独は体を攻撃する

私たちは今、「孤独」という社会問題に改めて向き合おうとしています。
2018年、イギリス政府が「孤独担当大臣」を任命したというニュースは大きな話題を呼びました。
日本においても2021年に「孤独・孤立対策担当大臣」が設置され孤独・孤立問題を省庁横断で扱う司令塔と位置づけられました。
アメリカでも2023年に米国公衆衛生局長官が孤独と社会的孤立の流行に関する勧告報告書を発表し、孤独を公衆衛生上の危機と位置付けています。
新型コロナウイルス禍は人々の交流を断ち切り、この「孤独の流行」を一層悪化させました。
世界中で多くの人が長い隔離生活を経験し、その副作用としてメンタルヘルスの悪化や社会への不安感が広がったのです。
しかし孤独の影響は、一人ひとりの心の健康や気分にとどまりません。
人は本能的に社会的なつながりを求める生き物です。
実際、私たちの祖先にとって仲間から切り離されることは命に関わる危険でした。
そのため進化の過程で、孤立を感じたときに私たちの体が警報を発するようになったと考えられています。
これが「孤独感」という主観的な痛みであり、他者とのつながり不足を脳が知らせるサインとして働くのです。
本来であれば、このサインをきっかけに社会的な絆を結び直すはずですが、長期間にわたって孤独が続くと問題が深刻化します。
シカゴ大学の神経科学者であるジョン・カシオポ博士とルイーズ・ホークリー博士の研究によれば、孤独を感じ続けること自体が慢性的なストレス要因となり、脳と体は常に警戒状態になります。
具体的には、視床下部—下垂体—副腎系(HPA軸)が過度に活発化し、ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されるのです。
このホルモンバランスの乱れは炎症反応を高め、免疫機能を弱体化させるとされています。
例えば血液検査で炎症の指標となるCRP(C反応性タンパク)などが上昇しやすくなる可能性も指摘されています。
このように孤独は体にとって、慢性的な炎症を誘発する大きなリスク要因と言えます。
健康面での影響も無視できず、孤独な人ほど高血圧や睡眠障害、さらにはうつ病や不安障害などメンタルヘルスの不調を抱えやすいことが多くの研究で示されています。
ブリガムヤング大学のジュリアンヌ・ホルト=ランスタッド教授によるメタ分析では、十分な社会的つながりがない人は、喫煙を1日15本行うのと同等のリスク増で早死にしやすい可能性があると報告されています。
孤独や社会的孤立が肥満や運動不足以上に健康に悪影響を及ぼすという結果もあり、もはや孤独は「気持ちの問題」にとどまらず、医学的にも放置できない状態と言えます。
しかし孤独が攻撃するのは体だけではありませんでした。
孤独は社会を激化させる主要因になり得るのです。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)