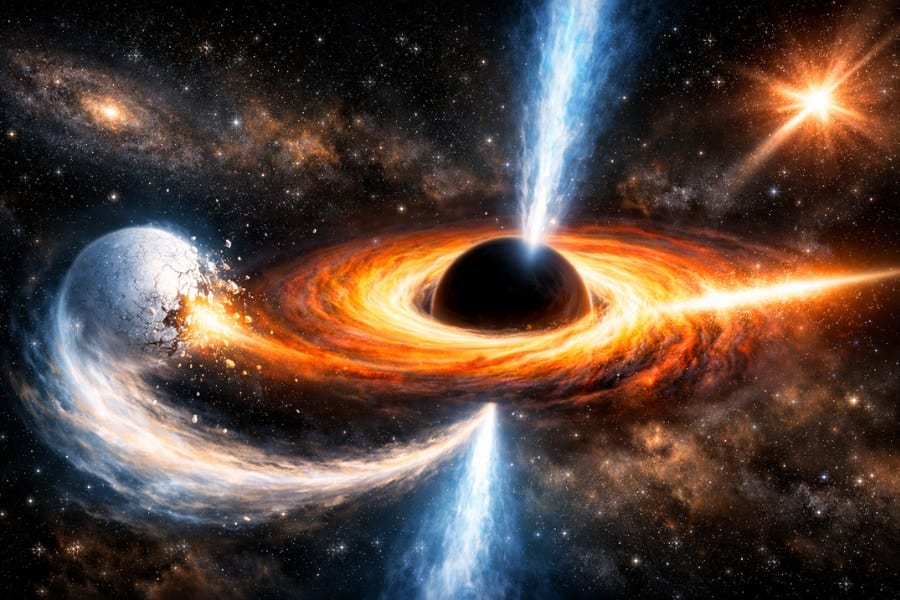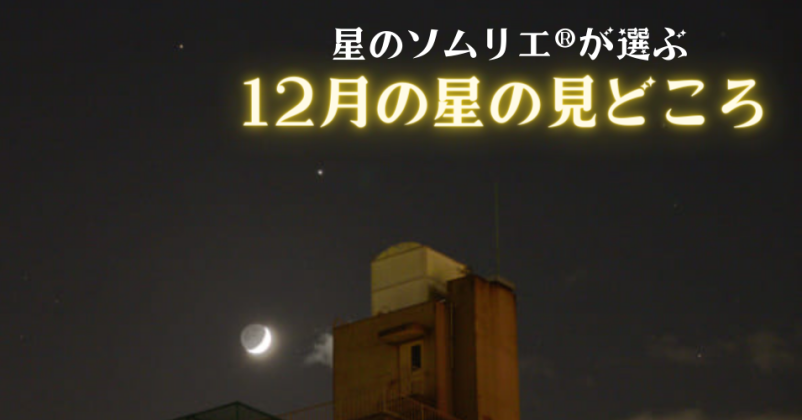衛星数が増えすぎると、地球に何が起こる?
これほど多くの人工衛星が地球を周回するようになると、私たちの暮らしや科学技術にさまざまな影響を及ぼすことが予想されます。
その最大の問題のひとつが「宇宙ゴミ(スペースデブリ)」です。
近年のロケットは一部再利用可能になっていますが、それでも使い捨てブースターなどが低軌道に残され、何年にもわたって漂い続けています。
こうした破片がほかの衛星と衝突すると、さらに何千もの小さな破片が生まれ、連鎖的な衝突リスクが高まるのです。
つまり、スペースデブリはネズミ算式にどんどん増え続けるというわけ。
このような事態が放置されれば、衝突の連鎖反応によって低軌道が事実上使用不能になり、人類が太陽系へ進出する道が閉ざされてしまうかもしれません。
この問題は「ケスラーシンドローム(Kessler syndrome)」と呼ばれており、すでに多くの研究者が「手遅れになる前に対策を講じるべき」と警鐘を鳴らしています。

また、人工衛星は地球の地表に太陽光を反射するため、光学望遠鏡を使う天文学者にとって大きな悩みの種です。
さらに衛星から漏れる電波が電波天文学にも悪影響を与えており、軌道上の収容能力の限界に達した場合、一部の電波観測は完全に不可能になると懸念する専門家もいます。
加えて、ロケットの打ち上げは温室効果ガスを放出し、地球温暖化の一因にもなっています。
打ち上げ1回あたりの二酸化炭素排出量は、商業航空機の平均フライトの最大10倍にもなるという。
環境への影響はこれだけではありません。
昔から「上がったものは必ず落ちてくる」といわれるように、人工衛星もやがて再突入して大気中で燃え尽きます。
最近の研究では、衛星が再突入時に燃焼する際、大量の金属粒子が大気中に放出されることが示唆されています。
この分野の研究はまだ始まったばかりですが、いくつかの科学者は「大気中の金属濃度が増加すると、地球の磁場まで狂ってしまう可能性がある」と警告しているのです。
もちろん、こうした民間衛星は、農村部やインフラの整っていない地域に高速インターネットを提供するなど、社会的に有益な側面もあります。
しかし、多くの専門家は「その利益が潜在的なリスクを上回っているのか?」と疑問を呈しています。
少なくとも、現状がよく理解されるまでは、人工衛星の打ち上げペースを落とすべきなのかもしれません。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)