医療ガスライティングをなくすには?
まず医師側の対応としては、患者の主観的な訴えも重要な医学情報として扱うことが求められます。
検査結果が正常であっても、「それでもつらい」という声を否定しない姿勢が必要です。
診断名がすぐに出せなくても、「一緒に考えましょう」という態度で臨むことが信頼関係を築く鍵になります。

一方で、患者側にもできることがあります。
日記やスマートフォンのアプリを活用して、痛みの強さや疲労感、眠れなかった日などの症状を記録し、それを診療時に提示することで、医師との対話がスムーズになります。
また、セカンドオピニオンを恐れず、必要であれば他の医師の意見を聞く姿勢も重要です。
さらに、同じ経験をした人たちとつながるために、患者会やサポート団体に参加することも、心理的支えとなります。
医療ガスライティングという言葉は、重く感じられるかもしれません。
しかし、この言葉が生まれ、学術的に研究されるようになったことは、まさに今苦しんでいる患者たちの「つらさ」が無視されるべきでないと認められた証です。
「何も異常はない」と言われても、「それでも苦しいんです」と言っていいのです。














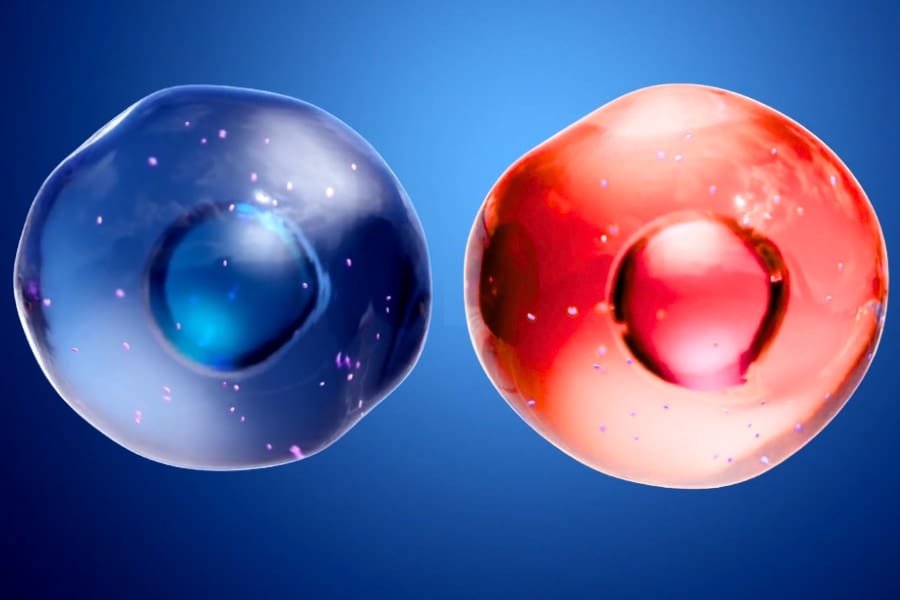















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)















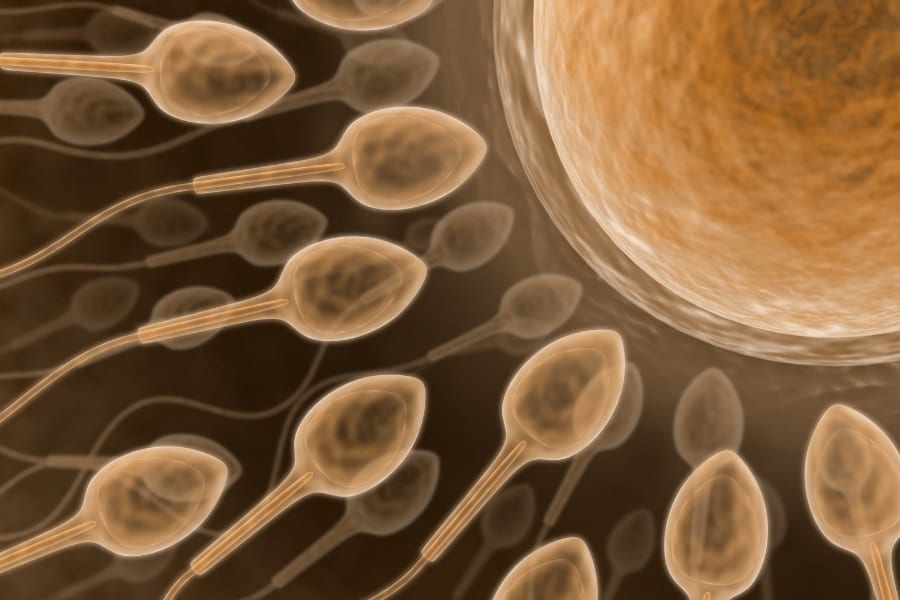

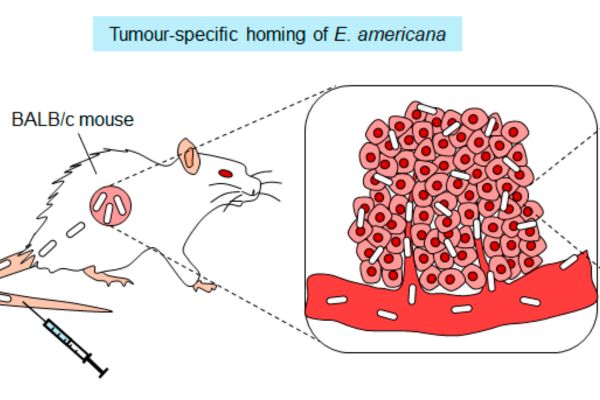


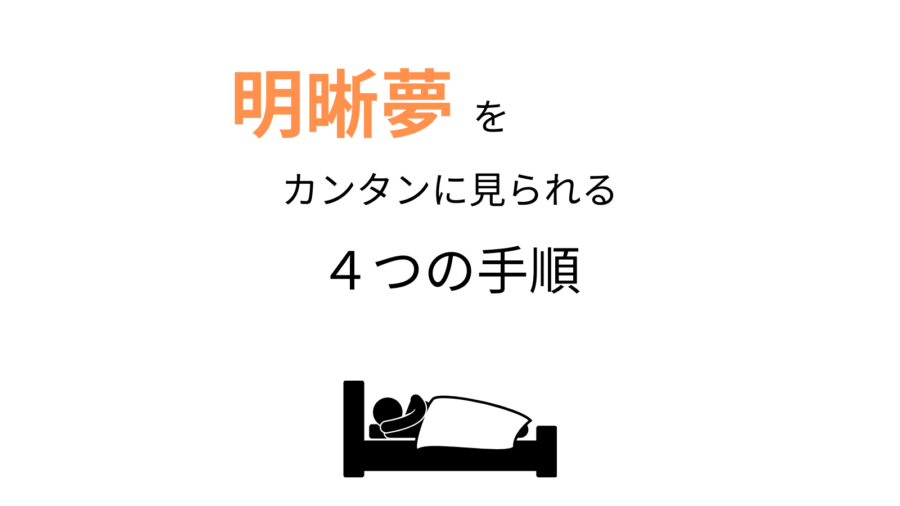







分からないことを素直に分からないと言えるってすごく大事なことでして、お医者さんもそれはできるようにならないとね。
原因分からなくても患者が痛いと言ってるなら痛み止めでも出すなりするだけでも患者の印象はだいぶ変わるわけで。
そうする今度はすぐに薬出して終わりにする医者とレッテル貼られるわけですがね。
眉を顰めるような犯罪を犯した者などのリストが一部医師の間で共有され、あるいは看護師などの口伝によって共有されることで、医師たちがそういった「好ましくない人間」に対し「確固とした医療ガスライティング」を行い、患者自ら医療を回避するようになるようしむけるような向きがあるようですね。法的には医師は診療拒否が許されないため、そういった手段をとるということのようです。こうした問題にもいずれ社会のメスが入ることが望まれます。
記事にあるように俺も35年前から過敏性腸症候群で苦しんでいました。当時はその名前すらろくに知られていなかったし俺も知りませんでした。10年前にFODMAPという概念が出来て今は食べ物を変えるだけで自己解決できるようになったものの、それ以前の症状が酷い時はどうにも出来ず、親に話しても「気のせいだろ」「病院に行け」の二択。どっちも言ってはいけないセリフの筆頭です。病院に行けと言うのがなぜ良くないのかは、相談された側は相談した側に対してお前の健康には関心なんて無いから他人を頼れという拒絶的意思表示になるからです。「病院に連れて行く」ならややましだけどそれも似たようなもの。まず相談された側は相手の訴えをよく聞いて相談者に承認を与えなければいけません。素人考えだろうと「たぶんこれが原因なんじゃない?」等と言うのもそれが医者に言わせればハズレである可能性は大きくても、相談された側自身が相談者の事を心配しているという意思表示になります。記事には身体的な病気しか書いてないけど特にメンタルを病んでいる人ならば「気のせい」「病院に行け」は最悪の対応です。だからそれらは身体的な病でもあんまり言わない方が良いんです。子供なら話を一通り聞く→親が原因を考えたり調べてそれも一通り子に話す→念のため病院に行く、がベストです。親が全く話を聞いてくれないのなら子は心を閉ざし医者にも症状を正直に話し難くなります。
そして俺はそういう毒親に育てられたからこそ過敏性腸症候群にもなった訳ですが、過敏性腸症候群はメンタル同様に医者にもはっきりした事は言えないし医者自身がそれで苦しんだ経験が無い限り大したアドバイスも出来ないし、俺もそれを十分理解していたので病院には行こうとしませんでした。症状が悪化して試しに内視鏡検査を受けたけど医者も案の定「何も分からない」。そして自然に治ったけど病院に行って分かったのは医者もやっぱり分からないという事だけでした。
俺は後に過敏性腸症候群を数年かけて地道に克服し、その具体的方法もあちこちに書いてるけど、誰もろくに読まないし、親自身が腸弱者の癖に俺のアドバイスを全く聞こうとしません。分かりにくい事はまず自分が分かろうとする必要があるけど、文中にもある通り承認不足に育ってしまうと他人を頼る気も無くなるし治そうとか自分で勉強して理解しようという気も無くなるものです。病は気からというのは鬱だとホルモンパランスが崩れて免疫が落ちてとか言う話に限らず、もっと単純な話として治す気が無くなってしまう事が一番の問題です。気のせいだと突き放してはいけないのは医者に限らず親でも先生でも上司でもあらゆる権威者にとって同じです。
私も同じ経験があります。
先天性の脊柱管狭窄症で脚が痛くて痛くて仕方なかったのですが、当時はまだ病名がわからず、どの病院へ行っても「気のせい」「2~3日で治る」と言われ続け、「自分の痛みは気のせいなんだ」とか「この程度の痛みで医者へ行くのは迷惑がられる」と悩み続けていました。
しかし、とうとう歩けなくなるほど悪くなり「やはり、これはおかしいぞ!」と確信を持つことができたので、そこから再び病院へ。
最初の数軒は予想どおり「気のせい」と言われ、最後のたどり着いた病院で「他の病院で言われたとおり僕も気のせいだと思う。症状から思い当たる病気が二つあるけれど検査してみますか?お金と時間の無駄だと思うけれど」と言われ、迷わず「検査したいです」とお願いしました。
検査結果が出たとき先生から「原因が分かりました。これは痛いよ」と、やっと原因が分かったのと、苦しみを理解してもらえたことに泣きそうになりました。