ハチミツの「分子の指紋」が2500年後に浮かび上がる
今回の再分析では、赤外分光法(FTIR)や熱分離型GC-MS、陰イオン交換クロマトグラフィー(AEC-MS)、さらにはタンパク質を分解して解析する「ボトムアップ型プロテオミクス」など、複数の手法が組み合わされました。
その結果、現代のミツロウやハチミツと非常によく似た化学的特徴が、壺の残留物から確認されました。
特に決定的だったのは、ハチミツに特有の「ヘキソース糖」が高濃度で検出されたこと、そしてローヤルゼリーの主要タンパク質(MRJP1・2・3)が検出されたことです。
これらのタンパク質は、セイヨウミツバチ(Apis mellifera)由来であることも突き止められました。

さらに銅製の壺内での化学反応により、ハチミツ中の糖が「フラン類」と呼ばれる耐久性の高い成分に変化し、保存されていたことも明らかになりました。
銅イオンが微生物の活動を抑え、糖の分解を防いだ可能性があるのです。
また、残留物にはハチの巣(ハニカム)そのものが供えられていたとみられ、焼けた砂糖のようなにおいを放つ褐色のフィルムも検出されました。
これは加熱や経年劣化によって糖がカラメル化したことを示しており、「焼けたハニカム」のような状態に変質していたと考えられます。
長年、謎に包まれてきた「神への捧げ物」の正体は、科学の力によってついに明かされました。
かつての祈りが込められた甘い黄金――それは腐ることなく、神殿の壺の中で2500年の時を静かに待ち続けていたのです。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)




















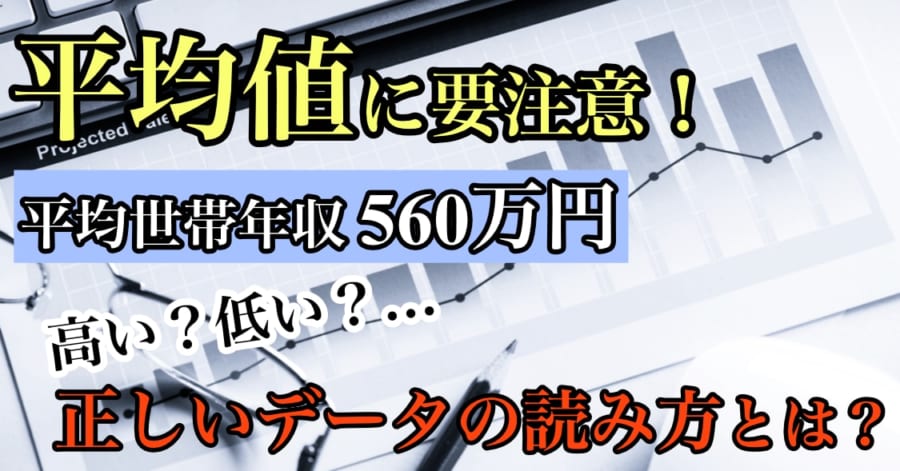







歴史って浪漫ですね。
現代の科学力の凄さ!
人類は、何処まで進歩するのか、楽しみです。
ナゾの供物がハチミツでよかった
禍々しいものじゃなくてよかった
現代の分析技術により蜂蜜であるという事が確認された事自体は結構な事だが、
>考古学者たちは、これが「ハチミツを神への供物として捧げたものではないか」と推測しました
とあるように蜂蜜であるという事自体は昔から言われていた事。
じゃあその昔から言われていた「蜂蜜」という仮説を否定する根拠となっていた
>1970年代から1980年代にかけて行われた複数の科学分析では、壺の中から糖類は一切検出されず、動植物性の脂肪やロウに近い成分が主体である
という分析結果はどうなったの?
ロウは蜜蝋が含まれていたから検出されるのは当然として、「糖類は一切検出されず」という結果になった理由や、「動植物性の脂肪に近い成分」が含まれていたのは何故なのか?
それらが間違いだったという理由も説明出来なければ、1970年代から1980年代にかけて行われた複数の科学分析と今回の分析結果の間には矛盾があるという事になり、どちらの結果を信用して良いのか判らなくなります。
AIに聞いて見ました。再分析のほうは省略しています。
1970年代〜1980年代の分析
この時期の考古学的な遺物分析では、主に**ガスクロマトグラフィー(GC)や薄層クロマトグラフィー(TLC)**が用いられていました。
* 詳細:
* ガスクロマトグラフィー (GC): 気化した試料をカラムと呼ばれる管に通し、成分によって分離する手法です。当時のGCは、成分を分離することはできましたが、その成分が具体的に何であるかを特定する能力(同定能力)が現在に比べて著しく低かったのです。検出器も、物質の存在を大まかに捉えるものが主流でした。
* 薄層クロマトグラフィー (TLC): ガラス板などに吸着剤を塗り、そこに試料を展開して成分を分離します。分離された成分を既知の物質(標準品)と比較して同定を試みますが、精度は高くありませんでした。
* 限界:
* 感度の低さ: 微量な成分を検出することが難しく、壺に付着した残留物の中から糖のような微量成分を見つけ出すのは困難でした。
* 同定能力の限界: 分離した成分が「脂肪やロウに近いもの」という大まかな分類はできても、それが具体的に何の植物や動物に由来するのか、あるいはハチミツやミツロウのような複雑な混合物であるかを正確に特定することは技術的に不可能でした。そのため、糖が検出されず、「動植物性の脂肪やロウに近い」という結論に留まったと考えられます。
両者の最も大きな違いは、**「感度」と「同定能力」**の飛躍的な向上です。
時代が進めば解析の精度も上がる。現在は極微量のタンパク質からDNA情報を取り出す事にも成功する。科学解析は時代と共に変化する。科学の基本の基ですね。その結果、定説も時代と共に塗り替わるのです。