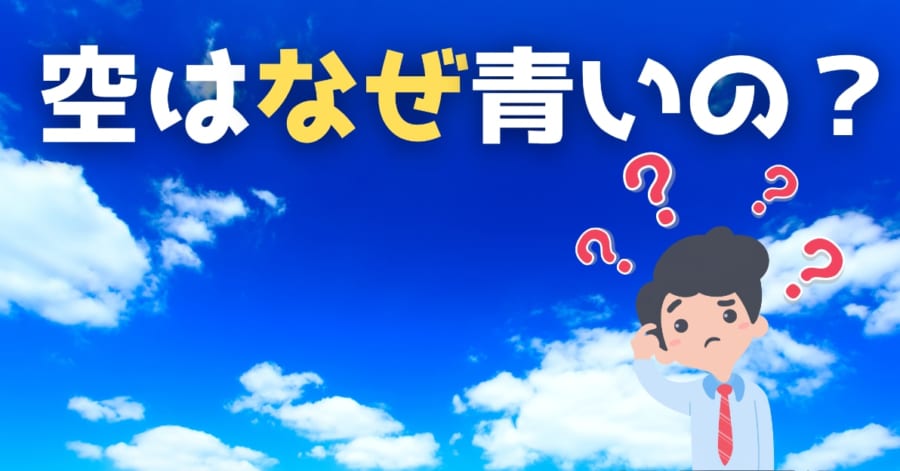増えず食べず、ただ修理だけする微生物の生き方
今回の研究が示した最も重要なことは、微生物がほとんど増殖せず、必要最低限の活動だけを続けることで、驚くほど長い年月を生き延びる可能性があるという点です。
私たち人間を含め、一般的な生物は定期的に栄養を取り、細胞が分裂して新しい細胞に置き換わることで命をつないでいますが、今回発見されたプロメテアルケオタは、それとはまったく異なる戦略を取っていました。
彼らはエネルギーを使って活発に増殖したり、環境に適応するために新しい仕組みを進化させたりすることはほとんどせず、ただ静かに、自らのDNAやタンパク質に生じるわずかな傷を修復することだけにエネルギーを使っていたのです。
人間の感覚に例えるならば、「自動車のエンジンを止めずに、最も燃料を節約するアイドリング状態で、長い渋滞の中をゆっくりと耐え忍ぶ」ようなものです。
また、こうした長期間の生存が特別な装置や新しい遺伝子など、特殊な仕組みによって可能になったわけではなく、もともと備わっている基本的な修復システムだけで実現されていたことも重要なポイントです。
これは、微生物が生きるために新しく何かを獲得したわけではなく、生命が本来もつ「傷を直す仕組み」をひたすら粘り強く続けていただけだということです。
例えるなら、特別な最新の修理道具を使うのではなく、家庭に元々ある道具を丁寧に使って、大切なものをずっと直し続けるようなものです。
今回の研究は、「生命とは、元々もっているシンプルな修復機能を使って、想像以上に長期間維持されうるものだ」ということを具体的に示した、非常に興味深い発見といえるでしょう。
しかしここで注意したいのは、この研究結果が「すべての生物が同じように長く生きられる」という寿命一般の法則を示したわけではないということです。
今回の研究が対象としたのはあくまでも「凍土」という非常に安定した極寒環境で、微生物がほとんど動けない状態に置かれた場合の話です。
通常、細菌などの微生物は、暖かく栄養が豊富な環境では急速に増殖して短期間で寿命を終えることが多く、私たちは「微生物はすぐに死んでしまう」と思い込みがちです。
ですが、今回の発見はそれとは逆に、「非常に安定した極端に寒い環境に置かれれば、微生物は活動を極限まで抑えて、数万年単位で生き続けることができる」というまったく新しい可能性を示しています。
つまり、生命の寿命は環境条件によって大きく変わるものであることが明らかになったのです。
さらに、今回の研究では、死んだ微生物のDNAだけでは、長期間にわたって維持されるDNAの量や質を説明できないことも分かりました。
研究チームが計算したところ、死んだ微生物のDNAは、たとえ凍った環境でも宇宙線などによって次第に壊れていき、100年程度でほぼ完全に分解されることが示されました。
したがって、今回発見された10万年以上もほとんど傷まないまま残っていたDNAは、微生物がわずかに生命活動を続けてDNAを絶えず修復してきた証拠であると考えられます。
これは、「完全に停止した生命活動」では説明がつかず、「わずかながら活動を続けている状態」こそが微生物の驚くべき長寿を可能にしていたことを意味しています。
今回の発見はさらに、地球を超えて宇宙における生命探査にも重要なヒントになります。
もし地球の極寒環境において、特別な仕組みを使わずに微生物がわずかな活動を保ちながら10万年以上生き続けられるのであれば、火星や木星・土星の衛星(エウロパやエンケラドゥスなど)といった極寒の天体でも、同じように長期間生き続けている微生物が存在する可能性があるからです。
地球外生命を探す研究では、生命がどれほど過酷な環境でも生き延びられるかが重要なテーマの一つです。
今回の研究成果は、「生命が存在できる環境の範囲を、私たちがこれまで考えていた以上に広げる必要があるかもしれない」という重要な示唆を与えています。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)