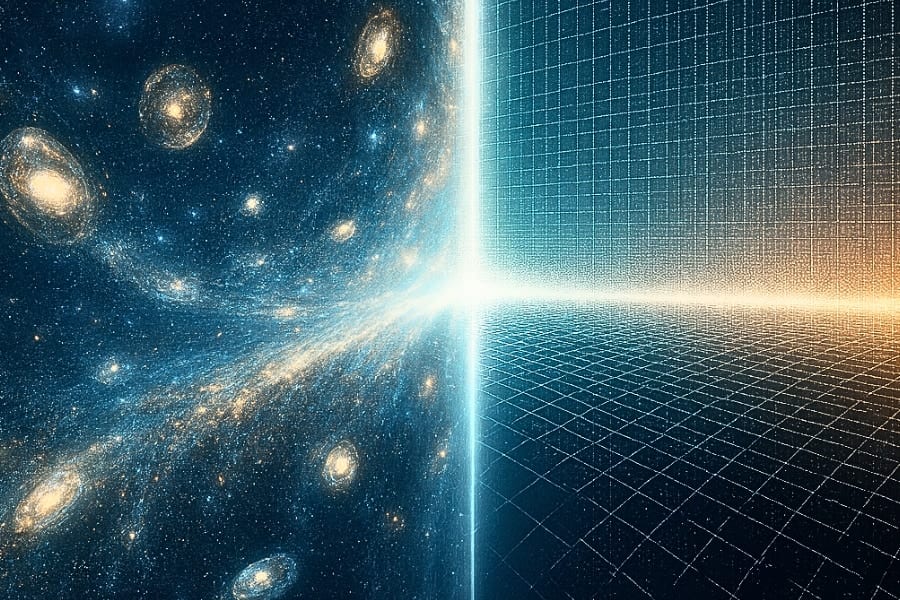明らかになった驚きの結果
解析の結果、人工甘味料の摂取量が多い人ほど認知機能の低下が速いことがわかりました。
最も多く摂取していた群は、最も少ない群に比べて全体的な認知スコアの低下が62%も速く進行していました。
これは8年間で約1.6年分の「追加的な脳の老化」に相当します。
中間の群でも35%速く、約1.3年分の老化が加速していました。
特に60歳未満の中年層では影響が顕著で、言語流暢性や全体的な認知機能の低下が強く関連していました。
一方、60歳以上の高齢層では明確な関連は見られませんでした。
また糖尿病を持つ人では関連がさらに強く、糖尿病を持たない人よりも認知機能の低下が速い傾向がありました。
これは、糖尿病患者が日常的に人工甘味料を砂糖代替として多用する傾向と関係している可能性があります。
甘味料の種類別にみると、アスパルテーム、サッカリン、アセスルファムカリウム、エリスリトール、キシリトール、ソルビトールはいずれも記憶力や言語流暢性の低下と関連していました。
一方、乳製品や果物に自然に含まれるタグアトースには認知低下との関連は見られませんでした。

重要なのは摂取量だけではなく「摂取頻度」でも関連が見られたことです。
毎日人工甘味料を摂取する人は、たとえ量が少なくても、時々しか摂らない人や全く摂らない人よりも認知機能の低下が速く進行していたのです。
人工甘味料は「砂糖より健康的」と考えられ、多くの人々の生活に浸透してきました。
しかし今回の研究は、その選択が脳の健康をむしろ損なう可能性を示しています。
認知症が社会的な大問題となる未来に向けて、私たちは砂糖や人工甘味料のどちらが「まし」かを選ぶだけではなく、食事全体をどのように整えるかを考える必要があるのかもしれません。













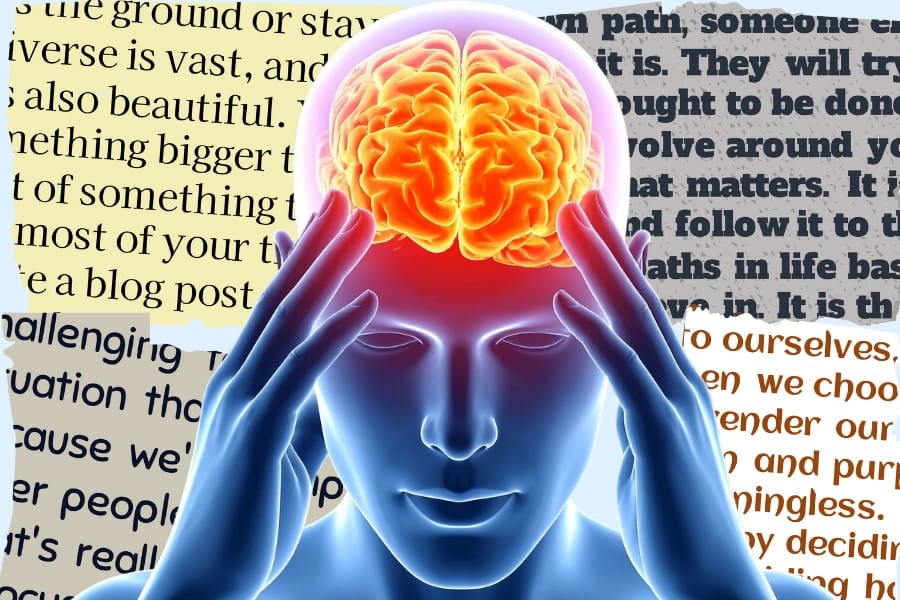

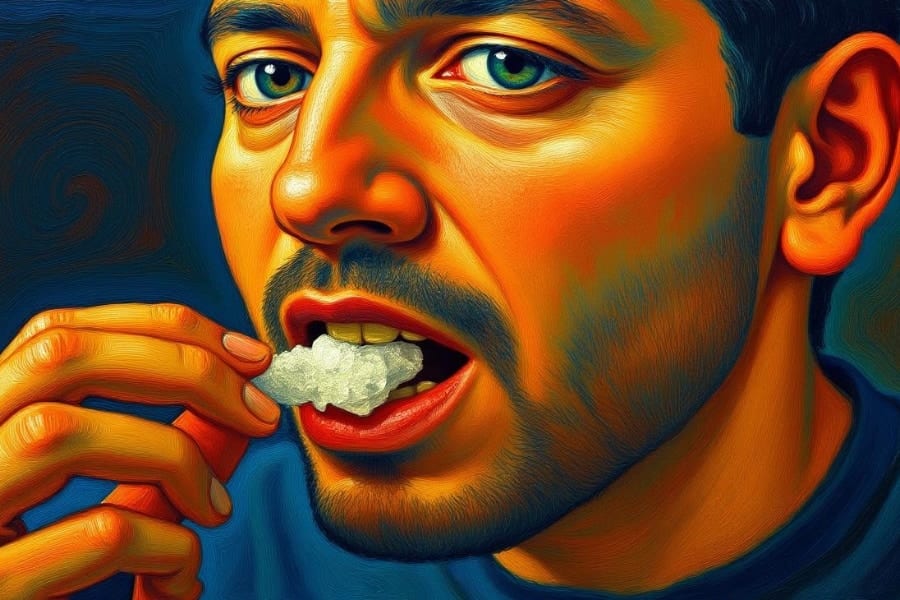


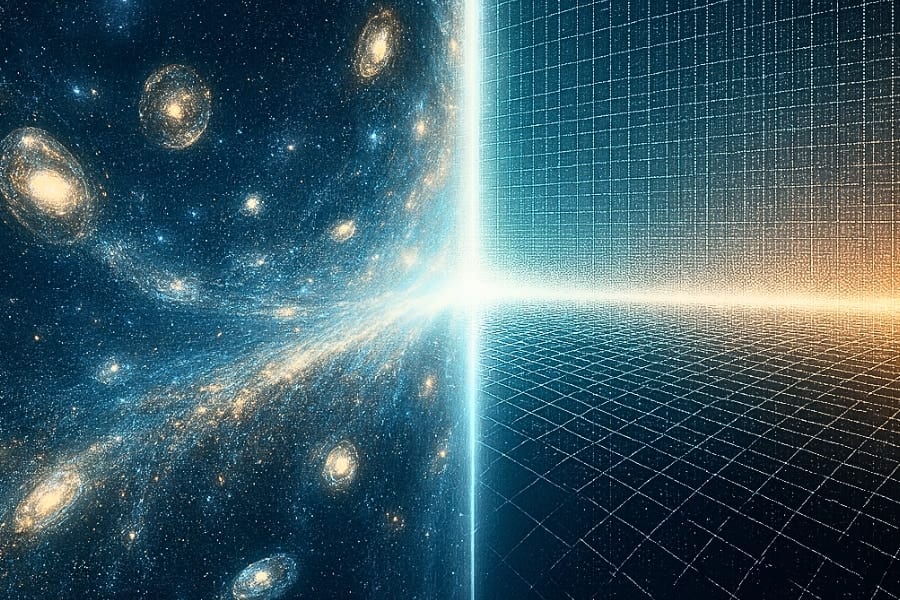

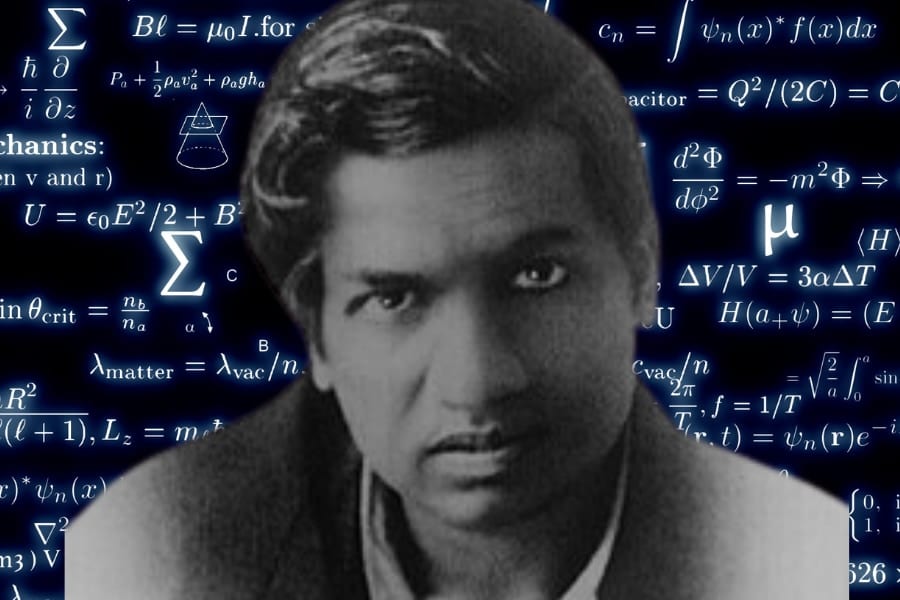








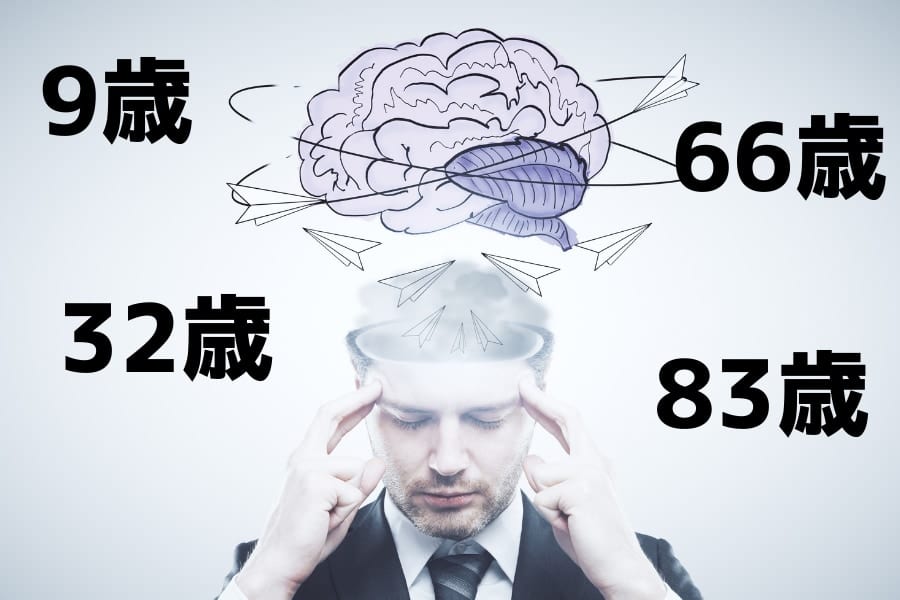


![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)