子どもの心を動かす「信頼される大人」とは?
調査の結果、子どもたちが親から注意や警告を受けたとき、「ただ叱られた」と感じる場合には、「自分のことを分かってくれない」「自由を奪われた」といった不満が強まり、かえって反抗したくなる傾向が明らかになりました。
たとえば「やめないとスマホを取り上げるよ」といった強い警告だけが続くと、子どもは「押し付けられている」と感じやすくなり、反抗的な反応との関連が示されました。ただし、本研究はアンケート調査(横断研究)であり、因果関係までは断定できません。
一方で、親が子どもの立場や気持ちを理解しようとする「視点取得(perspective taking)」の態度を示した場合、子どもは忠告を聞き入れやすいことが示されました。(視点取得:他者の立場や気持ちを自分のこととして理解しようと心理的態度)
「なぜそんなことをしたの?」「どんな気持ちだったの?」と、まず子どもの話をじっくり聞いてから注意することで、子どもは「分かってもらえた」という安心感を持ちやすくなり、実際に問題行動をやめることに大きく影響したのです。
こうした注意の仕方が重要というのは、理解しやすい理屈です。
それと併せて、今回の調査では、親がふだんから「言っていること」と「やっていること」が一致しているかどうかで、同じ注意でも子どもの受け止め方がまったく異なることが分かりました。
たとえば、「思いやりを大切にしなさい」と言うだけでなく、実際に家族や友人を助けている姿を見せていたり、「約束を守ることが大切」と教えるだけでなく、自分も時間や決まりごとをきちんと守っている。さらに、正直さを大切にしている親なら、間違えたときに素直に謝るといった日々のふるまいが、子どもの心にはしっかりと刻まれていたのです。
こうした「価値の体現(言行一致)」の割合が高い親ほど、警告が子どもの反発を引き起こしにくい傾向が示されました。
この研究から見えてくるのは、「口で言うだけ」や「その場しのぎの叱り」ではなく、注意する大人自身が日々のふるまいや誠実さをきちんと示していなければ子どもの心は動かないという事実です。
注意した大人の“生き方”が自体が、子どもにとっての信頼の土台となっていきます。
また、「なぜ?」を丁寧に聞く姿勢も大切です。
頭ごなしに叱るのではなく、「なぜそれをしたのか?」と対話によって相手の気持を理解する姿勢が、前向きな反応を得るためには重要なのです。
こうしたポイントは、当たり前のようでも、実践できていない大人が多いため子どもの反発を招いていると考えるべきでしょう。
ただ、こうした注意の仕方や親の言行一致の態度が影響するのは、その場で注意を聞き入れるかどうかに対してのみであり、「問題行動の再発」については、直接的な関連は見られませんでした。
飲酒や喫煙、スマホの使いすぎや門限など、反抗せずに素直に注意を聞き入れてもらえたとしても、子ども自身がやめることに納得がいかない問題は、誰がどういう言い方をしても、再発を防ぐことはできていませんでした。
注意は単にその場の問題に対して「危ないからダメ」などと述べるのではなく、なぜ危険なのか、その理由や代わりの行動を一緒に考えるという姿勢が、その後の変化に重要なのでしょう。
こうした工夫が、子どもとの信頼関係を深め、反発を減らすコツだと考えられます。
なお今回の研究はイスラエル南部の中高生を対象とした相関・横断調査であり、子ども自身の自己報告が中心となっています。そのため文化や家庭環境が異なる場合や、第三者の視点も含めた研究が今後は期待されます。
この研究は、「子どもに反発されにくい大人」とは、普段から自分の価値観を明確に示して貫いている人であり、子どもの話をしっかり聴ける姿勢のある人だということを示しています。
信頼は一朝一夕で生まれるものではありませんが、日々のふるまいの積み重ねが、子どもの心に届く言葉をつくっていくのです。
逆に言えば、子どもにすぐ反発される人は、自分が普段から行動と言動が一致しておらず、価値観が曖昧になっているのだと自省すべきなのかもしれません。













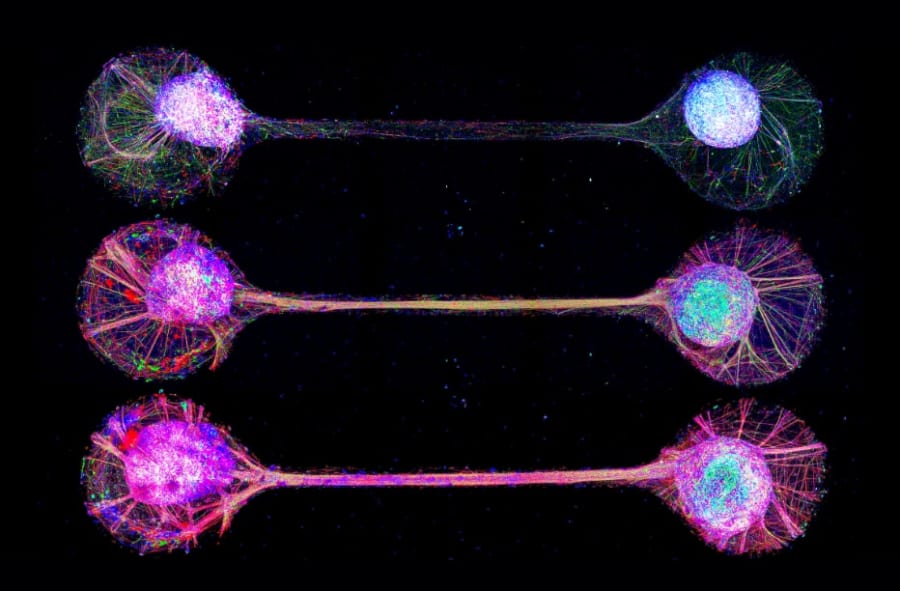


















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)





















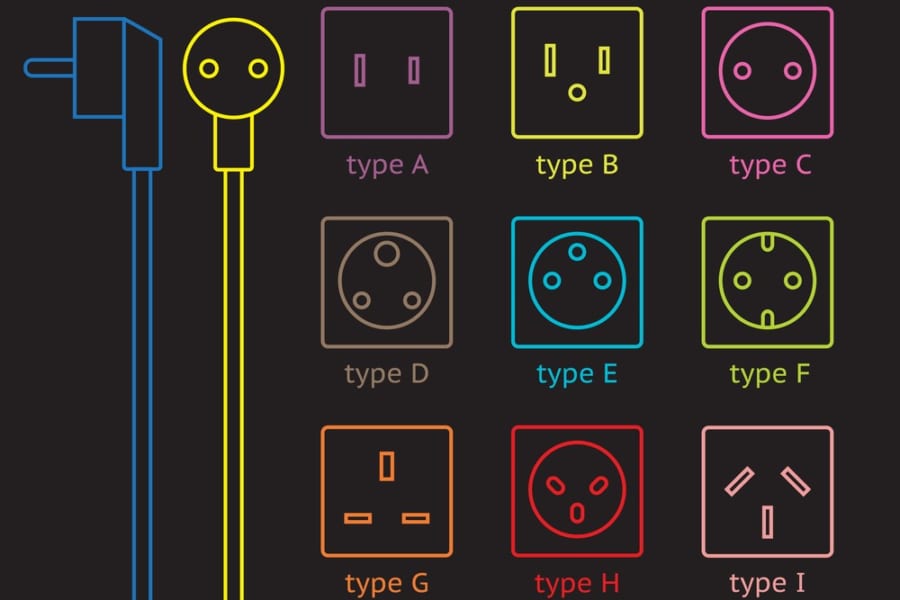






そらまともに自分を律することができていない親に何か言われたってどの口が言ってるんだって子供は反発するよね
子供は親を本当に良く見ている
叱る前にまず自分の普段の言動行動を顧みた方がいいね
子供の言うことを子供は聞いてくれないということですね。
まあ当然ですけど。
どうしてそんなことをしたの?は言ってないなママ…だから怒られたら「だって……」て言っちゃう。「だって何よ!」で言って余計言いにくくしてくるし。
なぜそんなことをしたの?と聞いて言った答えと実際の事実が異なった場合はどうしたら良いのだろう
子どもを信じられなくなる
下手に出たら成功体験が出来て子どもは上手に嘘を覚えていくのだが…
人って衝動で動くものだからなぁ
「なぜ?」とか「何が?」って問いに答えるには高度な学習や経験が必要で、子供はおろか大人でも結構難しい
その問いは本人にも理由が分かってない状況では、考えてもいない答えを言わせてしまう悪手
敵の失言を誘って、追い詰めるには有効な方法だけど
まず適切な選択肢を自分から提示して選んでもらうのが正解と思う
「何を食べたい?」みたいな選択肢の無い問いには、人生経験値の少ない子供には答えられない
けど「餃子とカレーがあります。どっちを食べたいですか?」みたいな問いには答えられる
そうした訓練を繰り返していくうちに、初めてその件に対して「何が?」の問いに答えられるようになる
>親がふだんから「言っていること」と「やっていること」が一致しているかどうかで、同じ注意でも子どもの受け止め方がまったく異なる
いいえ
単に言うこと聞きたくないだけだよ
で責めれそうなとこ探して、そうだ、大人自身がやってないから突っぱねていいじゃん、って理由を取ってつけてるだけ
ガキ舐めんな
そういう、子供は狡いことはしない純真な存在で、大人が真摯に接すればコントロールできる、って無自覚に言外に思ってそうな雰囲気を臭わせてるのがね、一番ダメなんだよ
結局一番長く過ごしてる手本となる大人は親だから親の態度が刷り込みで子供に影響するよね
言動不一致の親の下で育てば自然とそういう振る舞いになる