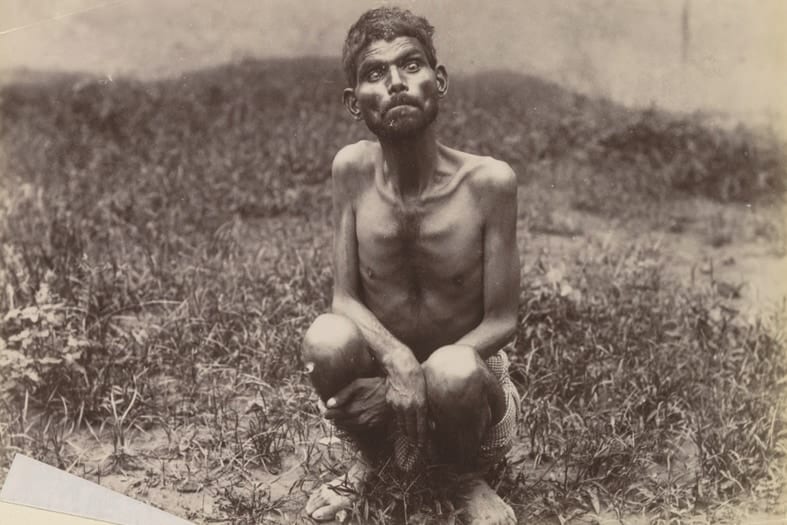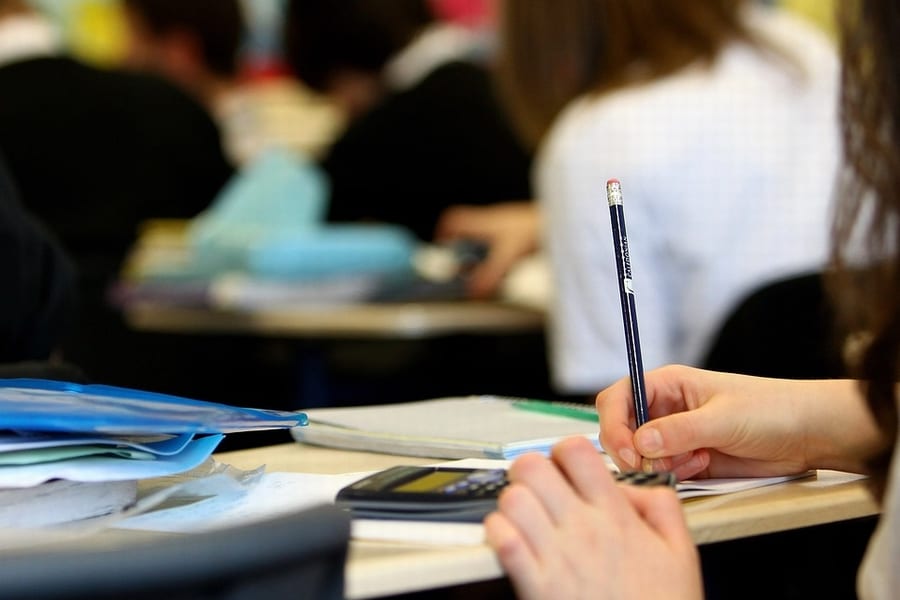93%の子どもが「怖いけど楽しい」活動を体験している
調査では、全体の93%の子どもが「少なくとも1つは怖いけど楽しい体験をしている」と親が回答しました。
ほぼすべての子どもが、「娯楽としての恐怖」を楽しんでいたのです。
さらに、週に1回以上そのような体験をする子どもは70%にのぼり、20%はほぼ毎日“怖いけど楽しい”遊びを楽しんでいることが分かりました。
特に人気が高かったのは、ブランコや滑り台、スケートボード、遊園地の乗り物など、速い動きや高い場所、深い場所で遊ぶ体験です。
その次に、怖い映画やテレビ、怖い物語の読み聞かせ、鬼ごっこやルールのある遊び、怖いビデオゲームなどが続きました。
一方で、痛みを伴う活動やルール違反といった一部の特殊な体験を楽しむ子どもは少数でした。
また、年齢による変化もはっきりと現れました。
1歳から4歳ごろの幼児期は、怖いテーマのごっこ遊びや家族や兄弟と一緒に身体を使って遊ぶ活動が中心となっていました。
小学生以降は、活動の種類がやや減るものの、ホラー映画やゲームなど、メディアを使った活動が増えていきます。
思春期以降は、友達や一人で体験する割合が増え、親が「どこで」「誰と」やっているかを把握しきれないケースも増加します。
活動場所についても、幼い時期は家庭や学校が中心ですが、年齢が上がるにつれて屋外や遊園地、SNSなど、体験する場所の幅も広がっていくことがわかりました。
では、なぜ子どもたちは「怖いけど楽しい」体験を求めるのでしょうか。
研究チームは、こうした体験が「安心できる場所で気持ちを上手に調整する練習の場」として大切なのではないかと考えています。
たとえば、怖い映画を観ているときに耳をふさいだり、怖い部分では目を閉じるなど、子どもたちは自分なりに怖さと付き合う方法を自然に身につけていきます。
また、親や友達と一緒に体験することで、怖さや驚きを分かち合い、仲間とのつながりや安心感も育まれていきます。
こうした遊びを繰り返すことで、嫌な気持ちになったときも自分で気分を切り替えたり、不安な気持ちをやわらげたりできる力がつく可能性もあると考えられています。
ただし、今回の調査にはいくつかの限界もあります。
今回の調査は親や保護者の視点に基づいているため、特に思春期や“ルール違反系”の活動については、実際よりも過小評価されているかもしれません。
また、調査が行われたデンマークという比較的安全で自由な文化圏の結果であり、他の国や文化では異なる傾向がみられる可能性も考慮する必要があります。
研究チームは、今後は子ども本人の声を聞く調査や、さまざまな国や文化を対象とした比較研究が必要だと提言しています。
「怖いのに楽しい」という感情は、ほぼすべての子どもにとってごく普通で、成長に欠かせない経験だということが、この研究から明らかになりました。
子どもの“ちょうどいい怖さ”を見守り、上手に楽しむ力を伸ばすことが、健やかな成長を支える大切な鍵になるのかもしれません。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)