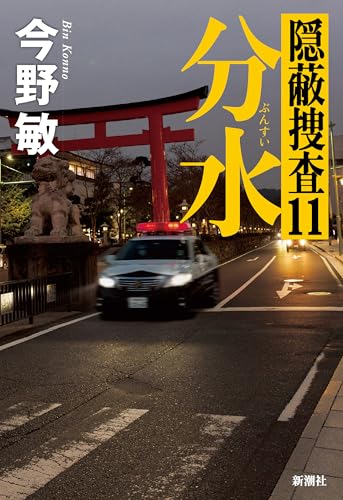かつての常識「アレルギーのリスクがある食品は食べ始める時期を遅らせるべき」
1990年代から2000年代初めにかけて、欧米の小児医療では「乳児の免疫は未発達で、強いアレルゲン(allergen:アレルギーを起こす物質)に早く触れると危険だ」と考えられていました。
アレルギーは主に「体質」や「遺伝的な素因」によって決まるとされ、外からの働きかけで変えられるものではない、というのが当時の医学的常識でした。
そのため、卵やピーナッツなどアレルギーを起こしやすい食品は、1歳を過ぎるまで避けるのが安全だとされ、日本を含む多くの国でも小児アレルギー関連のガイドラインでは同様の方針が取られていました。
ところが不思議なことに、こうした指導方針が普及していったのと同時期に、食物アレルギーの子どもが急増してきたのです。
イギリスやアメリカでは、ピーナッツアレルギーの有病率が1990年代から2000年代にかけて2〜3倍に上昇し、ピーナッツを少量食べただけでアナフィラキシー(全身の激しいアレルギー反応)を起こして救急搬送される子どもが増えるなど、小児科で命に関わる症例の対応が増えていきました。
社会全体にもその影響は広がり、学校給食ではアレルゲンの除去や献立変更が相次ぎ、外食産業や食品メーカーでも卵・乳・小麦・落花生など特定原材料の含有を商品ラベルに明記する「アレルゲン表示義務」が制度として導入されました。
医学界では「なぜ食物アレルギー予防のための指導を徹底したのに、症例が増えているのか」という疑問が相次ぎ、研究者たちは従来の考え方そのものを見直さざるを得なくなっていったのです。
免疫は皮膚に触れた「食べ物」を敵と認識する
研究の結果、アレルギーの発症には「免疫が食べ物をどう認識するか」が深く関わっていることが分かってきました。
私たちの免疫は、体に入ってくるものを敵として攻撃すべきか、安全なものとして受け入れるかを“学習”しています。そして、その学び方には2つの経路があることが明らかになってきたのです。
経路①:皮膚から入ると「敵」として覚えてしまう
乳児の皮膚は非常に薄く、湿疹などでバリア機能が弱まると、食べ物の微細なたんぱく質が皮膚から侵入することがあります。
このとき免疫は、異物として認識し、攻撃するように記憶してしまうのです。
この反応が、湿疹のある赤ちゃんがアレルギーを起こしやすい一因と考えられています。
経路②:口から入ると「安全」として学習する
一方、口から食べた場合、腸の免疫は「これは食べ物だから攻撃する必要はない」と判断します。この“慣れる”反応を経口免疫寛容(oral tolerance)と呼びます。
つまり、食べる経験を通じて最初に触れたタンパク質を、体は「安全な食材」として受け入れやすくなるのです。
しかし、食べ物を完全に避けてしまうと、この「正しい学習」の機会が失われてしまいます。その結果、皮膚などからの“誤った学習”だけが進み、免疫が本来安全なはずの食べ物を敵とみなしてしまうのです。
この新しいアレルギー発症のメカニズムを二重曝露仮説(dual-exposure hypothesis)と呼びます。
































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)