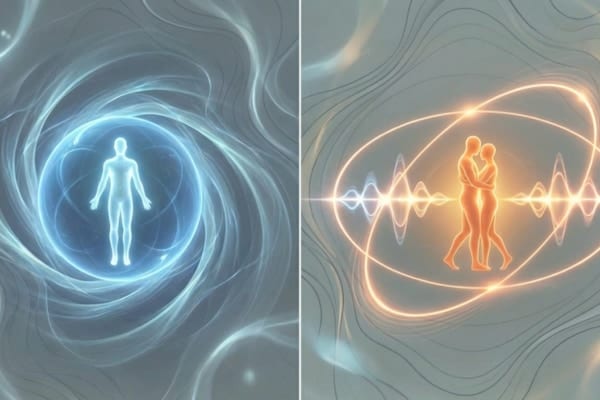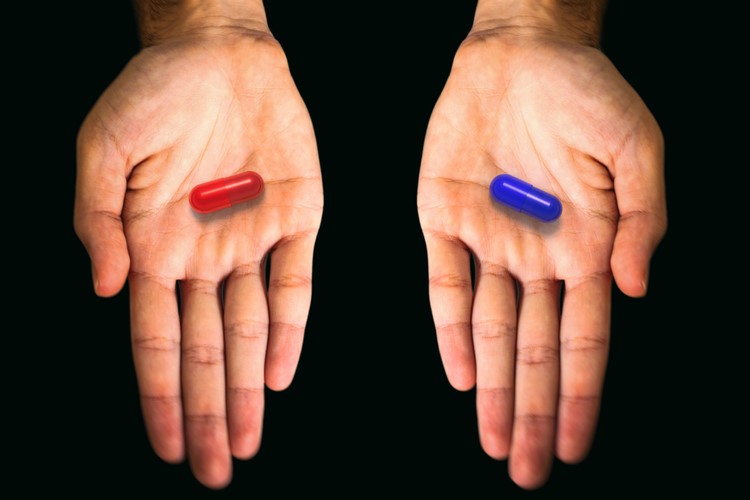「“タイプ分け”では見えなかった犯人の心」
連続殺人犯は、これまで「支配型」や「快楽型」といった分類で語られることが多くありました。
こうした区分は捜査の現場では便利ですが、実際には犯人の心理がより複雑で、いくつもの動機や感情が重なり合っていることが知られています。
今回の研究が取り組んだのは、その複雑さを“心の構造”として描き出すことでした。
研究チームが注目したのは「ナルシシズム(narcissism)」という心の特性です。
ナルシシズムは、連続殺人犯の語りに頻繁に現れる“自分を特別視する発言”や“被害者意識の強い語り”の背後にある心理を説明できる概念であり、過去の研究でも暴力行動との関連が指摘されてきました。
そのため、犯人の語りを理解するうえで中心となる性格特性として、今回の分析の主要なテーマに据えられました。
ナルシシズムと聞くと「自信家」や「うぬぼれや」という単純なイメージが浮かぶかもしれません。しかし心理学では、ナルシシズムは“一つの性格の中にまるで異なる二つの側面が共存している特性”と理解されています。
その二つの側面のひとつはグランド型(grandiose)と呼ばれ、過度な自信や支配欲、特別扱いを求める傾向を指します。
もうひとつは脆弱型(vulnerable)で、他人からの評価に過敏になり、孤立しやすく、深い被害者意識を抱く傾向を指します。
つまり「強く見える心」と「弱く見える心」が同時に存在しやすい複雑な性格なのです。
研究者たちは、この二つの面が連続殺人犯にどのように現れているのかを明らかにしようとしました。
調査の対象となったのは、アメリカで実際に逮捕・裁判を経験した45人の性的動機をもつ連続殺人犯です。
研究チームは、警察の自白調書、FBIの面談記録、裁判資料などを集め、犯人が語った言葉をすべて細かく読み込みました。
分析対象となった発言は、合計662のセグメントに分けられました。
研究チームは、犯人の語りに現れる心理的特徴を、まず「誇大的な側面」と「脆弱な側面」という二つの大きな枠で捉えました。
そのうえで、それぞれの側面をさらに細かく分け、最終的に四つの因子――賞賛を求める心理(賞賛欲求/admiration)、他者への敵対姿勢(競争・敵対/rivalry)、孤立感(isolation)、そして恨みや疑念(敵意/enmity)――として分類しました。
この四つの因子を基準にすることで、犯人たちの語りのどこに“強さ”と“弱さ”が表れるのかを定量的に評価できるようにしています。
この4つの因子をどれだけの犯人が持っていたのかを調べたところ、もっとも高い割合で見られたのは脆弱な敵意でした。
45人中84%の犯人が「他人に傷つけられる」「周囲が敵だ」と感じやすく、妬みや疑いを強く抱いていました。
内側に溜め込んだ不満や恨みが、他者への攻撃性へと変化しやすい心理です。
次に多かったのは、誇大的な賞賛欲求(76%)です。
犯人の多くが「自分は特別だ」「もっと評価されるべきだ」と語り、自分自身の能力や優位性を強調する場面が多く見られました。
続いて誇大的な競争心(71%)が高い頻度で確認されました。
これは、取調官や心理士に対して挑発的な態度を示したり、周囲を見下すような発言を繰り返したりする形で現れています。
最後に、脆弱な孤立(58%)が確認されました。
多くの犯人が子どもの頃から孤立しやすく、大人になってからも他者との関係をうまく築けないまま人生を歩んでいたことが明らかになりました。
興味深いのは、これらの因子が単独で現れるのではなく、半数以上の犯人が“誇大さ”と“脆弱さ”を同時に持っていたという点です。
たとえば、取調べでは堂々と「自分は天才だ」と言い放つ一方で、別の場面では「誰も理解してくれなかった」とこぼすなど、互いに矛盾する感情が同じ人の中に共存していたのです。
この“強さと弱さの同居”こそが、彼らの語りを理解するうえでの鍵になります。
そしてこの複雑な心理の組み合わせこそが、捜査官が犯人像を描くための重要なヒントとなるのです。
ではこうしたタイプでは具体的にどういう事件が起きているのでしょうか?
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)