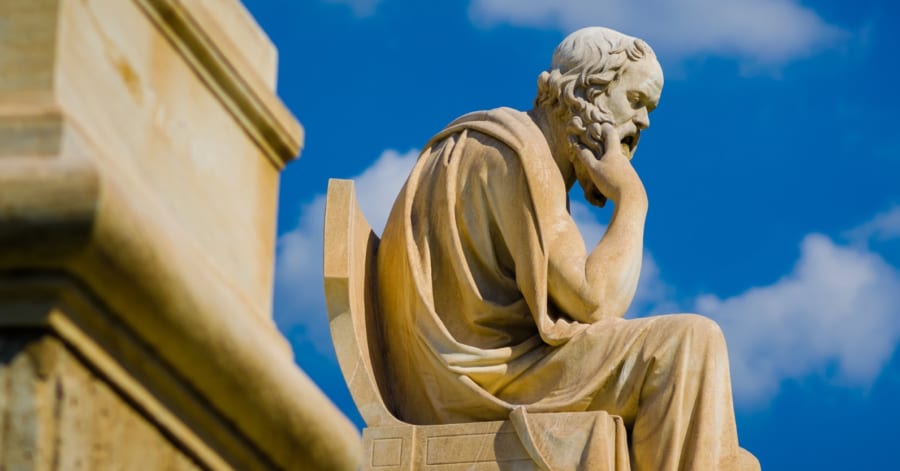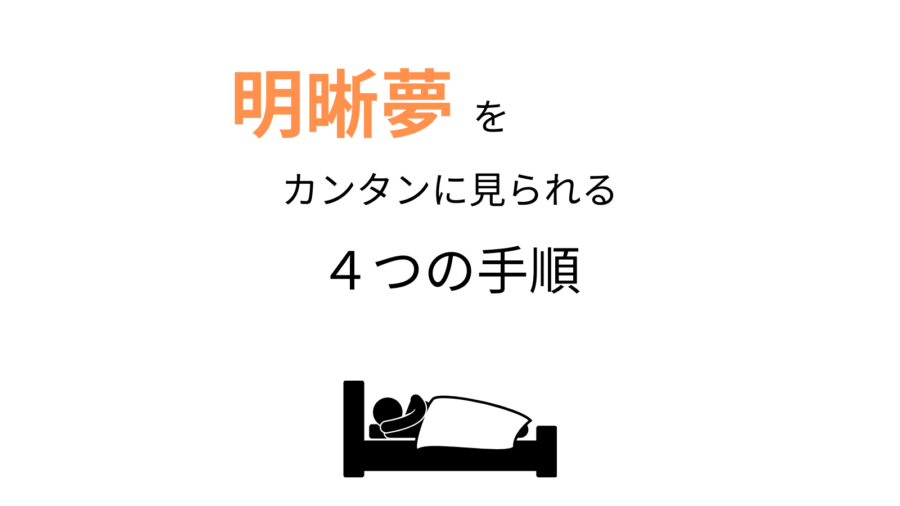言語野に障害を負った患者の見る色の世界

今回の研究の主役となる患者は、プライバシーの理由でイニシャルからRDSという名前で呼ばれています。
RDS氏は脳卒中により、言語を司る左脳に障害を残している患者です。彼は診断の結果、見た色が何色であるかを言語化する能力を失っていました。
RDS氏にとっては不幸な出来事ですが、色の命名と分類の関係を確かめるには重要な症例です。医師たちは、彼の色の識別能力について、詳細なテストを行いました。
すると、彼は色名はわからずとも、階調が異なっていても同種の色は、同じグループであると認識することが出来たのです。また、異なる種類の色を見分けることにも問題はありませんでした。
さらに興味深いことに、彼は「白」「黒」「灰色」という色については、名前を指摘することができました。これは、グレースケールの識別は、他の色彩とは異なる方法で脳が処理を行っている可能性を示しています。
Salpétrière病院の神経心理学者Katarzynaは、「RDS氏が赤、青、緑といった有彩色には名前が付けられない状態なのに、対象的に白、黒、灰色の無彩色については一貫して名前をつけられることに驚いた」と述べています。
もちろんこれは、たった一人の患者を対象としたケーススタディに過ぎません。広く一般的に、今回のケースが適用可能なのかはまだ分かりません。
しかし、最初に述べたとおり、まだ十分に理解されていない神経科学の分野について、この症例は深い洞察を与えるものです。
また、色の問題だけでなく、私達の言語と視覚認識の間にある関連性についても、今回の報告は重要な知見をもたらしていると考えられます。

モノクロームの映画は、色の濃淡だけで表現された世界ですが、私達はそんな映像から問題なく色彩豊かな世界をイメージし、鑑賞することが可能です。これもよくよく考えると、不思議なことのように思えます。こうした色認識に、今回の研究は何らかの解答を与えてくれるのかもしれません。














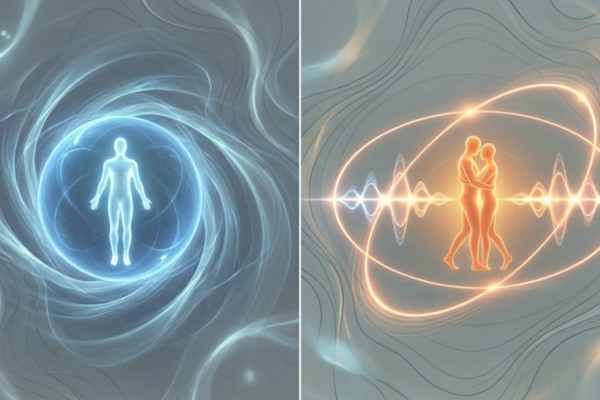
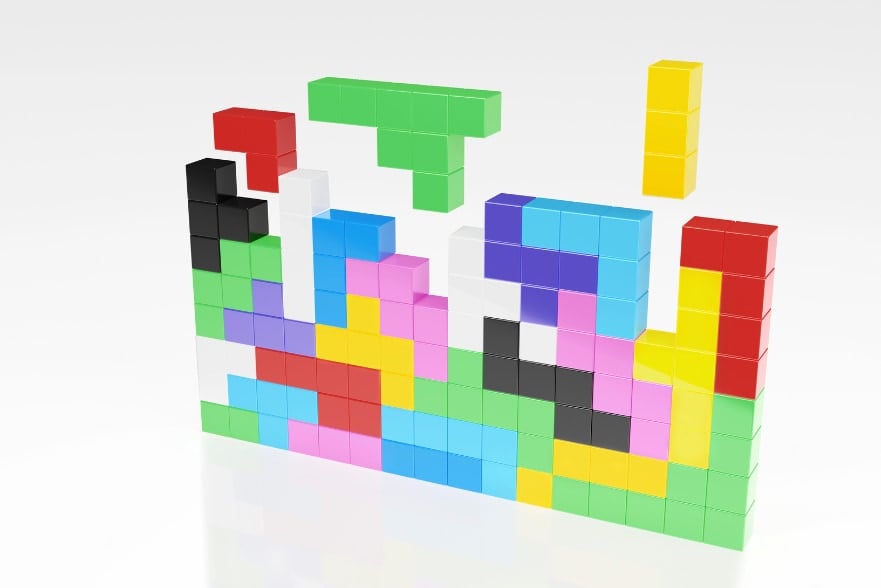













![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)