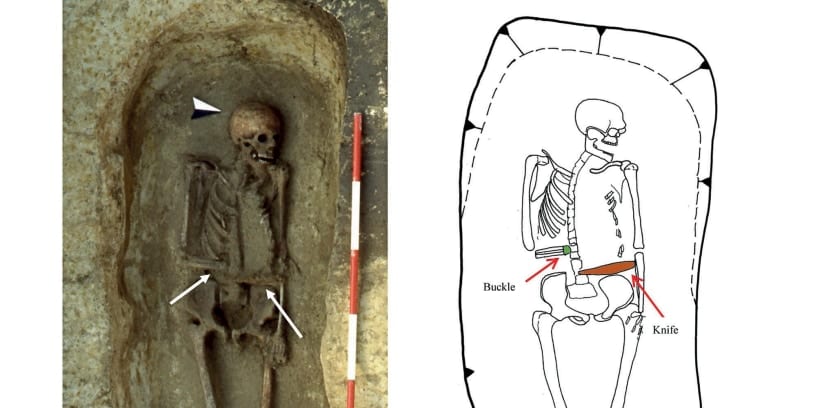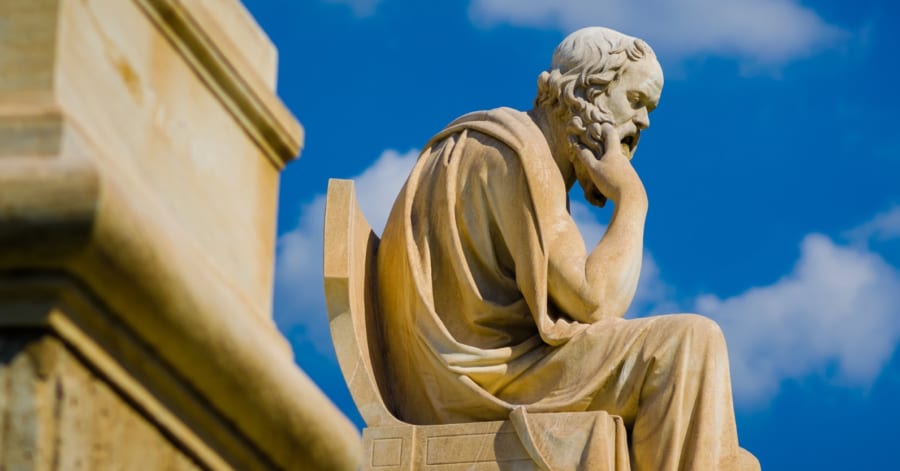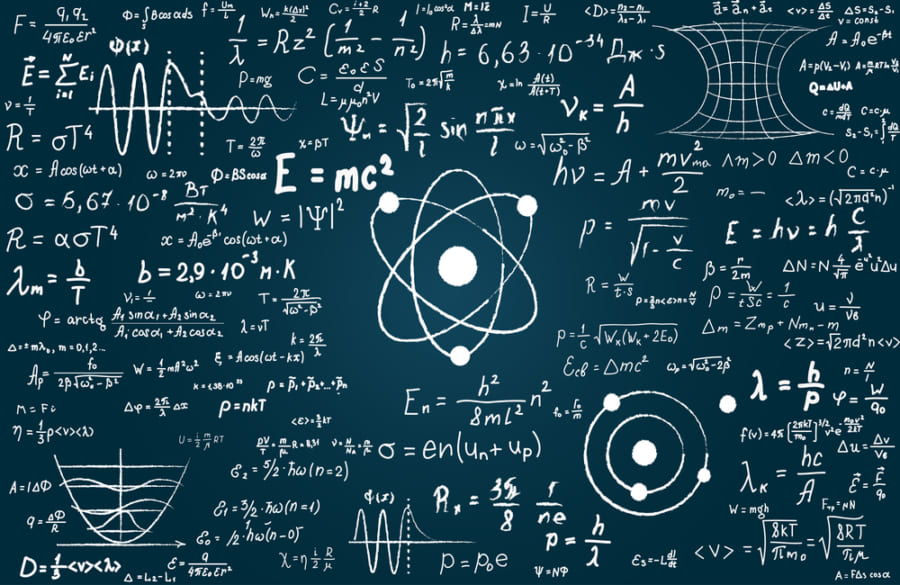
歴史で学ぶ量子力学【2】「自分が物理学など何も知らない喜劇役者だったらよかったのに」
歴史で学ぶ量子力学【3】「神はサイコロを振らない」
歴史で学ぶ量子力学【4(最終章)】※本記事
ニュートン以来、長きに渡って物理学が描いてきたのは、因果律に支配された決定論的な宇宙でした。
「現在が正確にわかっていれば、未来を予測できる」という、いわゆるラプラスの悪魔は、こうした古典物理学の常識を究極的に突き詰めていった場合に導かれる結論です。
しかし、ハイゼンベルクの不確定性原理は、こうした考え方にトドメを刺しました。
そしてそこから、ボーアは「物事は観測によって決定される」(逆に言えば、観測するまで物事は決まっていない)というコペンハーゲン解釈を発表しました。
「未来は決まっていない。あるのは可能性だけだ」というのは、少年漫画のオチみたいで素敵ですが、決定論と因果律を尊ぶ物理学者たちには受け入れがたいものでした。
特にアインシュタインは確率などに頼らず、明確に電子の状態を決定できる隠されたパラメータが存在するはずだと考えました。
例えばAとBの2つの箱があり、片方にだけボールが入っているとします。このときAの箱の中は、蓋を開けようと開けまいと、ボールが「ある」か「ない」かの2つに1つです。
それに対して明言を避けて「Aの中にボールがある確率は50%だ」と言われたら、単にわかんないから確率で誤魔化してるだけじゃないかと言いたくなりますよね。
アインシュタインが指摘したいのはそういうことでした。彼にとって確率に頼るというのは、わからないから白旗をあげていることに等しかったのです。
そして、こうした量子力学の不完全性を暴くべく、アインシュタインは次から次へと思考実験を考案してボーアに戦いを挑みました。
現在私たちがよく知る量子力学の解説の多くは、実はアインシュタインたちが量子力学を否定するために生みだした思考実験が元ネタです。
ここからは、馴染みのある量子力学の話しが数多く登場します。
ボーアを悩ませたEPRパラドックス
第二次大戦の影響で米国プリンストン高等研究所に移ったアインシュタインは、そこでも量子論の矛盾を指摘するための方法について考えます。
しかしプリンストンの研究所には、生まれたときから量子論を聞いて育った若手物理学者が多く、いつまでも量子論に理解を示さないアインシュタインは、頭のおかしい”老害”だと思われていました。
そんな中で、アインシュタインに賛同して研究に手を貸してくれる研究者が現れました。それがポドルスキーとローゼンでした。

3人は共同でコペンハーゲン解釈に疑問を投げかける論文を完成させ、それは3人の頭文字を取ってEPR論文と呼ばれました。この論文は、アメリカの物理学専門誌『フィジカル・レビュー』に掲載され、大きな話題を呼びます。
EPR論文が言っていることの要点は次のようなものでした。
【ある粒子(電子)AとBが一瞬だけ相互作用してお互い反対の方向へと飛び去ったとしましょう。このときAとBの性質は相関を持っています。
Aの粒子の性質――例えば位置、または運動量――を測定すれば、反対方向に同じ距離を進んでいるはずのBの位置(または運動量)を知ることができるはずです。
この方法なら、Bに一切なんの観測をしなくても(運動をかき乱すことなく)、実在の運動量か位置を知ることができるのです。】
これは「観測することで粒子は現実の値を初めて得る」と主張するコペンハーゲン解釈と矛盾する問題で、EPRパラドックスと言われています。
これに対してボーアは、2つの粒子は初めに相互作用して、1つの系になっているのだから、Aを観測することでその影響がBにも伝わり、Bの運動量や位置を予測することが可能になるのだと反論しました。
しかし、Aを観測しただけで、何もしていない離れたBに力学的な影響が及ぶはずありません。しかもこの影響は、理論上2つの粒子が数光年という距離を隔てている場合でも、瞬時に伝わることになります。
このためボーアの言うこの謎の影響を、アインシュタインは「不気味な相互作用」だと言って揶揄しました。

結局ボーアはEPR論文に対して、非常にあいまいで難解な解答しかできませんでした。
多くの物理学者が、アインシュタインは量子力学に対して再考を迫る決定的な一撃を与えたと感じました。
が、発表当初は盛り上がったものの、量子力学は実験と一致していて、ボーアの解釈で使っていてもなんの問題も生じないため、結局はやっぱりアインシュタインがどこか間違ってるんじゃないか、という雰囲気に落ち着いていってしまいました。



















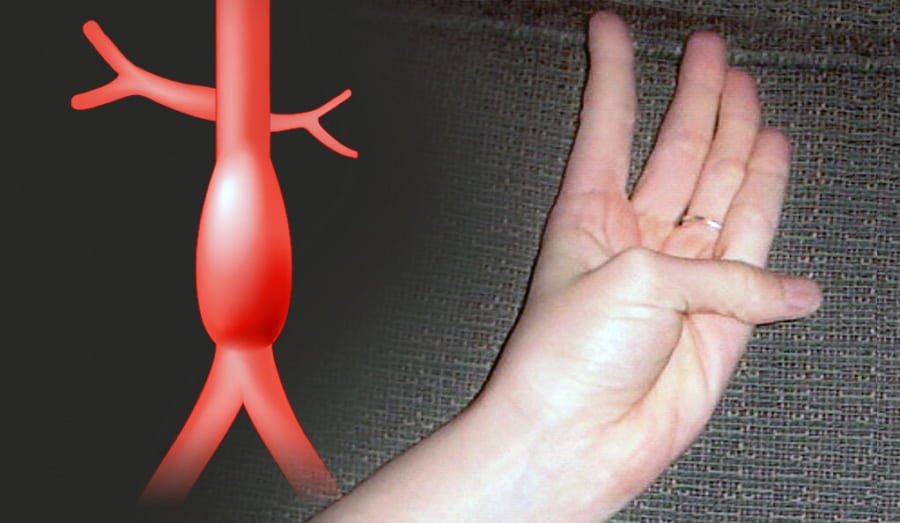










![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)