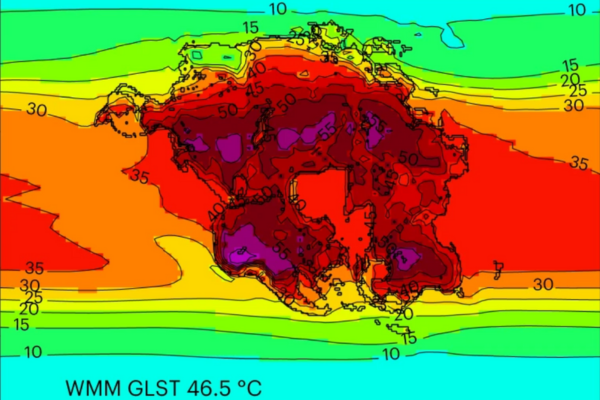「雷雨」はどのように発生するのか?
雷雨を発生させる基本的な要素は、「湿気」と「暖気の上昇」の2つです。
夏場は特に、この2つが手を取り合って、雷雨を発生させやすい状態を作ります。
まず、太陽光により地表面が熱せられると、湿気を含んだ空気が暖まって、上昇気流となります。
上空に行くにつれ、空気は冷えて水滴となり、それが寄り集まることで「雲」と化します。
また、上空では気温が氷点下に達するので、雲の中には水滴のほかに、氷の粒がたくさん存在します。
氷の粒は雲の中をさらに上昇し、それにつれてサイズも徐々に大きくなります。
そして、その重さが上昇気流の揚力を上回ると、今度は重力にしたがって、雲の中を下降します。
ですから結局、大きな氷の粒は雲の下側に集まります。

このとき重要なのは、雲それ自体が、一種の”静電発電機”のように機能することです。
氷の粒が互いにぶつかり合う中で、小さな粒はプラス電荷を、大きな粒はマイナス電荷を帯び始めます。
すると、小さな粒が集まる雲の上方は「プラス」に帯電し、大きな粒が集まる雲の下方は「マイナス」に帯電するのです。
このプロセスが続くと、雲のかたまりは、雷を発生させる「積乱雲」へと成長します。
さらに、静電誘導の作用により、雲の下側のマイナス電荷に対応して、地表にはプラス電荷がたまります。
積乱雲は電荷のバランスを取るために、プラスとマイナスの間で放電を繰り返します。
これが「雷」です。

雲の中での放電、あるいは雲同士の放電をそのまま「雲放電」といい、雲と地表の間の放電を「落雷」といいます。
そして雷は、抵抗が最も小さい経路を通るため、電気を通しやすいもの(導電性の高いもの)ほど、雷に打たれやすくなります。
これを踏まえ、雷害を避けるために注意すべき行動について見て行きましょう。












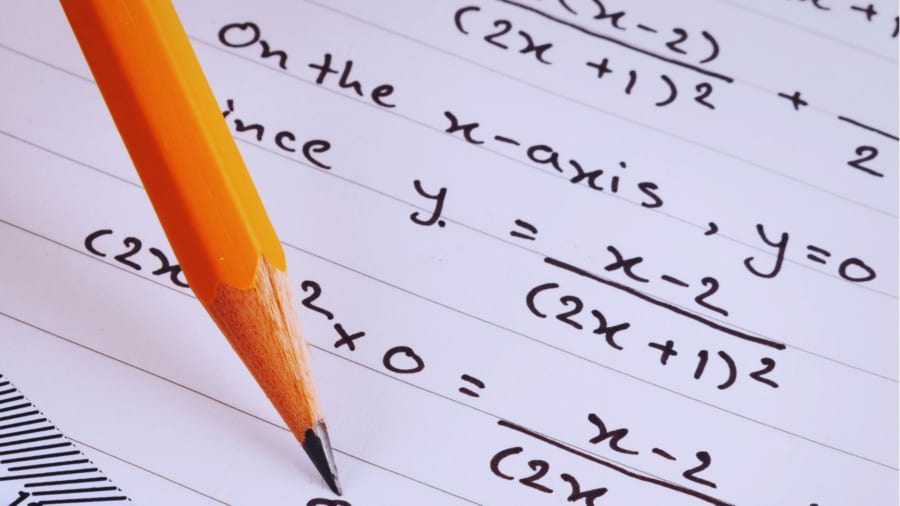

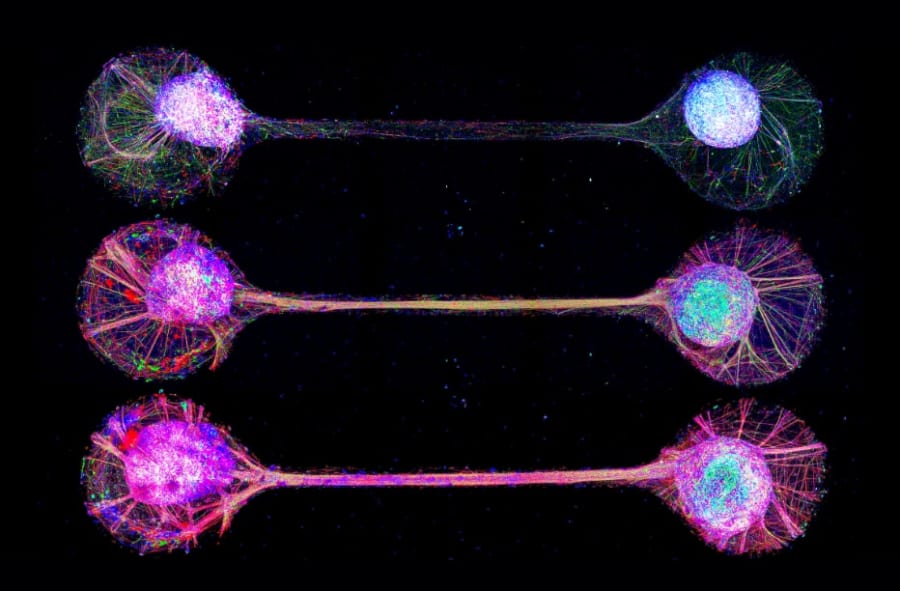














![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)