草地じゃなくて「樹木」がADHDの発症を防いでいた⁈
本調査は2020年10月〜2022年9月の間に南ポーランド在住の10歳〜13歳の子供689名を対象に行われました。
これらの子供は70.5%が心身ともに健康なグループ、29.5%がADHDを持っているグループに分けられています。
健康な子供は地域の学校から無作為に選ばれ、ADHDの子供は心理学者、医師、親を通して集められました。
調査では経験豊富な臨床心理士によって、子供のたちのメンタルヘルス、記憶力、注意力、実行機能などが徹底的に評価されています。
また保護者の協力のもと、子供の生活習慣や身体活動レベル、近隣の緑地環境について回答してもらいました。
緑地環境に関しては、自宅から半径500メートル以内に樹木や草地などがどれくらいあるかを評価しています。

これらのデータを総合的に分析した結果、近隣の緑地環境とADHDの有病率との間に直接的な関連性は見出されませんでした。
自宅近くに緑地がたくさんあるからといって、必ずしも子供のADHDの発症リスク低下にはつながっていなかったのです。
ところがチームはある重要な傾向を発見しました。
それは自宅近くの「樹木」面積が多いと、子供の身体活動レベルが有意に上昇しており、それがADHDの発症リスクの低下につながっている証拠を見出したのです。
興味深いことに、草地面積の多さはADHD有病率の低下と関係しておらず、子供のADHDを防ぐ効果はないことが示されました。
これについて研究者らは、平面的で背も低い草地は子供のたちの身体活動を促進しづらいことが関係していると指摘。
対照的に木々に覆われた場所は、例えば木登りであったり、ぶら下がりであったり、虫捕りやかくれんぼ、障害物の回避など、草地よりも遥かに強度の高い身体活動を促します。
これが子供たちの身体活動レベルを高めて、脳の有益な神経発達を促し、ADHDの発症予防につながった可能性があると説明しました。
都市設計に「樹木」を取り入れるべき
この結果を受けて、研究者は次のようにまとめています。
「私たちの発見は緑地、それも特に樹木環境への暴露とADHD発症率の低下との関連性を示しており、その2つは身体活動の上昇によって媒介されています。
要するに、身体活動を高める自然環境へのアクセスは子供たちの正常な神経発達を手助けする可能性があるのです。
したがって都市設計者は、特に運動不足になりやすい都市部の子供たちの精神衛生を守るためにも、街づくりにおける樹木環境の導入を積極的に推し進めるべきでしょう」

その一方でチームは次のステップとして、樹木環境へのアクセスが神経発達に与える長期的な影響を明らかにしたいと考えています。
今回の調査は、ある時点での子供たちの健康をスナップショット的に捉えた横断的なものであり、それぞれの子供たちを長期的に追跡した縦断的なものではありません。
そのため、樹木環境との触れ合いとADHD予防との関連性をより明確にするには、子供たちを経時的に追跡して、樹木環境の近くでの生活が認知や行動の発達にどのように作用するかを調べる必要があるといいます。
これと別に、近年では成人後にADHDと診断されるケースが増えており、大人もADHDとまったく無縁ではありません。
そこで樹木環境での活動が大人のADHD予防に効果があるのかも明らかにする必要があるでしょう。













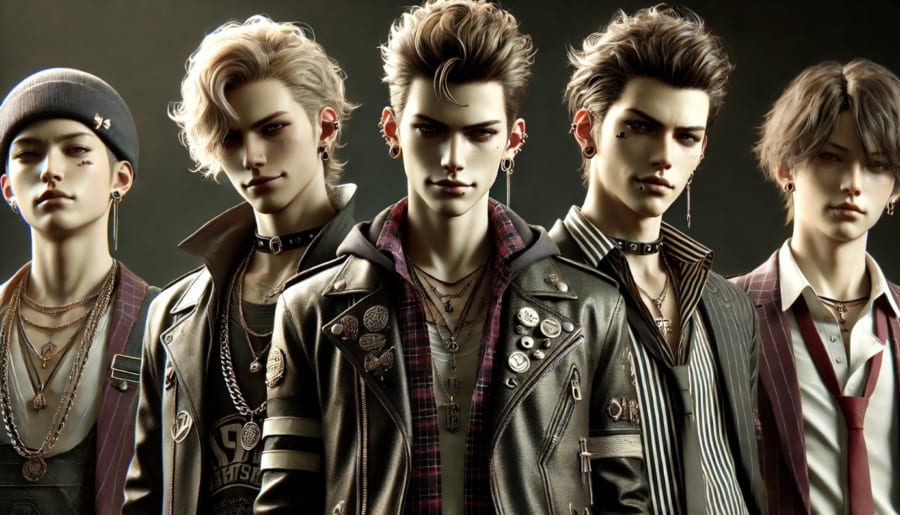

















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)





















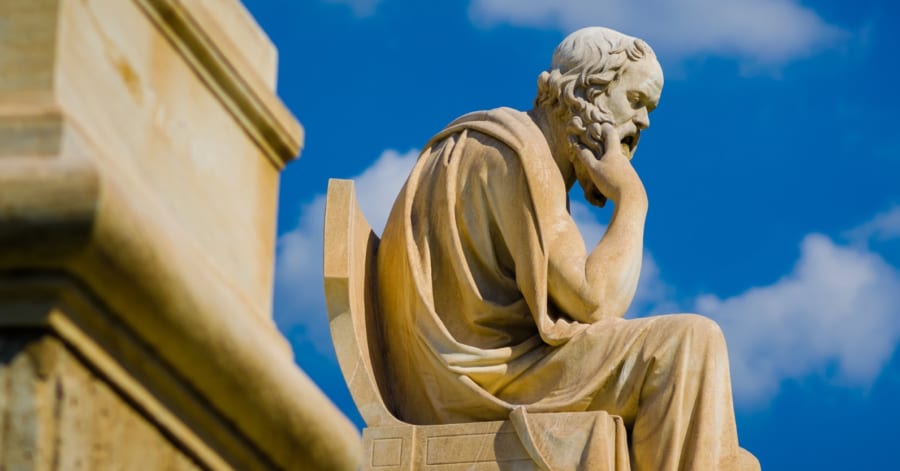






正しい自己効力感の量(実効量)の認知的協和が必要と言う事か
詳しく知りたいです。
運動と自己効力感の結び付きは分かりますが、自己効力感の実効量とは質問紙法などで実際に測定出来るもののことを指しているのでしょうか?
それが認知的協和(認知的不協和が起きていない状態?)がどう結び付いているのか理解が及びませんでした。
習慣的な軽運動がラットの恐怖記憶の消去を促進
この記事とも関連しそう
木というか立体的な構造と運動が有効なのでは?
危険とされて消える公園のジャングルジムとかの遊具があるかどうかでも結果が変わりそう
先天的な脳機能の問題である発達障害が後天的なものであるかのように書かれていて疑問が残る
基本的に遺伝子検査をする訳でもなく、最終的には知能検査や心理検査や言動を鑑みて”障害”かどうか判断されるもの。
診断基準(≒定義)を見てみても12歳かそこらより前にエピソードがあるかどうかくらいしか指摘に関連するところは無いはずだが、これは”後天的”要素でもある。
このような基礎研究的なものとは別に、現実は実際問題として障害なのかどうかを判断されている。
先天的なADHD→よく木に登って遊ぶ→落ちて死ぬ→ADHDが少なくなるってだけなのでは……
そんな死んでたらもっと話題になってるはずですよ
先天的なADHD自体はもっとたくさんいて、幼少期に上下動を含む運動をたくさん経験することでそれが問題ないレベルまで押さえ込まれるといった感じですかね。
多動になるということは体を動かしたいという欲求が大なり小なりあるからそうなっているのでしょうし、その欲求が満たされるまで動ければ症状としては落ち着くと。
ムラっと来たらそれを解消できる環境が心の健康には必要だってことなんだと思いますよ。
ツイに酷い事ばかり書かれてるけど
・ADHDは病気じゃねえよ←揚げ足取んな。誰だって疎い分野の誤用はしている。発達障害も広義では病気。
・発達障害は先天性だろ←障害の種を持っている事とそれが発現するかしないかは別問題。核爆弾スイッチ持ってるイコール原爆被害ではない。感染症だって保菌者の全てが症状を表している訳じゃない。
・ADHDは木から落ちて氏んで間引かれるからでは←そんなんだったら先進国の全ての公園から木が切り倒されるだろ。
・木がある所で育ったけどADHDになったぞ←サンプルサイズ少なすぎで反論根拠になってない。「なったよ」なら記事を咎めてる訳じゃないからセーフ。
ここまでクズの見本市。意見する資格無し。
木の効能として
・空気が綺麗になる。これは排気ガスなどの公害要素に対しての事なので次の事と矛盾しない。
・色んな菌を漂わせる事で子供に免疫力を付けさせられる。
・虫がたくさん育つのでそれを相手して遊ぶ選択肢が出来る
みんな木登りばかり連想してるけど果樹が植えられてる訳でもあるまいし家にゲームもネットもあるんだからそんなに木登りしないでしょ。先進国人で人生で百回登ったような人がどれだけいるのか。そんなに木登りに影響力があるなら一回登っただけで薬一瓶飲むくらいの効果がある事になる。だったらなんでこれまで木登りを推奨してこなかったのかって話になる。宇宙に住めるほどの技術がある一方でそんな灯台下暗しみたいな見落としがある方が不自然。但し雲梯ではどうなのかという論文も見た事があるような無いような。
テンプルグランディンは独房みたいに退屈な環境と、遊園地みたいに刺激的な環境のどちらで脳がADHD化するか実験した結果、動物によって結果が変わる事を突き止めた。人は退屈な環境に居続けるとADHD脳になる、些細な事で大きな刺激を感じる能になるので「刺激に満たされ易い」のではなく「刺激に餓えたかのような刺激依存」になる。
木があると視覚的にも聴覚的にも断続して情報が入って来やすいからね
脳が不必要な情報を処理するのには丁度良い訓練なのかもね
まあなんにせよ植物のない環境って言うのはとても体に悪いんだよ。
今、木のない家が増えてるからこれから問題が頻発すると思うよ。住宅街からどんどん木が減ってるからね
自分が子供の頃は足が滑って頭から落ちたら氏。みたいな遊具が小学校に一杯あったからなあ(をい
丸太組みの足場と下半分が埋まった大きな多数のタイヤで出来た足場の上で鬼ごっこするのが定番でした