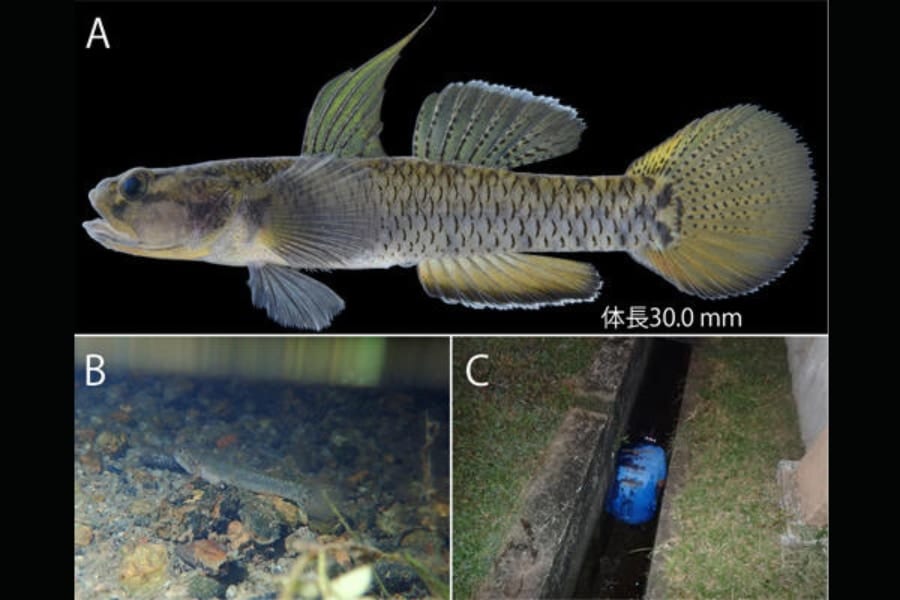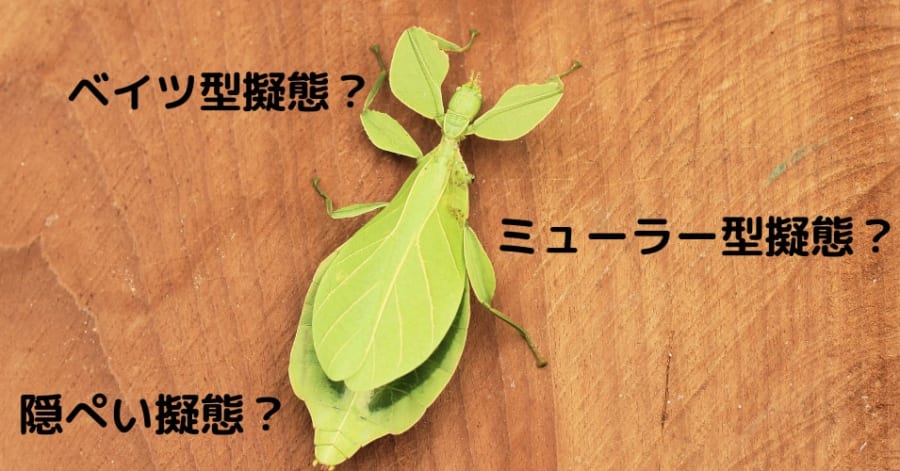逃走派はシャチに聞こえない周波数で歌う
この研究では、以下のような方法を用いてクジラの鳴き声とシャチの聴覚能力の関係を調査しました。
- 水族館でのシャチの聴覚実験のレビュー
シャチがどの周波数帯の音を聞くことができるのか、過去の研究データを精査しました。 - ヒゲクジラの鳴き声の周波数解析
各種のヒゲクジラがどの周波数で鳴くのかを分析し、シャチに聞こえる可能性があるかどうかを検討しました。 - 音の伝わり方のシミュレーション
海中で音がどのように拡散し、どれくらい遠くまで届くのかを解析しました。
その結果、「逃走派」のクジラの鳴き声は100Hz未満であることが多く、シャチにはほとんど聞こえないことが判明したのです。
一方、「戦闘派」のクジラの鳴き声は1500Hz以上のものも多く、シャチが容易に聞き取りやすいことがわかりました。
さらに逃走派のクジラの鳴き声は長時間持続する単純なパターンであることが多く、遠くの仲間にメッセージを伝えやすい反面、シャチに聞こえにくいという利点もあることが明らかになりました。
つまり、戦闘派はシャチに歌が聞こえてもいいから闘う方を選び、逃走派は低周波の鳴き声を使うことで、そもそもシャチに存在を気づかれにくくしていたのです。

この研究は、クジラが単なる受動的な捕食対象ではなく、進化的に音響戦略を発達させていることを示唆しています。
しかしこの「音響ステルス」戦略がどこまで効果的なのかは、今後の研究でさらに詳しく調査する必要があります。
例えば、シャチは狩りの際にエコーロケーションを使いますが、ヒゲクジラがそのエコーロケーションを回避する方法についてはまだ十分に解明されていません。
また気候変動によって海の環境が変わることで、クジラの鳴き声の伝わり方に影響が出る可能性もあります。
クジラたちがシャチから身を守るためにどのように進化してきたのか、これからの研究がさらに明らかにしてくれるでしょう。
海の中では、私たちが想像するよりもはるかに複雑な「音の戦略」が繰り広げられているのです。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)