脳科学の視点:なぜ“記憶の宮殿”が記憶を助けるのか?
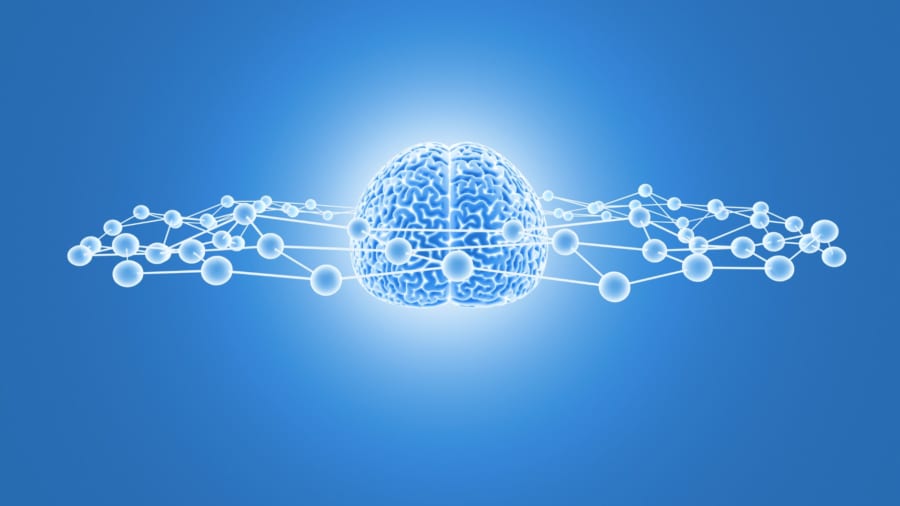
記憶の宮殿は、古くから続く記憶術でありながら、現代の脳科学においてもしっかりとした裏づけがあるとされています。
中でも注目されるのが「海馬」と呼ばれる脳の領域です。
海馬は空間認識や短期記憶、長期記憶への変換などに大きくかかわる重要な部位で、先ほど触れたとおりタツノオトシゴにたとえられる形状を持っています。
私たちが部屋の中を歩き回ったり、街を探索したりするとき、脳の中には「場所細胞(Place cells)」と呼ばれる特別な神経細胞が活発に働きます。
これらの細胞は「自分が今どこにいるのか」「どの方向を向いているのか」といった情報を脳内にマッピングしてくれるのです。
その結果、私たちはスムーズに道を覚えたり、空間の配置を把握したりできます。
この「空間を把握する力」と「情報を覚える力」は深い関係にあります。
先に述べたようにこれまでの研究でも、メンタルアスリート(記憶力大会の常連選手)が場所法を使っている際に海馬が普段以上に活性化している様子が観察されました。
簡単に言うと、脳がもともと持っている“場所を覚える力”を利用し、そこに覚えたい情報を結びつけることで、通常の暗記よりも強力な記憶痕跡が残せるというわけです。
さらに興味深いのは、記憶の宮殿を活用する人々が、ただ思い浮かべるだけで実際に空間を歩くのと同じような脳の活動を示すこと。
私たちの脳は「イメージの世界」と「現実の空間」を意外にも近いメカニズムで処理していることがわかっています。
場所法によって家や道などのイメージをくっきり描くと、脳は“あたかもそこに実際にいるかのように”空間情報を扱おうとするのです。
こうした仕組みを踏まえると、“自分の頭の中にある空間”に情報を配置することが、いかにパワフルな記憶手段であるかが想像しやすいでしょう。
脳科学の最先端研究でも、海馬が記憶の形成と空間認知をつなぐ“架け橋”になっていることが示唆されています。
記憶の宮殿はまさに、この架け橋を最大限に活用した「人類の知恵の結晶」といえるのです。




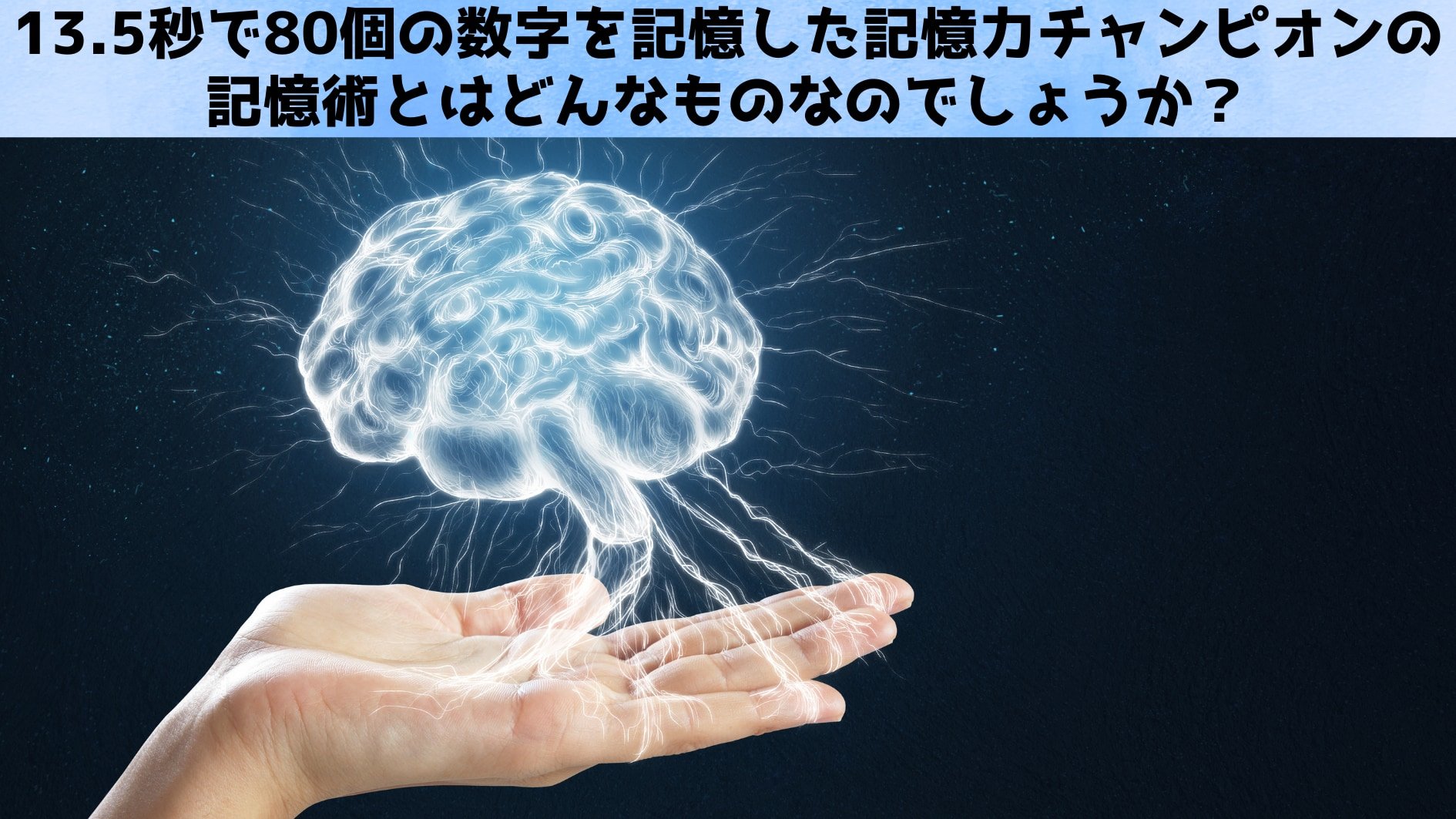
























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



























