まとめ:自己認識力がもたらす柔軟性

今回の研究が示唆するのは、私たちが「これは間違いなく正しい」と感じる道徳的確信には、主に二つの力が同時に働いているということです。
一つめは、「これは絶対に許せない」「これは何が何でも守るべきだ」といった強い感情的インパクト――脳が“重大事だ”と警鐘を鳴らすシステムが稼働する部分。
たとえるなら、火事のサイレンが一気に鳴り渡り、「これだけは最優先だ!」と全身を奮い立たせるような感覚です。
二つめは、同時に走る論理的なプロセス――「なぜこれは許されないのか」「どうしてこれが正しいのか」を自分の中で整理する認知の働きです。
いわば、燃え上がるエネルギー(感情)と、そのエネルギーに理屈を与える制御装置(認知)がタッグを組んで、「これは絶対だ」という確信を生み出しているわけです。
ところが、この“道徳エンジン”を安全運転するためにはブレーキにあたる仕組みが必要となります。
それこそが自分の思考の正しさを点検する「自己認識力(メタ認知)」です。
例えば何かに強い正義感を持ったときでも、「ちょっと待てよ、どこかに思い込みや誤解がないだろうか」「相手には何か別の正義があるんじゃないか」と自分の信念を冷静に振り返る能力があれば、過剰な興奮に流されることを防ぎやすくなります。
一方で、もし自己認識力が弱いと、脳は「自分こそ正しい!」という思い込みをまるで報酬のように扱い、“アクセル全開”で突き進みがちです。
そうなると、他者の声に耳を貸さず、「これが正義なのだから、譲る必要などない」と頑固な態度を取りやすくなってしまうでしょう。
今回の研究がおもしろいのは、「道徳的確信」「感情の強さ」「論理的制御」といった要素に、さらに自己認識力が加わったとき、脳内の仕組みがどのように変化するかを具体的に示した点です。
メタ認知が高い人は、たとえ「これは絶対に正しい」と感じても、その“サイレン”に従いつつ、必要なら音量を下げる術を心得ています。
一方でメタ認知が低い人は、サイレンの音量を下げるどころか、どんどん大きくしてしまう傾向があるのかもしれません。
実際、脳の報酬回路まで一緒に盛り上がってしまうので、「自分が正しい」という状態それ自体が、“快感”や“達成感”に似た満足を与え、ますます意見を覆すのが難しくなる可能性を指摘しています。
こうした仕組みは、社会のさまざまな問題の背景にも関係していると考えられます。
たとえば、ネット上で激しい議論が起きるとき、「あの人たちはいったいなぜあれほど頑固なのか?」と思うことはないでしょうか。
相手にモラルがないわけではなく、むしろ強い道徳的確信があるゆえに、「自分が正しい」というサイレンが止まらなくなっているのかもしれません。
そこに自己認識力というブレーキが備わっていなければ、対立は一気にエスカレートしてしまうわけです。
正義感や道徳心は、本来、社会を前に進める大切なエンジンです。
ただ、そのエンジンがいくらパワフルでも、ちゃんと停止やスピード調整ができないと危険になるのは当たり前のこと。
つまり、自分の正義を声高に叫ぶだけではなく、それを客観的に見直す冷静さがあってこそ、私たちは多様な意見と折り合いをつけつつ前へ進めるのかもしれません。
これは、政治対立の場でも、SNSでの口論でも、さらには日常のちょっとした意見の食い違いでも変わらない大切なポイントと言えるでしょう。


























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

















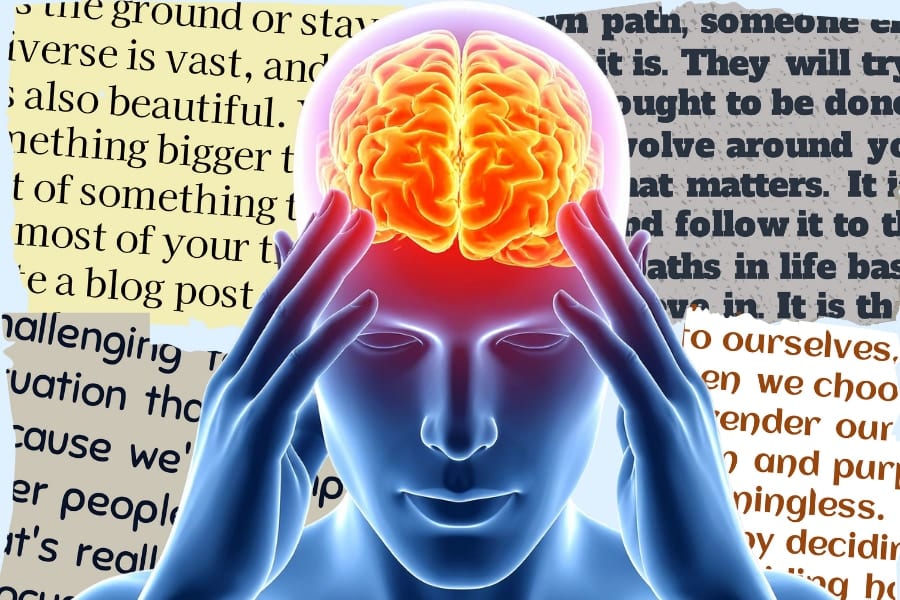










メタ認知能力や癖は、IQとの相関はもちろんありますが、よりEQに関わってくる(いやEQの根幹ともいえるかもしれない)と思います
今後、こういった調査が進み自閉症スペクトラムやアルツハイマーなど特定の特性・疾病をもつ方の自己認識が、健常者とどれくらい解離があるのか、彼らがどんな見え方で生きているのかが鮮明にわかってくるといいなぁと思いました(僕はアスペの方を友人にしがちなので)
コレは自分に置き換えて考えると結構難しい問題だ。こう言う思い込みは他人には全く理解できない事もあるしそうなると全く話が噛み合わなくなる。この感情的な対立は暴力の応酬に発展する。この解決方法はあるのだろうか?
いつも思うが、ナゾロジーの記事の多くは正確さをかなり犠牲にする比喩表現をつかった結論で記述するのに、テーマで登場する主要な単語のある程度正確な説明がない。
例えば、「自己認識力」であれば、訳註などで概論を補足し、また内面的自己認識と外面的自己認識の区別があるのだから、このテーマでは主にどちらなのかといった「論理的理解」に必要な情報を明示しておかないと「表面的な言葉のニュアンス」でフワッと読んだ読者が妄想で誤解するだろう。
記事に対しての意見ではなくナゾロジーそのものに対する意見なのでここに書くよりもナゾロジーそのものに発言した方がよいのでは?
とても酷く、そして配慮にも欠けた記事だね。
原文の記事を翻訳して読んだけど内容は『メタ認知に乏しいと道徳的確信が否定的な結果を悪化させる』という事しか書かれてない。
そしてそれを脳のどの領域が活性化してるのかをfMRIスキャンによって調べたって話。
道徳的確信の話はしてるが政治に対してヒートアップする人がメタ認知に乏しいとかは書かれてない。
あとメタ認知に対しての理解がも乏しい。
メタ認知=自己認識能力ではない。
あとから自分を省みることが出来ないのなら最初にどんな道徳をインストールさせるかが重要やな。低モラルもアレだがガチガチの強いモラルをインストールしちゃったらもう何も出来なくなるやろうなー。
皆さん元記事のリンクを踏んでそちらも読んでいるのだろうか?
元記事ではメタ認知のことを話しているが
いつからメタ認知が自己認識になったのだろうか?
これでは話がまったく違う
わたしが元記事を要約すると
①政治的抗議者の話を聞きながら意思決定する際に道徳的確信度の高い人の方が意思決定速度が早かった
②メタ認知の高い人は、道徳的に正しい(常識的に善悪を決める)のではなく客観的に判断をするプロセスがある
と言うことが言いたいらしい
まぁ、当たり前のことを言っています
これは、書籍「知っているつもりー無知の科学」の中でも多く取り上げられている事例の一つで、常識や道徳と言ったものを知っているつもりになっているから決定が早いだけのことだとおもいます
わたしにはなんの発見もないクソ論文です
当記事がこれだけ書いているのに、言葉の定義がどうだ元の論文がこうだと狭い視野でしか見れない“物知りさん”たちがいることが面白い。
“ある程度”の納得度で「自分を客観視できない人」のことを解説して、彼らのような人間を批判することが当記事の本音だろう。彼らには正しく思考する力が欠けている点を私たちに理解させる狙いもあるのだろう。そしてそうした人たちの群れが私たちの世界を危うくしつつあることも指摘したいのかもしれない。
しかし「自己認識力に欠ける“物知りさん”たち」は当記事の意図は理解せず、語彙や引用元の解釈の正確さばかりに気を取られる。その視点には『有益性』に対する渇望が感じられない。
開かれているコメント欄を有効活用して、元論文からの引用や解釈が間違っていないかどうか読者が検証しようとしているだけでしょう。どこまでが引用でどこからが記者の解釈なのかを客観的に検証することは、議論に厳密さを与える点で有益です。
> “ある程度”の納得度で「自分を客観視できない人」のことを解説して、彼らのような人間を批判することが当記事の本音
とありますが、批判することが本音かどうかは分からないと思います。
私は**批判**ではなく、脳のメカニズムを知ることで相手に対する**他者理解**を促すもの、そしてこの記事内容をふと思い出し、自分のことに当てはめてみて冷静さを取り戻して欲しいといった**注意喚起**を促すものだと最後のページから読み取りました。
また、“ある程度”の納得度、
という表現も記事中には見られません。
納得度ではなく、「道徳的確信」というエンジンと「自己認識力」というブレーキのバランスという表現・枠組みを用いて対立構造の原因を説明しています。