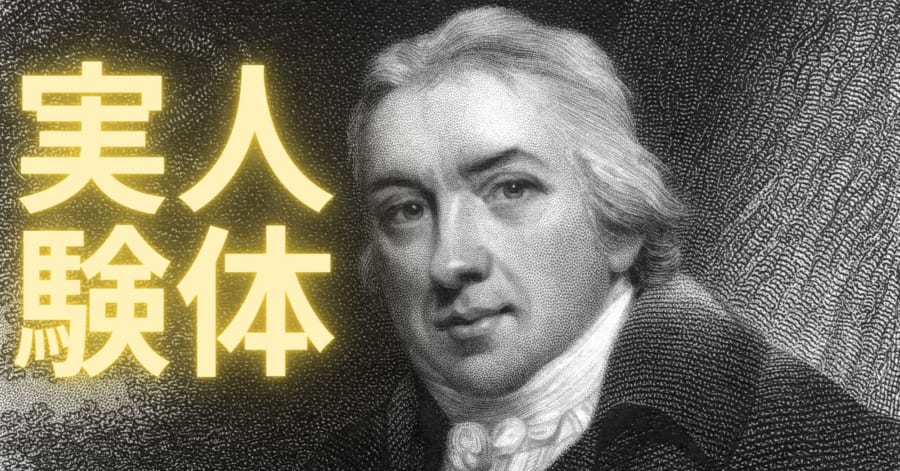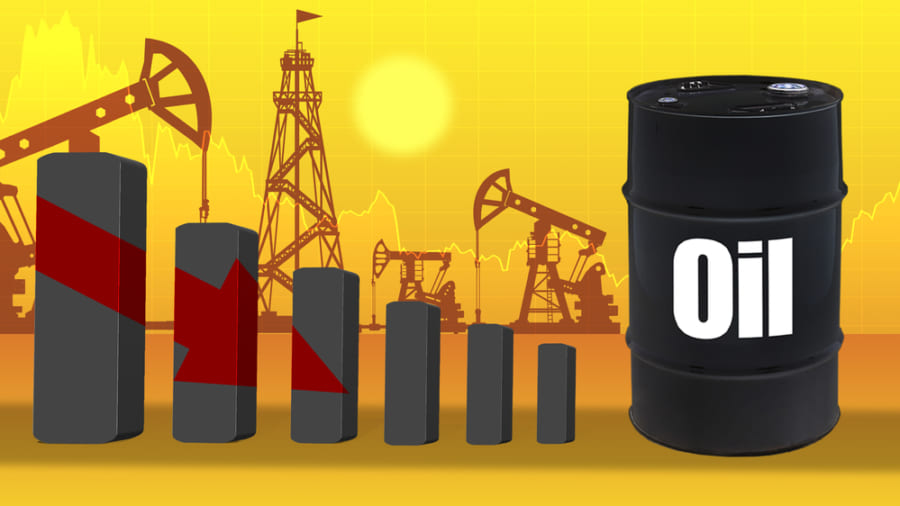無理して減塩しなくてもいい?カギはカリウム

「カリウムを多く摂ると血圧が下がる」という説は、実は今に始まった話ではありません。
1970年代以降、疫学調査や動物実験などを通じて、カリウム摂取と血圧低下の関連は科学的に指摘されてきました。
塩分(ナトリウム)を多く摂ると血圧が上がる一方で、カリウムを多く摂るとこの影響を和らげるということ自体には、以前から観察報告があったのです。
しかし、これまでの研究の多くはあくまで観察的な結果にとどまり、カリウムが具体的にどのような生理的メカニズムで血圧を下げるのか、あるいは男女間でその効果に違いがあるのか、といった点については十分に解明されていませんでした。
特に男女間の性差の影響については、これまでの多くの医学研究で、男性は女性に比べて高血圧のリスクが高く、また塩分摂取による血圧上昇にも敏感であることが知られているため重要なポイントでした。
実際、周囲を見回しても男性のほうが血圧の問題を抱えているケースが多いと感じる人は多いかもしれません。
このように昔からよく聞く説や問題であっても、中身には謎が多いというケースは多々あります。
そのため、この課題に対してカナダのウォータールー大学(University of Waterloo)の研究チームは、より踏み込んだ科学的検証を試みました。
彼らは、腎臓、心臓、血管、自律神経、ホルモン系(RAAS)といった血圧調整に関わる主要な生体システムを網羅した数理モデルを構築し、さらに男性と女性それぞれの生理的特性を反映させた個別モデルを作成して、カリウム摂取が血圧に与える影響を高精度にシミュレーションしたのです。
特に注目したのは、男女間でカリウムの効果に違いが生じるかどうか、またその違いがどの生理機構によって説明できるか、という点でした。
今回の研究では、既存の生理学研究から示唆されていた、閉経前の女性は男性に比べて、腎臓におけるナトリウム再吸収の抑制、血管拡張作用を持つ一酸化窒素(NO)の豊富さ、さらにレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAAS)の働き方の違いによって、塩分負荷や血圧変動に対して耐性が高い可能性がある、という仮説を取り入れ、このモデルに組み込んで検証を行いました。
シミュレーションの結果は、興味深いものでした。
カリウム摂取を増やすと、男女ともに血圧は低下しましたが、男性の方がその効果は大きく、女性ではもともと血圧変動に耐性があるため、低下幅はやや小さいことが示されましたのです。
この成果の意義は、単なる経験則や観察に基づく推測を超えて、血圧調整に関わる生理メカニズムを数理的に再現し、科学的な裏付けを持って「なぜカリウムが血圧に良いのか」を初めて体系的に示した点にあります。
しかも性差を考慮することで、男性と女性で推奨されるアプローチが微妙に異なる可能性も見えてきました。
そのため研究チームはこの研究成果を、一般の人にもわかりやすく伝えるために、「バナナやブロッコリーをもっと食べたほうが、減塩を頑張るより効果があるかもしれません」と語っています。
この発言に、海外のネット上では「バナナ業者から資金提供を受けたの?」と冗談交じりにツッコまれていますが、こうした身近なカリウムの多い食品を意識的に摂ることは、特に男性にとって有効となる可能性がありそうです。
この提案にはきちんとした科学的根拠があり、高血圧に悩む人は特に意識して取り言える価値が十分にあると言えるでしょう。



























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)



![エレコム スマホ 防水ケース お風呂 IPX8 水深10m 吸盤付き [ iPhone 16e / 16シリーズ / 15シリーズ / 14シリーズ /SE3 など、6.9インチ以下のスマートフォン対応] ホワイト P-WPSB04WH](https://m.media-amazon.com/images/I/31kbvYgtI7L._SL500_.jpg)